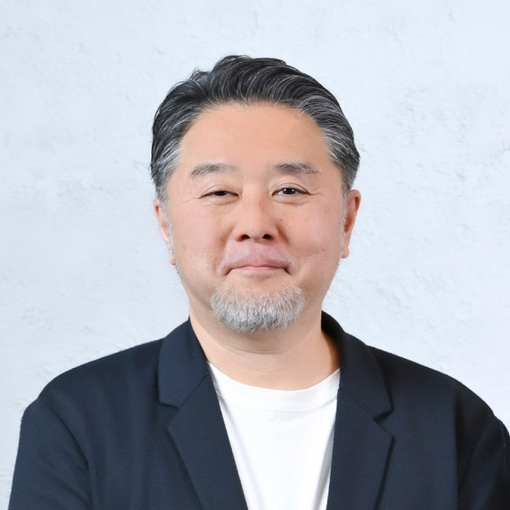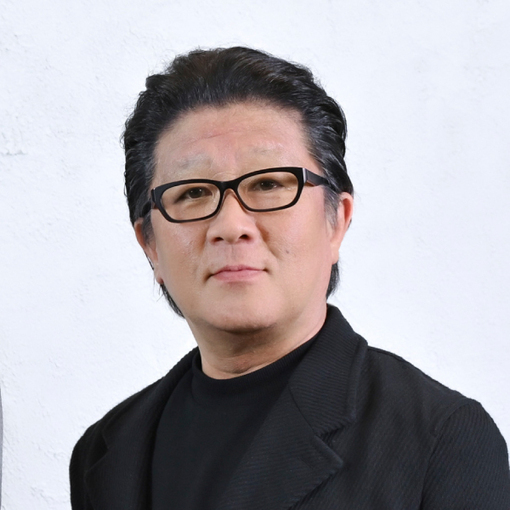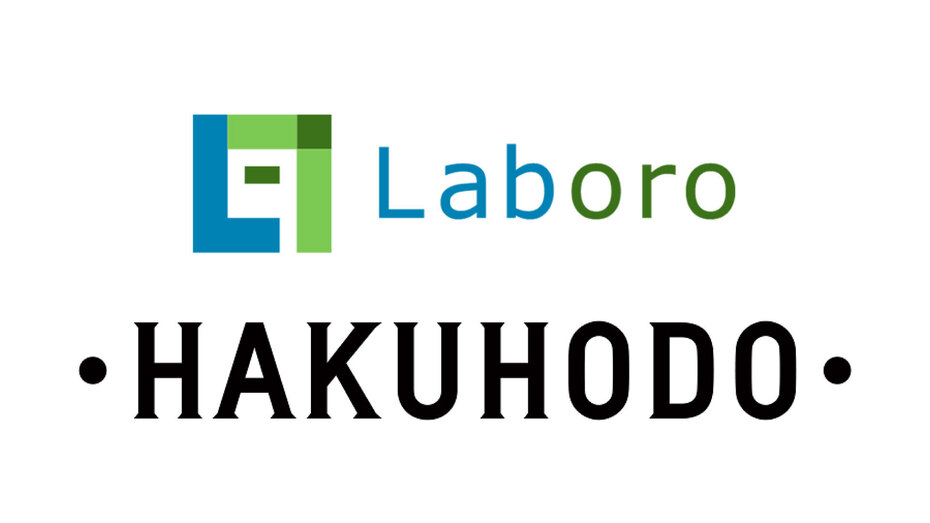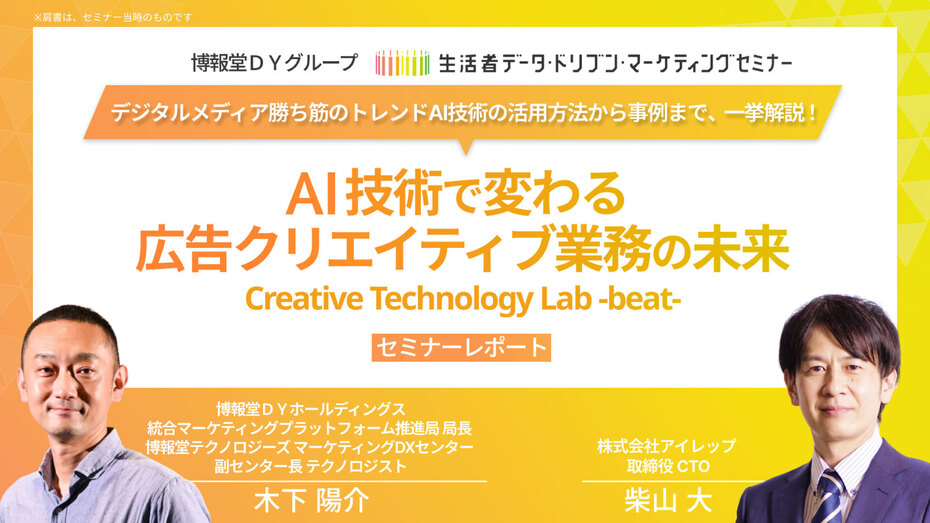【連載 Creative technology lab beat Vol.7】 ビジュアルの変革で世界とビジネスを豊かにしていく──博報堂プロダクツが推進する「VX=ビジュアルトランスフォーメーション」
「Creative technology lab beat」は、クリエイティブとテクノロジーを掛け合わせることによって生活者の心を打つ(beat)アウトプットを生み出すことを目指す博報堂DYグループの横断型組織です。そのメンバーが語り合う連載記事の第7回をお届けします。
今回は、博報堂プロダクツの「ビジュアルクリエイティブ」領域を率いる2人に参加してもらい、「ビジュアル×テクノロジー」の最新の取り組みと、そこから生まれる新しい価値について語ってもらいました。
木下 陽介
博報堂DYホールディングス Creative technology lab beat リーダー
統合マーケティングプラットフォーム推進室 室長
AIテクノロジーG GM
テクノロジスト
武内 寛雄
博報堂プロダクツ
執行役員 ビジュアルクリエイティブ領域担当
高橋 秀行
博報堂プロダクツ
取締役常務執行役員 フォトクリエイティブ事業本部長
顧客体験を「良質化」し、「感動化」する
──博報堂プロダクツは、「VX(ビジュアルトランスフォーメーション)」という新しい考え方を提唱し、具体的な取り組みを進めています。「VX」とはどのようなものか、ご説明いただけますか。

- 武内
- 近年、画像、映像、CG、生成AIによるアウトプットの境目がどんどんなくなってきています。視覚に訴える制作物すべてがシームレスになっています。僕たちは、その境目がなくなりつつある制作物を総称して「ビジュアルクリエイティブ」と呼んでいます。ビジュアルクリエイティブを絶え間なく変革することによって、生活者にリッチな視覚体験を提供すること。クライアントが求める顧客体験をより「良質化」「感動化」していくこと。そして、世界とビジネスと生活をより豊かにしていくこと──。それが、僕たちが提唱する「VX」の基本的な考え方です。
- 高橋
- 博報堂プロダクツの人材採用は職種別になっていて、現在は90を超える職種があります。そのうち、フォトグラファー、画像や映像の補正・修正・加工をするレタッチャー、プロデューサー、アシスタントなど、ビジュアルのプロフェッショナル計60職種のメンバーがVXの活動に関わっています。その多様なメンバーたちのスキルやアイデアの足し算、掛け算によって、クリエイティブの価値を最大化することができる。それが、VXという取り組みの大きなポテンシャルです。
──VXの活動を牽引している武内さんと高橋さんは、Creative technology lab beat(以下、beat)のメンバーでもあります。beatにおけるVXの意味合いとはどのようなものですか。
- 木下
- beatの活動は、「パフォーマンスクリエイティブ領域」「ブランデッド領域」「先端クリエイティブ領域」の3領域で構成されています。ビジュアルクリエイティブは、その3領域すべてに関わります。テクノロジーとクラフト(制作)の力を掛け合わせることで、beat全体の活動をドライブさせるのがVXの取り組みであると考えています。

- 武内
- 僕たちがbeatの活動に関わることで得た新しいスキルや方法論を博報堂プロダクツの事業にいかすこともできるし、VXの取り組みを通じて進化したビジュアルクリエイティブの力を博報堂DYグループに還元していくこともできる。そう考えています。もちろん、それらの取り組みを通じて、クライアントや生活者や社会に提供する価値を向上させていくことが最終的な目的です。
最新テクノロジーを活用したさまざまな取り組み
──現時点でのVXの具体的な取り組みを教えていただけますか。
- 高橋
- 1つに、ビジュアルによる高度なシズル表現創出に特化した「drop」というチームの活動が挙げられます。dropは、商品のいわゆる物撮りを専門とするフォトグラファーとレタッチャー6人によって構成されているチームで、チームならではの多角的なビジュアルアイデアの提案ができることや、複数のプロが同時撮影することによってスピーディにクリエイティブワークを進められることなどが大きな強みです。
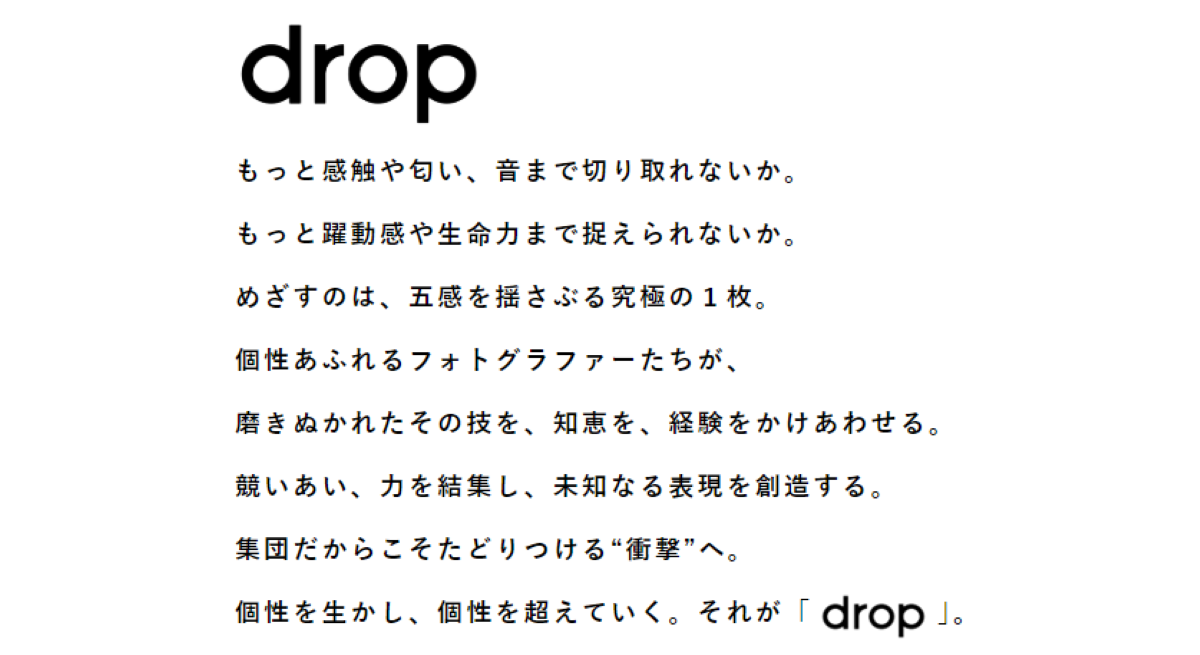
また、「Sizzle “Monitor” Stage」という独自の技術によって、商品画像と背景画像のリアルな組み合わせや、CGなどのバーチャル画像と実際の被写体の画像をリアルタイムで合成するバーチャルプロダクションも可能になっています。僕たちが活用しているバーチャルプロダクション設備は、小規模でありながら非常に実用的な点、LEDではなく液晶モニターを照明に使うことで極めて高精細な画像を生み出せる点などが特徴となっています。今後は、生成AIがつくった画像や動画を使う方向性も大いにありうると思います。
- 武内
- 「Sizzle “Monitor” Stage」を使って撮影したコスメ、ファッション、飲料、食品などのプロダクトショットのクオリティは、世界トップクラスであると自負しています。
- 木下
- バーチャルプロダクションの開発は世界中で進んでいて、例えばドローンで撮影した画像や映像をAIで補正するといった仕組みも実現しつつあります。「Sizzle “Monitor” Stage」もまだまだ進化する余地のある技術ですよね。
- 高橋
- もう1つ、今話に出たドローン撮影の取り組みも進めています。「pod」というチームによるもので、チーム名は「Perspective=視点」「Organized=組織力」「Development=発展性」の頭文字から取りました。

すでに写真や映像撮影でドローンは広く使われていますが、通常はドローンを操縦する人と撮影する人は別々で、フォトグラファーやディレクターが操縦者に指示を出して撮影をする方法がとられています。しかし、撮影のプロが自らドローンを操作して撮影するほうが、絶対にクオリティの高いビジュアルが撮れるはずだと僕たちは考えました。そこで、6名のフォトグラファーがドローンの免許を取得して、podというチームを組成したわけです。ドローンを操作できるフォトグラファーが6人もいる集団は、日本ではpodだけだと思います。
ドローンを使うことで鳥瞰したビジュアルの撮影が可能になるだけでなく、ドローンに照明をつけてこれまでは考えられなかったようなライティングを実現することもできるようになりました。また、GPSデータによってドローンの軌道を設定して、四季に合わせてまったく同じアングルから写真や映像を撮影するといったことも可能です。
ドローンは現在も進化を続けています。その進化にキャッチアップしながら、これまでにない新しい映像表現を生み出していきたいと考えています。

テクノロジーの進化にどう向かい合うか
──クリエイティブやクラフトは、人のスキルとテクノロジーの掛け合わせによって発展していく領域です。人とテクノロジー、あるいはスキルとテクノロジーの関係をどのように考えていますか。
- 武内
- 博報堂プロダクツには、クラフトのプロが2000人います。この2000人がテクノロジーを武器にしてそれぞれの能力を進化させることができれば、博報堂プロダクツやbeatの可能性は大きく拡大していくと考えています。
そのためには、最新のテクノロジーをスピーディに取り入れていくことが必要です。押し寄せてくるテクノロジーの波に対するスタンスは2つしかありません。波を乗りこなすか。波に飲み込まれるか。波に飲み込まれてしまう前に、上手に乗りこなせるようになれば、それがほかのプレーヤーとの差別化にもなるはずです。
- 高橋
- テクノロジーが今後も進化を続けていくことは間違いありません。それに向かい合うために必要なことは、「学習」と「柔軟性」と「チームワーク」だと僕は思います。新しいものを積極的に学び、これまでとは異なるやり方に柔軟に取り組むこと。そして、チームの力で新しい価値を生み出していくこと。この3つを大切にできれば、テクノロジーの進化に人のスキルをアジャストしていくことができると考えています。
- 武内
- テクノロジーは進化することによって、どんどんコモディティ化していきます。それをリスクと捉えるか、チャンスと捉えるか。それによって大きな違いが生じます。テクノロジーがコモディティ化し、民主化することによって、プロではない人たちが比較的簡単にクリエイティブをつくれるようになりました。従来のテレビCMに匹敵するようなクオリティの映像をつくることも今や不可能ではありません。それが僕たちプロの仕事をある部分浸食しているのは間違いないと思います。しかし、それは仕方のないことです。

僕はむしろ、「テクノロジーのコモディティ化」を僕ら自身が積極活用していく道に可能性を感じています。それは、コストをかけずに高いクオリティの作品がつくれるようになるということです。これまでは太刀打ちできなかったような、例えばハリウッド大作レベルの映像を低予算でつくることもできます。これは僕たちにとって大きなチャンスです。ライバルはハリウッドである──。僕は本気でそう思っています。「スキル×テクノロジー」によって、ハリウッドに対抗できるようなビジュアルクリエイティブを生み出していくこと。それが僕たちの大きな目標です。
- 木下
- テクノロジーがどれだけ進化しても、クリエイティブの質を決めるのは「何を伝えたいか」「どんな表現がしたいか」をしっかり設計して取り組んでいるかについて考え抜いているかということです。
広告会社で働く僕たちにとって最も大切なのは、「生活者に共感されるブランドの価値をどう世の中に伝えていくか」「生活者の心を動かす表現をどうつくっていくか」といったことです。それは昔からそうだったし、これからも変わらないはずです。その本質を見失わないようにしながら、新しいテクノロジーや、その活用によって実現する新しい業務プロセスを積極的に取り入れていく。そんなスタンスを大事にしていきたいと僕は考えています。
ビジュアルクリエイティブを通じてよりよい未来をつくっていく
──これからのVXやbeatの取り組みに対する意気込みを最後にお聞かせください。
- 高橋
- 僕は長年写真を撮ってきた人間として、「人を感動させる」ことを何より大事にしたいと思っています。
人を感動させるには、ものをつくる側がものをつくる過程を心から楽しまなければなりません。僕たち自身がビジュアルクリエイティブをつくることに没入し、楽しむことによって、人の心を動かす作品が生まれる。僕はそう信じています。その信念を揺るがすことなく、新しいテクノロジーの活用に取り組んでいきたいですね。
- 武内
- 博報堂プロダクツはこれまで、主に「広告制作」のビジネスを手がけてきました。
今後はそれだけではなく、ビジュアルクリエイティブの「制作手法」をビジネスにしていくべきだと考えています。テクノロジーを駆使して、最新革新的な制作手法を生み出すことで、クリエイティブを良質化し、感動化すること。それが僕たちにできる最大のクライアントへの貢献であり、社会への貢献だと思います。クリエイティブの良質化、感動化によって生活者体験を向上させることは、世界をよりよくしていくことにほかなりません。ビジュアルクリエイティブを通じて、よりよい未来をつくっていくこと──。それが僕たちの最大のミッションであると考えています。
- 木下
- 今後beatで注力していくべきことの1つは、武内さんや高橋さんが率いているチームのメンバーと、博報堂や博報堂テクノロジーズの人材が交流できる機会を増やしていくことです。「テクノロジー×クラフト」に興味があるメンバー間のコラボレーションを積極的に進めることで、ケミストリーを起こし、それぞれのスキルやアイデア力をどんどん進化させていく。そんな方向性を目指していきたいと思っています。
海外のテック系のカンファレンスなどを見ていると、クラフトやクリエイティブの領域において日本は決して海外に後れをとってはいません。むしろ日本でつくられているもののほうがレベルが高いと感じることもよくあります。今後はVXの取り組みをbeatの活動にどんどん取り込みながら、グローバルに通用するソリューションや仕組みをつくっていきたいですね。
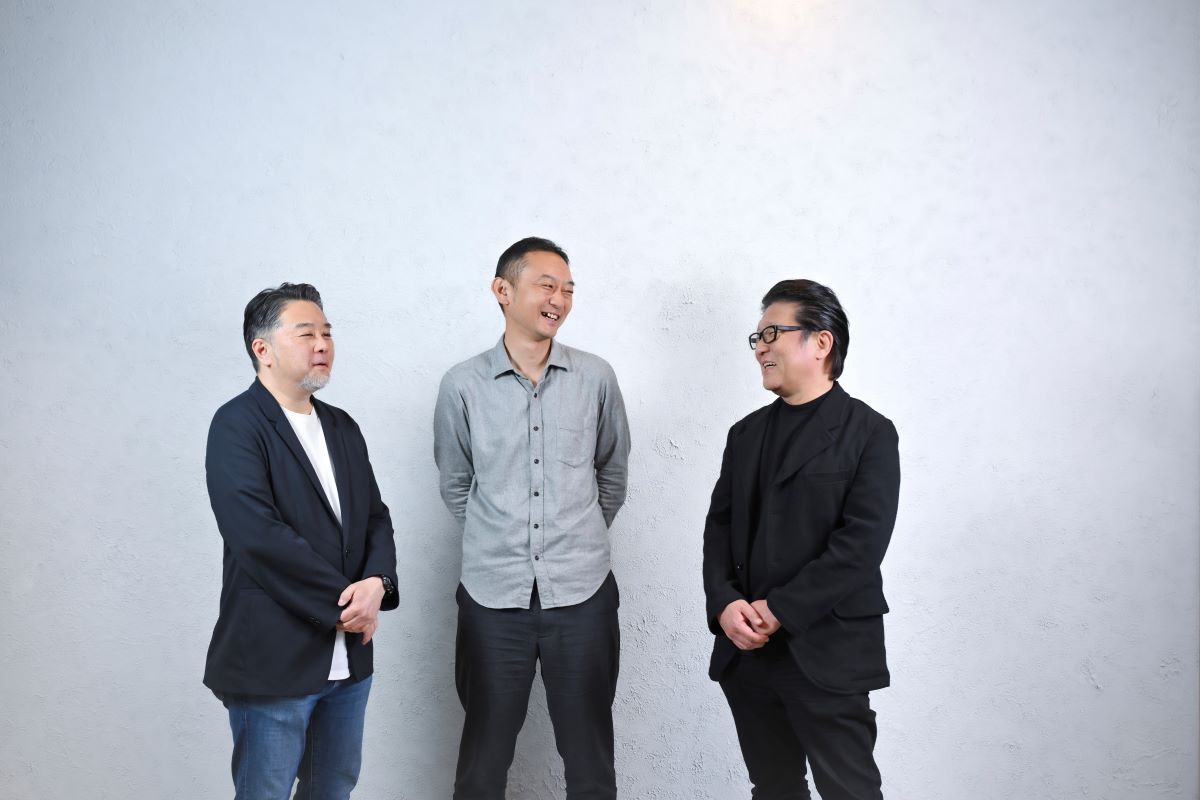
この記事はいかがでしたか?
-
博報堂DYホールディングス Creative technology lab beat リーダー
統合マーケティングプラットフォーム推進室 室長
AIテクノロジーG GM
テクノロジスト
-
博報堂プロダクツ
執行役員 ビジュアルクリエイティブ領域担当
-
博報堂プロダクツ
取締役常務執行役員 フォトクリエイティブ事業本部長