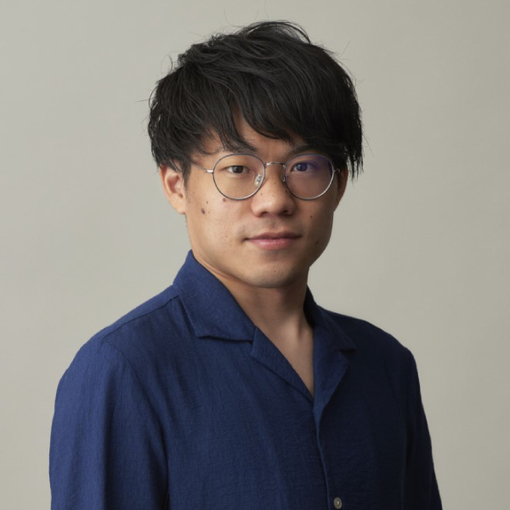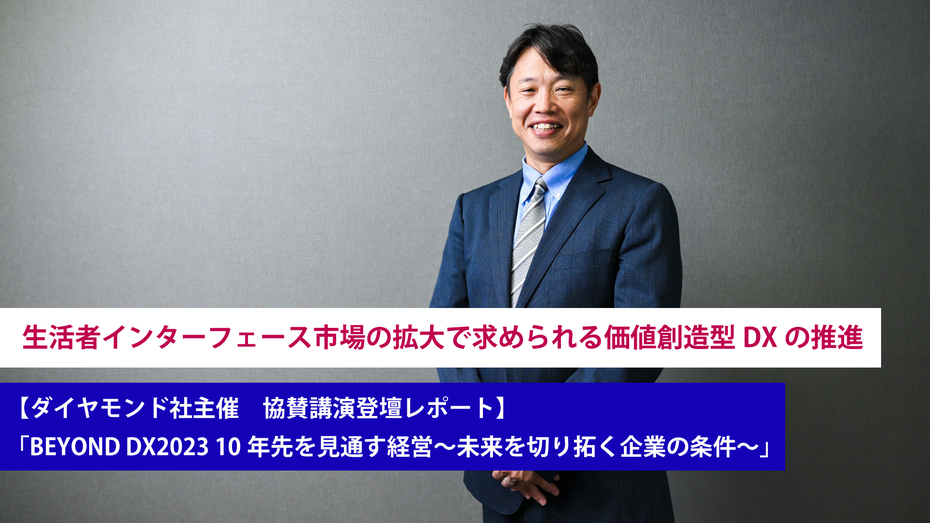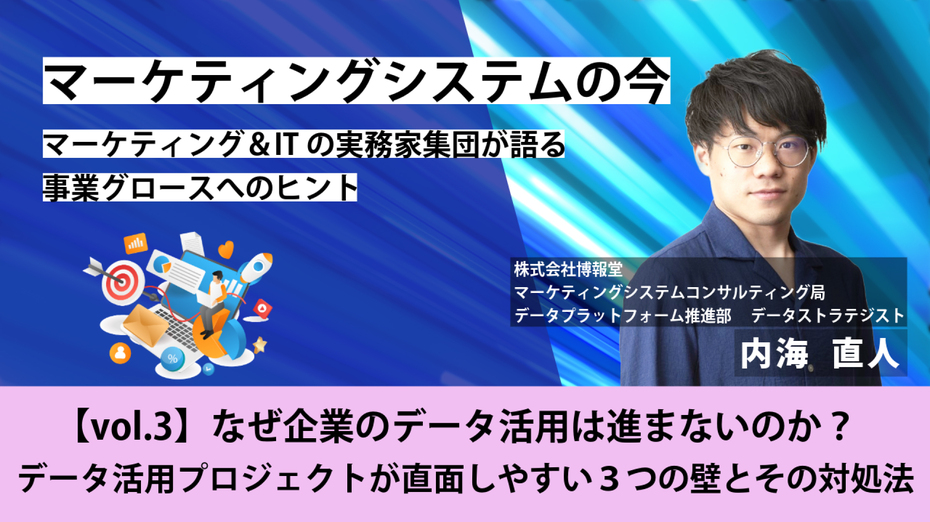

マーケティングシステムの今~マーケティング&ITの実務家集団が語る事業グロースへのヒント【vol.3】なぜ企業のデータ活用は進まないのか?―データ活用プロジェクトが直面しやすい3つの壁とその対処法
マーケティング活動において、データとテクノロジーが果たす役割は年々高まっています。データ基盤整備やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)活用、マーケティングオートメーション、AI活用といった言葉は、もはや特別なものではなくなりました。一方で、それらを「実際の事業成長」に結びつけられている企業は、想像以上に少ないのが実情です。本連載では、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局(以下、マーシス局)のメンバーが、事業グロースに向けた「生活者発想×データ×テクノロジー」の挑戦について、日々現場で向き合っている知見や視点から発信していきます。
第3回のテーマは「なぜ企業のデータ活用は進まないのか?」です。多くの企業がデータドリブンな経営を志向しているにも関わらず、実際のプロジェクトで活用が頓挫してしまう原因は何なのか。その背景にある3つの壁と、それに対する我々の支援アプローチを具体的にご紹介します。
連載一覧はこちら
内海 直人
株式会社博報堂
マーケティングシステムコンサルティング局
データプラットフォーム推進部 データストラテジスト
「データ活用が進まない企業」が直面しやすい3つの壁
近年DXの普及トレンドに合わせて、多くの企業がデータドリブンな事業・マーケティング運営を推進しています。特に最近では、データやテクノロジーを駆使した「CX(顧客体験)の向上」や「EX(従業員体験)の向上」などが注目を集めています。
一方、「データ活用がなかなか進まない」「システムを導入しても使いこなせない」「用途が限定的でスケールしない」など、実務としての課題も多く出やすいのもこのテーマの特徴です。
本記事では、過去の支援実績から「データ活用が進まない企業」が直面しやすい3つの壁とその乗り越え方を解説します。
図:データ活用が進まない企業が直面しやすい3つの壁
① 戦略の壁
まず1つ目の壁は、「データ活用戦略の解像度が低いこと」です。
データの活用はあくまで手段であり、そもそも”なぜ”データ活用が必要で、結果として”何を”生み出すのか、というイシュ―を明確化する必要があります。特に経営陣の投資判断を考慮するのであれば、データ活用によって得られる効果はなるべく定量化されていることが望ましく、そのために現場へのイシュー確認やビジネスインパクト算出なども重要です。また、保有データについても適切にアセスメントを行い、フィジビリティを確認しておかなければ実現可能性は担保されません。
データ活用が進む企業では、データ活用の目的やフィジビリティ確認など戦略策定の解像度が高い印象です。我々もプロジェクトのご相談をいただいた際には、まずプロジェクトが向き合っているイシューについて徹底的に調査し、時にはクイックにデータ分析を回すことで、データ活用戦略の解像度を高めるよう心がけています。
さらに我々は、戦略フェーズにおいて経営層・業務部門を横断した「イシュー可視化ワークショップ」などを実施し、意思決定に必要な要素を整理する機会を設けています。これにより、曖昧な目的や理想論に留まらない、現実的かつ実行可能性のあるデータ活用戦略を描くことが可能になります。
また、企業内で多く見られる「目的先行型の施策」ではなく、生活者理解に基づいたストーリー設計とセットで戦略を立てることも、データ活用の推進力となります。単なる技術導入ではなく、ビジネスにおける意味づけが伴っているかどうかが、その後の成功率を左右します。
図:戦略による企業差
② 組織の壁
2つ目の壁は、「部門がサイロ化されており連携不足であること」です。
データ活用の推進はその性質上、
・マーケティング/営業企画などの業務部門
・データ基盤/ITシステムなどを取りまとめるシステム部門
の双方の力が必要とされ、クロスファンクショナルでのプロジェクト推進が求められます。プロジェクトマネージャーは双方の部門の特性を理解し、それぞれに合わせた言語で会話できる素養が必要です。
このような「業務×システム」双方のケイパビリティを兼ね備えた人材がなかなか多くない背景から、我々マーシス局へご相談いただくケースも少なくありません。マーシス局には元コンサル、元事業会社DX、元デジマ、元Slerなど多彩な人材が集結しており、事業戦略~システム実装までワンストップで対応しております。
例えばあるプロジェクトでは、部門間の共通KPIを設定し、「用語のすり合わせガイドライン」を独自に作成することで、異なる部門同士の認識ズレを最小化した事例もあります。現場の摩擦を最小限に抑えるこうした地道な設計は、プロジェクトの成否を分ける重要なファクターとなります。
また、日々の業務では、社内の合意形成をスムーズに進めるために「フェーズごとの役割分担明確化」や「中間レビューのタイミング設計」なども支援することがあります。こうしたマネジメント設計を支えることも、我々の大切な役割です。
図:組織による企業差
③ 基盤の壁
3つ目の壁は、「マーケティングシステムのアジリティが低いこと」です。
データ基盤をはじめマーケティングシステムは業務の根本を担う存在であり、ツール選定やシステム設計によって施策のクオリティが左右されます。テクノロジーの進化が目まぐるしい昨今ですが、進化前に導入したレガシーシステムを継続して使用していたり、各組織が個別最適の視点でツールを選定していたりと、バックエンドのシステムそのものが課題に溢れてしまっている企業も少なくありません。
データ活用が進んでいる企業は、業務とシステムのFIT&GAPが少なく、システムがモダナイズされている印象です。我々マーシス局においても、最新のツールのケイパビリティを独自に調査する「先端ツールPoC」のタスクフォースを組成し、ベストオブブリードの思想でマーケティングシステムを設計しています。
例えば、段階的なモジュール導入によって移行コストを抑えながらモダナイズを進めたり、重要なシステム間連携を中心にPoCを設計し、業務影響の少ない形でシステムの刷新を実現した事例もあります。
さらに、施策実行部隊と密に連携しながら、仮説検証→改善→実装のサイクルを高速で回せるよう、システム自体の柔軟性・拡張性に注目した設計支援も行っています。こうした設計思想が、結果としてマーケティング活動全体の「機動力」向上に寄与しています。
図:基盤による企業差
いかがでしょうか。データを活用したCX・EXの構想は企業の競争力を高める上で非常に重要なテーマですが、一筋縄ではいかないことも事実です。特に目の前の業務に追われる現場の担当からすればやや優先度が劣後しやすいでしょう。だからこそ我々のような外部リソースをうまく活用することも1つの手ではないでしょうか。
今後も我々は、生活者理解に根ざした発想と、ビジネス実装力の双方を活かしながら、実効性ある支援を続けていきます。
この記事はいかがでしたか?
-
株式会社博報堂
マーケティングシステムコンサルティング局
データプラットフォーム推進部 データストラテジスト2021年博報堂入社。前職の事業会社在籍時より一貫して全社のデータ活用推進に従事。主に、マーケティング&セールスの業務高度化・効率化などをリード。現在はディレクターとして、データ活用を軸としたマーケティンググロースの戦略策定~戦術への落とし込み、システム実装までをワンストップでマネジメント。データのリアルな感触を掴むことを重視しているため、自身でデータ分析を行う側面も併せ持つ。