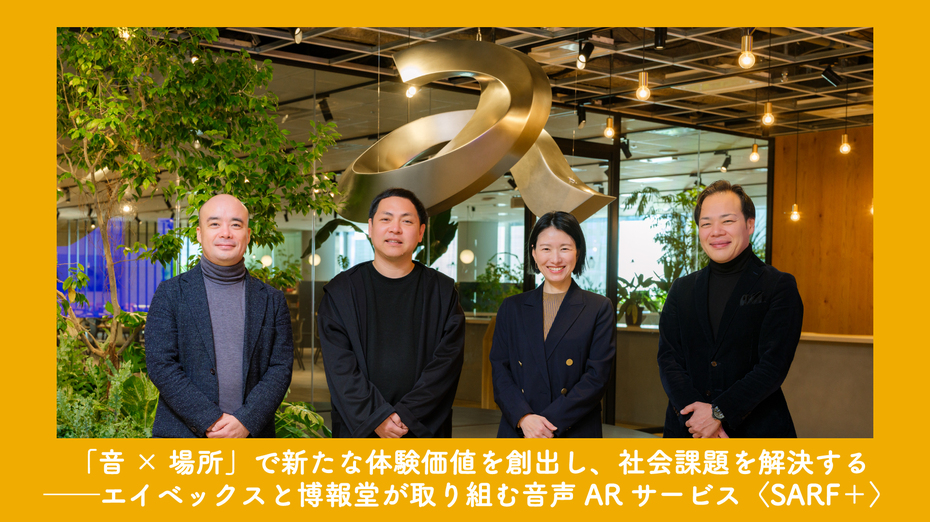

「音×場所」で新たな体験価値を創出し、社会課題を解決する──エイベックスと博報堂が取り組む音声ARサービス〈SARF+〉
エイベックスが提供してきた音声ARサービス〈SARF〉。観光の体験価値向上などに使われてきたその仕組みをベースに、エイベックスと博報堂が事業連携し、サービスの可能性をさらに大きく広げることを目指しているのが〈SARF+〉のプロジェクトです。両社のメンバーに、プロジェクトの具体的な取り組みや可能性について語ってもらいました。
内藤 桂氏
エイベックス・アライアンス&パートナーズ
事業開発グループ ゼネラルマネージャー
渡部 宏和氏
エイベックス・アライアンス&パートナーズ
事業開発グループ ゼネラルプロデューサー
世良 豪浩
博報堂 マーケットデザインビジネス推進局 局長補佐
佐伯 研
博報堂 マーケットデザインビジネス推進局
ビジネス開発部 アクティベーションディレクター
場所のイメージを豊かにする音の力
──AR(拡張現実)の技術を使ったサービスには各社が取り組んでいますが、エイベックスの〈SARF〉のように音声に特化したARサービスはあまりないと思います。音声ARとはどのようなものなのか、はじめにご説明いただけますか。
- 渡部
- 位置情報と音楽や音声のコンテンツを紐づけて、特定の場所における体験を「音」によってより豊かにしたり、より楽しくしたりする仕組みです。例えば、観光地と音声解説やその街を舞台に制作した音声ドラマなどを結びつけることで、これまでとは違った観光の形を生み出すことが可能になります。

──そのコンセプトに基づいて開発されたのが〈SARF〉ですね。
- 渡部
- そうです。きっかけは、「美術館の音声ガイダンスの仕組みを外に持ち出したら面白いよね」といった着想でした。美術館の音声ガイダンスは、「作品」の世界をより豊かに楽しむためのものです。それを特定の「場所」で試してみたらどうなるだろう。そんなシンプルな発想から始まったのが〈SARF〉です。音声ARは「心の中の現象」を生み出す技術だと思っています。小さい子どもは、布団の中に潜り込んで自分がヒーローになった姿を想像して楽しんだりしますよね。あれはまさに拡張現実です。同じように、〈SARF〉は音によってその場所に紐づいたイメージを心の中で拡張させるサービスと言えます。アプリとしてリリースしたのは2022年でした。
──音楽・音声コンテンツは視覚を必要としないので、屋外での移動中にも楽しめそうです。
- 内藤
- いわゆる「歩きスマホ」は、事故やトラブルのリスクを高めます。しかし聴覚だけを使う音のコンテンツは、そういったリスクを抑えて楽しむことができます。それも音声ARのメリットですね。
──「音」は、まさにエイベックスが得意とするコンテンツですね。
- 渡部
- 位置情報と音楽や音声を紐づけることは技術的には複雑ではありませんが、重要なのは音の「使い方」です。おっしゃるように、エイベックスは音楽を使った演出や、音に関連するコンテンツを魅力的に表現するノウハウをもっています。それがあるからこそ、ARという形でイメージを豊かに広げることができると思っています。
- 内藤
- 自社が保有する音楽コンテンツというIP(知的財産)を活用できるのも、大きな強みです。
〈SARF〉が新しい音楽との出会いを生み、音楽を楽しむ裾野が広がっていけば、エイベックスの本業である音楽コンテンツビジネスの成長が見込めるからです。エイベックスグループが手掛けてきたエンターテインメントビジネスは、ほかの業種業態のビジネスと組み合わせることで大きなシナジーを生むことができると考えています。

──これまではどのような協業があったのですか。
- 渡部
- 多くは、観光誘致を目指した地方自治体との協業です。「観光」というメインコンテンツを、「音」というサブコンテンツで支援して、その土地への滞在時間を延ばしたり、周遊を促したりする。そんな取り組みです。
二社のコラボレーションでサービスを進化させる
──その〈SARF〉のプロジェクトに博報堂が参画することで、新たにスタートしたのが〈SARF+〉ですね。参画の経緯を説明していただけますか。
- 世良
- 僕と佐伯は、エンターテインメント領域の新規事業開発を担当しています。
〈SARF〉を知ったときに、このサービスは生活者に新しい体験価値を提供できるだけでなく、社会課題解決の強力なツールになる可能性があると考えました。最初に思い浮かんだのは、インバウンドの増加にともなうオーバーツーリズムの解消に使えないかというアイデアでした。日本に来訪する外国人の数は年々増えていますが、その多くは特定の観光地を訪れるので、地域住民への負荷が高まったり、交通の過度な混雑が生じたりしています。その問題を解決するには、海外の人たちにはあまり知られていない観光地の魅力を伝え、いまの観光の在り方を変える必要があります。そこに音声ARの仕組みが活用できるのではないか。そう考えたわけです。そのようなアイデアをエイベックスの皆さんにお伝えして、共感いただくことができました。
- 佐伯
- 社会課題解決だけでなく、IPをうまく活用させていただくことによって、博報堂が得意とするクライアント企業のプロモーション支援ができるのではないか。そんなアイデアもありましたね。協業の動きが始まったのが2023年で、24年初頭に本格的なプロジェクトがスタートしました。

- 世良
- プロジェクトを進めるにあたって目指したのは、短期的な取り組みに終わらせるのではなく、長期的なビジネスにしていくことでした。多くの生活者や企業に活用していただける魅力的なサービスをつくるには、時間がかかるし、投資も必要です。そのようなフォーメーションをつくることについても、エイベックスの皆さんに賛同いただくことができました。
──〈SARF〉と〈SARF+〉の違いをご説明ください。
- 世良
- 〈SARF〉は、自治体などをパートナーとしてエンドユーザーに無料でサービスを提供するモデルでした。〈SARF+〉が目指したのは、博報堂DYグループのネットワークをいかしてパートナーを拡大していくこと、データを活用してユーザーへのアプローチの解像度を上げていくこと、それからユーザー課金の仕組みをつくることでした。
- 佐伯
- ユーザーにお金を払っていただくことで、コンテンツ活用の幅を広げ、より楽しく豊かなUX(ユーザー体験)を提供することが可能になると考えました。〈SARF+〉はオープンなプラットフォームなので、エイベックスのIPはもちろん、ほかのコンテンツホルダーのIPも活用することが可能です。さまざまな音楽・音声コンテンツを駆使して、これまでになかった音のUXを実現したい。それが僕たちの思いです。
──エイベックスから見て、博報堂と協業することにはどのような意義があると考えられますか。
- 内藤
- 博報堂の皆さんは、企業や自治体と日々向き合っているので、日本の社会で今何が課題になっているかを詳細に把握されています。また、生活者の最新動向に対する深い理解もあります。そういった視点をいかすことで、〈SARF〉の可能性を大きく広げることができると考えました。もちろん、私たちがグループとして目指しているIPの価値向上という点にも、いろいろなアイデアをいただいています。IP、UX、社会課題──。そういった要素を音声ARとうまく組み合わせて、これまでになかった企画を博報堂の皆さんと一緒につくっていきたいと思っています。
- 渡部
- 僕たちは、音声ARの仕組みを社会インフラにしていくという長期的な目標を掲げています。その目標を実現するには、いろいろなことにチャレンジして、活用のパターンを増やしていくことが必要です。その取り組みを進めるにあたって、博報堂の皆さんの経験、知見、ネットワークはとても貴重です。僕たちだけではできなかったことが、博報堂の皆さんとなら実現できる。そんなふうに考えています。
「エンターテインメント+サムシング」が生み出す価値
──〈SARF+〉の枠組みで、具体的にどのようなことに取り組んでいきたいと考えていますか。
- 世良
- 社会課題解決とUX向上の2つのテーマが柱になると思っています。社会課題解決については、オーバーツーリズム解消の取り組みのほかに、エイベックスの皆さんが実施された新宿での実証実験にも大きな可能性を感じています。災害が起きたときには、電話やインターネットがつながりにくくなりますし、仮につながってもネット検索をする余裕はありません。そこで、平時から外国語を含むいろいろな音声で避難場所や各種情報を伝えて、災害に備えてもらおうというのがこの実験です。こういったサービスを実用化することができれば、渡部さんが言うような「音声ARの社会インフラ化」が一気に進むと思います。

- 渡部
- 人々の人生や生活に働きかけて、心を動かし、価値観を変えるような体験を提供していきたい。そんな思いを「ライフエンターテインメント」と呼んでいます。これまでのエイベックスは、主にライブ会場のような非日常の空間でのエンターテインメントが中心でした。。そういった取り組みを日常の空間にシフトできるのが〈SARF+〉であると考えています。
ARには、通常はエンターテインメントとは共存しないと考えられているものを共存させる力があります。災害時対応の実験は、「備え」や「学び」と、「楽しさ」を共存させたものです。スタンプラリーなどの手法を使って、有事への備えを楽しく学べるようになっています。また、観光地としてはあまり知られていない地方の観光案内をしてオーバーツーリズムを解消する取り組みは、「混雑回避」と「楽しさ」を共存させたものと考えることが可能です。日常の空間において「エンターテインメント+サムシング」を生み出せるのが〈SARF+〉である。そう考えれば、できることはたくさんあると思います。
- 佐伯
- マーケティングの領域では、〈SARF+〉を活用したフルファネルのコミュニケーションを実現できると考えています。音楽コンテンツを使ってブランドの認知を獲得するだけでなく、会員登録をしたらアーティストのメッセージを聞くことができる。さらに店頭に行くとその場でしか聞けない新曲が聴ける。音声ARとIPを組み合わせれば、そんなプロモーションも可能になると思います。
「ライブ」と「駅」と「音声」を組み合わせた画期的な取り組み
──〈SARF+〉を活用した事例についてお聞かせいただけますか。
- 内藤
- 2024年の10月と12月に、EXILEなどが所属するLDHのライブイベントが大阪の京セラドームで開催されました。ライブには全国からファンが集まります。ライブを見るだけでなく、多くの人たちに大阪の街を楽しんでほしい。そんな願いを実現するために、〈SARF+〉の仕組みを活用して、大阪メトロの各駅でLDHのアーティストのメッセージを聞くことができるサービスを展開しました。アーティストの音声は駅ごとに異なるので、大阪メトロを利用してそれぞれの駅で音声を聞いてもらい、その駅近辺の街を楽しんでもらおうというコンセプトでした。
- 佐伯
- イベントの2週間前からサービスを実施したので、告知の効果もありましたね。もともとは移動経路であった各駅を、LDHファンの皆さんの「聖地巡礼ルート」にすることができたと思います。

大阪メトロ 駅構内での広告掲示の様子
- 渡部
- 最近は、プロモーションに動画や画像などのビジュアル的要素を使うことが主流になっていますが、この取り組みでは、音だけの仕掛けでイベントの体験価値が上がり、大阪メトロの乗客数の伸びを実現することもできました。UX向上とマーケティング効果の両方が実現したということです。この手法はさまざまなキャンペーンなどへの横展開ができるという確かな手ごたえが得られました。
- 世良
- この取り組みは、ライブというコンテンツに駅という場所を紐づけたケースです。LDHにはもともと熱心なファンがたくさんいます。そのコンテンツパワーが成功の大きな要因になったと思います。では逆に、ロケーションパワーがある場所にコンテンツを紐づけるケースではどのような展開がありうるか。それを考えることが、この取り組みによって僕たちに与えられた宿題です。
音声ARのヒットコンテンツをいかに生み出すか
──次の企画も進んでいるのでしょうか。
- 渡部
- 現在話を進めているのが、雑誌社との協業による「ミステリーツアー」です。過去に行ったことがある観光地でも、「ミステリー」というフィルターを通せば、まったく違った感覚でその土地の魅力を体験できるはずです。そのフィルターを、音声によるストーリーなどでつくっていくという企画です。伝承、妖怪など、土地ごとにいろいろなミステリーのストーリーをつくれる素材があると考えています。
- 世良
- ミステリーツアーは、エピソードという要素によって場所の意味のようなものを変えていく試みです。ほかにも、例えば昼と夜のコンテンツを切り分け、時間によって場所のイメージを変えていく方法もあるとも思います。
- 渡部
- 〈SARF〉を開発するときに意識していたのは、「多次元性」や「多層性」というキーワードでした。同じ場所でも、昼と夜、あるいは春夏秋冬によってコンテンツを変えていくことで、その場所を多次元的、多層的に楽しむことができるようになります。それを音で実現できるのが音声ARであると捉えています。
──〈SARF+〉のプロジェクトを通じて、今後実現したいことをそれぞれのお立場からお聞かせください。
- 内藤
- 〈SARF+〉というプラットフォームから圧倒的なヒットコンテンツを生み出していくこと。それが一番の目標ですね。エイベックスが得意としてきたのは、コンテンツの力でムーブメントをつくることです。〈SARF+〉の取り組みでも、そのノウハウをいかして多くの人々、多くの企業を巻き込んで、誰もが知っているような強力な音声コンテンツをつくっていきたい。そう思っています。
- 佐伯
- 僕にも同じ思いがあります。クライアントに〈SARF+〉にご紹介したときに、「ああ、あの〈SARF+〉ですね」と即座に言っていただけるくらいまで認知度を上げるには、ヒットコンテンツが不可欠です。エイベックスのIP力やエンターテイメント力と、博報堂のマーケティング力やネットワーク力。それらを上手に組み合わせることができれば、きっと多くの人に支持されるコンテンツを生み出すことができるはずです。
- 渡部
- 音声ARは、屋外で楽しむことができるフィールドエンターテインメントで、テレビ番組にあるような鬼ごっこゲームから、スマートフォン向けの位置情報ゲーム、あるいは音楽ライブ、演劇、スポーツなど多様な可能性があります。いろいろな可能性にチャレンジして、音声版フィールドエンターテインメントの定番となるようなコンテンツを博報堂の皆さんと一緒に開発していきたいですね。
- 世良
- 地図アプリや音楽配信アプリのように、外出するときには〈SARF+〉のアプリを使う。そんなライフスタイルが広まっていくことが理想です。そのためには、音声ARを「点」や「線」だけでなく、「面」で展開する方法を考えていく必要があります。生活者がいろいろな場所で〈SARF+〉のコンテンツを楽しむことができて、それが社会課題解決にもつながっている。そんなアイデアづくりに引き続き取り組んでいきたいと思っています。

この記事はいかがでしたか?
-
 内藤 桂氏エイベックス・アライアンス&パートナーズ
内藤 桂氏エイベックス・アライアンス&パートナーズ
事業開発グループ ゼネラルマネージャー
-
 渡部 宏和氏エイベックス・アライアンス&パートナーズ
渡部 宏和氏エイベックス・アライアンス&パートナーズ
事業開発グループ ゼネラルプロデューサー
-
博報堂 マーケットデザインビジネス推進局 局長補佐
-
博報堂 マーケットデザインビジネス推進局
ビジネス開発部 アクティベーションディレクター





















