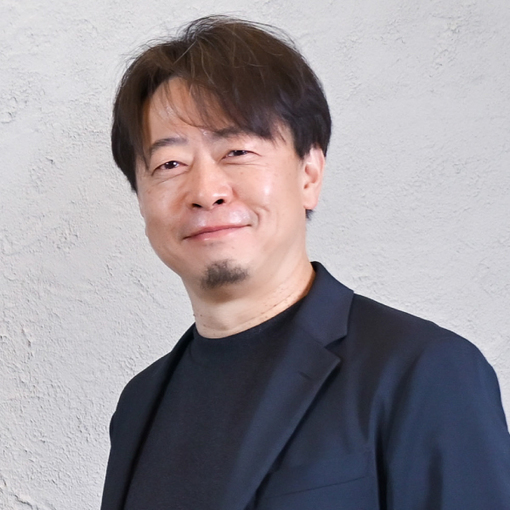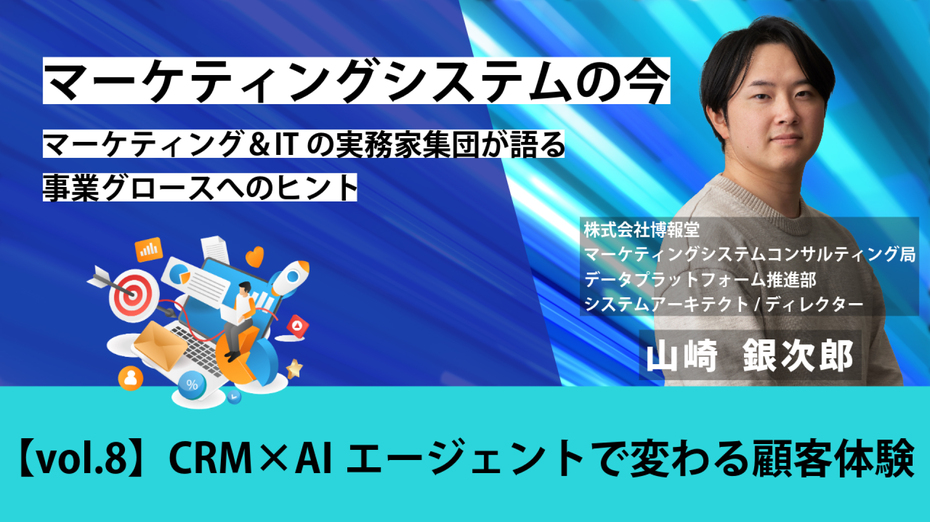対談!EC+【第19回】「購入後のEC体験」ってなに? 顧客をリピーターにするための新しい視点
博報堂DYグループのECプロフェッショナル集団「HAKUHODO EC+」が、外部の専門家を招いて、「これからのEC」について語り合う長期連載「対談!EC+」。今回は、商品購入後のコミュニケーションにフォーカスした事業を展開しているRecustomer株式会社の辻野翔大さんともに、「購入後CX(顧客体験)」というこれまでになかった視点でECの可能性を掘り下げました。
連載一覧はこちら
(写真左から)
漆山 乃介
博報堂DYベンチャーズ
マネージング・パートナー 取締役COO
矢野 裕
HAKUHODO EC+
博報堂プロダクツ コマーステクノロジー事業本部 部長
辻野 翔大氏
Recustomer株式会社 代表取締役COO
奥山 貴弘
HAKUHODO EC+ リーダー
博報堂 コマースコンサルティング局 局長補佐
「購入後」のコミュニケーションを支援する事業
- 奥山
- 省力性や利便性を追求する「売り場」から、新しいCX(顧客体験)を提供するコミュニケーションの接点へ──。僕たちHAKUHODO EC+は、それがこれからのECのあり方であると考えています。その新しいECについてさまざまな分野のプロフェッショナルをお招きして対話する本連載。今回は、「ECでの商品購入後」の体験価値向上に取り組んでいらっしゃるRecustomerの辻野翔大さんをお招きしています。まず、Recustomerの事業概要をお聞かせいただけますか。

- 辻野
- Recustomerは、EC事業者に向けて、ECに組み込むサービスを提供している会社です。創業は7年ほど前です。ご紹介いただいたように、現在はとくに「購入後」にフォーカスしたいくつかのソリューションを提供しています。
従来のEC事業の注力ポイントは、いかにECサイトに人を呼び込み、商品を買ってもらうかというところにありました。それに対して、商品配送状況のアナウンスや返品受付といった購入後のコミュニケーションに意識的に取り組むケースは少なかったと思います。僕たちはその購入後のフェーズが重要であると考え、「購入後CX」の質を高めるためのオペレーションを支援する事業を展開しています。
- 奥山
- Recustomerに出資し、事業を共同で推進している博報堂DYベンチャーズの漆山さんにも参加いただいています。出資に至った経緯をお話いただけますか。
- 漆山
- 博報堂DYベンチャーズは、コーポレートベンチャーキャピタルとして、成長可能性のある新しい企業に出資し、共同で事業成長を目指す取り組みを続けています。
Recustomerの皆さんとの出会いは、スタートアップのカンファレンスでした。EC事業は、購買接点を起点にして生活者と企業が「結び目」をつくっていける重要な領域であると僕たちは捉えています。「結び目」のつくり方にはいろいろな方法がありますが、「購入後」に着目してソリューションを提供している企業は、日本では事実上Recustomerだけでした。ぜひ、この事業を育てていくご支援をしたい。そう考えました。
- 奥山
- 博報堂プロダクツの矢野さんは、HAKUHODO EC+のメンバーとしてさまざまな場面で活躍されています。矢野さんたちの主な役割についても簡単にご紹介いただけますか。
- 矢野
- ECには、「構想」「実装」「運用」の3つのフェーズがあります。そのうち、戦略立案などに関わる「構想」のフェーズを主に担うのが博報堂の役割で、「実装」「運用」を主に担当するのが僕たち博報堂プロダクツの仕事です。建築に例えれば、博報堂が建築士で、博報堂プロダクツは現場監督。そう考えていただければいいと思います。とはいえ、それぞれのミッションが完全に分離しているということではありません。ワンチームの中で協力し合いながら、クライアント支援に取り組んでいます。
「一度買ってくれた顧客」を「次に買ってくれる顧客」に
- 奥山
- 「購入後のEC体験」に着目された理由をあらためてお聞かせいただけますか。
- 辻野
- 日本は人口減少が続いているので、小売事業の顧客の絶対数は今後次第に減っていくことになります。また、Cookieの活用が制限されたことで、新規顧客獲得コストも上がっています。
EC事業の売上を継続的に伸ばしていくには、既存顧客と長期的な関係をつくって、一人ひとりのLTV(生涯顧客価値)を高めていく必要があります。すでに多くのEC事業者が会員システムの拡充などの方法でLTV向上を目指していますが、先に触れたように、商品購入後のCXを高め、顧客との関係をリッチにしていくという発想はこれまでほとんどありませんでした。

「一度買ってくれた顧客」は「次に買ってくれる顧客」に一番近い存在です。一度買ってくれた人に次に買ってもらうには、「買ってもらった後」のケアがとても重要になります。商品注文後の出荷・配達の状況を丁寧に知らせたり、商品到着後の返品処理をスムーズにしたりすることで、「購入後CX」の質を高めることができれば、顧客がロイヤルカスタマーになる確率は高まる。そう僕たちは考えました。
- 奥山
- 「返品」が「ロイヤルカスタマー化」につながるというのは新しい視点です。
- 辻野
- カタログ通販業界の方から聞いたお話では、「返品した人のLTVは高い」というデータは、すでに20年くらい前からあったそうです。ECにおいても、返品ポリシーをしっかり整備して、スムーズな返品ができるようになれば、既存顧客のリピート率は上がると考えられます。
- 矢野
- これまでもEC事業者が返品ポリシーを明確に伝えるケースはありましたが、そのほとんどは、「ご満足いただけなかったら全額返金します!」といったように、安心材料を提供して新規顧客を獲得することが目的でした。既存顧客のロイヤリティを上げるために返品オペレーションを整備するという考え方は、確かにこれまであまりなかったと思いますね。
- 漆山
- ECの返品率は、日本では3%から5%程度なのに対して、アメリカでは16.5%というデータもあります。返品がCXの中に当たり前に組み込まれているということだと思います。
売り手から生活者に商品を届けるプロセスの逆、つまり返品受付、受け取り、検品、保管、再販という流れは、「リバースロジスティクス」と呼ばれています。アメリカではそのプロセスを担う事業者がこの数年で非常に増えていて、市場も拡大しています。日本ではまだほとんど取り組みが進んでいない領域なので、大いに伸びしろがあると考えられます。

- 辻野
- 購入後にフォーカスしたサービスを提供しているアメリカのスタートアップの中には、市場評価額10億ドル以上のユニコーン企業もあります。漆山さんがおっしゃるように、非常に大きな可能性がある領域だと思います。
ポイントは「生活者の快適さ」の実現
- 奥山
- 日本のEC事業者が購入後のCX向上に取り組んでこなかったのはなぜなのでしょうか。
- 辻野
- コストの問題が大きいと思います。逆に言えば、コストを下げることができれば、多くのEC事業者の皆さんが購入後のCXに取り組むチャンスは広がるということです。僕たちの役割はまさにそこにあります。
配送状況のアナウンスや返品オペレーションのDX(デジタルトランスフォーメーション)を進め、比較的低コストで購入後CXをリッチ化できるサービスを提供すること。さらに、それが継続的な売り上げ向上につながる道筋づくりをご支援すること。それがRecustomerのミッションであると考えています。
- 奥山
- 生活者視点から見た場合の購入後CXの重要についてもご意見をお聞かせください。
- 辻野
- ECの商品を買う際に、「いつ届くだろうか」「間違いなく届くだろうか」といった不安を感じる人は少なくないと思います。また、アパレルや靴の場合には、「サイズは合うだろうか」「色やデザインはこれでいいだろうか」といった不安もあるはずです。
その不安を払拭するのが、配送状況のアナウンスサービスや返品受付サービスです。それらがしっかり整備されていれば、ほしいものをストレスなく買えるようになると僕たちは考えています。
- 奥山
- EC構築を支援するプロの立場から見て、購入後CXへの取り組みにはどのような重要性があると考えられますか。
- 矢野
- クライアントへの購入後CXのご提案には、難しい点があります。例えば、リバースロジスティクスの体制を整備するには、フルフィルメント(受付、発送、受け取りなどの一連のプロセス)の仕組みを拡充する必要があります。スタッフを増やしたり、新しい拠点をつくったりしなければならないケースもあると思います。その取り組みは、事業運営の体制そのものを増強する、つまり固定費を増やす話になるので、事業主であるクライアントとしても相応の投資判断になります。
しかし、購入後CXを向上させることは、マーケティングコミュニケーションの「地盤」づくりに確実につながると思います。地盤がしっかりしていれば、辻野さんがおっしゃるように、生活者はストレスなくものを買うことができるし、事業者側からすれば、それによって売り上げを上げることができます。つまり、間違いなくマーケティングの効果があるということです。コミュニケーションの観点から見ても、「配送状況をご確認いただけます」「返品可能です」というキャッチコピーは、シンプルですがとても強力だと思います。今後はRecustomerの皆さんと一緒に、購入後CXの重要性をクライアントにご提案し、ご理解いただける道筋をぜひ考えていきたいですね。

- 漆山
- クライアントに提案する際のポイントになるのは、「生活者の快適さ」だと思います。購買する際の不安を払拭することで、快適な買い物体験が実現する。そしてそれは、EC事業者やブランドの評価に確実につながる。買い手と売り手のウィンウィンの関係をつくっていくために、購入後CXへの取り組みは必須である──。そんな認識を広めていくことができるといいですよね。
返品率が上がることのメリットとは
- 奥山
- 一方、返品率が上がることはEC事業者にとってマイナスであるという考え方もあると思います。
- 辻野
- 確かに、返品にはネガティブなイメージがあると思います。しかし、返品ポリシーを整えた結果として返品が増えたとすれば、ポリシーを整備する前は、ユーザーが「返品したくてもできなかった」ということです。「返品させないポリシー」を掲げていたと言ってもいいかもしれません。
僕たちが理想であると考えるのは、商品を売る側と、商品やブランドを愛好してくれる側の両方が納得し、一緒に商品を育てていける関係をつくることです。返品ポリシーがしっかり整備されることで、売る側はユーザーに本当に合った商品を使ってもらうことができるし、買う側も自分に合わないものを無理に使い続けるということがなくなります。
また売る側にとっては、「返品された理由」を知ることに大きな意味があります。例えば、いろいろなカラーバリエーションがある商品の中で、特定の色の商品の返品率が際立って高かったとします。その理由が「イメージと違った」ということだとすれば、ECサイトに載せている写真の色と実物との間に乖離があったのかもしれません。それを知ることで、ECサイトのビジュアルを改善することが可能になります。あるいは、商品そのものに問題があるケースもあるかもしれません。その場合は、商品を改善するきっかけが得られたことになります。

- 奥山
- 返品は決してネガティブなことではないということですね。
- 辻野
- そうです。返品の仕組みをしっかりつくったうえで、長期的に返品率を下げていけばいいのだと思います。
返品が増えることが必ずしもネガティブではないもう1つの理由は、返品のプロセスが顧客とのきめ細かなコミュニケーションの機会になることにあります。Recustomerが提供している返品ソリューションには、オペレーションを自動化してコストを下げられるだけでなく、返品ポリシーを顧客のステイタスなどに合わせて変えることができる機能もあります。会員ランク、購買額、購買した商品などによって、複数のポリシーを設定することができます。例えば、会員歴の長い顧客の返品手数料を無料にするというポリシー設定によって、ロイヤリティを高めていくことが可能になります。返品ポリシーの運用によって、多様な顧客との多様なコミュニケーションを実現できるわけです。
- 奥山
- 配送に関するソリューションについても教えていただけますか。
- 辻野
- EC事業者の多くは商品出荷時にメールを配信していまが、その後の商品到着までのアナウンスは物流事業者にすべて委ねているのが実情です。Recustomerのソリューションは、物流事業者からの情報をユーザーにメールで送り、メール中のリンクをクリックするとEC事業者のサイトに飛んで配送追跡ができる仕組みになっています。
この仕組みの利点は、ユーザーの許諾がなくてもプッシュメールを送れる点にあります。メールの開封率はときに80%に、リンククリック率は20%に上ります。つまり、メール配信をより深いコミュニケーションのきっかけにできるということです。
買い手にとっては、配送の流れをそのつど確認できることによる安心感があり、売り手にとっては、適切な情報伝達を入り口にしてコミュニケーションを広げていくことができる。それがこのソリューションの大きなメリットです。

グローバルに通用する「購入後のEC体験」モデルを
- 奥山
- 今後はどのようなソリューションを提供していきたいとお考えですか。
- 辻野
- 今後展開を予定しているのが、お試し購入サービスです。商品を仮決済で購入してもらい、商品が届いたあとに実際に買うかどうかを決めて本決済の手続きをしてもあらう。それがこのサービスの仕組みです。ユーザーには、実物を見て買うかどうかを決められるメリットがあり、メーカーには、ユーザーに本当に合うものを提供できることに加えて、客単価が高くなる可能性があるというメリットがあります。例えば、同じアイテムの色違いの商品を2点取り寄せたユーザーが、その両方を買ってくれるといったケースがあるからです。
またこのサービスには、通常のECよりも売り手と買い手のコミュニケーションの期間が長くなるという利点もあります。その中で有効なメッセージ発信を行うことで、関係性を深めていくことができると僕たちは考えています。
- 奥山
- 「購入後のEC体験」は今後どうなっていくか。それぞれのお考えをお聞かせください。
- 矢野
- 「買ってもらうまで」だけでなく「買ってもらったあと」という視点が導入されることで、ECのサービスはどんどん広がっていくのではないでしょうか。購買時のストレスを解消するだけではなく、よりワクワクする体験を購買後に提供できるよう、Recustomerの皆さんともディスカッションを重ねながら、新しいアイデアをどんどん出していきたいですね。
- 辻野
- 「買ってもらうまで」の施策はやり尽くしたと感じているEC事業者の皆さんは少なくないと思います。しかし矢野さんがおっしゃるように、「買ってもらったあと」にできることはたくさんあります。新規顧客獲得のハードルが上がり、CRMがより重視されるようになっている中で、購入後CXの質をより高めていくという流れは今後いっそう加速していく。そんなふうに思っています。
- 漆山
- 日本は他の国に先んじて人口減少が進んでいる国です。その中で、「購入後のEC体験」という視点で新しい領域にチャレンジしていくことによって、海外のECプレイヤーに対抗できるモデルがつくれるのではないか。僕はそう期待しています。何が勝ち筋になるのかはまだわかりませんが、取り組みを続けていくことで必ず見えてくるものがあるはずです。これからも、HAKUHODO EC+のメンバー、Recustomerの皆さんとともにチャレンジを続けていきたいと思っています。
- 奥山
- 購入後に豊かなCXを生み出すチャンスがある──。これは、僕たちにとってこれまでなかった視点です。HAKUHODO EC+としても、その視点を活かしながら、クライアントと生活者の関係をより確かなものにしていく支援を続けていきたいと思います。今日はありがとうございました。
この記事はいかがでしたか?
-
 辻野 翔大氏Recustomer株式会社 代表取締役COOAppleのテクニカルサポート業務を経験後、株式会社リクルートマーケティングパートナーズ(現 株式会社リクルート)へ中途入社。リクルートでは営業業務に従事。在籍中に柴田とともにANVIE株式会社を創業。
辻野 翔大氏Recustomer株式会社 代表取締役COOAppleのテクニカルサポート業務を経験後、株式会社リクルートマーケティングパートナーズ(現 株式会社リクルート)へ中途入社。リクルートでは営業業務に従事。在籍中に柴田とともにANVIE株式会社を創業。
RecustomerにおいてはCOOとしてビジネス領域全般を管掌。
-
博報堂DYベンチャーズ
マネージング・パートナー 取締役COO博報堂DYグループにおいて、メディアビジネス開発やベンチャー投資を推進。また、当社グループの社内ベンチャープログラムである「Ventures of Creativity」の選出委員として新規事業開発・立ち上げを支援。当社グループへの参画以前は、ベンチャーキャピタルにてパートナーとしてベンチャー投資業務に従事。それ以前には、大手人材サービス企業で複数の新規事業・サービス開発を経験。
-
HAKUHODO EC+
博報堂プロダクツ コマースDX部コマーステクノロジー事業本部 部長2016年の博報堂グループ入社以来、ダイレクト・ECビジネスのプロデューサーとしてマーケティングコミュニケーション領域に留まらず、事業計画/データ分析といったコンサルティング領域、コンタクトセンター/システム/物流といったフルフィルメント領域、BI/MA/CDPといったデジタル領域など、川上から川下まで担当。
-
HAKUHODO EC+ リーダー
博報堂 コマースコンサルティング局 局長補佐2004年博報堂中途入社。大手通信会社を中心に長らく営業職を担当し、2019年より現職。EC領域に特化した組織横断型プロジェクトチームである「HAKUHODO EC+」のリーダーとしてEC領域を起点とした事業支援および協業パートナーとのアライアンスを推進。