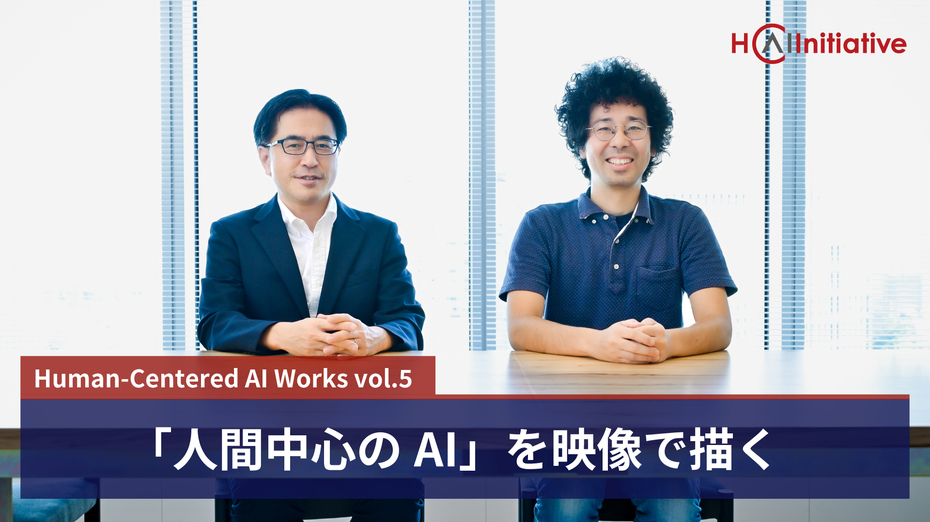AIの台頭に対し、人間の創造性はどこへ向かうのか? MIT石井教授が語る「造山」思考(前編)
博報堂DYホールディングスは2024年4月、AI(人工知能)に関する先端研究機関「Human-Centered AI Institute」(HCAI Institute)を立ち上げた。
HCAI Instituteは、生活者と社会を支える基盤となる「人間中心のAI」の実現をビジョンとし、AIに関する先端技術研究に加え、国内外のAI専門家や研究者、テクノロジー企業やAIスタートアップなどと連携しながら、博報堂DYグループにおけるAI活用の推進役も担っている。
本格的なスタートを切ったHCAI Instituteを管掌する、博報堂DYホールディングスのCAIO(Chief AI Officer)である森正弥が、AI業界をリードするトップ人材と語り合うシリーズ対談を「Human-Centered AI Insights」と題してお届けする。
第5回は、マサチューセッツ工科大学(MIT)教授、メディアラボ副所長の石井裕氏を迎え、「人間中心のAI」という概念自体に疑問を投げかける視点から対話を展開する。石井氏はデジタル情報を物理的な形にして操作できる「タンジブルインターフェース」の先駆者として知られているが、本対談では特に「造山思考」と「テレアブセンス」という二つの概念を軸に、AI時代において真に人間らしい創造性とは何か、そして技術と人間の関係性をどう捉え直すべきかについて語り合った。
「人間中心のAI」を疑う
- 森
- 今日はお忙しい中、時間を作っていただきありがとうございます。石井先生とはこれまでも何度かお会いする機会があり、いつも刺激的なお話をいただいていますが、今日は「人間中心のAI」というテーマで掘り下げてお話できればと思います。
まず、我々博報堂DYグループのAIに関する取り組みを少しご紹介させてください。2024年4月に「Human-Centered AI Institute」を立ち上げたのですが、この名前には実は色々と思いが込められています。 - 石井
- 「Human-Centered」という言葉を掲げているんですね。この言葉自体に疑問を持つところから始めたいと思います。「人間中心」と言っても、人間は千差万別で、良いことも悪いことも全てやれる存在です。性善説的な前提の下で「人間中心」を唱えていないか、あらゆるテクノロジーが、悪意を持つ人間の手で武器化されているリアリティを見落としていないか。世界の「中心」である「良い人間」のために、というドグマは、楽観的な幻想に過ぎないのではないか?

- 森
- 確かにその指摘は重要ですね。我々も実は内部でどのような考え、想いをもって「Human-Centered」という言葉を使うべきか、かなり議論を重ねてきました。
- 石井
- 2016年のケンブリッジ・アナリティカの事例を覚えていますか?彼らはソーシャルメディアを使って違法に収集したデータを使って、米国の不満を持つ有権者への標的爆撃を行い、民主主義を転覆させました。「安全神話」と技術の誤用・悪用がいかに悲惨な結果をもたらすか、我々は3.11の地震・津波・原発メルトダウンの連鎖で、深い痛みを持って学んだばかりです。テクノロジーは、天災・人災、多様な原因でコントロール不能になるリスクを常に孕んでいるんです。「人間中心」という美しい言葉の陰には、こうしたリスクが隠れている可能性を常に考える必要があります。良い例は、Edward Snowden の事件による、それまでの情報セキュリティ安全神話の崩壊です。
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden

- 野田
- 私は博報堂DYグループでAI関連のプロジェクトに携わっていますが、石井先生のご指摘はまさに日々感じていることです。技術を活用する上で、私たちはどのような責任を負うべきか常に問われています。
- 石井
- 本質的な問題は「人間とは何か」という本質的な問いにあります。テクノロジーを使う主体としての人間を考える際、同時にそれを“悪用”して人を傷つけ、民衆主義を破壊するのも人間です。自己中心的で、短期的利益に走り、エコーチャンバー効果で人々の偏見と対立を強化する側面もある。ある意味で我々人間は皆、そういう矛盾を抱えていますよね。そもそも「人間中心」という概念(ドグマ)自体を疑う姿勢が必要なんです。
- 森
- 我々が掲げる「Human-Centered AI」には、二つの意味を込めています。一つはAIによって人の創造性を高めていくという点。これは先生のおっしゃる「造山思考」にも通じる部分があると思います。
もう一つは「生活者」という視点です。博報堂DYグループは長く「生活者発想」を大切にしてきました。単に消費者という「人がもつ多様な面の一部分」だけを切り取って人を見るのではなく、時に働き手でもあり、時に学び手でもあり、遊ぶ人でもあり、親でもあり、子でもあり、兄弟でもあるというような総合的な視点で人を捉え、その人の望みや実現したいことを考える。広告を作る際も、単に商品を売るためだけでなく、社会にとって本当に価値のあることは何かを考えるアプローチです。 - 石井
- 「生活者」という言葉には共感します。しかし、それもある種の理想化された小市民的な極めて限定された人間像ではないでしょうか。インターネットで行われているターゲティング広告は、データを使って消費者の心を操作する、都合の良いトレンドを作り上げるという側面がある。メディアがそうしたツールになるおそれはすでに現実になっています。広告業界もそうした流れの中にあると思いますが、どう考えていますか?
- 森
- 重要なご指摘です。それゆえにデジタル広告の世界はプライバシー保護のための変化を余儀なくされています。クッキーなどの情報収集が制限される中で、かえって関心や属性とは関係のない無差別的な広告配信が増えるというリスクも生じています。我々はこうした状況を踏まえて、本当の意味での「人間中心」、単なるスローガンではなく実質を伴う形で追求していかなければならないと考えています。

「人間のリアリティ」を問い直す
- 石井
- 「人間中心」と言うなら、その「人間」とは一体何か、本気で考える必要があります。人間は多様であり、多くが自己中心的であり、互いに戦い、殺し合い、リソースを奪い合っている現実があります。「コミュニケーションで分かり合える」というのはある種の幻想かもしれない。歴史を見れば、誰がリソースをより多く取るかという争いが現実であり、勝者が都合よく歴史を書き換えるという事実があります。
- 森
- 確かに「人間」の捉え方があまりにポジティブであると、見落とす部分、見えなくなる部分が多い。
- 石井
- 地球温暖化や戦争といったカタストロフの中で、人間はお互いに獣になりうる。満州で徴兵された私の父は、シベリアでの抑留体験から、「目の前にある食べ物を最初の0.5秒で食べられると認識し、次の0.5秒で食らいつかなければ、飢えて死ぬ」という地獄を体験してきました。こうした極限状態での人間の姿を、我々は忘れてはならない。我々は、幸い豊満日本で生物学的な飢えを知らずに生きている。しかし、自分たちを向上させようとする知的な飢餓感を、我々は持っているのか?社会の抱える深い問題に立ち向かうためのエネルギー源としての飢餓感を忘れてはいないか?このリアリティを見据えずに「人間中心」と言っても空虚になってしまいます。
- 野田
- その視点は現代の子どもたちとAIの関係にも通じるかもしれません。私の娘は中学生ですが、「話聞くよおじさん」というAIアプリを使っています。人に相談できないことをAIに話す。そこには、人間同士のコミュニケーションの難しさも見え隠れしているように思います。

- 石井
- 興味深い例ですね。若い世代は私たちと違うAI観を持っています。彼らにとって、AIは単なるツールではなく、感情を持つ友達的や先生的な存在として認識されている可能性がある。「AIに好意を持ってほしい」と考える若者が増えているのは象徴的です。これは今のデジタル技術が単にIQ的な情報処理能力だけでなく、EQ的な感情面での応答を持ち始めていることの反映かもしれません。
- 森
- 我々が昨年行った調査でも、10代のAI観は他の世代と大きく異なることがわかりました。彼らはAIを使いこなしながらも、同時に不安も抱えている。「AIネイティブ」とでも言うべき新しい世代が登場しているんですね。
- 石井
- それが示すのは、テクノロジーと人間の関係がより複雑になっているということです。かつてはAIと人間を単純に分けて考えていましたが、今やAIが人間の分身となりつつあり、境界が極めて曖昧になっている。人間の定義そのものを再考する必要があるのではないでしょうか。
(後編へ続く)
この記事はいかがでしたか?
-
 石井 裕マサチューセッツ工科大学(MIT)教授、メディアラボ副所長1956年東京生まれ。1978年に北海道大学工学部卒業、1980年に同大学院情報工学専攻修士課程修了、日本電信電話公社 (現NTT)入社。NTT 研究所にて、ヒューマンインターフェースとリモートコラボレーション支援技術の研究に従事。1992年に北大から博士号取得。1995年からMITメディアラボにおいて直接操作・感知可能なタンジブルユーザインタフェースの研究「タンジブル・ビッツ」そしてその発展系「ラディカル・アトムズ」を進める。現在MITメディアラボ副所長、タンジブルメディアグループ・ディレクター、工学博士。2001年にMITからテニュア(終身在職権)を授与され、2006年にACM SIGCHIよりCHI Academyを受賞。2019 年には、ACM SIGCHI Lifetime Research Award (生涯研究賞)を受賞。2022年に ACM Fellow に選ばれる。
石井 裕マサチューセッツ工科大学(MIT)教授、メディアラボ副所長1956年東京生まれ。1978年に北海道大学工学部卒業、1980年に同大学院情報工学専攻修士課程修了、日本電信電話公社 (現NTT)入社。NTT 研究所にて、ヒューマンインターフェースとリモートコラボレーション支援技術の研究に従事。1992年に北大から博士号取得。1995年からMITメディアラボにおいて直接操作・感知可能なタンジブルユーザインタフェースの研究「タンジブル・ビッツ」そしてその発展系「ラディカル・アトムズ」を進める。現在MITメディアラボ副所長、タンジブルメディアグループ・ディレクター、工学博士。2001年にMITからテニュア(終身在職権)を授与され、2006年にACM SIGCHIよりCHI Academyを受賞。2019 年には、ACM SIGCHI Lifetime Research Award (生涯研究賞)を受賞。2022年に ACM Fellow に選ばれる。
https://tangible.media.mit.edu/person/hiroshi-ishii
https://www.facebook.com/ishii.mit
https://www.linkedin.com/in/ishii-mit/
-
博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO
Human-Centered AI Institute代表外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用したDX、企業支援、産業支援に従事。東北大学 特任教授、東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、日本ディープラーニング協会 顧問。著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。
-
博報堂DYホールディングス
Human-Centered-AI-Institute
マネジメントプランニングディレクター通信会社にてメディア系企業の大規模システム開発に従事。
マッチングメディア企業に転職し、雑誌からネットへのビジネスモデル転換とビジネス構造改革による業績のV字回復を実現。
IPOに伴う事業統合と新会社設立、海外進出戦略策定をリード。英会話アプリや大手企業と提携した新規事業開発にも携わる。
博報堂に転職後は、グループ横断のオープンイノベーション推進プロジェクト、イノベーションコンサルティング事業、DX子会社、AI のグループ横断CoE形成、2024年にAI新組織の立ち上げを行う。CoEはグローバルに跨る10社100名規模に拡張しAI戦略と活用を推進中。