

データから”価値”を見出せ~「データ×クリエイティブ」でUXはもっと進化する
テクノロジーは、クリエイターの新しい道具となって、創造の幅を広げています。データとクリエイティブの掛け算によって、どのような地平が開けているのでしょうか。博報堂でクリエイター向けにテクノロジーを活用する実戦型プロジェクトを手掛ける、第三クリエイティブ局長の二見均と、博報堂のフェローでありCCTO(Chief Creative×Technology Officer)の福田敏也が、データとクリエイティブによって進化するこれからの時代のUXと、そこで活きる博報堂のケイパビリティについて議論しました。
※本対談はオンラインで実施いたしました。
辺境の地が中央に コミュニケーション領域の地殻変動
- 二見
- 博報堂では数年前から、社内のクリエイター向けに最新のテクノロジーを活用する実戦型プロジェクトを行っているのですが、ある程度続ける中で課題がクリアになってきた一方、博報堂だからこその強みを再認識することも多々ありました。今回は、その活動を一緒に進めていただいている福田敏也さんと、データとクリエイティブについて幅広い観点でディスカッションできればと思います。
僕自身、博報堂に入社して最初の10年は展示施設やイベントなどのリアルプロモーション領域を経験し、その後の20年はずっとデジタル領域メインで仕事をしてきました。当時、デジタルは広告業界ではいわば辺境の地だったわけですが、いつの間にかマス広告を含めたあらゆるコミュニケーションデザインの大前提に、さらには事業・サービス開発領域業務の大前提にもなりました。なので僕は、ほとんどマスクリエイティブ現場を経験していないのですがデジタル領域の経験をクリエイティブに活かすべくクリエイティブ局長になった、という経歴なんです。気が付いたら、デジタルという思想は“真ん中”になっていたんです。
- 福田
- 二見さんの経歴は象徴的ですよね。僕は博報堂でCMプラナーを15年経験してから、90年代後半に立ち上がった「博報堂電脳体」というデジタルチームに参加しました。その後、2003年に独立して以降もずっとデジタル領域で、進化する世界に相対しながら仕事の幅も広がって今に至ります。気づいたらデジタルが大前提になっていたというのは二見さんと同じ実感ですね。
今は自分の会社と並行して博報堂のフェローとCCTO(Chief Creative×Technology Officer)、美大や芸術祭での仕事、デジタルモノづくり拠点やグローバルアワードの運営などいろいろなことをしていますが、一貫して考えてきたのは「生活者にどう振り向かれるのか?」という点です。生活者そのものは基本的には変わらないけど、時代変化とともに振り向かれる理由は多様化しているので、そのアップデートを各所で支援していたら顔が増えていった……みたいな男です。
- 二見
- 「生活者はそんなに変わっていない」というのは重要なポイントのひとつですね。今、UXがマーケティングコミュニケーション上の課題ではなく、事業戦略上で重要なものだと多くの企業が認識していると思います。データの取り扱いを始めとして、さまざまなデジタル技術がUXの創出と改善に有効ですが、UXが体験である以上、そこには必ず人の心を動かす何かがないといけない。クリエイターの視点でその“何か”をつかみ、盛り込むことができれば、体験の精度は上がっていきます。
そこで今回のテーマを「データ×クリエイティブでUXはもっと進化する」としてみました。裏を返すと、「データ×クリエイティブ」の思考や発想にはまだまだのびしろがあるけれど、そこにはいくつかの課題があるのが現状です。
広告からサービス開発や事業開発へ、単発勝負から長距離走へ
- 二見
- 課題のひとつは、先ほど“真ん中”になったと表現したデジタル領域と、従来からあるマス広告のような領域をコミュニケーションデザインで融合させていくことが難しいことです。この融合を推進して次の進化点をつくることを博報堂のクリエイティブでは目指していますが、なかなか慣れ親しんだやり方から抜け出せない。例えばコピーやグラフィックなど特定職域のプロとして、分業で広告を完成させるやり方で成功体験を積んでいると、どうしてもデジタル領域のインタラクティブな思考ができないという課題があると思います。
- 福田
- “完パケ”が目的化していると立ち行かなくなる、ということですよね。デジタルの仕事は、“完パケ”ないものもたくさんあるから。
- 二見
- まさに、そうですね。先ほどおっしゃった「どう振り向かれるか?」の変遷にも通じると思いますが、昔は完成された広告を提示して振り向いてもらう、アテンション文化が浸透していました。それがデジタルの広がりによって受け手の反応が取れるようになり、何が見られ、何に反応し、何が買われるのかという行動データが取れることを前提にクリエイティブをつくり、改善していく、インタラクションをデザインする思考とそれを実現できる技術の理解が大事になってきました。
さらにそれが継続していくと、一回買ってもらって終わりという単発、短距離走の勝負から、長距離走的に継続的な関係構築を目指せるようになる。これはもはや広告ではなく、事業サービス領域にまで入っていくことになる。博報堂が提唱している生活者インターフェース市場も、その流れを捉えて定義された市場だと思っています。
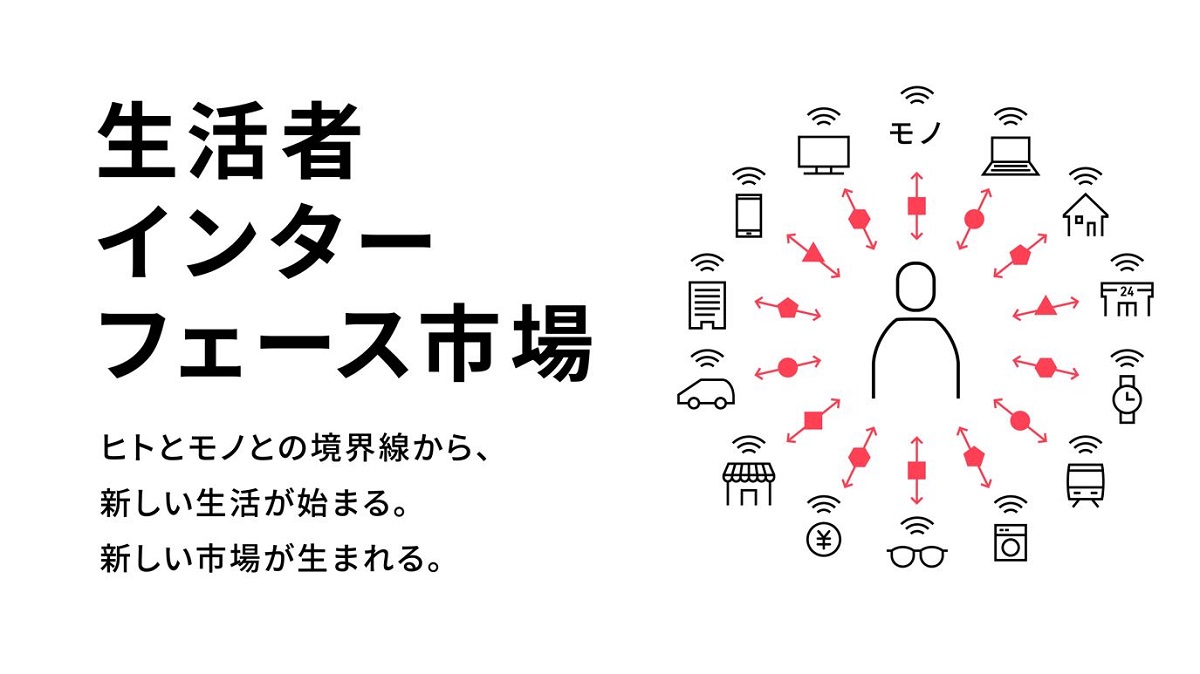
- 二見
- そこでは、生活者とのタッチポイントをどう見つけ、提示したそばから生成されるデータをどう読み取って次のアクションに活かすか、プラットフォームの構想にまでもクリエイティブ発想が必要になります。……前振りが長くなってしまいましたが、そんな時代変化に対応するために、クリエイターは何を考えるべきだと思いますか?
- 福田
- まず、自分たちに期待される役割が変わっていることを認識する必要があると思います。ご指摘のように、今ではクリエイターに商品体験の抜本的な改革や、ブランド体験全体の設計まで求められるようになっています。
すると当然、短期的にモノを売るためだけに僕らがいるのではなく、「体験の設計」や「継続的な事業へのクリエイティブの寄与」のためにいるのだと、僕らの存在意義=コアの捉え直しがまず大事だと思います。
時代に“問い”を立てなければ成果が出ないフェーズへ
- 福田
- その重要性がわかる端的な例を挙げると、今、クライアントに対する課題の聞き方が変わってきましたよね。以前はオリエンシートにまとめられた、「当社のカラーテレビの訴求点は色の美しさ」という要件をそのまま受けて、色がきれいなことを訴えるいくつもの表現を提案していました。
ところが今は、それでは成果が出ないフェーズに入っています。クライアントの意見を受けつつ、「本当に色の美しさが争点なのか? そもそも何を世の中に提示するべきか?」をみずから掘り下げて、クライアントに“問い”を立てて議論する役割を担うようになっています。
- 二見
- “問い”を立てる。まだ見えていない課題を洞察し、争点を提示するということですね。
- 福田
- そうですね。クリエイターの能力の拡張というよりも、そうしないと勝てなくなってきた。
同時に、僕らにはいつの時代も変わらないコアもあります。それは、世の中を自分はどう見るかという視点、一定のビューを持つことです。時代気分や時代リアリティを持っていないと、どんなコミュニケーションも有効に届いていかない。例えば秋元康さんや、気鋭の編集者の箕輪厚介さんといった各領域で第一線を走る方々は皆、常に世の中に対する視点と解釈を持っていると思います。人によって精度はまちまちでも、クリエイティブの職種の人間には欠かせない要素です。
時代に一定のビューを持つこと、その時代に大胆な問いをたてること。それはこの先のクリエイターの基礎体力のようなもので、その上でスマホに代表される新デバイス/新メディア、5Gのような次のデジタルインフラ、AIやIoTなどのテクノロジー、膨大に増えるデータ群などのさまざまな時代変数を掛け合わせて体験を創り出していくことが迫られています。
- 二見
- 思考のベースがしっかりしていないと、どんなにすばらしい技術が生まれたところで使いこなせない?
- 福田
- そのとおりですね。さっき二見さんがおっしゃった、マーケティングコミュニケーションもブランド活動も短距離走から長距離走的になっていることと同じで、体験においても時間軸の設計が重要ですよね。アプリ体験においてUIを良くするためにボタンを大きくするとか、そういう表層的な点の話じゃない。ブランド体験全体におけるアプリ体験の意味を踏まえて、どんな価値を提供できるかという視座に立って設計しないと、振り向かれる理由になり得る“体験”なんて生まれないわけです。
もちろん道具立てはどんどん変わるから、次の道具の意味と使い方を理解していくのも大事です。ただ、データやテクノロジーはどこまでいっても道具なので、その習熟が本質ではありません。世の中に対するビューを持って目の前のパズルに向き合ったとき、今ある新しい技術はどう捉えると有効なのか、どんなシナリオを描けば人の心に訴える体験のアップデートができるのか。それが、今度どんなクリエイターにとっても大きなテーマになると思います。
そして、提供された体験に高い満足を得て、その関係を継続することを喜んで受け入れてもらえたら、サブスクリプションにも自然に同意してもらえますよね。そうやって、関係性も単発から長期へとアップデートしていくことができるのです。
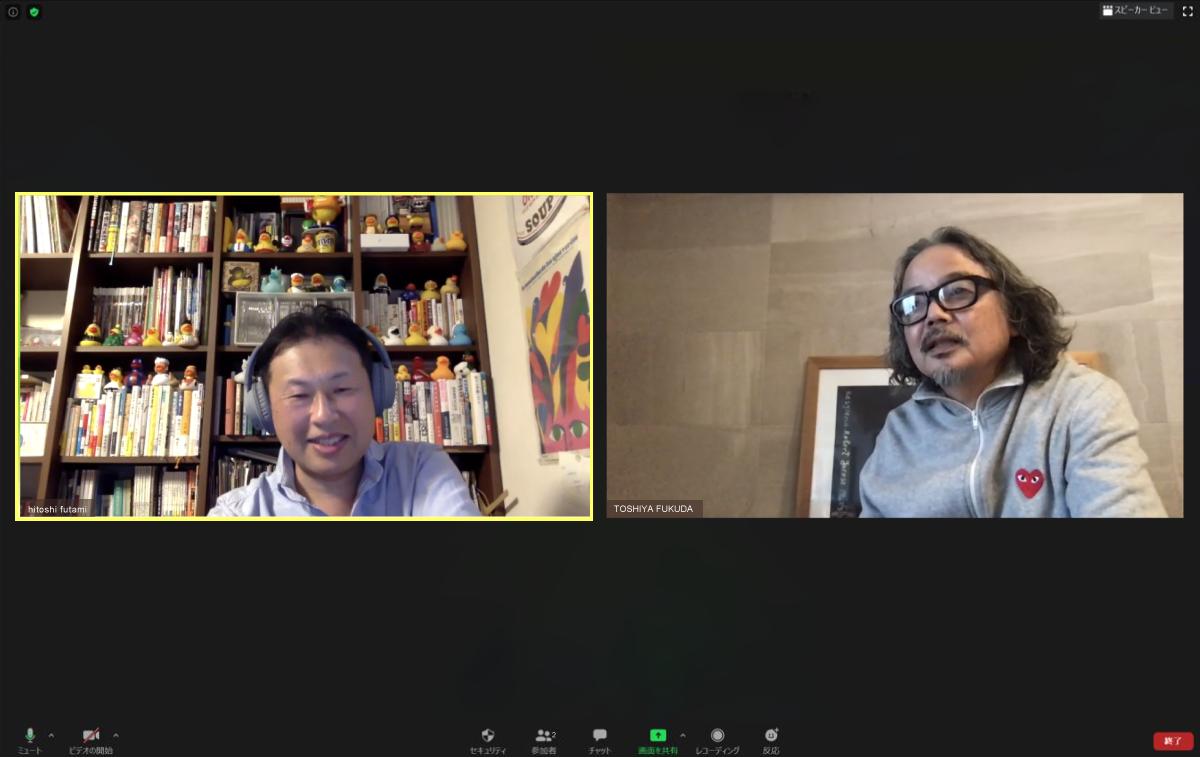
そのデータは生活者価値にどう転換できるか?
- 二見
- 課題が複雑化しているとき、答えではなく問いの提示、問う姿勢こそ必要だというのは僕も強く共感します。それはクライアントに対してだけでなく、生活者に対しても同じような側面があるかなと思います。問いを立てると、議論が生まれる。今スタンダードになりつつある、インタラクションを前提にしたコミュニケーションにおいては、ユーザーからの反応が多いほど次の体験を充実させていけるから、問いかけるのはその点でひとつの手段でもあると捉えています。
で、その反応とはつまり、データですよね。次に、データを使って体験をどう深めていくかを話したいのですが、僕はそのパターンは2つしかないと思っているんです。ひとつは、ストラテジックプラナー(以下、ストプラ)がデータを分析し、得られた結果や示唆に対してクリエイターが掛け算していくという方向性です。以前はその際のアウトプットがコピーやビジュアルなどに限られていましたが、今は道具立ても、データの見立てができたときの打ち手も大きく広がっているので、体験を深めることにつながっています。
もうひとつはさらに一歩進んで、“得られた結果や示唆”というのがもはやリアルタイムで生成されるようになっているので、それを前提としてストプラとクリエイターが一体となって体験の精度を高めていくという方向性。捉え方を間違えると、機械的なABテストのようになってしまいますが、そうではなくて。
- 福田
- 単に売上の最大化を求める改善ではなく、今この瞬間のユーザーにどんな体験還元ができるのか、クリエイティブの視点を加味して発案していく……ということですよね。
- 二見
- そうです。リアルタイムのデータ活用はもちろん有効ですが、そこに左脳的な観点しかないと、予定調和になってしまう。生活者にある種の発見や気づき、セレンディピティを感じてもらうことは難しいですよね。データをクリエイティブの視点で見立てて、問いに変換し、それをまたデータを使って検証する。そうすることで、効率発想の改善では生まれない、生活者にとって驚きや飛躍のある体験の価値を磨いていくことができます。
- 福田
- そこに活きるのが、博報堂が昔から培ってきた生活者発想ですね。
- 二見
- そうですね、僕らには「生活者にとってのベネフィットは何なのか」を見つめる姿勢が根付いているし、クリエイターはその最前線にいると思います。なので、そのデータは生活者にどのように価値転換できるかを常に考えられるはずですし、実際に今、冒頭でお話しした実戦型プロジェクトでも本業においてもその方向性を強く推進しています。
ストプラとクリエイターの協業で、まだ見ぬ着地点を目指す
- 福田
- 冒頭で、「データ×クリエイティブ」の思考や発想にはのびしろがあるものの、まだ課題があるとおっしゃいましたよね。課題のひとつは、従来からのマス広告の領域とデジタル領域の融合がうまくいかないことだと。
- 二見
- そうですね。そして今お話ししている、リアルタイムに近いデータが得られる状況で継続的なクリエイティブを生み出していく、いわば運用型のクリエイティブの仕組みや作り方に順応することも、もうひとつの課題だと思っています。
敏也さんがおっしゃった“完パケ”文化から抜けることの難しさというのが、まさにそれにあたると思うのですが、どうお考えですか?
- 福田
- なかなか高いハードルですよね。磨き上げ、仕上げたものをもって勝負してきた人には、ユーザーとのインタラクションによって変わることを前提としたクリエイティブの感覚はつかみづらいと思います。
YouTubeが登場したとき、多くのプロの映像作家や映像クリエイターは、あんな素人がつくった映像の断片に何の意味があるのかと、まったくピンときていなかった。プロの仕事をなめんなよ、くらい思っていたかもしれません。でも、それがこんなに人気を集め、YouTuberが憧れの職業になるまでになっている。それはやはり、時代に合わせて「いい映像とは何なんだ」という自分のものさしを変化させていかないと厳しいということだと思います。
- 二見
- ものさしを変えていかないと、データを従来のクリエイティブの視点だけで見立てようとしても難しいのでは、と。
- 福田
- そうです。問いとビューの話にも通じますが、ある種の仮説を持ってデータに向き合わなければ、それはただのでかいデータの塊です。「皆が東京に住みたいと思っている」「皆がiPhoneが好きだ」みたいな、世の中に当たり前に流通している定説を、たとえデータでそう出ているとしても「本当にそうなの?」と疑問を呈してみる。本当は違うんじゃないか、という視点でデータにあたると、また違う分析の仕方が思い浮かぶし、定説とは正反対の示唆を見出せるかもしれない、そうなって初めてデータが無限の可能性を秘めたものになるのだと思います。
- 二見
- 同感です。まさにそこがストプラとクリエイターの協業クリエイティブが必須な理由でもありますね。
- 福田
- 仮説立てには世の中へのビューと、クリエイティビティが必要ですから。
2017年、米の家電ブランドWhirlpoolが、貧困による児童の不登校問題の解決に取り組んだ「care counts」というソーシャルキャンペーンを展開しました。IoT搭載の洗濯乾燥機を約50の小学校に配布したところ、不衛生な服を学校で洗えるようになった子どもの登校率が上がったんです。洗濯乾燥機の稼働と学籍番号をひもづけてトラッキングすることで、服の汚れと登校率に本当に因果関係があることを突き止めました。
これは、不登校の子どもに関するデータとにらめっこしていても、絶対に出てこないアイデアです。「もしかして、服が汚れているのが恥ずかしくて学校に来られないのでは?」と誰かが発想し、その仮説を携えてデータ分析を重ねていったから、確度の高い企画に着地したんだと思います。
- 福田
- 自分の時代感覚のもとに仮説を立てられる人が、こういったデータ活用事例を生み出せる。これはけっこう重要なことで、データはすべてのものをつまびらかにするかもしれないけど、相当量のゴミも含んでこの先もっともっと膨れ上がっていくわけですよね。そんなどろどろした巨大な塊に対して、大胆な仮説の槍を刺し貫けるか。そのセンスが、またさらにクリエイターに問われています。
そこでも、博報堂のケイパビリティが活きるはずです。真摯に生活者を見つめて、自分のわずかな違和感に気づけるクリエイターの力と、じゃあその正体は何なのかをしっかり分析できるストプラの力が合わさることで、生活者体験のアップデートを高度に実践するプロ集団になっていくと思います。
新しい絵筆を取ってクリエイティビティを進化させよう
- 二見
- 今の敏也さんの話は、僕も常に感じています。対立構造ではないのに、なぜか昔からストプラとクリエイターの間にはプロセスの分断が生まれやすい傾向がありました。ときにクリエイターの発想は「思い付き」と捉えられてしまうこともあります。この先、個人の主観やセンスも残るとは思いますが、小さな気づきをもとに仮説を立ててデータにあたり、ファクトをつかんで、また仮説を修正して検証していくという流れ自体が、データに寄り添った新しいクリエイティブと言えますね。
- 福田
- そう思います。
- 二見
- チャンスですよね。旧来の広告制作の成功体験にとらわれてインタラクティブな思考に転換できないのは、本当にもったいない。博報堂のクリエイティブは本当に優秀で、もっといろいろな領域でクリエイティビティが発揮できる力があると思います。簡単ではないのは承知だけど、もはや前と同じ方法だけではやり続けられないから。
- 福田
- テクノロジーもデータも、それは道具です。画家にとっての絵筆と同じです。変わりゆく絵筆をどう使うのか。その知恵の戦いです。プログラムも絵筆になる、遺伝子組み換え技術も絵筆になる。そしてデータも絵筆になる。それにいち早く気づき、テクノロジーやデータを体験に変換するクリエイティブ。その領域で成功する博報堂CDも生まれてきています。
- 二見
- クリエイターにとって、これまでデータの海で仮説をつくり、世の中に問いを立てる思考の訓練はあまりされてこなかったと思います。博報堂内の実戦型プロジェクトはまだ継続しますが、この訓練を強化すると同時に、社外のプレーヤーとも協業しながら最新の道具をキャッチアップして、発想と実装の幅を広げていきます。プロジェクトですでに動き出しているプログラムも複数あるので、ぜひまた紹介できればと思います。
※本インタビューはオンラインで実施いたしました。
この記事はいかがでしたか?
-
博報堂 第三クリエイティブ局長
エグゼクティブ・インタラクティブ・ディレクター1990年博報堂入社。
展示設計施工、イベント企画実施業務を経て、2000年より志願してデジタルインタラクティブ領域の業務担当に。以降一貫してデジタル領域を中心に担当。3年前よりクリエイティブ局長に。本文中に紹介されたテクノロジーを活用したクリエイティブ実戦型プロジェクトなど、次の博報堂クリエイティブの“伸びしろ”をつくる会社横断のプロジェクトを多数推進。週末は畑で農作業。デジタルデトックスに励む。
-
博報堂フェロー、CCTO(Chief Creative×Technology Officer)1982年博報堂入社、2003年に独立後、2015年にフェローとして博報堂復帰。
CMプランナーとしてマス広告設計の現場で広告基礎を習得したのち、インターネット時代の到来を予感してデジタル広告の実験的組織「博報堂電脳体」に参加。その後2002年にアジアで初めてカンヌのサイバー金賞を受賞。それが日本のクリエイターの世界的デザイン賞での活躍の先駆けとなる。以降、デジタルやテクノロジーが変えるコミュニケーションやサービスの可能性を提案する役割を担ってきた。渋谷のFabCafeを友人と立ち上げデジタルとリアルを融合させるコミュニティ設計を模索したり、早くから大学でのテクノロジー×デザイン教育に関わってきたり、その活動の場は広い。















