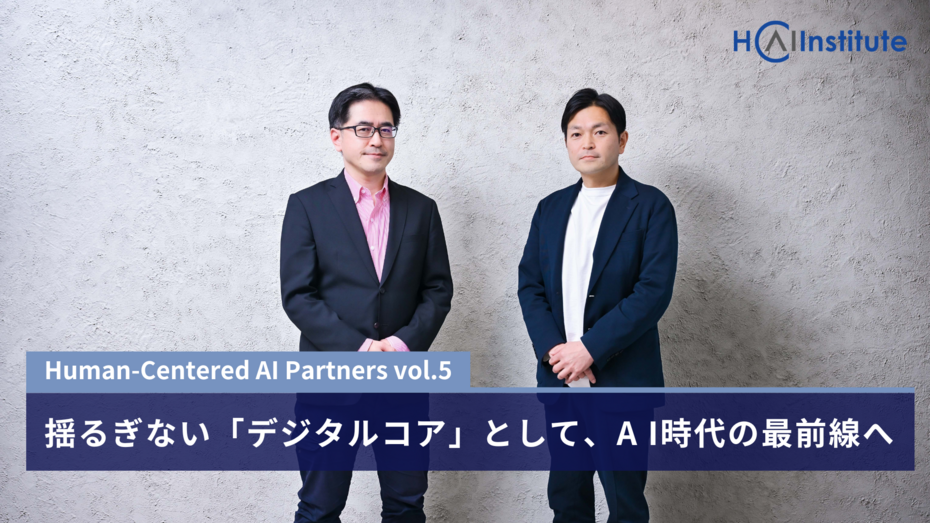

対談〈AI PARTNERS〉第5回──揺るぎない「デジタルコア」として、A I時代の最前線へ
博報堂DYグループのAI研究の拠点「Human-Centered AI Institute(HCAI)」の代表である森正弥が、AIをテーマにしてグループのキーパーソンと対話する連載〈AI PARTNERS〉の第5回。今回は株式会社Hakuhodo DY ONE代表取締役会長の田中 雄三に、今後特に注力する施策やAIを活用した価値提供のあり方などについて聞きました。
連載一覧はこちら
田中 雄三
株式会社Hakuhodo DY ONE 代表取締役会長
森 正弥
博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO
Human-Centered AI Institute代表
“デジタルコア”としての使命を果たす成長戦略
- 森
- DACとアイレップの2社が培ってきたナレッジやリソースをひとつに結集させたHakuhodo DY ONEは、博報堂DYグループの「デジタルコア」として位置付けられる組織となっています。新年度のスタートを切るこのタイミングで、どのような成長戦略を描いているのでしょうか?
- 田中
- Hakuhodo DY ONEはデジタルマーケティングカンパニーであることから、ビジネスの中で一番主眼に置いているのは「広告」です。この広告領域はもちろん重要な軸ですが、企業のビジネス成長のパートナーとしてご支援すべき領域は、広告以外にも多岐にわたります。「デジタル」という言葉の概念も広義になっており、広告の枠を超えて、顧客の事業そのものを支援していく体制を創っていくことが重要だと考えています。

- 森
- マーケティング活動を一気通貫でとらえる「フルファネル」が肝になっているということですね。
- 田中
- おっしゃる通りです。僕らは「広告の領域」と「テクノロジーの領域」の両輪を担わなくてはならないので、広告ビジネスだけではなくマーケティングソリューション領域のビジネスを立ち上げていくことを今期の大テーマに掲げています。
また、いかに少人数で今のパフォーマンスを出せるかも大きな課題だと思っています。社員数を維持しながら売り上げを伸ばし、新しい領域にも進出していく。さらに、広告運用を担当していた人材を、広告ではなくテクノロジーやマーケティングソリューションの領域に移していく。これらが実現できれば、より包括的な顧客支援体制を構築できます。
そして、今日のテーマであるAIの活用も起点になってくるでしょう。直近では、生成AIからAIエージェントへの移行が進んでおり、人材とAIをうまく組み合わせることが求められると考えています。
デジタル人材の育成に注力し、クライアント企業のビジネス成長を支えるパートナーを輩出する
- 森
- AIを活用した価値創出が大きなポイントになりそうですね。既存の広告ビジネスからウイングを広げて、優先的に取り組むビジネス施策や目標を教えてください。
- 田中
- 今期は広告オペレーションや広告サービスの運用、メディア対応などの領域を一つに集約し、さらにはマーケティングソリューション領域にも事業を広げて広告外収益の増加を目指しています。例えばSNSマーケティングで言えば、SNSの広告運用だけではなく、アカウント運用に必要なBPOサービスの提供や、AIを活用してLINEのメッセージを自動配信する「DialogOne®」などのソリューションを軸にビジネス拡大を見据えています。
もう一つは、クライアント企業のEC運営における伴走型支援のサービス提供です。テクノロジーが複雑化するなかで、多くの企業が悩んでいるのはAmazonや楽天市場でのEC店舗の運営や店長業務の管理です。クライアント企業の自社EC運営のニーズをしっかりととらえ、それに応じた伴走型のECコンサルティングを手がけていく必要性を感じています。
また、これらすべてに紐づいてくるのがクリエイティブです。商品の魅力を最大限に引き出す商品撮影や説明文の作成、さらには販促施策としての動画制作やSNS運用まで、クリエイティブの作り込みが大事になります。そして、これらのプロセスにAIを活用することで工数削減に取り組むことも必要です。
- 森
- 広告やマーケティングの領域は非常に広がっており、それに合わせて私たちのビジネスも拡大していくことが大事だと認識しました。単にモノを売るだけでなく、サービスとしての運用が求められる時代になっている今、CRMやアカウント運用、ECサイトの管理や店舗業務のサポートなどあらゆる業務を引き受けていくことが必要不可欠だということですね。

- 田中
- そうですね。広告に関連するDX領域では、単に自社のツールを販売するのではなく、マーケティング領域で多く利用されるツールの知識や運用スキルも求められますし、AIを活用するならプロンプトエンジニアリングのスキルも大切になります。こうした状況で鍵になるのが「デジタル人材」です。
僕らは、旧DACや旧アイレップの頃から広告運用のために大量採用を実施してきたため、「人材教育」にはかなり力を入れています。SQLの習得にいたっては「データ塾」というのを立ち上げ、年間で100~200名程度の社員が受講しています。その中で有望な社員はさらに半年間の実地研修を行い、SQLを実践で使えるようになるまで指導するのです。
SQLでデータ分析できるようになると、改善点を見つけて「同じことを繰り返す」のではなく、「より良くしていく」ことが可能になります。これにより、CRM運用を担当している人がデータを活用して、お客様のビジネス成長を支えるパートナーになることができるわけです。最近ではプロンプト研修も実施しており、累計で800人以上の社員が参加しています。
- 森
- 800人以上がプロンプト研修を受けているのはすごいですね。多くの人材がAI活用のスキルを身につけ、業務効率化や生産性向上に取り組めているのは、それだけ会社全体でAIへの関心が高まっていることだと言えるでしょう。
- 田中
- 広告業界が従来の「マージンビジネス」から脱却し「フィーモデル」への転換が求められるなかで、社内で研修を受けた人材がスキルを向上させ、担当できる領域を拡張できれば、市場でも高く評価されるでしょう。CRM領域やCDP、データ活用領域など、さまざまな分野に対応できる人材を企業に常駐させ、業務を担う常駐型モデルの拡大に注力していきます。
Dify導入で社内のAI活用が活発化した
- 森
- AI人材やデジタル人材の育成、デジタルスキルの向上といったテーマはよく取り上げられますが、どうしても「どのAIツールが使えるのか」「どのデジタルサービスが活用できるのか」といった話に留まりがちです。しかし重要なのは、事業のウイングを広げることに加え、さまざまな業務運用をどのように最適化し、引き受けられる体制を整えるかという視点です。人材の育成においては、単なるツールの習得ではなくより実践的なスキルアップを目指し、組織全体のアップスキリングを推進していくことが大事だと感じました。

- 田中
- AIの活用においては、業務効率化だけでなく「AIでどのように収益を生み出すのか?」という視点が非常に重要です。AIを活用できる人材がいなければ、そのスタートラインに立つことすらできないでしょう。Hakuhodo DY ONEでは社員が安心して生成AIを活用できるセキュアなクラウド環境として、「HAKUNEO ONE」という環境を整備しており、累計UU(ユニークユーザー)が全社員およそ3,000人のうち2,900人を超えています。
- 森
- 大企業でも生成AIの基盤を全社導入したというケースは増えてきているものの、日常的に活用している社員の割合はそれほど高くないのが現状です。導入が進んできている金融系の企業でも、実際に業務で使用しているのは社員の10~15%程度という話もあります。
- 田中
- 当社で具体的にAI活用が進んだのは、ノーコードツールであるDifyの導入が大きな転機となりました。ファイルを完全にオープンにしつつも、情報漏洩のリスク回避や機密情報を守りながら、DifyでAIアプリケーションを作れる環境を構築したのです。その結果、現在では230人ほどの「Difyクリエイター」と呼ばれる人材が生まれました。
運用面で工夫しているのは、彼らが作成したツールを毎週ランキング化していることです。ランキング上位に入ると、社員の大きなモチベーション向上につながるわけですね。特に人気のあるツールの一つが「0次分析」で、これはURLやターゲット層、競合情報などを読み込ませることでクライアント企業の商品情報を取得し、ペルソナ分析を自動で行うことで、効果的な広告戦略を立てることができます。
こうした取り組みからも分かるように、非エンジニアの広告運用を担当するメンバーが次々とアプリを開発し、それが社内で広がっている状況です。今ではプロンプトを書くこと自体が身近なものになっていると感じており、Difyの導入がきっかけでAIの社内活用が加速したのは大きな成果でしたね。
- 森
- そういう意味では、AIスキルを習得することで、今までやってこなかった業務にも挑戦できるようになると言えるでしょう。ルーティンワークをこなすだけではなく、AIの活用で自ら業務のシステム化に積極的に取り組める人材が大事になると思います。
- 田中
- まさにそうですね。理想を言えば、全員がプロンプトを扱えるようになることを目指したいのですが、現実的には難しい部分もあります。ただ、その取っ掛かりとしてDifyの導入は非常に大きかったと思います。
また、社員とAIが一緒に働く上でAIエージェントの普及はすごく有用だと思う反面、人間がいないと片付かない問題はすごくたくさんあります。つまり、AIを理解しているフロントラインやサービスライン、ソリューションラインが重要だと考えています。
AIが普及した後こそ企業競争力の明暗が分かれてくる
- 森
- AI時代に働くうえで、どのようなマインドセットが重要だとお考えですか?
- 田中
- 当社では、今までは広告営業と広告オペレーションで完結しており、職種の選択肢が限られていましたが、SQLやプロンプトエンジニアリングなど、新たなスキルを身につけることでキャリアの選択肢を広げる取り組みを行うようになりました。
もし自分のキャリアを成長させたいなら研修を受け、スキルを習得した上で異動することも可能なため、「転職せずに、社内で違う部署へチャレンジしよう」というマインドの醸成につながっていると考えています。

- 森
- 「この仕事をしているから自分はこういう人間だ」と決めつけて、何かを求めるために会社の外に出るのではなく、AIやデジタルを活用しながらスキルを磨き、社内で新しい挑戦ができる風土を作っていくということですよね。そうすることで、個人のキャリアが広がり、会社としてもより大きな可能性を生み出せる。
- 田中
- 今後、一般企業がAIを標準的に使いこなせるようになっていくと、いずれAIコンサルティングや常駐型モデルの需要は減っていくわけですが、企業が自社でAIを活用できる人材を育成し、AI活用の浸透が進むのはどのくらいの期間で実現すると思いますか?
- 森
- 現在の事業や業務をAI化していく過程はおそらく2~3年で完了すると思います。それは、AIの汎用性向上によって、「とにかくなんでも放り込んで判断してくれる」というのが一般化しているからです。これからAIエージェントが登場してくれば、さらに利用用途が広がっていくと予想されます。
しかし、人間は基本的に「当たり前になると違うことをやりたくなる」という習性を持っており、クライアント企業から「何かAIでこういうことやりたい」というニーズが生まれると、既存ビジネスの枠を超えた取り組みを始めなければなりません。
そのため、自ら当事者として新しいことに挑戦し、既存のビジネスを変えていくことが必要になるので、「AIが浸透した後に企業競争力の明暗が分かれてくる」と考えています。
- 田中
- 僕自身もDAC時代からテクノロジー領域を牽引し、データの利活用を通じて企業のマーケティング活動の支援を手がけてきました。そして今後はAIの利活用が重要になってくるわけですが、データに精通した人材がいても、そもそもマーケティングの知識がなければ意味がありません。
当社の強みは、マーケティングに強いAI人材が多数在籍していることです。他の企業との差別化を図るためにも、AIを活用して生活者発想に基づいたマーケティングができるという信頼をいかに築けるかを意識したいと思っています。

生活者と企業の橋渡しとなり、両者を効果的に結んでいくAIエージェントを目指す
- 森
- AIエージェントによる付加価値の創出を考えると、一般的にはDifyやRAGといった技術が進化していくことで効率化や自動化が進むという文脈でしか語られていません。一方で、Hakuhodo DY ONEが提供するAIエージェントは単なる効率化や自動化の枠を超えて、生活者と企業の間に立ち、両者を効果的につなぐ役割を果たすことができるという点が大きな特徴です。
例えば「AI東京ドームシティ新聞」や「DDDAI」などの先行事例のように、企業が生活者について理解を深め、生活者が企業やブランドの理解を深めるのにAIエージェントを活用するアプローチは、我々ならではの強みだと言えるでしょう。
- 田中
- リード獲得やCRMに蓄積したデータ活用、デジタルの広告運用など、全ての領域においてマーケティング活動が必要不可欠です。そういう意味では、当社がこれまで培ってきた独自の強みやノウハウを持ち、マーケティングに強いAI人材がたくさんいるという付加価値を、Human-Centered AI Institute(HCAI)で積極的にアピールしてほしいなと感じています。
- 森
- 今は多くの企業が日進月歩で進化するAIに追いつこうと必死になっています。次々と新しい技術が出てきているので、正直なところ「誰にとっても勝ち目がない世界」だと感じる部分もあります。だからこそ、我々はその中で何を強みにしていくかをしっかりと見極めていかなければならない。
例えば医療の分野では、AIが画像診断に用いられ、診断の精度やクオリティを高めていますが、それが可能なのは、MRIやCTなどの高精細な画像を撮影できる医療機器の進化があってこそです。どんなに賢いAIがあっても、元の画像が粗ければ正しい診断はできません。AI単体ではなく、自社の強みとの融合が不可欠です。
- 田中
- プロンプトエンジニアがたくさんいるだけでは、どうしても途中で行き詰まると思っていて、思考が停止した時こそ、マーケティングに特化したAIアプリケーションが求められるわけです。そういう意味でも、「AIを活用する際にはHakuhodo DY ONE」と、企業や顧客から、第一想起してもらうようにプレゼンスを発揮していくことが大事だと考えています。今回、HCAIという旗が立ったので、博報堂DYグループ全体でAIによる新しいビジネスの可能性を見出す議論を推進できるようにしていきたいですね。
この記事はいかがでしたか?
-
株式会社Hakuhodo DY ONE 代表取締役会長2002年、他業界を経てデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現・株式会社Hakuhodo DY ONE)に入社。営業統括、開発部門統括を歴任。取締役、常務取締役を経て、2022年に代表取締役社長に就任。2024年4月より現職。デジタル広告運用、データ・テクノロジー・AI活用によるソリューション開発、人材育成など幅広い領域で国内外のデジタルマーケティング支援に従事。
-
博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO
Human-Centered AI Institute代表外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用したDX、企業支援、産業支援に従事。東北大学 特任教授、東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、日本ディープラーニング協会 顧問。著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。


















