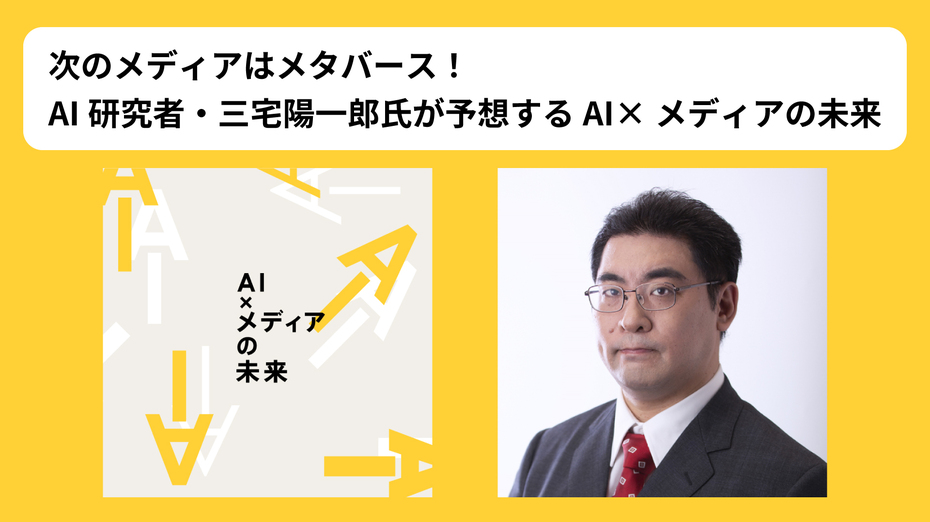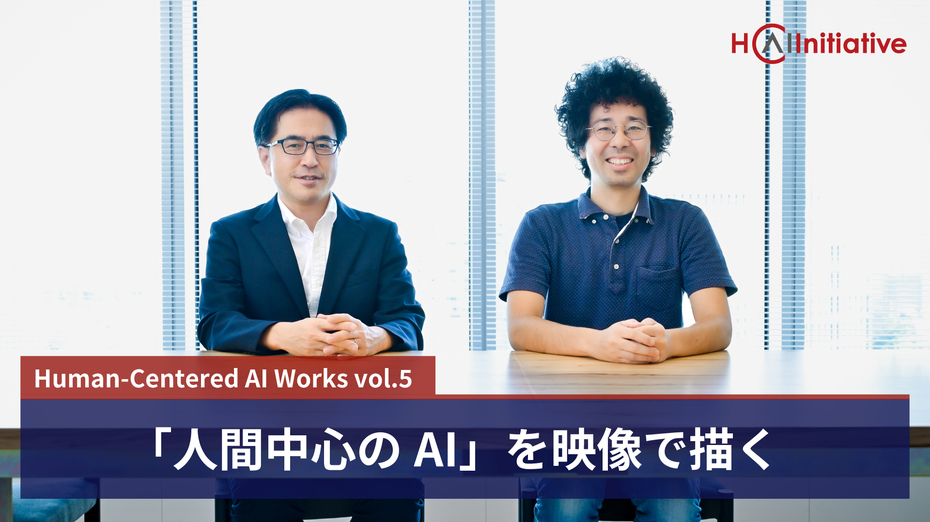日本に上陸した映像コンテンツ配信サービス〈FAST〉──「完全無料」「ワンテーマ」「編成配信」というスタイルがもたらす新しい視聴体験
10年ほど前にアメリカでスタートした映像配信サービス〈FAST〉。無料で配信される映像をテレビモニターで見るこのサービスには、従来の地上波テレビやオンデマンドサービス、あるいはインターネットの動画メディアのいずれとも異なる特徴があります。FASTの概要とその可能性について、日本で初めてこのサービスを手掛けたBBMの福崎伸也氏と、テレビ広告ビジネスに詳しい博報堂DYメディアパートナーズの田代奈美、内藤匠哉に語ってもらいました。
福崎 伸也氏
BBM 代表取締役CEO
田代 奈美
博報堂DYメディアパートナーズ
ナレッジイノベーション局 局長/メディア環境研究所 所長
内藤 匠哉
博報堂DYメディアパートナーズ
AaaSビジネス戦略局 戦略二部 部長/TV AaaS Lab 編集長
ワンテーマでコンテンツを編成する
──FASTはこれまで日本になかった映像サービスです。はじめに、その概要をご説明いただけますか。
- 田代
- FASTは「Free Ad-supported Streaming Television」の頭文字をとったもので、インターネットにつながったテレビモニターに無料で配信される映像サービスを意味します。
FASTがアメリカでスタートしたのは10年ほど前からです。アメリカではもともと、有料のケーブルテレビでコンテンツを見るスタイルが主流だったのですが、2000年代に入って放送局がインターネットでのコンテンツ配信を始め、その後SVOD(サブスクリプションビデオオンデマンド)のサービスも始まりました。さらに、広告を入れることで割安でサービスを提供するAVOD(アドバータイジングビデオオンデマンド)も拡大しました。
FASTは、AVODがさらに進んだものと考えられます。アメリカでは「Tubi」「Roku Channel」「Pluto TV」の3つが、「3大FASTプラットフォーム」と言われています。
- 福崎
- もっとも、アメリカでもFASTの定義にはややあいまいなところもあって、AVDOのように完全無料ではないサービスをFASTに含めるケースもあります。日本では、あくまでも「完全無料配信」という点にこだわってサービスを展開しています。
──視聴者はどのようにしてFASTを見るのですか。
- 田代
- SVODやAVODは「オンデマンド」、つまり視聴者が個々のコンテンツを選んで見る仕組みになっています。それに対して、FASTにはチャンネル側の「編成」があって、コンテンツは自動で流れます。その点では、地上波テレビに近いと言えますが、最大の違いはチャンネルごとにテーマが決まっていることです。それぞれのチャンネルには、料理、旅、ペット、スポーツといったテーマがあって、ワンテーマの中でコンテンツが編成される。それがFASTの大きな特徴です。

- 福崎
- アメリカでは2000以上のFASTチャンネルがあるので、誰もが自分好みのテーマを選べるようになっています。
- 内藤
- ハワイの海の風景ばかりを集めたチャンネルや、焚火の映像だけを流すチャンネルなどもあるようですね。ターゲットを絞ったニッチなテーマの中でコンテンツ編成をする点が、総合編成が基本の地上波との大きな違いと言えそうです。
「リーンバック」という新しい視聴態度
──視聴者はどのようなスタイルでFASTを見ているのでしょうか。
- 福崎
- FASTの視聴態度を示す言葉としてよく使われるのが「リーンバック視聴」です。
ゆったりとソファーにもたれて、リラックスしながら心地よくテレビを眺めるというスタイルです。
この視聴態度は、オンデマンドサービスやインターネット動画配信サービスで映像を見る場合の「リーンフォワード視聴」という言葉としばしば対比されます。自分でコンテンツを選ぶサービスや課金サービスの場合は、「コンテンツを見る」というスタンスを明確にして、テレビモニターに意識を集中させることになります。しかし、そのような視聴スタイルを長時間続けるのは疲れるので、いわば「息抜き視聴」も必要になります。その息抜き視聴のメディアとしてFASTが選ばれるケースも多いですね。
- 田代
- オンデマンドやインターネット動画配信サービスは、自分でコンテンツをその都度選んだり、視聴コンテンツの傾向によりレコメンドされるコンテンツを視聴することが主だと思います。一方、地上波テレビは選ばなくても番組が流れ続けますが、総合編成なので、視聴者にとって興味がないものもその中には含まれます。
FASTの場合は、チャンネルさえ選べばコンテンツを選択する必要がなく、しかも流れてくるのは好みのテーマのコンテンツだけです。自分が好きなものをずっと流しておいて、心地よい時間を楽しみたい──。そんな生活者にとって、とても便利なサービスと言えると思います。

- 内藤
- これまでになかった視聴体験が得られるし、「リーンバック」というキーワードも今の時代に合っていますよね。ほかの映像サービスと共存することもできそうです。
- 福崎
- アメリカでは実際に共存していますね。もちろん、日本でも共存可能だと思います。私たちが集めたデータを見ると、夕方から8時くらいまでFASTの視聴数は大きく伸びるのですが、8時を過ぎるとがくんと視聴数が下がります。さらに、その後11時くらいになると再び視聴数が上がってきます。
おそらく8時から11時の間は、オンデマンドや地上波でコンテンツを楽しむ人が多いのだと思います。そして11時くらいから就寝までの間は、リーンバックのスタイルで好きなコンテンツを眺めていたいと考える人が増えると私たちは考察しています。アメリカでは、FASTはほかのテレビ視聴を補完するメディアであると言われることがあります。日本でも、そういうスタイルが定着していくと考えられます。
FASTに適合する広告のスタイルとは
──BBMが日本国内で初めて本格的なFASTのサービスを始めたのは、2024年8月とのことです。サービス開始の経緯についてお聞かせいただけますか。
- 福崎
- 私が、コンサルティングファームから独立してコンテンツ開発などを手掛けるBBMを設立したのが2017年のことです。その後、FASTという新しい映像サービスがアメリカで人気を集めていると耳にして、23年にFAST事業をコンソーシアムの形で進める会社を立ち上げ、24年にサービスを開始しました。

これまで、料理店、エンタメ、旅行、ペット、時代劇、キャンプ、キッズ、健康、ビジネス、韓流、フードをテーマにした計11チャンネルを展開してきました。4月にはこれが20チャンネルまで、今年中に30チャンネルまで拡大する予定になっています。現在のユーザー数は、20万人を超えています。
──それぞれのチャンネルはどのように運営されているのですか。
- 福崎
- 私たちが配信の仕組みを提供し、チャンネルの運営は個々の企業にお任せする。そんなモデルになっています。チャンネル運営者が自らコンテンツを制作したり、コンテンツホルダーと協力してコンテンツを集めたりして、プラットフォームで無料配信する。それが、私たちが展開しているFASTサービスです。
──広告モデルについてもご説明ください。
- 福崎
- 現在は、デジタル広告が自動的に配信されるいわゆるプログラマティックの仕組みになっていて、5分おきに30秒のCMが流れます。
これに加えて今後は、広告主に個別にアプローチして、チャンネルごとに最適なCMを流す仕組みをつくる構想があります。このモデルをつくるにあたっては、博報堂DYグループのような広告会社との協業が必須であると考えています。
- 内藤
- FASTというこれまでになかったプラットフォームの中でどのような広告展開がありうるかを、まさに福崎さんとディスカッションさせていただいているところです。動画広告枠や番組連動CMのようなマーケティングコミュニケーション領域の取り組みはもちろんのこと、私たちが「オーディエンスアクション」と呼んでいる生活者の視聴後の行動をデザインするような取り組みも実現させていきたいです。
──FASTに広告を出稿するクライアントには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
- 内藤
- 最近は単純な視聴単価の効率だけでなく、実際に広告を注視している人の割合や掲載されるコンテンツの内容、同じコンテンツ内で掲載されている他社の広告など、掲載面や視聴の「質」も重視されるようになっています。注視率は重要な指標ですが、一方FASTにおけるメディア価値は別のところにあると僕たちは考えています。テレビをじっくり見るというよりも、リラックスして眺めている中で、気に入った情報があったらスマートフォンで検索したり、後日店舗に足を運んだりする。そんなスタイルの広告展開がFASTには向いていると思います。例えば広告主が指名検索をテレビCMの広告効果として求めている場合、必ずしもスマホとダブルスクリーンでリーンバック視聴しているというスタイルはマイナスではないのです。その点では、従来の地上波テレビに近い面もありますが、チャネルごとのテーマが明確なので、ターゲットがより絞られる点に大きな違いがあります。
- 福崎
- 例えば、時代劇のようなシニア層向けのチャンネルであれば、健康食品や健康器具、旅行といったカテゴリーがフィットすると考えられます。
- 田代
- いわゆる「コンテクスチュアル広告」と呼ばれる手法ですよね。それぞれのチャンネルの文脈に合った広告を流すことで、大きな効果が期待できそうです。
- 内藤
- コンテキストに合った商品やサービスの情報、あるいはチャネルのコンテンツにマッチしたクリエイティブを流すことで、視聴者の心を捉える。それがFASTにおける広告展開では非常に重要になりそうです。実際AaaSでテレビCM効果の分析を行ったところ、中学受験のドラマやクイズ番組で流した塾のCMでものすごく検索数が増えたという事例もありました。
- 福崎
- FASTは数千万人の視聴者がいるメディアではないので、よりターゲットを絞って、より深いメッセージを発信していく手法が合っていると思います。これまでの映像系メディアにはなかった広告手法もありうるかもしれません。広告会社やクライアントの皆さんと対話しながら、新しい手法を生み出していきたいですね。
テレビモニターがもつ大きな可能性
──今後の展開の見通しをお聞かせください。
- 福崎
- チャンネル数を増やして、FAST体験を広げていくことが今の一番の目標です。
課題はコンテンツの確保です。
アメリカでは、IP(知的財産)の権利処理の仕組みが整っているので、過去の映像コンテンツをデジタル環境下で配信することが比較的容易です。一方、日本ではコンテンツのデジタルシフトにさまざまなハードルがあります。そういったハードルを乗り越えて、コンテンツ活用をよりスムーズにできる道筋をビジネスパートナーと一緒に探っていきたいと思っています。
- 田代
- 日本には豊富なコンテンツ資産があります。ドラマ、アニメ、特撮もの、時代劇──。そういった過去のコンテンツが生活者の目に触れないのは、とてももったいないことです。コンテンツ資産をどんどん活用できる仕組みが整うといいですよね。
- 内藤
- 僕は、福崎さんと一緒に「FAST×ローカル」の可能性を追求していきたいと思っています。地方の放送局と協業して、エリアコンテンツをFASTで配信していくことができれば、地方の生活者やクライアントに大きなメリットを提供できると考えるからです。

- 田代
- テレビモニターの可能性は年々広がっています。博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所の調査では、インターネットに接続しているスマートテレビの所有率はおよそ6割、テレビをインターネットに接続できるコネクテッドデバイスの所有率はおよそ4割となっています。「テレビ×インターネット」でできることはたくさんあると考えられます。
先日アメリカで開催されたCES(コンシューマーエレクトロニクスショー)では、テレビモニターに絵画作品を映す機能を搭載したテレビが紹介されていました。FASTもまた、テレビの新しい使い方を提示するサービスの1つだと思います。メディア企業、コンテンツ企業、広告主、広告会社、そしてプラットフォーマーといったプレーヤーのそれぞれに大きな可能性が開かれている。そんなふうに思います。
- 福崎
- FASTを日本で普及させていくには、総合マーケティング企業の力が必要です。
博報堂DYグループの皆さんとお話をさせていただいていつも感じるのは、新しいことにどんどんチャレンジしようというカルチャーが定着しているということです。これまでになかったFASTサービスを広げていくにあたってパートナーシップを組める仲間だと感じました。
ぜひ、FASTをともに普及させて、新たな映像体験を提供していきたいですね。
- 内藤
- ありがとうございます。本日お二人と話をする中で、日々刻々と変化する動画市場における新しい視聴体験や新しい市場の可能性を感じることができました。私は自社のアイデンティティである「メディア効果をデザインする」という言葉が大好きです。今後福崎さんをはじめとした動画市場の開拓者のみなさんと様々な取り組みにチャレンジしていきたいです。福崎さん今後ともよろしくお願い致します!
※出演者の肩書は取材当時のものです。
この記事はいかがでしたか?
-
 福崎 伸也氏BBM 代表取締役CEO
福崎 伸也氏BBM 代表取締役CEO
-
博報堂DYメディアパートナーズ
ナレッジイノベーション局 局長/メディア環境研究所 所長
-
博報堂DYメディアパートナーズ
AaaSビジネス戦略局 戦略二部 部長/TV AaaS Lab 編集長