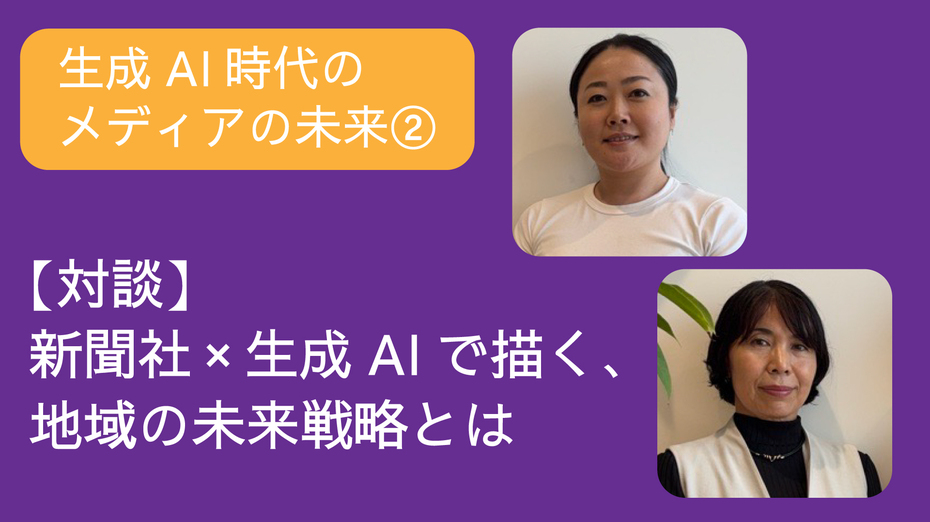EdTechが変えていく教育の未来 【Media Innovation Labレポート47】
コロナ禍を経て急成長したEdTech市場。EdTechの普及は教育環境にどんな変化をもたらし、幼少期からEdTechに触れてきた子どもたちが成長した未来には、どんな製品やサービスが求められるのか。EdTechを取り巻く現状から未来予想まで、博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所の小林舞花と、Hakuhodo DY ONE 高橋二稀が語り合います。
■全世界で急速な成長を遂げているEdTech市場
- 高橋
- EdTech(エドテック)について、まずは私たちが認識している定義について押さえておきたいと思います。
EdTechはEducationとTechnologyを組み合わせた造語で、主な領域は、幼児教育から生涯学習、社会人雇用や研修も含めた広義での“教育”となります。たとえば教材や授業、テスト、自宅学習など学習者向けのサービスや、教員や教育機関など学習を管理する側のシステム、また教育関連の情報の検索や奨学金のマッチング、さらには社会人の能力評価、資格認定などもこの領域に含まれます。
- 小林
- ここ数年、EdTechという言葉は“GIGAスクール構想”という言葉とともによく聞かれるようになり、国内はもちろんグローバルで見ても、コロナ以降に著しい成長を遂げています。一方で、2024年にAIが台頭してきてからはEdTech関連の投資が減少傾向にあるのも事実です。
- 高橋
- 確かに生成AIにはさまざまな領域が含まれていて、規模の大きいEdTech関連企業の倒産もありました。市場としては、2023年の2205億ドルから、2026年までに3258億ドルに達すると予測されていて、2020年のEdTechの盛り上がりに比べると、若干成長が鈍化しています。ただ、通信速度の向上や新興国での教育需要の高まりもあって、需要はある程度続くと考えられます。
- 小林
- もともと「EdTechの波が来る」と予測されていましたが、コロナ禍でさまざまな製品やサービスの導入が予想以上に急速に行われました。仕事や教育などが急遽オンラインに移行し、「コロナ禍でも教育を止めない」という動きや、2021年にユネスコが発表した、経済的物理的な教育格差の解消を目指す「教育2050」という目標にもつながりました。

ちなみにコロナ禍前の2015年には、すでにモンゴルの15歳の少年がハーバード大学とMITが共同で立ち上げたオンラインシステムで学び、学費免除でMITに入学したことがニュースになったり、日本の小学生がオンラインで海外の大学の講義を受講するとか、教授の指導を受けているといった事例もあります。
■各国の課題やニーズに合致したEdTechサービスが次々と生まれている
- 小林
- ではここから、世界と日本におけるEdTech市場の現状を見ていきます。
欧米では、生成AIを導入した先生向けのアプリやソフトが多数生まれています。AI導入の指南をする教材動画も増えていて、授業でどうAIを活用していくかという議論もさかんです。
実際多くの現場で、生徒や保護者との連絡や授業用の教材制作、テスト作成など、バックエンドの業務がAIに次々と置き換わり始めていて、残業時間を削減しつつも先生が生徒と関わることに時間を割けるようになっているようです。たとえば、一般に出回っている動画などを含む教材を生徒の学習レベルに合わせて生成したり、それを基にしたテスト問題を簡単に作成できるソフトもあります。
現場の教員にとっては非常に便利な技術として歓迎されているようですね。
そもそも欧米では習熟度別に授業を進めることが一般的でしたが、今後はそうした学習への伴走がさらに簡単になっていくことが期待されています。
アジア各国ではどんなことが言えますか?
- 高橋
- EdTech市場が特に進んでいるのがインドです。
インドは、理数系の優秀な人材がグローバルで多数活躍している印象が強いですが、国内においては深刻な就職難という課題があります。その結果、個人の努力でより水準の高い教育を受けるニーズが高まっており、最近ではより安価で高品質な授業を受けられるオンライン学習サービスが人気です。こういった企業は月謝ではなく広告による収益化を行っていたり、インド国内の試験に特化している点も特徴的です。ローカルで、かつ緊急度の高い課題に最適化したサービスであることが、コロナ禍以降も継続的な利用に繋がっている大きな要因だと思います。
一方中国は、コロナ禍で市場が一変しました。
そもそも教育市場の規模が非常に大きく、教育熱や親の経済的負担が課題となっていました。そのため国が家庭外での学習サービスに対して規制をかけ、結果的にEdTech企業の倒産や投資の縮小が起きています。ただ、その中でも学校の主要科目以外にフォーカスしたり、授業をパーソナライズするなど、柔軟な教育も広がっているようです。
韓国は、私教育が一般化しており、他のアジア諸国同様、教育格差が生まれています。それに対応する形で、来年から主要教科で導入されることになっているのが、AI教科書です。
AI教科書には、動画やクイズ、ARやパーソナライズコンテンツなどのほか、教員に対する指導のアドバイスもAI搭載されており、指導力の底上げにも期待が寄せられています。
環境が似ている日本に進出する韓国企業も少なくなく、日本企業と事業連携する事例もあります。また、韓国発の数学学習アプリQANDAは日本でも人気です。数学の問題を写真に撮りアップロードするとAIやオンラインの回答者が解説してくれるというもので、実際に私の知人の高校生も、家庭での自主学習に活用していると言っていました。
■日本におけるEdTech市場の概況
- 小林
- 日本においては、かねてより進められていたGIGAスクール構想(教育現場でのICT環境整備構想)がコロナ禍で前倒しされ、令和6年度、小学校1年生から高校3年生までの“全校1人1台端末”が整備完了しています。
ただ、2022年度に実施された全国学力学習状況調査結果によると、PCタブレットなどのICT機器を「ほぼ毎日」もしくは「週3回以上」「週1回以上」使用している児童生徒が8割を超えている一方で、「月1回以上」や、「月1回未満」という回答も小学校で16.6%、中学校でも19.2%と、学校間の格差があります。とはいえ、特定の支援を必要とする子どもにだけでなく、全員が端末を利用できるという公平性が担保されたことは、インクルージョンの視点からも評価すべきかと思います。
ちなみに、2020年頃に端末を導入した学校はそろそろ機器の入れ替えのタイミングを迎えるようで、メーカーは学校からのフィードバックを受け、子どものニーズに合わせた機器の改良を続けているようです。たとえば、ポートに鉛筆を刺してショートさせてしまったり、机の上から落としてしまうケースもあり、子どもの使用を前提とした堅牢性が求められています。また、タッチペンにわざわざ持ち替えなくとも、鉛筆をそのままタッチペン代わりに使用できるような端末も新たに出てきています。
EdTech市場への投資は、全体としては確かに減少傾向にありますが、市場に勢いのあるときは実験的な製品やサービスが数多く生まれるもので、それらのすべてが必ずしも使いやすいとは限りません。今後は淘汰、集約のフェーズに入っていくと考えると、使い手にとっては喜ばしいことかと思います。
- 高橋
- 文科省が進めるオンライン学習システムにのっとった「MEXCBTテスト」も全国的に実施され始めています。
オンラインならではの、動画や音声を使った記述型の柔軟なテスト形式は今後ますます手軽になっていき、テストをもとにしたデータの利活用も進められていくでしょう。学習進度のデータの他にも、出欠や学習指導履歴など質的なデータを含む情報が、大きく“教育データ”に含まれていくことになります。データ分析はかなり複雑化していくでしょうし、個人的には今後どういった基盤やテクノロジーが活用されていくかに、大いに注目しています。国が考えるデータの活用先としては、学校や家庭や教育機関に加え、民間企業も含まれています。EdTech関連企業も、その流れにうまく乗っていくことで成長につながるのではないかと、期待感を持っています。

■手軽に楽しく効果的に学べて、学習の可能性を広げてくれるEdTechの具体例
- 小林
- では、より具体的なEdTechのサービスについて見ていきたいと思います。
まず代表的で、多くの人になじみがあるのはオンライン学習かと思います。
時間や場所にとらわれずインターネット上で授業や研修が行われるというもので、コロナ禍をきっかけに、デジタル教材で学習履歴を確認できたり、思考のパターンや個人の課題に対応した問題が出てくるといったサービスが数多く生まれました。
- 高橋
- 中でも家庭学習向けのサービスは、コロナ以降も人気が定着していますね。
AIやオンラインで、遠隔にいる教師、あるいは同級生と、教材を共有したり出題してもらったり、あるいは自分だけの学習ゲームを作ったりするサービスが成長しています。
先ほどの韓国発のアプリQANDAのほかにも、文章や写真、音声から自分のまとめノートや暗記カードをAIが作成してくれるalgorというサービスや、他の学生が作成したノートや暗記カードが見られる学習プラットフォームKnowunityというのもあります。
- 小林
- 自宅学習が基本の学校や、不登校の子どもの受け皿になっているような現場は、そうした学習スタイルと特に親和性が高そうですね。
コンテンツやプログラムへのARVRの活用も進んでいて、より感覚的で実際の体験に近い学習、業務の習得や訓練、疑似体験学習を行うことも可能になっています。たとえば医療現場や災害現場、宇宙空間など、現実ではなかなか体験することが難しいような分野や場所での技術の習得も、今後より簡単になっていくでしょう。
- 高橋
- 生涯学習の領域においては、ショート動画やショートポッドキャストアプリなど、手軽に短時間で学習できるサービスが増えている印象です。TikTokでは教育系のコンテンツも人気で、有名な研究者や教育系のタレントが身近な題材をテーマに作成した解説動画は、楽しく気軽に専門知識を勉強でき、支持を集めています。手軽に頭に入ってくる教育エンタメは特に忙しい社会人や若者にとって需要が高く、今後も長く息が続くコンテンツかと思います。
- 小林
- ゲーミフィケーション、つまりゲーム的な要素を加えることで、より自発的、能動的な学習を可能にしているんですよね。また、特に語学学習においては、かなり柔軟に正誤を判断し、模範解答以外の解答も許容するものが多いようです。実践的な会話が身につくうえ、学習意欲の維持にもつながる。マイナー言語の習得も容易になり、学びの可能性が多いに広がりそうです。
- 高橋
- 私は生成AIを使った英語のスピーキング学習アプリを利用しています。生成AIだとちょっとしたスペル間違いも許容してくれるし、生身のネイティブの先生と話す際の恥ずかしさや緊張がなくなる。スピーキングの挑戦ハードルが低くなりますね。
ゲームフィーケーションに関しては、キャラクターを使った学習アプリなどもあります。学習継続の誘導が巧みで、スマホのウィジェットにキャラクターが出てきてリマインドをしてくれるのですが、キャラクターの表情やメッセージが豊かで、学習をしなければと思わせてくれます。IPとしてもしっかりマーケティングを行っており、SNSでの発信やグッズ展開も積極的です。生活の一部に勉強習慣が自然と入り込むような体験設計をしていて、こうした工夫は今後ほかの学習アプリも求められていくような気がします。
- 小林
- 我が家でも学習アプリのゲームで子供と対戦しています。「もうすぐ連続記録がとだえちゃうよ」といったメッセージが出ると「やらなきゃ」と思うし、アイコンがすごくかわいくて、SNSでもいろいろなアイコンの画像をユーザーが投稿しています。それを見てまた、「やろうかな」と思う。設計が上手ですよね。
あと感情認識や表情認識の技術も進んでいて、学習者や部下の興味度を測ることも可能になってきています。さらに、たとえば会社で、上司との面談前に、個人の興味ポイントややる気ポイントが可視化されるようなテストを受けることもあるかと思いますが、ここに生成AIを組み込むことで、相手のタイプによって伝わる話し方、伝え方などを瞬時に生成してくれるようなソフトも出てきている。こうした、個人の考え方ややる気スイッチの分析、話し方のアドバイスなども学習ソフトに活かされるようになれば、教育や学習がもっと楽しく、やりがいのあるものになっていきそうです。
■教育を皮切りに、あらゆる領域でハイパーパーソナライズが当たり前になっていく
- 小林
- いろいろな事例を見てきましたが、今後、あらゆる教材の中からその人のレベルに合ったものが提供され、さらにその人特有の、学習効果を上げるための“ツボ”も押さえてくれるようになるとしたら、それは究極のハイパーパーソナライズと言えるのではないかと思います。ハイパーパーソナライズされた教育サービスを当たり前に享受できる時代になっていくとすると、生活者のメディア行動も大きく変化していくはずです。
これからは個人の趣味趣向だけじゃなく、習熟度やその時々の感覚に合ったコンテンツでなければ、生活者に響かない社会になっていくかもしれません。たとえばニュースは、自分の好みに応じた話題を自分の考え方に近いリポーターに読んでもらい、さらに自分の理解度に合わせた速度、難度、深度で説明してもらえるようになるかもしれません。ドラマだったら、自分の好みや気分に応じてストーリー展開を変えられたり、好みの出演者や、好みの視点で見られるものが求められるかもしれません。スポーツも、推しの選手を中心に見たいのか試合そのものを見たいのか、楽しみ方に合わせた中継方法が選べるようになる…といった具合です。教育のみならず、日常で触れるメディア全体としても、個別最適化が進んでいくような気がします。
- 高橋
- 面白いですね。一方で、今日本で想定されている教育のパーソナライズは、学習指導要領や資格検定で定められたカリキュラムのもとに学習者向けに内容を提供しており、ある意味教育内容の画一化が進んでいるようにも見えます。
より個人の特性や趣向を活かすような、ハイパーパーソナライズされた学習とは、むしろ自主学習に近いのかなと思います。幼児向けに、習った単語を入力すると単語を使った物語のコンテンツを自動生成してくれ、学習をさらに深められるサービスは既に出てきています。今後そうしたサービスが高等教育向けにも登場するのは想像できますね。
生成AIを教育の場で使うのには否定的な声もありますが、リテラシー教育も前提として、生成AIを使いこなして自分に合った学びの方法を開拓していくことが、一般的になっていくのではないかと思います。
- 小林
- 確かにそうですね。
ハイパーパーソナライゼーションがEdTechに導入されれば、メディアを始め様々な分野に波及していくと思います。それが当たり前になったとき、生活者がメディアや社会に対してどんなことを求めるようになるのか。メディアはもちろん、あらゆるビジネスの今後のあり方として、注目していくべきかと思います。
- 高橋
- 実際の教育現場で、先生自身が授業に人気ゲームソフトの内容を上手に活用しているケースもあります。教育という聖域と、マーケティング領域をうまくマッチングさせるという意味で、広告会社が入っていくことはできそうです。
また、EdTech領域は、シニアでも学習が困難な子どもでも、誰にでも教育が行き届くという、インクルージョンの視点もポイントになります。社会課題解決という意味でも、広告会社の社会を動かす力を応用できそうな領域だとは思います。
- 小林
- ゲーミフィケーションの手法を使った企業のPR施策はすでに複数見られます。
企業が発信する情報を、明らかにマーケティング的な見せ方ではなく、EdTechの文脈に乗せて、楽しみながら学び、知ってもらうという設計になっている。金融教育など、教育現場ではあまり行われていないテーマにおけるゲーミフィケーション事例もあります。教育×テクノロジー×マーケティングという視点で見たときに、私たち広告会社の力が活かせる余地は大いにあるのではないかと思います。

※Media Innovation Lab (メディアイノベーションラボ)
博報堂DYメディアパートナーズとHakuhodo DY ONEが、日本、深圳、シリコンバレーを活動拠点とし、AdX(アド・トランスフォーメーション)をテーマにイノベーション創出に向けた情報収集や分析、発信を行う専門組織。両社の力を統合し、メディアビジネス・デジタル領域における次世代ビジネス開発に向けたメディア産業の新たな可能性を模索していきます。
この記事はいかがでしたか?
-
博報堂DYメディアパートナーズ
メディア環境研究所 上席研究員 兼 Media Innovation Lab
-
Hakuhodo DY ONE
新規テクノロジー事業開発本部 研究開発局 広告技術研究室 兼 Media Innovation Lab