

安藤元博×森永真弓×嶋浩一郎|未来の広告ビジネスとマーケターのあるべき姿とは? 【前編】
今年3月に『広告ビジネスは、変われるか? テクノロジー・マーケティング・メディアのこれから』を上梓した安藤元博と、4月に『欲望で捉えるデジタルマーケティング史』を上梓した森永真弓。
これまでの広告産業を振り返りながら、マスマーケティングとデジタルマーケティングが融合するこれからの広告ビジネスの展望を示したふたりに、嶋浩一郎がインタビュー。本稿では、B&Bで開催されたトークイベントの内容をご紹介します。
歴史を知ることで世代間の意思疎通がスムーズに。点と点が“線”になる
- 嶋
- この春、ほぼ同じタイミングで本を出された安藤さんと森永さん。今日はおふたりに、これからの広告パーソンはどうあるべき?というお話をきいていきたいと思うのですが、まず森永さん、この本を書いたきっかけというのは?
- 森永
- きっかけは仕事の依頼で、とあるデジタルマーケティングに強い会社からインターネットの歴史の勉強会をしてくださいと頼まれたんです。最初はデジタルマーケティングに強い会社がなぜ外部に?と思ったんですが、デジタル業界は現在人材流動性が高くて、長く継続的に所属していたり、長く流れを見ている人がいないということで。さらには、メディアの話だけできる人はいるけど、メディアもマーケティングもクリエイティブも、様々な視野から語れる人がいないんですよね。そんな理由で依頼が来て、これまで誰もマーケティング目線ではインターネットの歴史をまとめていないし、おもしろそうと思ってお引き受けしました。その資料がドキュメントになって、本になったというかたちです。
- 嶋
- 本を出してみて反響はどうでしたか?
- 森永
- 若い人の感想が興味深かったですね。はじめは歴史書みたいな感覚で「遠い話だな」と思いながら読んでいたのが、ミクシィとかモバゲーとかスマホが出てきたあたりから急に「あ、これ知ってる!」となって、その瞬間、点と点がつながって歴史が線になって見えてきたと言っていて。
- 嶋
- これまで上司の言っていることがよくわかんなかったけど、この本で歴史を知ることによって、あぁ、あのとき上司が言っていたことはこういうことか、と再解釈されたってことだよね。歴史を振り返ってまとめてみたいま、新たに気になっていることはありますか?
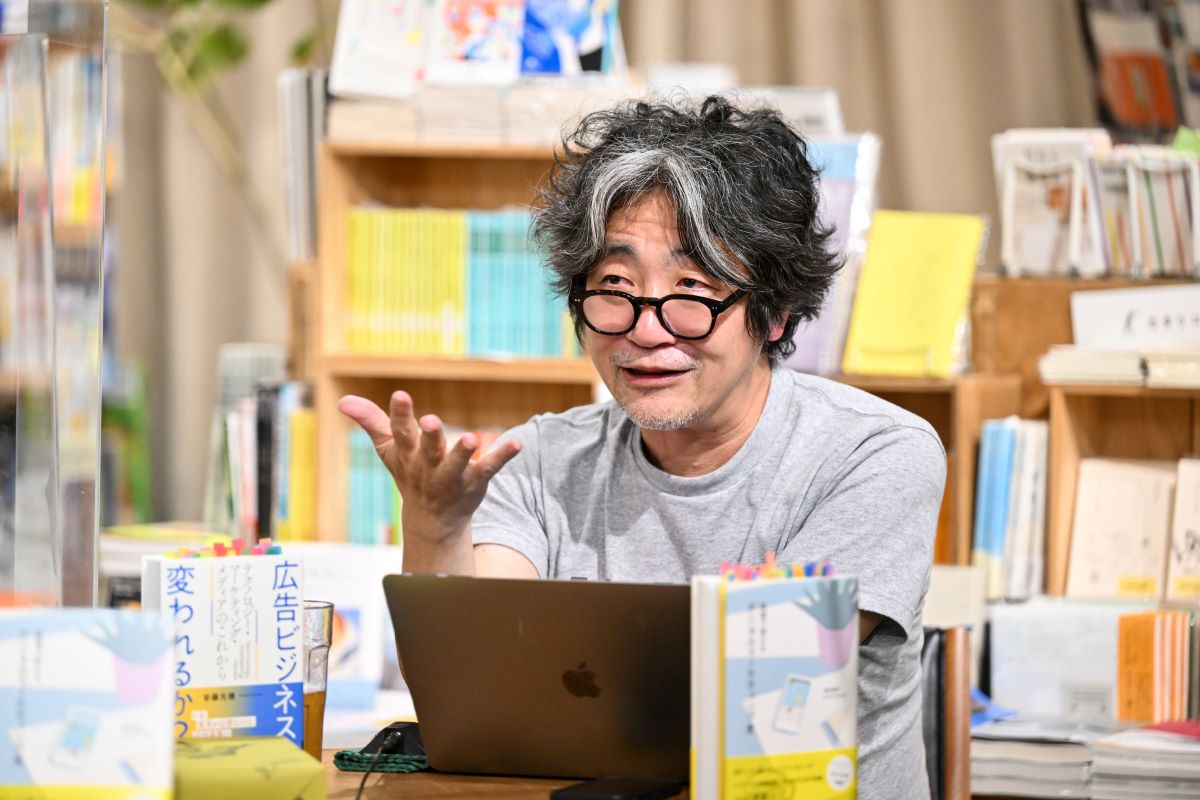
好きな人のコンテンツ生産力を“延命”するため。投げ銭はネット上のタニマチ
- 森永
- 最近おもしろいなと思っているのが、YouTubeとかのいわゆる投げ銭で一番稼いで
るのが日本のVtuberたちだということ。あと、小説投稿サイトの「小説家になろう」とか「アルファポリス」などのクリエイターエコノミーの勢いを、韓国や中国では出版社ではなくデジタルプラットフォーマーがネット完結のコンテンツビジネスを展開しているのにも注目しています。『梨泰院クラス』のようにWeb漫画からNetflix作品になったり、ものすごいビジネスになってる。発信したい、作品を作りたい、という欲望がボランティア的に消費されてしまうのではなく、どんどん収入につながってきていることはは素晴らしいなと。
- 嶋
- 投げ銭のビジネスって、どういう人の“欲望”で成り立っているんだろう?
- 森永
- 投げ銭は基本“人”につくファンですね。突き詰めると相撲のタニマチみたいな感じです。海外にある寄付文化とはちょっと違って、自分の好きな人が長くコンテンツを提供してくれるように、その人の生産力の“延命”のために投げているので、実は非常に個人的な充足のための世界かと。投機・投資的な「支援者」という感じとも違うんですよね。でも結果的に西洋的な寄付金と変わらない状態になっているのがおもしろい。
- 嶋
- 歴史的にはデジタルの投げ銭ってどのあたりから出てきたものなの?
- 森永
- モバゲーであったのが、掲示板で質問を書くと知恵袋みたいに答えてくれるというもの。たとえば宿題を教えてもらうとか。答えてあげるとポイントがもらえて、それでアバターが買えたり、みたいなエコシステムがありましたね。
- 安藤
- なるほどね。投げ銭って、外から見たらちょっと理解できないような、ある種非合理的なやりとりのように感じるんだよね。いわゆるグローバル化って、文化や言語の違いを超えた合理的な等価交換で成立すると思うんだけど、それとは異なる“不等価交換”の文化のような。
- 嶋
- そういうマイノリティコミュニティの存在がインターネットの世界で可視化されたっていうことなんだよね。100人ファンがいれば生き残れる、みたいな。グローバルプラットフォームにのらない価値が、ガラケーの中で生まれたということなのかな。
狙ってないのにじわじわ浸透する、日本カルチャーのおもしろさ
- 森永
- ガラケーもそうですし、2ちゃんねるとかニコニコ動画もそうですよね。以前コンテンツ産業をやっているアメリカの方に「日本おそろしい」と言われたことがあって。いやいやこちらから見たらアメリカの大手アニメ会社の方がよっぽどこわいですよ(笑)って言ったら、こちらでは綿密に計画を立てて世界1位を取ろうと思ってやっている、と。でも日本は狙っていないのにいつの間にかヌルッと入り込んでくるって。日本食だって、気づいたらアメリカ文化のなかでヘルシーな食事の代名詞になっていておそろしいって言われて(笑)。そういう「支持者がいつの間にか増えていて受け入れられている」ところが日本のカルチャーの魅力なのかもしれないと思いました。

あと、この本にも書いたのですが、そういう日本的なカルチャーから生まれてバーッと盛り上がるものがあると、必ずビジネス側の人がお金のにおいを嗅ぎつけて食いついてくるんですよ。それでカルチャーサイドの人から「お作法が違う」と言われて炎上するみたいな。その繰り返しをずっとやってるんですよね。
今まさにメタバースでカルチャーを育んでいる人がいるときに、ブロックチェーンやらNFTだのって投資勢がやってきていて…炎上前夜みたいな状況ですよね。
作品の価値は、つくられる過程と受け取ったあとの体験込みで成立する
- 嶋
- NFTビジネスをやっている一部の人は、NFTを売ること自体が目的になっていて、コンテンツのカルチャーを理解していない人もいる。そういう人はメジャーなタイトルを売ろうとするんだけど、一方で、人気作家の過去の作品じゃなくて、まだ知名度のない新作漫画をNFT化している出版社もでてきている。若いクリエイターを応援して育てていける仕組みになってるんですね。今後価値が上がっていったら、「自分は最初に見つけてたもんね」と言えるような。だから、いま「NFTだから買う」んじゃなくて、そのカルチャーを楽しんでいる人にとって、なにがうれしいのかをちゃんと考えることが大事。そういう意味で、カルチャーサイドに対するビジネスのアプローチのコツとかありますか?
- 森永
- 投げ銭の話もそうですが、いまって全部“人”にファンがついてるんですよ。会社や企画にファンがついているわけじゃない。だから、企業を主語に広告したいというときに、すごくコミュニケーションがむずかしい時代だと思います。
- 嶋
- 企画にファンがついているわけじゃない!もうちょっとショックを受けちゃうような言葉ですね(笑)。
- 安藤
- 広告にも本来はそういう側面があるんじゃないかと思ってるんですよ。今まで広告っていうのは、ある広告枠になんらかの広告コンテンツをのっける、そのことそのものに価値があると考えられていたかもしれない。だけど、本来は広告をきっかけにして送り手と受け手の間に相互に生じる変化、プロセスにこそ価値が生まれるんだよね。
それを博報堂DYグル‐プではAdvertising as a Service(AaaS)と言っているけど。
芸能だってサービス業って言うけど、ずっとレコードとか作品という、ある固定化した「モノ」を売っていた。でもいまはそうじゃなくて、作品が生まれる過程や、いっしょに育てていく過程、あるいはライブだったら送り手と受け手の間の、その場限りの再生不能な相互作用のプロセスに価値を求めてお金を払う。それが、いわばas a Service。
そういう変化が、自動車産業であれ芸能であれ広告であれ、同じように起きているんですよ。

- 嶋
- 昔のブランディングは経典をつくる仕事だったけど、いまは余白をつくって、そこに受け手が上書きしていく、その体験にお金を払う時代。だから、すごく権威のある作家さんでなくても、自分で見つけて、余白を上書きできる作家が売れていくという現象が起きているんですよね。
- 森永
- 若い人と話していてショッキングだったのが、映画を観ている2時間が辛いと言っていて。
早く映画を見終わった後の自分になりたいって言うんです。つまり、映画を楽しみたいというより、その後友達と感想を言い合っている状態に早くなりたいということ。コミュニケーションまでセットになって、はじめて映画を観たことになるんです。
- 安藤
- 突き詰めると、作品そのものがいいか悪いかじゃなくて、それについて誰かと話すことも込みで作品なんだよね。今後はそれが当たり前になっていくと思うな。
- 森永
- 広告も、これまでは「この期間に認知を取りたい」というように設計していたと思うんですが、これからは最初の情報発信からいかにして人にコミュニケーションしてもらって、情報やコンテンツを延命させるかを考えたほうがいいですよね。
- 嶋
- ここまでで“延命”という言葉が二回も出てきましたね。「私にとって素敵なコンテンツを提供し続けてくださいね。」という延命と、コンテンツの延命。おそろしい時代になってきました(笑)。
『欲望で捉えるデジタルマーケティング史』をまとめた森永真弓の視点を中心に、カルチャーと広告の関係について話題が展開した前編。後編は、『広告ビジネスは、変われるか? テクノロジー・マーケティング・メディアのこれから』で安藤元博が投げかけた問いについて話をききます。

後編はこちら
この記事はいかがでしたか?
-
博報堂DYホールディングス 取締役常務執行役員
博報堂 取締役常務執行役員
博報堂DYメディアパートナーズ 取締役常務執行役員
-
博報堂 執行役員 エグゼクティブクリエイティブディレクター
-
博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員



















