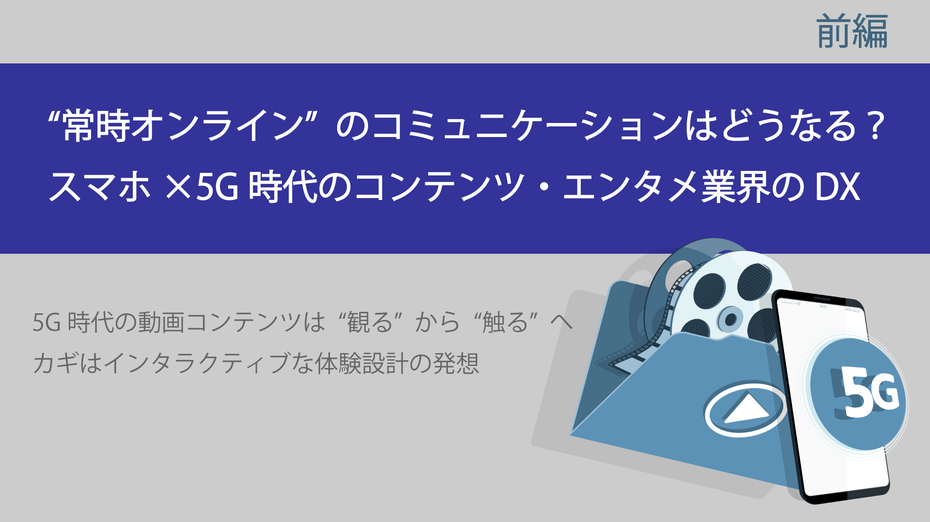

5G時代の動画コンテンツは“観る”から“触る”へ カギはインタラクティブな体験設計の発想
さまざまな領域のデジタル化が進む中、新型コロナ禍はその動きを一気に加速させたと言われています。一方で通信領域においては2020年の商用化から数年をかけて定着すると言われている5Gが、コンテンツ・エンタメ業界のDXを大きく推進すると言われています。生活者の“オンライン常態化”が加速している、今だからこその新しい楽しみの提供には、どのような形があるのでしょうか? すでに数多くのトライアルを重ねているLiveParkの安藤聖泰氏に、博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所の森永真弓が聞きました。
「コンテンツは触るもの」という新しい前提の誕生
- 森永
- 安藤さんには、先日メディア環境研究所のオンラインイベントで「2-3年かけて準備していく予定だった5Gによる進化として想定していた状況が、新型コロナ禍によって一気に前倒しされていっている感覚がある」とお話いただきました。今日は、そのあたりを事例を交えて詳しくうかがいたいと思います。はじめに、簡単に安藤さんのご経歴とLivePark社について紹介いただけますか?
- 安藤
- 私自身はテレビ局でキャリアをスタートし、以降ずっと放送と通信の領域の先端で仕事をしてきました。地デジの立ち上げとデータ放送、ネットとの融合、SNS連動の企画などですね。直近では日本テレビとバスキュールが合同で立ち上げたHAROiDの代表を務め、昨年エンタメ事業とデータ事業で分社化して、そのエンタメ事業を担うのがLiveParkです。スマホアプリ「LIVEPARK」上で主にライブコンテンツを企画・提供しており、パートナー企業のビジネス化まで支援しています。
- 森永
- 5Gが浸透すると現状よりも通信環境に余裕ができますから、ライブ配信のような動画サービスは利用しやすくなり、更に身近なものになるだろうと考えられますよね。大容量高速通信という特徴によって、リッチコンテンツについて語られることが5Gの話題では多いですが、既存の動画コンテンツはどうなるのでしょうか?
- 安藤
- 「テレビ起点」という従来の常識が変わると思います。これまでの動画コンテンツは、大画面で、また幅広いマスのターゲットが観る前提で制作されていて、それが通信波でも視聴可能になっていったという経緯があります。一部、NetflixやHuluオリジナルなど配信サービス起点のコンテンツが登場していますが、基本的にはテレビ起点の動画の楽しみ方が一般的でした。
それが今、起点が変わりつつある。具体的には、スマホに代表される「触れるデバイス起点」になっています。触れるとはつまり、距離が近いんですね。テレビが3mなら、スマホは30cm、次にヘッドマウントディスプレイだと目の前3cm、究極的にコンタクトレンズ型のデバイスができたらゼロですね。距離が近くなると、手が届き始めます。テレビはリモコンで、PC画面はキーボードで操作しますが、スマホやタブレットになって初めて「観ているものと触るものが同一」になった。つまり、動画コンテンツは触るものという新常識が誕生しました。
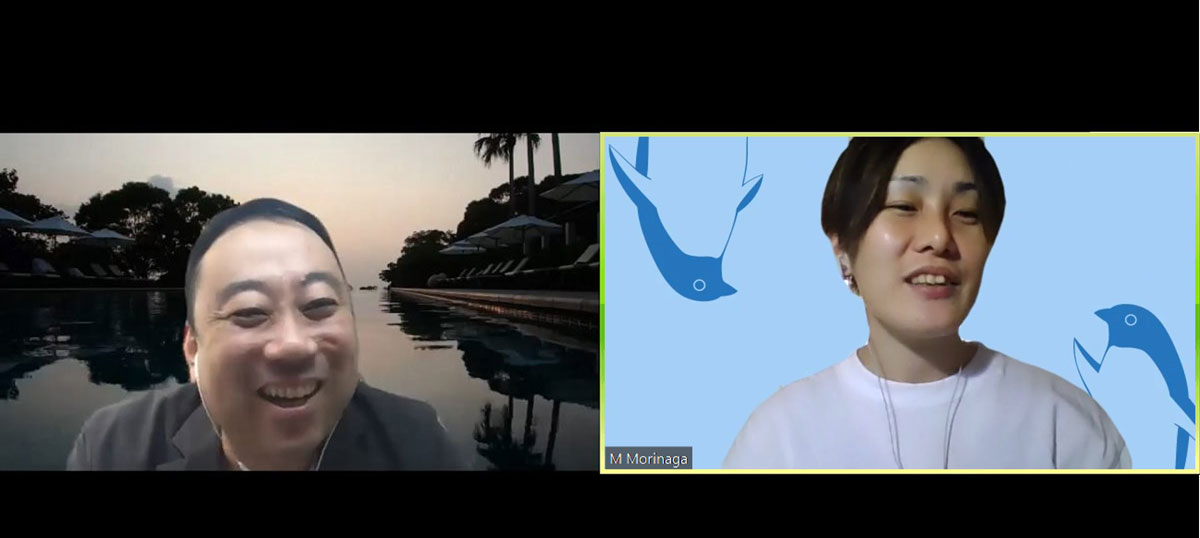
- 森永
- なるほど、そうですね。たしかにテレビ番組や映画といった従来の動画コンテンツは、触る前提がない。「うちの子がテレビで画面スクロールしようとしていた」と笑い話で語られるぐらいですからね(笑)。
- 安藤
- そうなんです。ただ、「触る前提のコンテンツ」を十分楽しむには、まだ技術的に足りていいませんでした。解像度不足や臨場感の欠如、それから遅延。“パケ死”“ギガ死”の問題。ちょっと笑ってしまいますが、一時期は僕らの企画も「月末の配信は避けよう」などと言っていました。これらを解消するのが、5Gの技術です。5Gも最初は4Gのネットワーク基盤上に展開するので、すぐにすべては改善されませんが、ネットワーク全体が5Gになったら大きく変わります。
そうすると働き方や、医療や教育の形などあらゆる領域に影響するでしょうが、エンタメ領域で注目すべきは、物理的距離の捉え方とコミュニケーションのあり方が根本から変わることですね。その世界を見込んで僕らも昨年から準備していましたが、コロナ禍において変化が一気に加速した、という印象です。
インタラクティブなコンテンツは、むしろ“イベント”
- 森永
- 新型コロナ禍関係なく、すでに取り組まれていた“触る”ことを前提に考えられた企画は、どういったものがあるのですか?
- 安藤
- 例えば昨年10月に配信した視聴者参加型の番組「“生配信”共闘バトルQ-SHUTSU」は、出演者のどちらかを応援することで脱出させるというリアル脱出ゲームです。初回は鈴木奈々さんとゆきぽよさんに出ていただき、それぞれのファンがクイズなどに参加した結果でどちらが先に脱出できるかを競いました。
スマホって普通、ひたすら画面を触りますよね。それに各アプリが反応したり画面が遷移したりする。ただ、従来型の動画コンテンツを観るときだけは、むしろ触らないのが基本でした。触ると停止してしまうし、集中して観ているから別のアプリやページへの誘導をタップしにくいですよね、そういうテンションじゃない。でも、スマホ起点の動画コンテンツはむしろ逆です。観て楽しむというより、触って楽しむ。
- 森永
- 確かに動画配信に分類されるものではあるのでしょうが、「観る」というより、スマホを介して「体験する」という方が感覚的に近いですね。こうなると発想としては、番組を考えるというよりは、イベントを企画するような感覚になりますか?
- 安藤
- そうですね。触って楽しむことだけを考えると、ライブじゃない形もあるでしょうが、画面の向こうの人と同じ時間を共有し、生のリアクションがあるというリアルタイム性が熱量につながっていると思います。それって、まさにイベントですね。
リアルタイムの共有が大きなポイントなんだと気づいたのは、お笑いの配信がきっかけです。お笑いってただ無観客ライブを配信すると、ひどいことになるんですよね。普通におもしろいのに、笑い声やリアクションがないと、すべった感じになってしまう。
松竹芸能さんが「新宿角座」と「心斎橋角座」というリアルな場を持たれていて、コロナ禍で営業が厳しくなった3月、LiveParkがある虎ノ門からオンラインの「虎ノ門角座」を配信したんです。ただ、少しやってみると、お笑いライブやお笑い番組のおもしろさを維持するのが相当難しいとわかりました。たとえテレビの画面越しに一人で観ていたとしても、あれはその場にいる観客と一緒に観ていたんですね。そもそもがインタラクティブなコンテンツだった。

松竹芸能「虎ノ門角座」
- 森永
- “笑いどころ”に皆で同調して盛り上がる、場の空気感、熱狂が抜け落ちてしまうんでしょうね。お笑いは、ネタそのものを堪能する以上に、複数人で笑い合って楽しさを共有することまで含んで一式、ワンパッケージだったんだ、と。
- 安藤
- そうなんです。だからその代替として、例えばテキストでリアルタイムにどんどんコメントが重なっていくような要素が重要になります。ただ、間がずれると芸人さんも拾えなくてテンポよく進まないので、前述の遅延の影響が大きいんです。
また、ビジネスモデルの問題もあります。オンラインの動画コンテンツのマネタイズは、広告モデルかコンテンツ自体への課金モデル、買い切りまたはサブスクリプションしかありませんでした。そこに投げ銭のようなギフティングやライブコマースという仕組みが生まれ、手数料が媒体社に入る形になっています。するとますます、触るというアクションが入らないといけない。
だからこそ、インタラクティブな仕掛けで“観ながら触る”要素を強めていく必要があります。ただ、既存のギフティングの仕掛けだと、盛り上がれば盛り上がるほど配信者が「ありがとう!」と言い続けているだけの動画になったりする(笑)。僕らのライブ配信でそれをやってしまうとコンテンツが成り立たないので、例えばギフトを贈る人だけにメッセージを届けられるなど、コンテンツの展開自体を妨げない仕組みを模索しています。
この記事はいかがでしたか?
-
 安藤 聖泰株式会社LivePark 代表取締役社長日本テレビ放送網株式会社入社。日本テレビ放送網株式会社入社。地上デジタル放送、ワンセグ放送の立ち上げやインターネット関連サービスの企画立案実施。SNSを活用した企画などを複数実施。IT情報番組iCon(アイコン)を手掛け、ソーシャルテレビ視聴サービス「JoinTV」なども立ち上げる。2015年5月株式会社HAROiDを立ち上げ、代表取締役に就任。2019年8月テレビ視聴データ部門を分社化、新たに株式会社LiveParkを設立。
安藤 聖泰株式会社LivePark 代表取締役社長日本テレビ放送網株式会社入社。日本テレビ放送網株式会社入社。地上デジタル放送、ワンセグ放送の立ち上げやインターネット関連サービスの企画立案実施。SNSを活用した企画などを複数実施。IT情報番組iCon(アイコン)を手掛け、ソーシャルテレビ視聴サービス「JoinTV」なども立ち上げる。2015年5月株式会社HAROiDを立ち上げ、代表取締役に就任。2019年8月テレビ視聴データ部門を分社化、新たに株式会社LiveParkを設立。
-
博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員通信会社を経て博報堂に入社し現在に至る。 コンテンツやコミュニケーションの名脇役としてのデジタル活用を構想構築する裏方請負人。 テクノロジー、ネットヘビーユーザー、オタク文化研究などをテーマにしたメディア出演や執筆活動も行っている。自称「なけなしの精神力でコミュ障を打開する引きこもらない方のオタク」。










