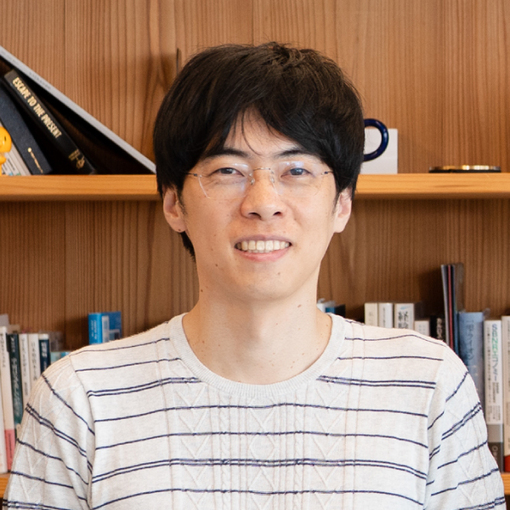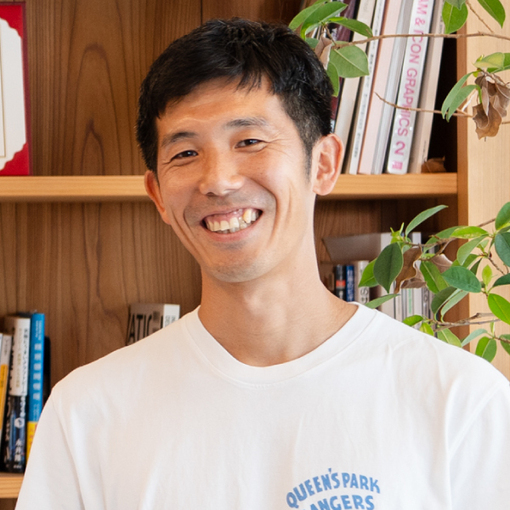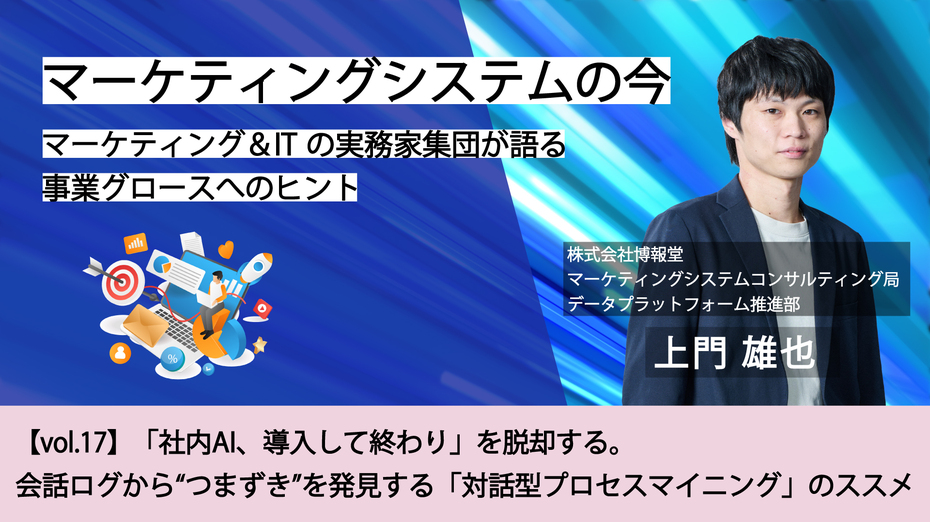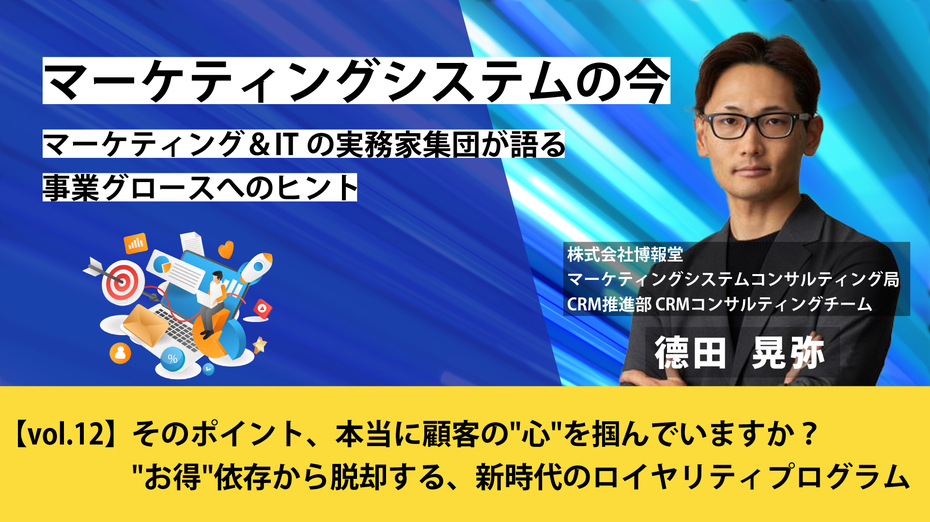AI・ブロックチェーン・生体認証等の最新技術がもたらす「生活者主導型CRM」への可能性【第1回】分散型ID(DID/VD)がどう課題を解決できるのか?
国内の人口が減少し市場が縮小していくこれからの日本において、顧客と長期的な関係を築いていくCRMは、多くの企業にとってこれまで以上に重要な取り組みとなります。AIやブロックチェーンといった最新技術を駆使した新しいCRM。その方法論を探る連載記事をお届けしていきます。第一回となる今回は、事業会社で新しいチャレンジに取り組んでいるお二人と、博報堂グループでweb3事業をプロデュースする博報堂キースリー、博報堂マーケティングシステムコンサルティング局のメンバーを招いて、現在のCRMの課題と、新しいCRMを構築する道筋について語り合いました。
樋口 雄哉氏
NEC デジタルプラットフォームビジネスユニット
バイオメトリクス・ビジョンAI統括部
web3ビジネス開発グループ
岸本 隆平氏
トヨタファイナンシャルサービス 戦略企画部
ブロックチェーングループ シニアマネージャー
白子 義隆
博報堂 マーケティングシステムコンサルティング局
松井 大輔
博報堂 マーケティングシステムコンサルティング局
ファシリテーター:寺内 康人(博報堂キースリー)
生活者情報のトータルな把握は可能か
- 寺内
- 博報堂は「生活者発想」というフィロソフィーを掲げています。消費や購買という行動だけではなく、人々の生活を360度の方向から理解し、その洞察に基づいてマーケティング活動を行うべきである──。それが生活者発想の考え方です。
しかし、この考え方と従来のデジタルマーケティングの間には、乖離があるように感じます。デジタルにおける生活者理解は「点」や「線」にとどまっており、360度からの理解が必ずしも実現していないのが実態です。
今回お招きした皆さんは、その課題を解決できる視点をお持ちの方々です。連続座談会を通じて、生活者発想に基づいたCRMの新しい可能性を探っていきたいと思っています。

はじめに、現在のCRMの課題について、NECの樋口さんに伺いたいと思います。
- 樋口
- デジタルマーケティングにおけるCRMには、「打率の低さ」という課題があると感じています。例えば、ある人にメールで情報を送っても、その人がその情報を本当に必要としているかどうかはわかりません。むしろ、その人のニーズにヒットする確率の方が低いでしょう。アプローチの「打率」を上げるには、その人の行動データや購買データを統合して、その人が何を欲しているかといったファクトを把握する必要があります。
もう一つの課題は、情報のフレッシュさです。企業がAという人の情報を最初に獲得した時期がその人が学生の頃だったとすると、Aさんの登録上の属性はずっと「学生」のままである。そういうケースが少なくありません。同様に、職業、家族構成、住所などの情報も、最初の登録時のままということがよくあります。そのような更新されていないデータを持ち続けていても、確度の高いアプローチは実現しません。
これからのCRMには、フレッシュな情報を1つのID(アイデンティティ)(※)としていかに把握するかといった視点が求められると思います。
※ID …本座談会では、単なる識別子という意味だけではなく、個人の属性や行動ログも含めたデジタルアイデンティティという概念で使用。

- 白子
- そういった課題は、プラットフォーマーだけでなく、ファーストパーティデータ(※)の保有者である事業会社も抱えていますよね。多くのプレーヤーに共通する課題と言っていいと思います。
※ファーストパーティデータ…企業が直接収集して保有する顧客データのこと
- 岸本
- 生活者の立場に視点を移してみると、「自らをトータルに表現することができない」という課題と言えるかもしれません。デジタル上では、プラットフォームやサービスごとに異なるIDがあります。一方でリアルにおいても、店舗や施設ごとにIDが存在します。それらが統合されて、自分をデジタル上で表現することが可能になれば、生活者はあらゆるタッチポイントで自分に合ったサービスを利用できたり、本当に欲しい商品のリコメンドを受けたりすることができるようになるはずです。
- 寺内
- それを実現できるテクノロジーはあるのでしょうか。
- 岸本
- 「DID/VC」はその一つになるかもしれません。一人ひとりの生活者がIDを直接管理して、自らの意思に基づいて開示することを可能にするのがDID/VCで、DIDは「分散型識別子」、VCは「検証可能な証明書」を意味します。特定のプラットフォームに依存してIDを管理するのではなく、ユーザー自らIDを管理できるのが大きな特徴です。

ユーザーを中心としたエコシステム
- 寺内
- 10年近く前に開発された、個人がデータを提供し、データを活用した企業がメリットを提供する仕組みである「情報銀行」も、生活者の情報のトータルな把握を目指したものでした。DID/VCと情報銀行の違いについて教えていただけますか。
- 岸本
- 個人が同意したデータを特定の企業やコンソーシアムに預けるのが情報銀行の基本的な仕組みです。しかし、この試みは現在のところあまり普及していません。理由はいくつかあります。
まず、自分の情報をまとめて第三者に預けることに対する不安が生活者側にあります。情報を預かる側にも情報の管理や運用を的確に行わなければならないという大きな責任が発生します。また、コンソーシアムであれば、参加企業の目的や利害関係を調整し、可視化の先の活用にまでつなげることも必要です。

- 樋口
- 生活者側から見れば、インセンティブがなければ情報を預けようというモチベーションは生まれません。例えば、ジムに行ったときに、預けた情報をもとに最適なトレーニングメニューが提供されるとか、異なる医療機関で同じ薬が処方されるといったことです。そのようなインセンティブが実現していないという問題もあります。
それ以前に、自分の機微な情報が第三者に管理されていることの抵抗感もあると思います。それに対してDID/VCは、どのような個人情報をどこに対して開示するかといったことをすべて自己主権的に決定することができるのです。
- 岸本
- 私がDID/VCに興味を持ったきっかけは、MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)に関わったことでした。MaaSは、人のなめらかな移動を実現するコンセプトであり、具体的には生活者一人ひとりの移動目的に応じて、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行えるようにするサービスです。それは単体ビジネスというよりは、移動に関わるさまざまなプレーヤーが連携する「エコシステム」として成立します。しかし、それを構築し、継続的に運営していくのは簡単ではありません。共通のビジョンをつくり、利害関係の異なるプレーヤー間の調整をしなければならないからです。情報銀行と共通する課題ですね。
ここで、そのエコシステムの中心に生活者がいると考え、MaaSに含まれるさまざまなサービスの利用や、そこで必要とされるデータの管理と流通を生活者中心に捉えなおせば、エコシステムは回り始めるのではないか。DID/VCはその可能性を十分に秘めているテクノロジーだと考えています。
- 松井
- 私も以前MaaSに関わったことがあるので、その課題意識はよく理解できます。MaaSを適切に実装し継続的な運用を実現するには、エコシステム全体をビジネス化する必要があります。しかし、なかなかビジネス化の道筋をつくれず、参加していた企業が撤退していくケースが少なくありません。しかし、それはMaaSに参加しているプレーヤーの視点で考えていたからで、岸本さんがおっしゃるように、ユーザー側がMaaSのサービスやデータ管理の主体であると捉えれば、ビジネス化の可能性は大いに高まると思います。

「コンテクスト」と「インテント」のループ
- 樋口
- MaaSの場合は日常的な用途が多い一方で、より広い意味でのエコシステムもあると思います。その一つが、インバウンドに関する観光や移動です。
例えば、日本に一週間滞在する、とある外国人がどのような嗜好性を持っていて、どのような場所を訪れたいと考えているかは、データがないのでまったくわかりません。しかし、過去の旅行履歴や動画サイトの閲覧履歴などのデータを集めることができて、それを把握できれば、適切なリコメンドができるかもしれないし、その人が訪れた場所で優れた体験を提供できるかもしれません。つまり、デジタル上のタッチポイント、リアルな施設、観光地などを含む緩やかなエコシステムをつくるということです。
2025年のインバウンド人口は4000万人と見込まれています。国は、2030年までにこれを6000万人に増やす目標を掲げています。あと5年で2000万人増やすにはどうすればいいか。そう考えたときに必要になるのが、観光客のアイデンティティを理解し、よりその人に合った様々な体験をレコメンドできる仕組みではないでしょうか。そのようなエコシステムをつくることが、今後大きなバリューになるような気がします。

- 寺内
- 日本を訪れた外国人の意図や目的を把握して、それに合った提案をしたり、サービスを提供したりするということですよね。
- 岸本
- まさにこれからのマーケティングに重要なのは生活者の意図や目的、つまり「インテント」であり、さらにそれを「コンテスト(文脈)」と連動させてループを形成することだと思います。コンテクストとは、ログの履歴などに基づいた「過去の事実」です。一方、インテントとは「これからしたいこと」です。「これまで何をしたか」と「これから何をしたいか」がうまくつながると、移動・観光における本当のワントゥワンマーケティングも実現するかもしれません。
- 白子
- インテントが把握できれば、最適なモーメントに最適な情報を届けることも可能になります。問題は、それをどう把握するかですね。
- 松井
- AIエージェントがインテント把握の入り口になる可能性があると思います。ユーザーが何をしたがっているか、何を求めているかといった情報がAIエージェントに蓄積されて、そこから導き出されるインテントに基づいてCRMを実現していく。そんな仕組みができたら新しいCRMの世界が開けるのではないでしょうか。
- 岸本
- 日本では今後、観光業が代表的産業の一つになっていくと言われています。インバウンドをメインターゲットとした移動・観光のエコシステムづくりは、非常に重要な課題になりそうです。
これからのデータマーケティングとは
- 白子
- 先ほど、事業会社のファーストパーティデータの話をしました。Cookieが制限されるようになってから、企業のファーストパーティデータの重要性が高まっています。しかし、ファーストパーティーデータだけで精度の高いマーケティングを実現するのは難しいことがわかってきています。求められているのは、企業が保有するユーザーデータを外部の行動データなどと紐づけて、データをリッチ化していくことです。今日のお話を通して、その方向性が見えてきた気がします。

- 松井
- 目指すべきは企業間のデータ連携と統合ですが、それ以前に一企業内でのデータ統合も依然として大きな課題です。まずは、博報堂としてはクライアントの社内データ統合をご支援し、そこから企業間データ統合につなげていく。そんな流れをつくっていきたいですね。
- 岸本
- さまざまな事業ドメインを抱えるグループ企業では、グループ内のデータ活用が喫緊の課題となっています。活用のためには企業内統合、グループ内連携、企業間連携と、ハードルを一つ一つ着実に越えていくことが必要です。
CRMに関わる人たちにとって、ID統合とその先にあるデータ活用は悲願と言っていいと思います。その真の目的の達成のためには、生活者を中心にデータが流通するような、新しい考え方や技術を取り込んでいくことが大切なのではないでしょうか。生活者、事業者ともに理解を広げることは決して簡単ではありませんが、そのインパクトは大きいからこそチャレンジする甲斐があります。
- 寺内
- 岸本さんが指摘した、「生活者を中心にデータが流通する」仕組みを創るためには、生活者への提供価値が鍵になります。生活者への価値提供という名目のもとに、異なるステークホルダーが力を合わせて「新しいCRMのカタチ」が生まれてくるといいですね。今後の座談会では、皆さんの取り組んでいる事例をお話頂きながら、新しいCRMのカタチを構築する道筋をさらに探っていきたいと思います。
この記事はいかがでしたか?
-
 樋口 雄哉 氏NEC デジタルプラットフォームビジネスユニット
樋口 雄哉 氏NEC デジタルプラットフォームビジネスユニット
バイオメトリクス・ビジョンAI統括部
web3ビジネス開発グループ
-
 岸本 隆平 氏トヨタファイナンシャルサービス 戦略企画部
岸本 隆平 氏トヨタファイナンシャルサービス 戦略企画部
ブロックチェーングループ シニアマネージャー
-
博報堂 マーケティングシステムコンサルティング局
-
博報堂 マーケティングシステムコンサルティング局
-
博報堂キースリー