

デジタル広告配信メディアとしての屋外広告──LIVE BOARDと博報堂DYアウトドアが開くデジタルOOHの可能性
繁華街のビル、電車やタクシーの車内、小売店舗の店頭、ビューティーサロン──。さまざまな場所でデジタルサイネージを目にする機会が増えています。それらをデジタル広告媒体として活用して大きな成果を上げているのが、デジタルOOH※1(以下、DOOH)の日本におけるトッププレイヤーであるLIVE BOARDです。DOOHと従来の屋外広告の違いや、それがクライアントにもたらすメリットについて、LIVE BOARDの髙山晋太郎氏と喜多健太郎氏、同社と協業している博報堂DYアウトドアの大村駿介に話を聞きました。
髙山 晋太郎氏
LIVE BOARD
クライアントサービス部 ディレクター
喜多 健太郎氏
LIVE BOARD
テック部 テクニカルスペシャリスト
大村 駿介
博報堂DYアウトドア
デジタルプロデュース部 ディレクター/メディア一部
(兼)博報堂DYメディアパートナーズ
OTTアカウント推進部
全国6万面超の屋外広告をネットワーキングする
──LIVE BOARDの概要をご説明いただけますか。
- 髙山
- 2019年に創業したDOOHを手掛ける企業です。OOH※2をネットワーキングして、データドリブンに広告を配信する事業を手掛けています。2024年には博報堂DYメディアパートナーズからも出資いただいています。
──媒体社と考えればよろしいですか。
- 髙山
- 自社で屋外媒体を運営しているという点では媒体社と言えますが、一方でプラットフォーマーという立場もあります。自社媒体だけでなく、他社が運営する屋外、駅、電車内、タクシー内、店頭などの媒体を結んでLIVE BOARDマーケットプレイス※3を形成しています。
LIVE BOARD広告は、デジタル広告同様、DSPとSSPの仕組みを活用し、RTB※4などによって必要なタイミングで必要な広告枠を購入できるサービスです。マーケットプレイスに接続されている媒体は、現在全国で6万面を超えています。

──OOHをデジタル広告配信メディアの1つとして活用できるということですね。
- 大村
- そのとおりです。OOHは、もともとは屋外の看板やポスターのような媒体でした。もちろん、現在でもそういった媒体は有効に活用されていますが、近年はデジタルサイネージ化も進んでいます。OOHがデジタルサイネージになることによって、PCやスマートフォンのように動画を配信することが可能になりました。それがDOOHです。
DOOHの使い方は、大きく2つに分けられます。
1つは、渋谷や新宿のような繁華街のサイネージを使って、街を歩く人たちに向けてブランドなどの訴求をしていくエリアマーケティング的な手法。もう1つは、ネットワークでつながっているサイネージを使って、リーチを最大化していく手法です。僕たちがLIVE BOARDの皆さんと一緒に進めている取り組みの多くは、後者にあたります。
──一般的なデジタルメディアのように、広告の運用も可能なのでしょうか。
- 髙山
- 私たちが最も得意としているのが、まさに運用型のプログラマティックOOH※5です。クライアントのニーズに応じて、広告を配信する場所、ターゲット、時間帯などを設定し、目標とする成果を達成していきます。
- 喜多
- 私たちが自社で運営する媒体はインターネットに接続されており、HTMLファイルにも対応しています。
そのためAPI連携を通じてクリエイティブを動的に更新することやHTMLを活用してリアルタイムにコンテンツを変更することも可能です。広告を見ている生活者の反応に合わせて、より効果的なクリエイティブへの差し替えができるのもプログラマティックOOHの大きな特徴です。
インプレッション数をいかに算出するか
──屋外に大きなPCやスマートフォンの画面があるようなイメージですね。
- 大村
- おっしゃるとおりです。従来のOOHは、トータルのメディアプランにおけるオプションの位置づけとなるケースが多かったです。しかし、デジタル化とネットワーク化によって、テレビ、PC、スマホなどと同等のレベルでプラニングに組み込むことができるメディアになったと言えます。
──一般的なデジタルメディアは、インプレッション数を正確に出すことができて、かつ広告配信後の効果検証をすることも可能です。DOOHでも同様のことができるのでしょうか。
- 髙山
- 可能です。媒体によって仕組みは異なりますが、LIVE BOARDの株主であるNTTドコモのデータを主に活用しています。それができるのも、LIVE BOARDの大きな強みとなっています。
──具体的な仕組みを教えてください。
- 喜多
- スマートフォンなどのモバイル端末は、稼働中は各地の基地局と通信している状態にあります。その通信情報を活用することで、特定のエリアにどのくらいの人がいるかを推計することができます。
とくに、NTTドコモのデータには「シングルID×フルファネル」という特徴があります。お客様から事前に利用許諾を取得し、個々のユーザーの契約情報、dポイントの情報、基地局との通信情報などを統合、利用者の個人情報が特定されない統計的な情報として配慮された上で、IDベースでユーザーの行動を把握することができます。これによって、例えば渋谷駅前の大型モニターの前にいる人たちの数や属性を把握できるわけです。
- 髙山
- OOHの場合、ディスプレイを視認できる範囲には物理的な限界があります。
その範囲を、基地局データをもとにしたモバイル空間統計®※6やその他位置情報などを活用して定め、視認可能なエリアにいる人数をカウントし、属性と紐づけます。この仕組みによって、インプレッション数を明確にしたターゲティング配信が可能になります。もちろん、電気事業法に則ってプライバシーに配慮することや、データ活用に関するユーザーの許諾をとることは必須となります。
──NTTドコモのユーザーに限ったターゲティングということでしょうか。
- 髙山
- NTTドコモの契約者データや様々な公的データをもとに、ドコモ利用者以外の人数や属性もあわせて拡大推計することができます。これによって、日本の全人口を対象としたインプレションを数値化することが可能になるわけです。
もっとも、視認エリアにいるすべての人がディスプレイを見ているわけではありません。そこで、VRゴーグルを装着した検証などで、実際の視認率に限りなく近い数値を算出して、それをインプレッション数として広告主に提示しています。
- 大村
- モバイル空間統計®は、コロナ禍の中で政府が街の人流などを把握する際にも使われていた信頼性の高い手法です。データ数はモバイルキャリアの中では日本最大規模のため拡大推計もより精緻にでき、正確性の高いインプレッション数を出すことができます。

- 喜多
- インプレッション数のベースとなるのは、ヒストリカルデータです。
つまり、過去の平均値などをもとに、現在の数を推計するということです。DOOHは欧米で先行して普及していますが、欧米におけるDOOHのインプレッションの数値が更新されるのは、半年、あるいは1年に一度くらいの頻度です。様々なロケーションにあるネットワーク化されたすべての媒体のインプレッション数を算出するにはたいへんな労力と技術を要するからです。
それに対して、私たちが運用している媒体のインプレッション数は、基本的にひと月に一度更新されます。つまり、「鮮度」が非常に高いわけです。その数値を使うことで、高精度のプランニングを実現することができます。
──屋外ディスプレイ以外のOOHの場合は、インプレッション数をどのように算出するのですか。
- 大村
- 店頭や車内など、ディスプレイの設置場所や種類によって手法は異なります。カメラでディスプレイの前を通った人を撮影し、骨格の角度などから視認を判定する方法や、Wi-Fiの接続データなどを活用する方法などがあります。
──効果検証の方法についてもお聞かせください。
- 髙山
- さまざまな方法があります。NTTドコモの位置情報データなどを活用したブランドリフト調査、たとえばテレビ・デジタルメディアなどの他媒体も含めた広告認知率、態度・行動変容などを可視化する方法など。
アプリのダウンロードや起動などのアクションから広告効果を計る方法やdポイント・d払いのようなサービス利用と紐づけて、購買行動をトレースする方法──。
そういった方法の中から、クライアントの課題やニーズに応じて最適なものをご提案します。
- 大村
- 博報堂DYグループ独自の効果測定方法としては、AaaSの仕組みを活用したものがあります。ディスプレイごとの広告効果を測定するだけでなく、テレビの実視聴データ、デジタルの広告配信データなどと組み合わせて、媒体を横断した統合的な広告効果を把握することが可能です。
DOOHの仕組みをいかしたインタラクティブキャンペーン
──DOOHを活用した具体的な事例をご紹介ください。
- 大村
- TOKYO FMをキーとする全国ネットで放送されているラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司 ~ BEYOND THE AVERAGE ~」のキャンペーンをご紹介します。これは、2023年の年末に実施したもので、一年間頑張って働いてきた会社員の皆さんが、ドラマに登場するキャラクターのセリフを交えた応援メッセージを、自分自身や同じ境遇の全国の会社員に向けてイニシャルつきで送ることができるというキャンペーンでした。

- 髙山
- 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の繁華街にある屋外ディスプレイにQRコードを掲出し、それをスマホで読み取ると、独自のメッセージを作成してリアルタイムでディスプレイに表示させられるという仕組みをつくりました。
- 大村
- 一種のインタラクティブ広告であり、よく知られたキャラクターを使ったファンマーケティングでもありました。SNSでの拡散効果を想定しながら、番組の聴取率向上や聴取層の裾野を広げることを狙いました。狙いどおり多くの話題を集め、2024年の「デジタルサイネージアワード」で優秀賞を獲得しています。
- 喜多
- 技術的には比較的シンプルで、ウェブでの広告配信とほぼ同じでした。屋外ディスプレイに表示するHTMLファイルと、スマホに表示させるHTMLファイルをつくり、それらをリアルタイムにシンクロさせるという仕組みです。
- 大村
- もう1つ、花粉症の薬の広告展開をご紹介します。花粉の飛散が多くなる季節に、屋外ディスプレイで薬の広告を配信した事例です。花粉が飛び交う屋外を歩いている最中に広告に接することで、薬を購買するモチベーションを高めることができると考えました。
- 髙山
- 天気データをトリガーにしたRTB配信で、花粉レベルが高いときに入札リクエストを出すことができる仕組みをつくりました。最適なモーメントに最適な場所で最適なメッセージを発信する。そんな取り組みだったと言えると思います。
日本のDOOHモデルで世界をリードしていきたい
──DOOHの現在の課題がありましたらお聞かせください。
- 髙山
- 一番の課題は指標づくりですね。
まずは業界としてDOOHの広告効果指標を確立し、その次の段階でテレビ・デジタルメディアなどとの共通指標をつくることがこれからの大きな目標です。
共通化に際してひとつの鍵となるのは「アテンション率」だと思います。アイトラッキングの技術などを用いて、実際に広告が見られている割合、視認率を算出、加味した指標です。OOHで言えば、ディスプレイを実際に視認している人の割合が加味されたインプレッションということになります。LIVE BOARDでは設立以来のテーマとして取り組んできた領域ではありますが、それが共通指標になる未来はそう遠くはないと私は考えています。

- 喜多
- 技術面の課題は生成AIの活用です。
AIを上手に使えば、ターゲットや時間帯などに合わせて即時に最適なクリエイティブを生成することが可能になります。欧米ではそのような取り組みがすでに進んでいます。私たちもその波に乗り遅れることなく、AIを活用した柔軟な広告配信の仕組みを確立していきたいと考えています。
──DOOHを活用して今後どのようなことに取り組んでいきたいか。それぞれのビジョンをお聞かせください。
- 大村
- DOOHをより生活に根付いたもの、より見ていて楽しいものにしたいです。「ライブ」がひとつキーワードになると考えています。
例えば、音楽のライブ配信にチャレンジしてみたいですね。通常、ライブ演奏を聴くことができるのは、チケットを買って会場に入場した人やペイパービューを購入した人だけです。しかし、DOOHを使ってライブの様子をリアルタイムで配信することができれば、会場にいる人以外にもその音楽の魅力が伝わり、ファン層を広げることができるはずです。大勢のファン潜在層が大きなモニターを囲み一緒に見て楽しめるのは、DOOHならではの体験ではないでしょうか。
実施までの課題はありますが、LIVE BOARDのネットワークを使って、全国のDOOHで同時にライブ配信を展開できたら大きな話題を集めると思います。
- 喜多
- ウェブはこれまで1.0、2.0、3.0と進化を遂げてきました。1.0はユーザーがウェブ上にあるコンテンツに一方的にアクセスする段階、2.0はユーザー自身が情報の発信者になれる段階を意味します。先ほど紹介されたTOKYO FMのインタラクティブキャンペーンは「DOOH2.0」と言えます。
ウェブ3.0は、ブロックチェーンの技術を使った分散型インターネットが実装された段階に当たります。DOOHも同様に、ブロックチェーンを駆使しながら広告の信頼性を高める「DOOH3.0」を目指すべきだと考えています。アドベリフィケーションと呼ばれる広告のリスク検証の仕組みを確立し、広告の品質保証を実現するとともにAIを活用した柔軟な広告配信の仕組みを確立ができるようになれば、DOOHのメディア価値はさらに高まっていくはずです。そんな未来を目指していきたいと考えています。
- 髙山
- プログラマティックOOHの取り組みはこれまで欧米がリードしてきました。アジア太平洋地域でも徐々にOOHのプログラマティック化が進んでいますが、浸透するのはまだまだこれからです。一方、日本はアジア太平洋地域の中でデータに基づくDOOH活用が最も進んでいる国のひとつです。今後もプログラマティックOOHの取り組みを推進して、日本のDOOHのモデルでアジアから世界をリードしていくこと。それがこれからの大きな目標です。
※1 デジタルOOH:Digital Out of Homeの略。交通広告、屋外広告、商業施設などに設置されたデジタルサイネージを活用した広告媒体
※2 OOH:Out of Homeの略。交通広告や屋外広告、商業施設での広告など、家庭以外の場所で接触する広告媒体の総称
※3 LIVE BOARDマーケットプレイス: LIVE BOARDが取り扱う自社・他社を含めたデジタルOOH広告枠(インベントリ)の全体を指す
※4 RTB:Real Time Biddingの略。広告1回表示ごとにリアルタイムでオークションが行われ、表示される広告が決まる仕組み
※5 プログラマティックOOH:Programmatic (Digital) Out Of Homeの略。時間帯や、天気・気温など、エリアごと、オーディエンスデータごとにプラットフォームを介して広告配信の自動化が行えるDOOH(交通広告、屋外広告、商業施設などに設置されたデジタルサイネージを活用した広告媒体)
※6 モバイル空間統計®:「モバイル空間統計」は株式会社NTTドコモの登録商標です。日本全国の1時間ごとの人口分布を24時間365日把握し、「いつ」「どんな人が」「ドコから」「ドコに」動いたかを推計することができます。
この記事はいかがでしたか?
-
 髙山 晋太郎LIVE BOARD
髙山 晋太郎LIVE BOARD
クライアントサービス部 ディレクター
-
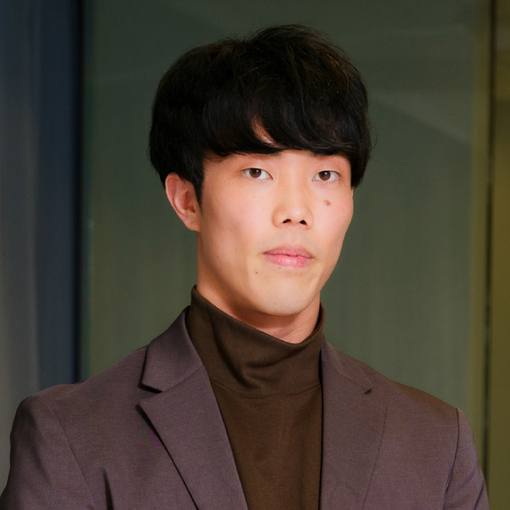 喜多 健太郎LIVE BOARD
喜多 健太郎LIVE BOARD
テック部 テクニカルスペシャリスト
-
博報堂DYアウトドア
デジタルプロデュース部 ディレクター/メディア一部
(兼)博報堂DYメディアパートナーズ
OTTアカウント推進部


















