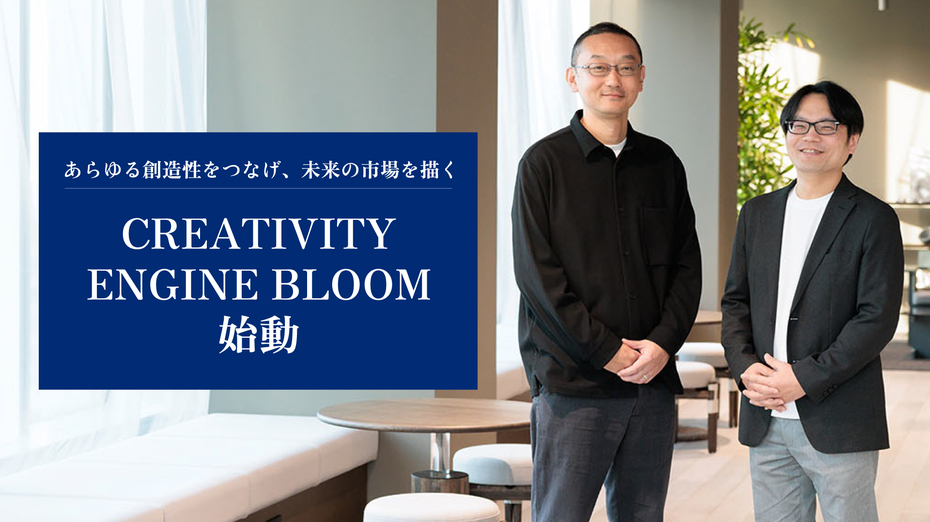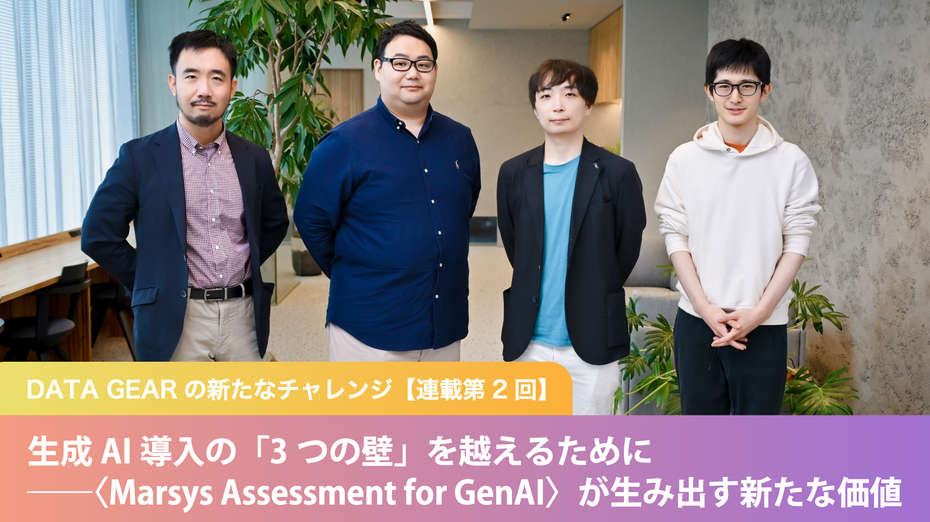【連載 Creative technology lab beat Vol.8】最新のテクノロジーによってクラフトを刷新していく
「クリエイティブ×テクノロジー」によって、生活者の心を打つ(beat)アウトプットを生み出すことを目指す博報堂DYグループの横断型組織「Creative technology lab beat」。この組織には、クラフト(制作)のプロである博報堂プロダクツのメンバーも参加しています。beatにおけるクラフトの取り組みについて、博報堂プロダクツの新部門「Promotion X室」の室長を務める石﨑優と、beatのリーダーである木下陽介が語りました。
木下 陽介
博報堂DYホールディングス Creative technology lab beat リーダー
統合マーケティングプラットフォーム推進室 室長
AIテクノロジーG GM
テクノロジスト
石﨑 優
博報堂プロダクツ 執行役員
Promotion X室 室長
最新の技術をいかした制作ワークを
──石﨑さんが代表を務めていた動画制作のスタートアップ、Emergeが博報堂プロダクツにジョインしたのは2019年でした。それ以前の歩みと、現在のお立場などについてお聞かせいただけますか。
- 石﨑
- 大学時代は農学部でバイオテクノロジーを学ぶかたわら、ベンチャーキャピタルでインターンをしたり、先輩とシェアハウス事業を手がけるスタートアップを立ち上げたりしていました。修士卒業後にコンサルティングファームで2年間働いたのちに、大学の同級生がタイで起業した農業ベンチャーに参加しました。しかしその事業に見込みがないことが早い段階で明らかになったため、日本企業向けのオフショア映像制作サービスに事業をピボットしました。その会社がEmergeです。
2019年に博報堂プロダクツと資本提携をしてからは、Emergeの社長を務めながら、コンサルティングのスキルをいかして、博報堂プロダクツの事業企画室で中期経営計画の策定などに携わってきました。新設された「Promotion X室」の室長となったのは、この4月からです。
──Promotion X室とはどのような部署なのでしょうか。
- 石﨑
- 博報堂プロダクツの社内システムやクリエイティブの制作体制などのトランスフォームを担う部署です。とくに、デジタルテクノロジーを活用したトランスフォーメーションをミッションとしています。
──博報堂プロダクツとCreative technology lab beat (以下、beat)との関係についてご説明ください。
- 木下
- 一昨年ぐらいから、beatのソリューション開発のワーキンググループに、石﨑さんをはじめとする博報堂プロダクツのメンバーに参加してもらっています。beatはこれまで、「パフォーマンスクリエイティブ」「ブランデッドクリエイティブ」「先端クリエイティブ」の3領域のソリューション開発に取り組んできました。そのすべての領域の、とくに制作プロセスづくりに博報堂プロダクツの力が発揮されています。
従来は、パフォーマンス型広告のクリエイティブとブランディングを目的とする広告のクリエイティブは、制作ノウハウやプロセスが異なっていました。beatは、その2つの領域の制作ワークを統合していくことを目指しています。その取り組みにおいて、博報堂プロダクツの知見やスキルが活かされると考えています。
「クラフト×AI」の大きな可能性
──現在、クリエイティブの領域でも生成AI活用が進んでいます。一方で、生成AIにはさまざまな問題点があるという指摘もあります。生成AI活用に関するお考えをお聞かせください。
- 石﨑
- 2022年末ぐらいまでは、クリエイティブにAIを活用するのは難しいという意見が大半だったと記憶しています。しかしその後、生成AIが一気に進化したことで、「クリエイティブ×AI」というテーマは避けて通れなくなっています。

難しいのは、よく言われるように、人間のクリエイティビティとAIができることをどうバランスさせていくかということです。AIはあくまでの人のよきアシスタントであるべきである。僕はそう考えています。現段階では、人のクリエイティビティを侵食するまでの精度はAIにはありません。しかし今後AIの進化がさらに進み、例えばキャリアの初期段階にあるデザイナーレベルをAIがつくれるようになったとき、人とAIの協力関係はどうあるべきか。それを今から真剣に考えておく必要があると思います。
昨年、映画製作におけるAI利用をめぐって、ハリウッドの俳優たちがストライキを実行しました。AIが映像を生成できるようになることで、自分たちの仕事が奪われるかもしれない。俳優たちはそんな危機感を抱いたわけです。ああいった動きが、今後さまざまな領域で起こる可能性があります。AI活用に反対する声にも真摯に耳を傾けながら、社会全体で合意を形成していくことが必要だと思います。beatや博報堂プロダクツも、クリエイティブに関わる立場から、そのような合意形成に向けて積極的な役割を果たしていかなければならないと考えています。
- 木下
- 生成AIの活用が進むことによって、広告会社のクリエイターが必要なくなる。そういった極端な議論があるのは事実です。しかし、広告ビジネスに関わっている実感から言えば、クリエイティブ職がなくなるということは絶対にないと思います。一方、制作現場には生成AIに対する忌避感がまだまだあるとも感じます。すべてをAIに任せるのではなく、またAIを一切使わないということでもなく、AIが得意なところはAIに任せて、それによって空いた時間でどれだけ人間的な仕事ができるか。生活者の心や社会を動かすアイデアをどれだけ生み出せるか。大切なのはそういった考え方です。石﨑さんらのお力を借りながら、そのような前向きな視点で制作現場の皆さんとAI活用について対話していきたいですね。
- 石﨑
- 博報堂プロダクツのメインの仕事は「クラフト」、つまり制作です。
クラフトの対照になる言葉は「インダストリアル」だと僕は思っています。どちらも「ものづくり」ではありますが、クラフトは人の手や頭を使った職人的な営みであり、一方のインダストリアルは機械の力によって自動化された工業的な製品づくりです。もしクリエイティブがAIによって自動化されるとすれば、広告づくりはクラフトではなくインダストリアルになります。しかし、そうはならないし、すべきではないと僕は思います。
- 木下
- まったく同感です。もっとも、AIを活用することで制作ワークのプロセスが変わったり、新しいアイデアを生み出すための切り口が得られたりすることは大いにあると思います。また、生成AIを上手に使えば、これまで別々に動いてきたマーケティングとクリエイティブのスタッフが、具体的なアウトプットのイメージなどを共有しながらディスカッションすることも可能になります。その点で、「クラフト×AI」には大きな可能性があると言えます。
- 石﨑
- AIは、あくまでよりよい制作物を生み出すためのツールということですよね。
- 木下
- そう思います。では、「よりよい制作物」とは何か。
そう考えたときに、単にアイデアやデザインやパフォーマンスにおいて優れているだけではなく、「社会や生活者に新たな価値や未来の可能性や兆しをもたらす制作物」という視点がとても重要になると思います。生成AIを活用した新しいクラフトのあり方を模索する中で、博報堂DYグループのフィロソフィである生活者発想があらためて試されることになる。僕はそう考えています。
生成AIによって「人の心を打つ」精度を上げていく
──それぞれのお立場から、今後のbeatの活動に見通しについてお聞かせください。
- 石﨑
- 博報堂プロダクツは制作のプロである反面、マーケットの情報やプラットフォームの情報に直接触れられる機会は決して多くはありません。本来、制作にはそういった情報が不可欠なはずです。それがないと、誰に対してどのような価値を届けていくかという視点が曖昧になってしまうからです。
beatに博報堂プロダクツが参加することによって、マーケット視点、プラットフォーム視点、生活者視点でのクラフトが可能になると僕は考えています。制作物や制作プロセスの付加価値を高めていくための取り組みを今後も続けてきたいと思っています。
- 木下
- これからbeatが注力していくべきテーマは大きく3つあると個人的に考えています。
「コミュニケーション」「エクスペリエンス」「クラフト」です。
チャットボットやバーチャルヒューマンといった技術によって、企業やメディアと生活者のコミュニケーションのあり方は今後大きく変わっていくはずです。また、メタバースやXRの活用が広まっていくことで、生活者体験もまったく新しいものになっていくと考えられます。クラフトも、ここまで述べてきたように、テクノロジーによってどんどん刷新されていくことは間違いありません。この3つのテーマを探求しながら、ビジネスとして成立するエリアを見極め、そこで活用できるソリューションやサービスを考えていくことが、今後beatがやるべきことであると考えています。
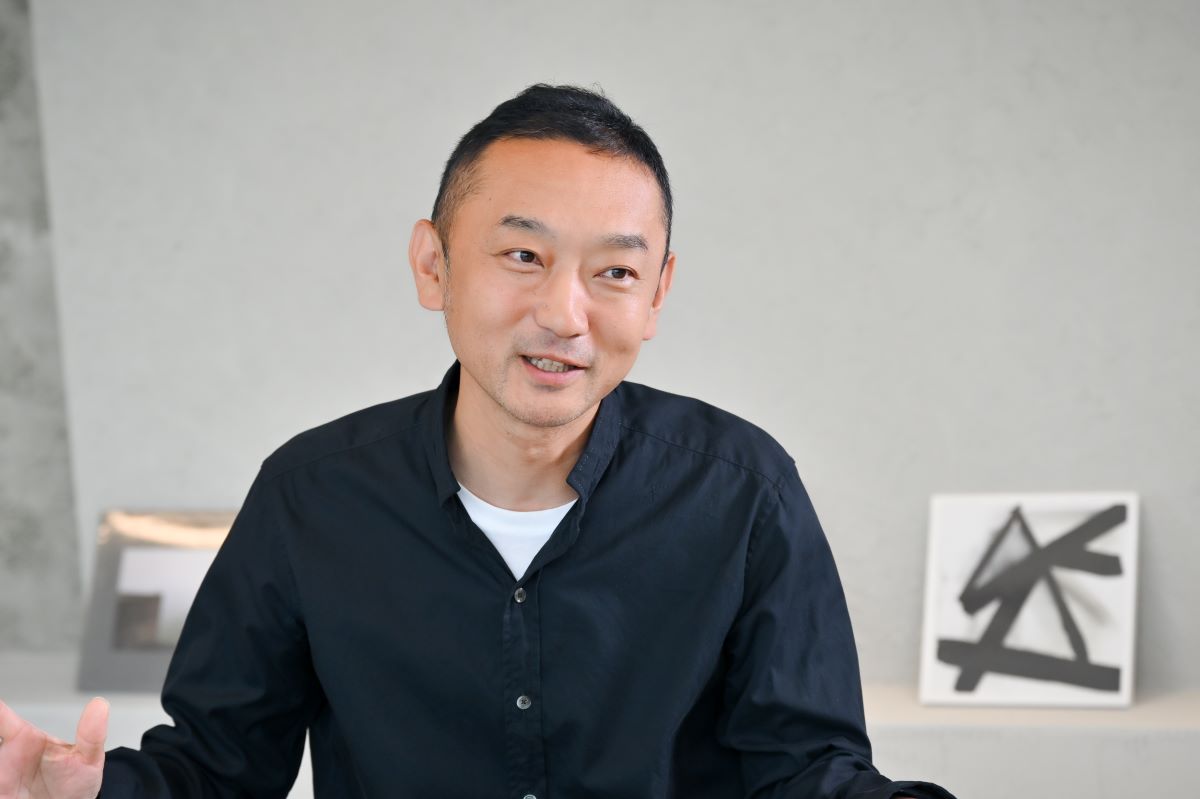
──生成AIの活用もさらに進んでいきそうですね。
- 石﨑
- 生成AIがこれからとくに力を発揮していく領域は、パーソナライゼーションだと思います。個々の生活者に対して最適なアプローチをするには、フルカスタムのオーダーメイドコミュニケーションが必要になります。しかしこれまでは、それを実現するのは技術的にもコスト的にも難しいと考えられてきました。生成AIが登場したことで、そのオーダーメイドコミュニケーションが実現する可能性が高まったと僕は考えています。その人が最も必要としているもの、最も心が動くものを提案していくことができるようになるということです。beatという枠組みの中で、その仕組みづくりを目指していきたいと思います。
──まさに、人の心を打つ(beat)精度を上げていくということですね。最後に、外部から博報堂DYグループのメンバーとなった石﨑さんの立場から、グループのカルチャーやフィロソフィについての率直なご意見をお聞かせください。
- 石﨑
- 僕が博報堂DYグループの一員となったのは5年前でした。グループの皆さんからすれば得体のしれない人間だったと思いますが、そんな僕に対していろいろな人が興味を持ってくれて、僕が手掛けてきたビジネスやスキルなどについてさまざまな質問をしてくれました。新しい人、新しい考え方、新しい潮流などに対する好奇心がとても強い会社であるということを本当に実感しましたね。
テクノロジーが日進月歩で進化する時代に求められるのは、最新の技術に積極的に触れて、いち早くその技術に順応していくことです。その点で、博報堂DYグループには新しい技術から新しい価値を生み出していく素地が間違いなくあると思います。僕もそのマインドを大切にしながら、クラフトの領域でこれまでになかったことにどんどんチャレンジしてきたいと考えています。

この記事はいかがでしたか?
-
博報堂DYホールディングス Creative technology lab beat リーダー
統合マーケティングプラットフォーム推進室 室長
AIテクノロジーG GM
テクノロジスト
-
博報堂プロダクツ 執行役員
Promotion X室 室長