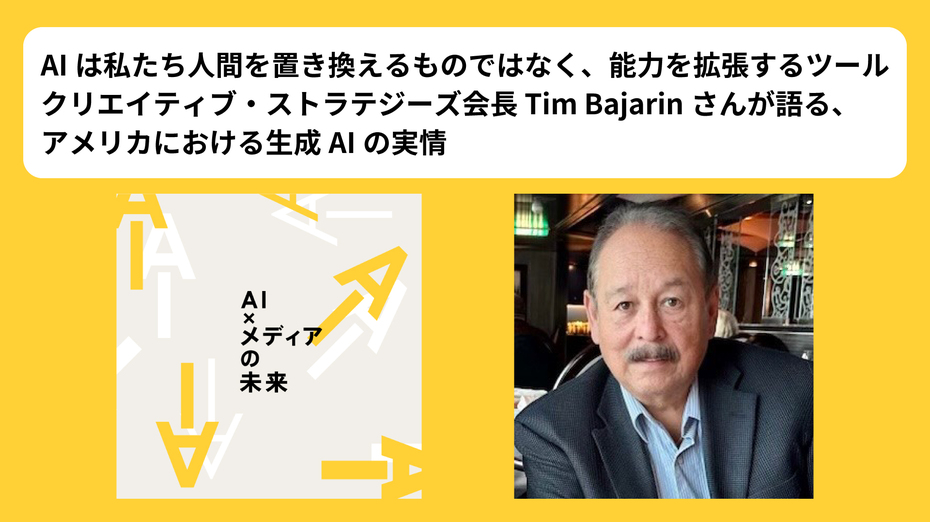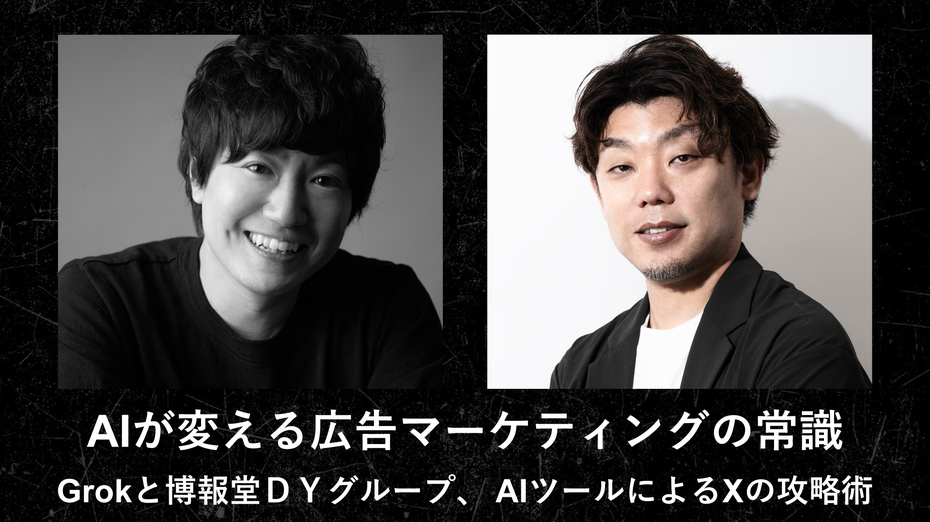マルチAIエージェントがつくる、人とAIの新しい働き方 ~「Nomatica」が挑むマーケティングDXの最前線~
マーケティングにおけるデータ活用やDXが叫ばれるようになって久しいですが、AIは本当に実務に直結する力を発揮する救世主になり得るのか。味の素AGF株式会社が導入したマルチAIエージェントサービス「Nomatica」が、その問いに対する具体的な答えを示し始めています。
自社データを活用した専門家AIエージェントを含む複数のAIが連携して提案を行う「マルチAIエージェント」の仕組みを取り入れることで、調査・資料作成・戦略立案といったマーケティングの諸業務が大きく変化。現場からは「個人による先入観や思い込みのない調査ができる」「打ち合わせ準備の工数が削減された」「専属コンサルタントが常にそばにいるようだ」といった声が寄せられています。
本インタビューでは、導入の背景から具体的な活用事例、そして今後の展望までをひも解き、AIがもたらす“マーケターの新しい働き方”のヒントを探ります。
味の素AGF ファンマーケティング推進部
山本 耕平
味の素AGF ファンマーケティング推進部
岡原 一真
味の素AGF ソリューションビジネス部
斎藤 哲也
博報堂テクノロジーズ DXソリューションセンター
畠山 卓也
博報堂テクノロジーズ DXソリューションセンター
田中 孝明
独自のノウハウやデータを使った専用AIエージェントを作れる点が魅力
――まずは簡単に自己紹介からお願いします。
- 山本
- 味の素AGFファンマーケティング推進部マーケティング高度化グループで、マーケティングリサーチや生活者解析を担当しながら、AI活用の推進もおこなっています。
- 岡原
- 同じくマーケティング高度化グループで、製品まわりのリサーチや生活者調査を担当しています。「Nomatica」については、実際に活用しつつ、効果的な使い方のシェアもおこなっています。
- 斎藤
- ソリューションビジネス部で、コーヒー以外、たとえばココアやスープ等の商品の企画・開発を担当しています。
- 畠山
- 博報堂テクノロジーズDXソリューションセンターのシニアマネージャーとして「Nomatica」のプロダクト責任者をしています。
- 田中
- 同じくDXソリューションセンターでデータサイエンティストとして「Nomatica」の開発に携わっています。
――AIエージェント「Nomatica」の活用を始めたきっかけを教えてください。
- 山本
- 我々マーケティング高度化グループのミッションの一つはテクノロジーの力を使って社内のマーケティング業務全体を進化させることです。その中で、直近の大きなテーマとなっていたのが「AIの活用」でした。会社としてもさまざまな形でAIの導入を試みており、その流れの中でAIエージェントという新しいテクノロジーに注目しました。
中でも「Nomatica」に魅力を感じたのは、自社のマーケティングノウハウや、コーヒーに関する調査データなど、独自の知見を組み込んで専用のAIエージェントを構築できる点です。これは当社の業務に非常に適した仕組みだと感じました。
まずは1か月間のトライアル※1を実施し、社内でヒアリングを行った結果、活用価値が高いという評価を得ました。そのため、まずは希望者から導入を進め、徐々に活用範囲を広げていく方針を決定しました。

- 岡原
- 導入後は、説明会や勉強会を通じて社内への浸透を図りました。特に「Deep Research」や「資料作成モード」といった新機能がリリースされた際には、実際にデモ画面を用いて紹介し、具体的な活用シーンを共有しています。機能の進化にあわせて理解を深めてもらうことで、業務への定着もスムーズに進みました。
- 斎藤
- 私はトライアルの終盤に初めて使用しましたが、その時点で「これはすぐに導入したい」と感じました。それまで利用していた生成AIは、一般的な内容にとどまりやすい印象がありましたが、「Nomatica」は実務に即した、より具体的な提案を行ってくれます。この“業務に直結する精度”こそが、大きな差別化ポイントだと感じています。
- 畠山
- トライアル期間中は、味の素AGF様とともに業務活用の可能性を検証しました。その結果、商品開発やマーケティング領域において、リサーチ・分析・戦略立案など幅広いシーンで活用いただけることが確認できました。AIエージェントが業務のパートナーとして実際に機能しはじめたことを強く実感しました。
博報堂DYグループの生活者に関するデータがAIに活かされている
――実際に使ってみてどんなところに魅力を感じましたか?
- 斎藤
- 最初に驚いたのは、各AIエージェントの「専門性の高さ」でした。他のAIツールと比較しても、こちらの意図をより深く理解し、専門的かつ具体的な提案を返してくれる点が非常に印象的でした。
あるとき、お茶の市場に関する約50ページの資料を別のAIに読み込ませて提案を依頼したところ、一般的な内容にとどまってしまったことがありました。そこで同じ資料を「Nomatica」に読み込ませて分析させたところ、より専門的で実務的な提案が返ってきたんです。そのときに、博報堂DYグループが持つ生活者データの強みが確かに活かされていると実感しました。
一方で、当社では業務用コーヒー以外の分野に関して自社データが少ないため、「Deep Research」を活用する機会が多くあります。ゼロだった情報が1、あるいは2に変わるだけでも業務上の価値は非常に大きいです。コーヒーには含まれない成分の比較や、他業界との関連性など、これまで調べきれなかった領域を補完できるのは助かっています。

- 畠山
- 活用が進んでいるユーザーの多くは、単なるタスク処理ツールとしてではなく、「業務の思考パートナー」として「Nomatica」を位置づけています。たとえば、企画立案のプロセスにおいては、まず「Deep Research」で情報を収集し、その後「相談」モードでアイデアを整理・検討。そして最終的に「資料作成」モードでアウトプットを生成する。そういった一連の流れで、各段階「Nomatica」と対話しながら業務を進めています。
こうした一貫した活用スタイルは、「Nomatica」のベストプラクティスの一つであり、私たちとしても積極的に共有・発信していきたいと考えています。

調査から分析、資料化まで「Nomatica」だけで完結
――社内での活用事例を教えてください。
- 斎藤
- 私の部署では競合調査を日常的に行っていますが、特に中小規模の企業の場合、メディア掲載や公式サイトでの情報発信が少なく、市場に出ている情報だけでは十分な分析が難しいケースが多くあります。
そのような中で「Nomatica」を活用すると、自分で検索しただけでは見つけられない情報を抽出してくれたり、限られたデータからでも深い洞察を導き出してくれたりする点が非常に有用です。さらに、「Nomatica」が出力したレポートをそのまま資料形式に整えてもらうことで、資料作成の工数も大幅に削減できています。上司やチームとのミーティングで即活用できるレベルの精度とクオリティでアウトプットが完成する点は、大きな業務効率化につながっています。
- 岡原
- 外部パートナーと連携する際、最初の段階で「課題が整理できていない」「どの部分を依頼すべきか判断がつかない」といったケースは少なくありません。その点、「Nomatica」は社内にいながら専門家と壁打ちをしているようなレベルの対話が可能です。これにより、外部パートナーへ依頼する前の社内調整や情報整理の負担が大幅に減り、コミュニケーションの効率が格段に向上しました。

- 山本
- 特に価値を感じたのは、「コーヒー市場調査員エージェント※2」を構築したことです。過去の調査データをもとに方向性を提示してくれるこのAIエージェントは、戦略的な意思決定に直結する支援をしてくれました。
以前、事業戦略の方向性に関わる重要な資料作成を任された際、課題が複雑で方向性に悩んでいたのですが、このエージェントに相談したところ、自分では気づかなかった視点やフレームワーク、見落としていたデータを提示してくれました。その結果、納得のいく資料を完成させることができたんです。まさに、AIエージェントが事業判断に寄与した瞬間だったと思います。
また、私たちの部署では継続的に調査を行っているため、過去のデータを活用しきれない場面も少なくありません。今回のようにAIが過去の知見を掘り起こし、新たな提案をしてくれることは、データ再活用の促進という点でも大きな価値があります。
- 田中
- 一般的な検索や生成AI の場合も、その背後には莫大な情報が含まれており、うまく引き出すことができれば有用な情報を取得できる可能性があります。しかし、情報量が膨大であるがゆえに、欲しい情報を正確に取得するのが難しいのが現状です。「Nomatica」は、カスタムエージェントを含めた独自の設計により、公開情報と社内ナレッジをうまくつなぎ合わせ、必要な情報を取得しやすくすることを理念としています。
これまでのお話を伺って、「Deep Research」のような汎用的な調査機能と「コーヒー市場調査員エージェント」のようなカスタムエージェントを組み合わせて情報を抽出し、「資料作成モード」で資料にまとめるという一連の使い方は、機能を意図通りに活用いただいている形であるため、非常に感銘を受けました。
AIに上手く接するコツは「100%を求めない」
――AIに向き合うコツなどありますか。
- 斎藤
- 「Nomatica」に限らず、AI全般との向き合い方に共通して言えるのは、“100%の答えを求めない姿勢”が重要だということです。正直に言えば、AIから返ってくる回答が必ずしも自分の求めているものと一致するとは限りません。
AIに「最終的な正解」を期待してしまうと、思ったような成果が得られないこともあります。そうではなく、AIを“最終アウトプットを導くためのインプット”として活用したり、自分の考えを整理するための補助ツールとして使う。そうした心構えで向き合うことで、より実践的で有効な使い方ができると感じています。
- 畠山
- 私たちは、AIと人が明確に役割を分担することで、より大きな成果を生み出せると考えています。
たとえば、AIは「成功確度を高めるパートナー」として、リサーチ・レポート作成・データ分析・初期企画案の生成や壁打ちなどを担当します。一方で、人は「新たな価値を創造する存在」として、AIが収集したデータや仮説をもとに判断し、人を動かし、実現へと導く役割を担います。
つまり、AIに“答え”を委ねるのではなく、AIが提供する情報やアイデアをもとに“人が意思決定する”という役割分担を徹底することが重要です。こうした体制が整えば、より魅力的な製品や広告をスピーディーに市場へ届けることが可能になります。
- 田中
- AIと人の役割分担を明確にし、人は最終的な意思決定に集中することが重要です。そしてAIはそのための補助ツールである。この考え方は基本となると考えています。
AIを活用される方の中には、AIの出力内容に些細なズレが生じ、人間が修正する手間がかかることを懸念される声もあるかもしれません。しかし、AIの進化は目覚ましく、半年足らずでこれまで「AIにはできない」と思っていたことができるようになるケースも珍しくありません。だからこそ、AIとの向き合い方として重要なのは、現段階でできることだけに焦点を当てるのではなく、将来的な変化を見据えて業務への組み込み方を柔軟に考えていくことです。最終的な判断や価値づけは人間が担う——この役割分担を前提としながらも、AIの成長を見越した戦略的な活用姿勢が求められると考えています。

今後も企業に新しい働き方を提供し、イノベーション創出に貢献したい
――今後の展望を聞かせてください。
- 山本
- 今後は、コーヒー市場調査員エージェントにさらにデータを追加し、私が介在しなくても「Nomatica」が自律的に回答できるようにしたいと考えています。
理想は、「自社のブランドマネージャー」のようなAIエージェントに育てることです。現在は、他部署やチームメンバーから日々さまざまな質問を受けていますが、AIエージェントが一次回答を担えるようになれば、やり取りの初動を効率化できます。結果としてメンバーはスムーズに情報を得られ、私もチームメンバーとのディスカッションに時間を割いたり、新しい業務にチャレンジしたりと、可能性を広げることができる。そうした相互効果を期待しています。
- 岡原
- 今後は、毎月の定例報告など定型業務の自動化にも取り組みたいと考えています。マーケターの業務は、データの収集・整理・報告資料の作成などに多くの時間を取られるのが現状です。そのような業務をAIに任せることで、マーケター自身がより創造的で戦略的な業務に集中できる環境を整えたいと思っています。AI活用の目的は単なる効率化ではなく、「人がより価値を生み出す時間を確保すること」だと考えています。
- 畠山
- 今後は、お客様が保有するデータを活用した“企業独自のAIエージェント”構築をさらに推進していきたいと考えています。
特に、生活者調査や過去のマーケティング施策の企画・効果分析など、長年にわたって蓄積された大規模データについては、活用したいという要望がある一方で、その運用に課題を抱える企業も少なくありません。
こうした場合、長年のデータを学習したAIエージェントを構築することで、誰でも容易に情報を検索・分析し、インサイトを得ることが可能になります。結果として、山本様や岡原様が述べたように、ブランドマネージャーやマーケターがよりクリエイティブな発想に時間を割けるようになる。私たちは、そのような“人とAIが協働する新しい働き方”の実現を支援していきたいと考えています。
※1 サービスローンチ以前の限定トライアル。2025年9月に受付終了。
※2 味の素AGF様が保持しているデータを用いて作成した専用AIエージェント。

この記事はいかがでしたか?