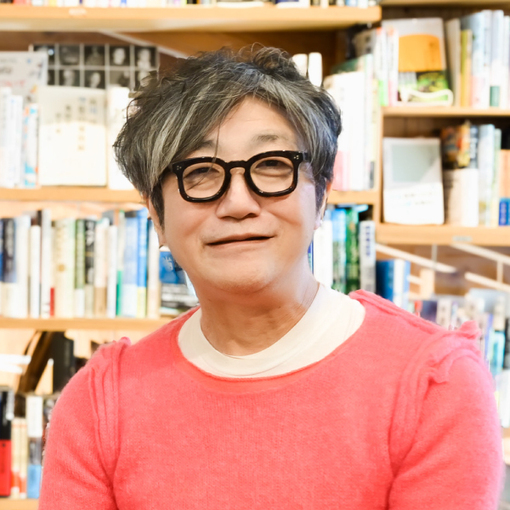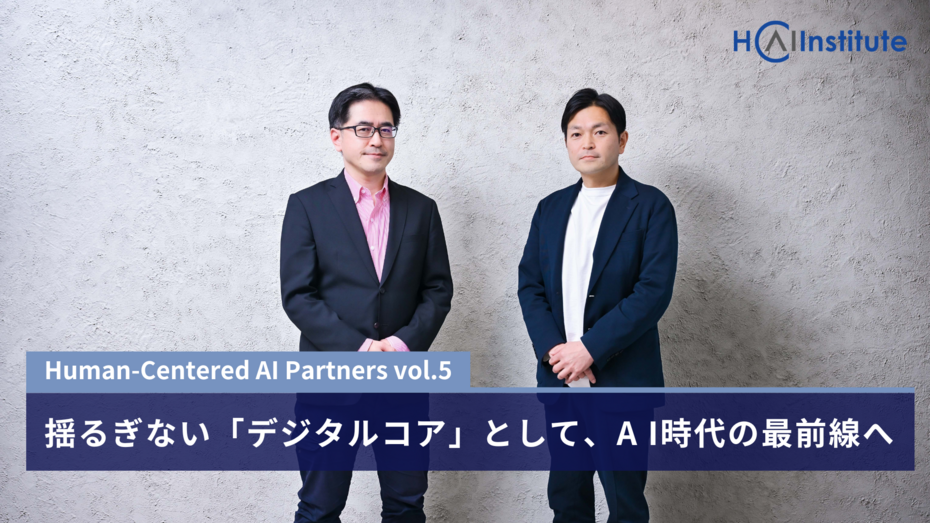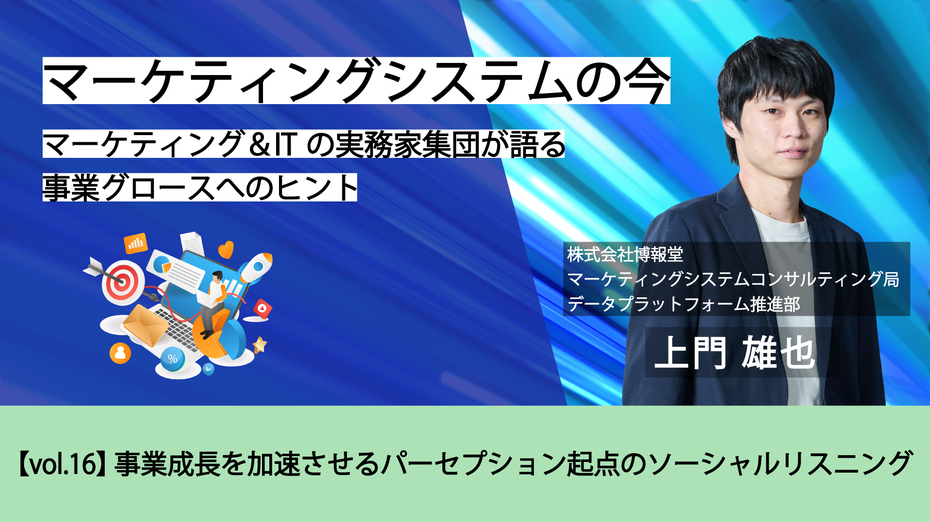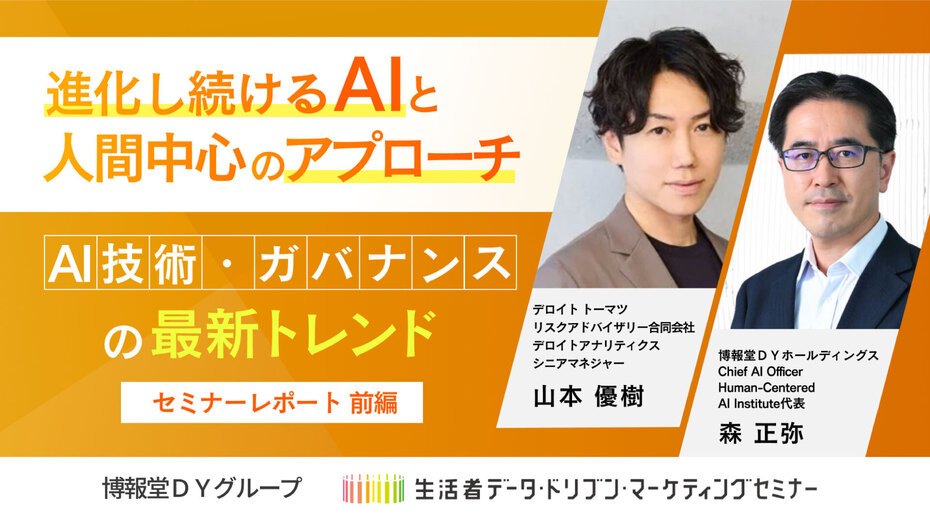対談〈AI PARTNERS〉第3回──AIを「あたりまえ」にする方法、AIで「あたりまえ」をつくる方法
博報堂DYグループのAI研究拠点「Human-Centered AI Institute」の代表を務める森正弥とグループのキーパーソンが語り合う連載〈AI PARTNERS〉の第3回。今回は、東京・下北沢の「本屋B&B」を経営、「本屋大賞」の立ち上げにも参画し、昨年『「あたりまえ」のつくり方──ビジネスパーソンのための新しいPRの教科書』を上梓した嶋浩一郎とともに、AI活用のアイデアを掘り下げていきます。
嶋 浩一郎
博報堂 執行役員 エグゼクティブクリエイティブ・ディレクター
博報堂ケトル ファウンダー
森 正弥
博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO
Human-Centered AI Institute代表
AIの「空気を読まない力」をどう活用するか
- 嶋
- 大好きな話があって、チェスの世界チャンピオンがAIに負けたのは1997年のことだったんですが、負けたチャンピオンがどうしたかというと、AIと人間のチームをつくってチーム同士での対戦を始めたんですよね。AIを敵にするよりも協力しあった方が、さらに強くなる。きっと、AI相手にチェスをしながらそう気づいたのでしょうね。AIはバディ(相棒)にすべき存在だと。
では、AIをバディにして優れたチームをつくるにはどうすればいいかっておもうんですけれど、以前、あるセミナーで森さんとお話ししたときに、森さんは「AIは他人からどう思われるかを気にしない。忖度するということがない。それが強みである」とおっしゃっていました。その視点がAIとのチームづくりの大きなヒントになると僕は思っています。
優れたマーケターは、世の中でいち早く行動を起こす「ファーストペンギン」の行動を観察して、そこから次の時代の兆しや新しいインサイトを発見します。しかし、これは簡単なことではありません。なぜなら、人はどうしても「人というのはこうあってほしい」とか「こうあるべき」という意識を働かせて、観察した結果をきれいに整えてしまうからです。インサイトを無意識に捏造してしまうと言ってもいいかもしれません。
その点、AIはまったく忖度しないし、無意識の願望を働かせたりもしないので、事実や現象から捉えたことをもとに、結論をストレートに導き出します。偉い人に「ですよね」とか会議で相槌打っちゃう人を見てAIは、「あの人、そんなこと思ってないはず」といい当てちゃう。
インサイトを発見する力において、AIは場合によっては優れたマーケターを上回るかもしれません。そのAIの力と人間の力を合わせれば、とても強力なチームができるのではないか。そんなふうに思います。

- 森
- いわば「空気を読まない力」ですよね。最近のAIはその力がどんどん強化されているように感じます。とくに生成AIが進化し、因果推論AIと呼ばれる技術が登場してから、ロジックを積み重ねてよりストレートな答えを出す傾向が強まっています。もっとも、Googleの〈Gemini 2.0〉のように、空気はまったく読まないのだけれど、答えを出したあとに「役に立ちましたか?」とか、「以上がアドバイスになります。頑張ってくださいね」といった気遣いのメッセージを加えるAIもあります。
- 嶋
- AIが空気を読まなすぎることに腹を立てた開発者がいたのでしょうね(笑)。一方で森さんがおっしゃっていた人間の強みは「人はつまらないと感じることができること」。AIは何でもズバズバ言ってくるけれど、その内容が面白いとは限らない、むしろつまらないことの方が多い。つまらないか面白いかを直感的に即座に感じられるのは人だけで、AIにはつまらないものを排除する力はないのだと。
森さんのそのお話を聞いて、AIにも強みと弱みがあることがよく理解できました。その理解が進むと、AIとつき合うのがグッと楽になりそうです。
- 森
- 最近は、AIごとの「性格」の違いもよく感じます。AIの性格に合わせてつき合い方を変えるという方法もあると思います。例えば、〈ChatGPT〉と〈Gemini〉は空気を読まない性格は共通していますが、〈ChatGPT〉に若さが感じられるのに対して、〈Gemini〉には先ほどお話ししたような気遣いがあります。一方、〈Claude〉は言葉遣いに文学的知性があるように思います。
- 嶋
- なるほど、AIごとのキャラの違いも出てきているわけでね。それを聞いて、なおさらAIとつき合いやすくなったような気がします。
AIを世の中の「あたりまえ」にする方法
- 森
- 嶋さんはご自身の著書『「あたりまえ」のつくり方』の中で、PRとは新しい「あたりまえ」をつくるテクノロジーであるとお書きになっています。世の中の「あたりまえ」は常に更新されていきます。では、AIは新しい「あたりまえ」になれるのか。嶋さんはどうお考えですか。
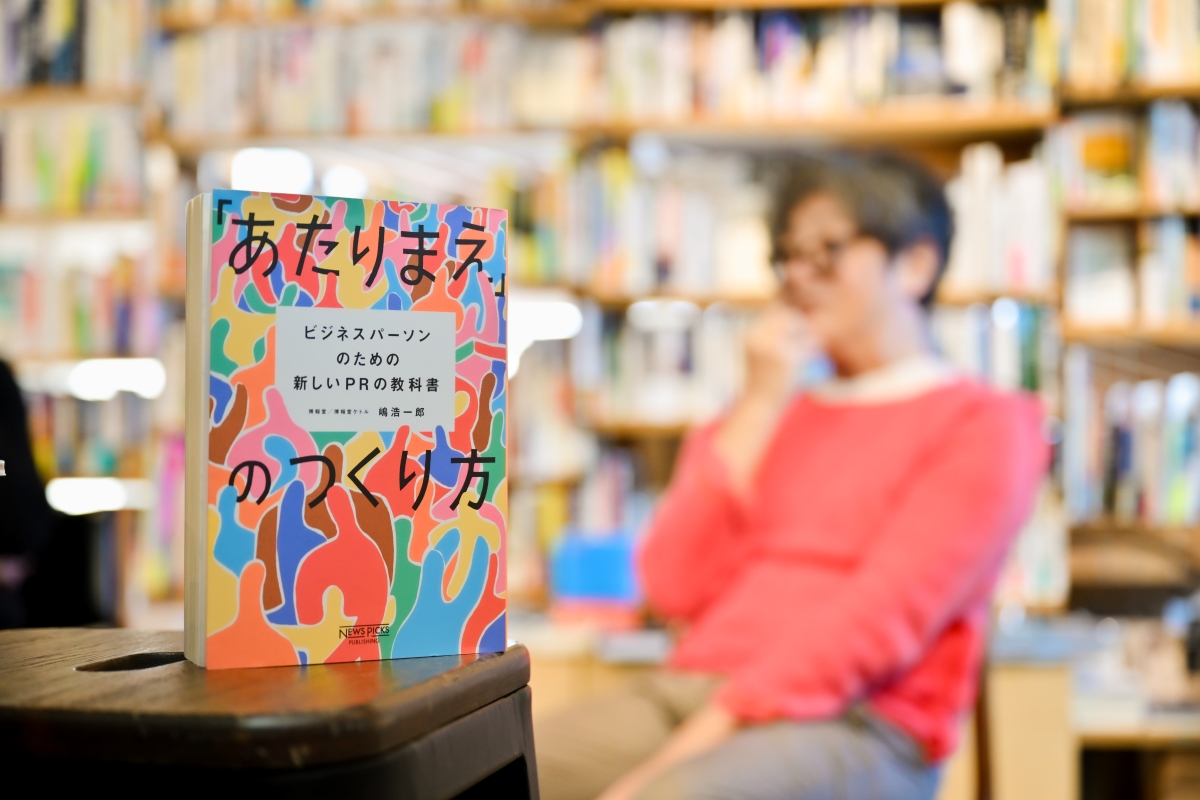
- 嶋
- 新しい事象やテクノロジーが「あたりまえ」のものとして定着していくには、受容や解釈の多様性が必要であると僕は思っています。事象の受け手やテクノロジーの使い手が自由に解釈し、独自の発想を広げていける余地があること。それによって、新しいものは文化となり、世の中の「あたりまえ」になっていく。そう考えています。
例えば、日本の寿司職人がアメリカ人に寿司を教えた結果、カリフォルニアロールという日本にはなかった新しい寿司が生まれました。寿司づくりの原理主義の立場からすれば、アボカドを使うような寿司は邪道かもしれません。しかし、そのような新しい寿司が生まれた結果、寿司の裾野が世界中に広がり、文化として定着していったわけです。
AIにも同じことが言えると思います。AIには性格の違いがあるというお話がありました。それは、人とAIが多様な関係を結べるということであり、AIが出してくる答えを多様に解釈できるということだと思います。いろいろな人がいろいろな形でAIをバディにし、多様な成果を出していくことができれば、AI活用の裾野が広がり、AIがある世界が「あたりまえ」になっていくのではないでしょうか。

- 森
- 自由に選択ができて、解釈できる余地があって、クリエイティブで多様なアウトプットを出すことができる。それによって、多くの人がAI活用を自分ごと化して、AIを利用するシーンが世の中に広がり、定着していく。カリフォルニアロールが寿司の裾野を広げ、寿司が世界的な文化になっていったように──。そういうことですね。
AIで「あたりまえ」をつくる方法
- 森
- もう1つお聞きしたいのは、世の中の「あたりまえ」をつくることにAIはどう貢献できるのかということです。僕は、「あたりまえ」をつくるための「組み合わせ」のアイデアを出すところにAIを活用するのが有効なのではないかと思っています。
僕はこの間、まったくの別領域にある2つの概念の相違点と共通点、シナジーの可能性をAIに説明させるということをやってみました。例えば、「生成AI」と「ブルーオーシャン戦略」という2つの概念があります。人間から見れば、それぞれ何の関係もないので比べる意味もないということになりそうですが、AIは意味があるかないかを考えずに説明してくれます。結果、AIは次のような答えを出しました。
「生成AI」と「ブルーオーシャン戦略」の相違点は、一方がテクノロジーであり、一方が企業の競争戦略であることである。共通点は、「どちらも新しいものを生み出すことができる」ことである。そしてシナジーは、「企業がブルーオーシャン戦略を描いたときに、新しいビジネスモデルのプロトタイプを生成AIでスピーディにつくることができる」こと、あるいは「ブルーオーシャン戦略によって創出した新しいビジネスを生成AIによって効率化していく」ことである──。

- 嶋
- とても面白いですね。すごく距離があるように見える2つのものの間に、実は共通点があり、組み合わせによるシナジーも期待できる。そのことをAIが教えてくれるわけですね。
僕が『「あたりまえ」のつくり方』で書いたのは、「こういうことが世の中のあたりまえになったらいい」と合意してくれる人の裾野が広がれば広がるほど「あたりまえ」は定着しやすくなるということでした。誰かが目指したいと考える未来があって、それに賛同してくれる人をたくさん集めることで新しい「あたりまえ」をつくっていく。ときには、最初は新しい価値観にネガティブな態度を示した人たちも含めて新しい「あたりまえ」を浸透させていった時に、「あたりまえ」はより強固なものになっていく。そんな合意形成を進めることがPRの重要な役割であると僕は考えています。
ポイントは、意外なプレイヤー同士、距離が離れているように見えるプレイヤー同士の合意をつくることです。協力し合うプレイヤー間の距離が離れていれば離れているほど、より遠くまで飛ぶことができます。しかし、そのような「意外な協力者」を見つけることは簡単ではありません。そこにAIの力を使えるのではないかと僕は思います。
このメーカーはこんなものをつくっている。このNPOは地域でこんな活動をしている。この大学ではこんな研究をしている──。AIがそんな発見をしてくれて、それぞれの結びつきのあり方を提案してくれれば、これまでになかった官民共創プロジェクトや事業開発のフォーメーションがつくれるかもしれない。それがAIによって新しい「あたりまえ」をつくっていく1つの道筋になるのではないでしょうか。
- 森
- 人間から見たら共通点がないと思われるプレイヤー同士が結びつく可能性をAIに考えてもらうということですね。
- 嶋
- そう、「生成AI」と「ブルーオーシャン戦略」の共通性とシナジーをAIが見出したように。それは一種の編集作業であると言えます。これからの広告会社は、異なるプレイヤーや異なる要素を組み合わせて新しい価値を生み出す編集者のような役割を担うようになるはずです。その編集作業に活用できる強力なツールがAIなのだと思います。
セレンディピティの宝庫としての本屋
- 森
- 本屋B&Bは、書籍の並び方が一般の書店とは違っていて、いろいろな発見があります。セレンディピティ(偶然の出会いや発見)の宝庫という感じですね。

- 嶋
- 40坪ぐらいの小さな店舗で、棚をひと通り見るのに5分もかかりません。しかし、そこには恋愛小説があり、アポロ計画の本があり、苔の研究書もある。本の陳列にも意外性がある。わずかな時間でものすごい量の情報に触れることができる。それがこの店の大きな特徴です
例えば、私が立ち上げに関わった「本屋大賞」の第一回受賞作品である小川洋子さんの『博士の愛した数式』という小説があります。これは数学者が出てくる話なので、この本の隣に数学者のポール・エルデシュの本が並んでいてもいい。また、その数学者は熱心な阪神タイガースのファンという設定なので、野球に関するエッセイが隣にあってもいい。小川さんの作品だけを並べるとか、小説だけを並べるというのとは違った棚のつくり方がありうるわけです。とくに優れた小説の世界観は複雑で多様なので、組み合わせの可能性は無限にあります。おっしゃるように、そこにセレンディピティの可能性が大いにあります。メタバース技術が進んだらいつか追い越されてしまうかもしれませんが、現在のところ、セレンディピティという点でリアル書店はネット書店を凌いでいると僕は思っています。
- 森
- 私は楽天の研究所のファウンダーなのですが、その最初の研究所を設立したとき、僕が最初に手掛けたのは楽天ブックスにおけるAI活用の研究でした。その研究で僕がぶつかったのが「村上春樹問題」でした。この本を買った人は、この本も買っている──。そういう分析を繰り返していくと、どこからスタートしても最後は村上春樹の本、あるいは『ハリー・ポッター』シリーズに行き着いてしまう。それを僕は「村上春樹問題」と呼んでいました。
データとAIを使った書籍リコメンドの仕組みをつくると、結局一番売れている本をすべての人に薦めてしまうことになってしまうわけです。売り上げを上げるという点ではそれでいいのかもしれませんが、ユーザー体験という視点から見れば、かなりお粗末な仕組みと言わざるを得ません。この問題を完全に解決した人はまだいません。
それに対して本屋B&Bは、人間の発想で優れたセレンディピティの機会をつくり、豊かな顧客体験を創出しています。嶋さんがおっしゃるように、まさにテクノロジーを凌いでいると言えると思います。

- 嶋
- 本と本の組み合わせは多義的である──。それは言葉自体の多義性に通じます。例えば、国際語として人為的かつ合理的につくられたエスペラント語は、言葉と意味の対応関係がほぼ1対1になっています。しかし、僕たちが知っている言葉には多義性があります。「優しい」という言葉から、家族や友人の人柄を想起する人もいれば、素材の触感の柔らかさをイメージする人もいます。
最近、ウィトゲンシュタインやクラウスといった言語哲学者の本を読む機会がありました。ウィトゲンシュタインはこんなことを言っています。人は単語をそれ自体ではなく、文脈の中で捉えている。だから、文脈によって単語の意味やイメージが変わることを受け入れられるのだ、と。
リアル書店もそういった文脈をつくる場です。一冊一冊の本のコンテキストを考え、多様な書籍を並べて、生活者に新しい発見を促すことができるのがリアル書店の強みです。AIを活用することで、オンライン書店でもいずれそういったことができるようになると思われますか。
- 森
- 本屋B&Bのような体験をAIがつくり出すにはまだ時間がかかると思います。クリエイティブなコンテキストをつくれるのは今のところ人間だけです。もちろん、その文脈づくりにAIの力を借りることは可能です。AIが出すヒントをもとに、新しい文脈、意外性のある文脈を人がつくっていく。それが現時点における人とAIのあるべき関係と言えるのではないでしょうか。
この記事はいかがでしたか?
-
博報堂 執行役員 エグゼクティブクリエイティブ・ディレクター
博報堂ケトル ファウンダー1993年博報堂入社。2002~04年博報堂刊「広告」編集長。2004年「本屋大賞」創設に参画。2006年博報堂ケトルを立ち上げ多数の統合キャンペーンを実施。雑誌「ケトル」の編集等コンテンツ事業も手がける。主な著書に『欲望する「ことば」~「社会記号」とマーケティング』など。カンヌクリエイティビティフェスティバル、ACC賞など多くの広告賞で審査員も務める。
-
博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO
Human-Centered AI Institute代表外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用したDX、企業支援、産業支援に従事。東北大学 特任教授、東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、日本ディープラーニング協会 顧問。著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。