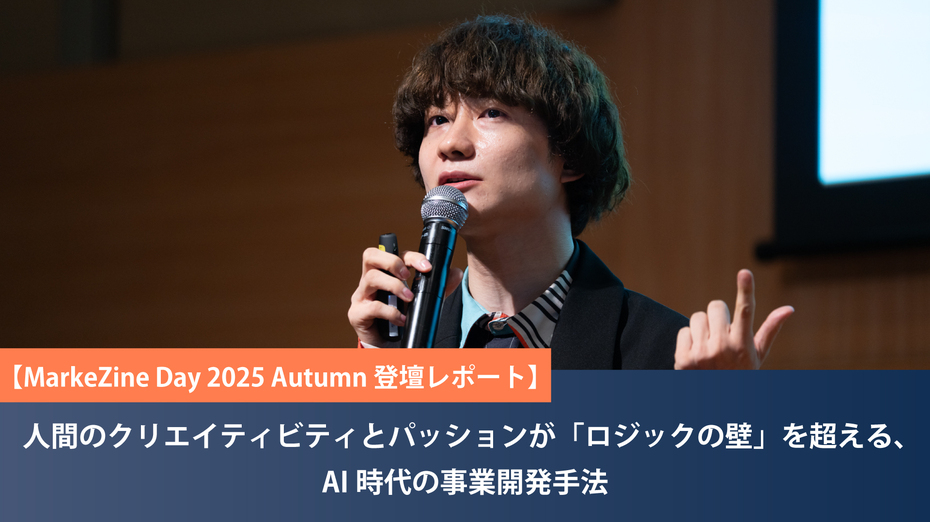万博レガシーを社会実装する異業種3社の挑戦。「医療の手前」にある新たなヘルスケア市場を切り拓く(前編)
半年間の会期を経て閉幕した大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンでは、「カラダ測定ポッド」による未来のヘルスケア体験が提供されました。
日常にヘルスケアが溶け込んだ社会の実現を見据え、大阪ヘルスケアパビリオンにおける体験を継続的に提供していくために博報堂、BIPROGY、JR西日本3社で構成される「PHRコネクト共同企業体」が発足。
各社の強みやアセットを活かし、生活者目線やクリエイティビティを起点にした新たなヘルスケアサービスや体験の場をつくっていく。
今回は、3社がタッグを組んだ理由や各社の役割、「カラダ測定ポッド」の反響についてプロジェクトのメンバーに話を聞きました。
参考リリース:博報堂、BIPROGY、JR西日本、PHRコネクト共同企業体として
大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンにおける体験の社会実装に向けた事業を推進
三宅 裕昭氏
BIPROGY
事業開発本部 事業推進三部長
畑 康介氏
西日本旅客鉄道
デジタルソリューション本部 ソリューション営業企画部 WEST LABO事業共創
ヘルスケアPJ統括/DotHealth OSAKA店舗計画・設計・施工責任者
岩宮 克臣
博報堂
関西マーケットデザインビジネス推進局
チーフビジネスデザイナー/事業共創コンサルタント
万博レガシーの社会実装へ。PHRコネクト共同企業体の挑戦
── はじめに、皆様の自己紹介をお願いします。
- 岩宮
- 私は博報堂の関西支社でマーケットデザインビジネス推進局に所属しており、ビジネスデザイナーとして事業創出におけるコンサルティングやビジネス設計を担当しています。今回のプロジェクトでは「PHRコネクト」という組織でBIPROGY、西日本旅客鉄道(以下 JR西日本)とともにチームを組み、事業共創に携わっています。 特に大阪・関西万博におけるレガシービジネス(パビリオン終了後の継続事業)の事業設計や経営/運営推進をリードする立場として本プロジェクトに参加しています。
- 畑
- 私はJR西日本において建築分野を出発点とし、これまで駅舎をはじめとする建設計画・設計・施工に携わってきました。現在はJR西日本 デジタルソリューション本部 ソリューション営業企画部WEST LABO事業共創に所属し、新規事業開発を担当しています。
本プロジェクトにおいては、JR西日本内のヘルスケアPJ推進の統括的な立場から関与しており、JR大阪駅構内のヘルスケアサロン「DotHealth OSAKA」についても、建築計画から設計・施工に至るまでを一貫して手がけました。現在はこの拠点や弊社アセットを活用し、事業の検証、他企業との共創を推進しています。
- 三宅
- 私はBIPROGYの中でも事業開発部隊に所属しており、社会課題解決に資する事業創出を担当しています。BIPROGYはITの技術基盤を活かしながら、新規事業開発にも積極的に取り組んでいる企業です。こうしたなかで、「日常の中にヘルスケアを溶け込ます」という志のもと、大阪ヘルスケアパビリオンでの取り組みを活用しながら、ヘルスケアに関する社会課題解決を進めていきたいという思いで今回のプロジェクトに参画しました。
本プロジェクトの本質的な目的は、「万博のレガシーを社会実装していくこと」だと考えており、PHRコネクト共同企業体では当社が代表企業を務めています。
── PHRコネクト共同企業体が推進するのはどのような事業になりますか。また、PHR(Personal Health Record)についてもお話しいただきたいです。
- 岩宮
- PHRコネクト共同企業体では、日常生活の中で手軽に健康状態を把握し、一人ひとりに最適化されたヘルスケアサービスを享受できる体験の社会実装を、万博会期後も継続的に取り組んでいくことを目的とした事業です。
具体的には、「カラダ測定ポッド」による健康データの計測サービスや、健康データを継続的に管理できる新しいアプリケーションの開発、「DotHealth OSAKA」内での新商品・サービスの紹介など、生活者が日々の日常生活の延長で、無理なく健康管理や健康対策ができる環境を整え、心身ともに豊かな社会を実現することを目指しています。
PHRとは、個人が自身の健康に関する情報を、一元的に収集・管理・活用するための仕組みを指します。PHRを活用することで、個人の健康診断の結果や服薬履歴、日常の活動量データなどを自ら管理できるようになり、そうした健康データをもとにパーソナライズされたヘルスケアサービスを受けることが可能になります。
パビリオン展示を引き継ぎ、各企業のシナジーで新しい価値を生み出す
── 異業種の3社が「PHRコネクト共同企業体」を構成し、今回の事業に取り組むことに至った経緯についてお聞かせください。
- 三宅
- 元々BIPROGYでは、医療業界向けに病院の電子カルテシステムなどを提供していましたが、5~6年前から、個人のパーソナルデータを活用して何か新しい価値を提供できないかと考え始めました。
しかし、日本では、主体的に健康行動を起こす文化があまり根付いていません。そのため、ヘルスケア領域で新たにビジネスを広げるには、健康状態の可視化からその人に合ったサービスの提供までを一気通貫で行う必要があると感じました。
とはいえ、弊社単独ではそのアセットを持っていなかったのですが、今回博報堂からお声がけいただき、大阪ヘルスケアパビリオンの展示を、PHRコネクト共同企業体として引き継ぎ、社会実装していくという形で進めることになりました。
- 岩宮
- 大阪ヘルスケアパビリオンには450社以上の企業が出展し、多くの事業者から関心を集める展示となりました。この経験から、単なるイベントにとどまらず、社会実装へとつなげるためには、各企業が持つ知見や強みを結集してシナジーを生むことが重要だと考え、「PHRコネクト共同企業体」を立ち上げました。
特に、医療の手前のヘルスケア領域では、PHRを活用することで、生活者のニーズを捉えた商品開発や販売促進にもつなげられると考えています。
例えば、野球やサッカーといったスポーツでは以前に比べて、指標を示す数値データがすごく増えているんですね。その結果、表彰の種類や分析の切り口も多様化して、スポーツの見方が広がり、盛り上がりに貢献していると思います。

ヘルスケアに関しては、これまで数値化できる領域が少なかったため、自分で管理したり比較したりする仕組みも育っていませんでした。しかし近年のテクノロジーの進化により、身体の様々な健康指標を数値化・評価できるようになっています。今後、自分の健康状態を見える化し、具体的な指標をもとにしたセルフマネジメントや、エンタメ性を伴った新たなサービスが生み出せるのではと考えています。
従来のダイエットやトレーニングは、カロリーや筋肉量などに注目していましたが、健康や美容の価値はそれだけではありません。免疫力の高さや脳の活性度、肌のキメの細かさなど、“自分の魅力を引き出す指標”はたくさんあります。
このようにヘルスケアの指標を可視化することで、単なる他人との比較ではなく、「自分の人生に彩りを加える健康のあり方」を示すことになり、それが結果的に企業の新たな商品開発やサービス開発にもつながっていくと考えます。
- 畑
- 私からは、JR西日本がヘルスケア分野に関わるようになった背景についてご説明します。その背景には、コロナ禍での経験が深く関わっています。
鉄道事業を中核としてきた弊社は、パンデミックによる移動需要の急減に直面し、運輸収入が大幅に落ち込みました。この出来事は、「鉄道に頼った収益構造では持続的に会社を支えられない」という課題を社内に強く印象づけました。そこで、新規事業の開発に本格的に取り組む必要性が明確になり、その一つの柱とできるようヘルスケア分野への参入を検討してきたという経緯がございました。
私たちは以前からライフサービス分野にも注力しており、その延長線上で「日常生活に寄り添う新しい価値を生み出すこと」をテーマに掲げました。そのなかで、博報堂と連携しながら「事業共創ラボ」という枠組みを立ち上げ、新しい事業の可能性を模索してきました。
議論を重ねていくなかでヘルスケア分野に注目したのは、JR西日本の持つ日常的な移動の動線や、駅空間、生活インフラとしての接点を最大限に生かせる分野だと考えたからです。鉄道ネットワークや施設を通じて、生活者に対して自然にヘルスケアサービスを届けていきたい。そのような思いから、新規事業開発の一環として今回の取り組みを進めています。

大阪・関西万博での協賛にあたっても、弊社がセンサーやシステムを複合的に組み上げていくという鉄道に携わる企業としての技術的な強みを持っていたことから、新しい価値創出に貢献できると思い、プロジェクトに参画したのが始まりでした。
「医療の手前のヘルスケア」に見出した生活者のインサイト
── 大阪ヘルスケアパビリオンで展示した「カラダ測定ポッド」の反響はいかがでしたか。
- 三宅
- 「カラダ測定ポッド」では心血管、筋骨格、髪、肌、歯、目、脳の7項目の健康データを測定できるのですが、当初は世の中的にも、健康予防領域でのデータ利活用に対して懐疑的な声がありました。
というのも、日本では先ほども述べた通り「病気になってから動く」という人が多く、「お金を払って自分の健康を維持する」という文化が根づきにくい傾向があります。
そんななかで、我々は大阪・関西万博の場で予防・健康増進の文化を新しく作ることに挑戦してきました。取り組みを継続していくうちに、最初は半信半疑だった人も、実際に「カラダ測定ポッド」を体験し、自分の健康データが可視化されることにポジティブな感情を持つようになり、共感してくれる人が増えていきました。また、プロジェクトの注目が高まるにつれて社内の理解も進み、サポートしてくれる部署も増えていったのです。

今回の取り組みでは、これまでの「健康診断」や「人間ドック」といったものとは異なり、ヘルスケアをよりカジュアルで身近に感じてもらえるようになったことは大きな変化でした。
- 岩宮
- 博報堂もこれまで多くのクライアント企業とヘルスケア領域の事業に携わってきましたが、健康維持や健康管理といったテーマは、どうしても課金のハードルが高く、継続的に利用していただくサービス化する上での難しさも感じてきました。
ヘルスケアという言葉は非常に広く、スマートウォッチで歩数や消費カロリーを記録する日常的なものから、生活習慣病予防のような医療寄りのものまで幅があります。しかし、医療に近い領域になると専門的な領域の話になってしまい、なかなか一般の生活者を巻き込んだ盛り上がりを作りづらかったんです。
ところが、大阪駅構内に設置した「カラダ測定ポッド」では、病気の診断を目的としたものではなく、脳の活動や体のちょっとした変化を、生活の延長線上で手軽に計測できるものだったこともあり大盛況でした。半年間の実証実験を通して、想像以上に生活者の方の関心が高いことがわかったのです。
今回の取り組みでは、肌を定期的に測りたいというニーズが非常に高く、また目の動きから脳の認知機能を測定することにも興味を持つ方が多かった印象でした。
自分の肌の状態を知って化粧品選びに役立てたい、自分のコンディションを把握しておきたいといったように、「定期的に健康データを測って、自分の健康状態を確認したい」という生活者のインサイトを発見できたのは大きな成果でしたね。
今までビジネス化が難しいとされてきた「医療の手前のヘルスケア」とは異なるニーズが存在し、そこには確実に新しいビジネスチャンスがあると感じました。私たちのチームとしても、この領域をもっと深掘りして、サービスを磨いていく必要があると思っています。

カラダ測定ポッド
- 畑
- 弊社も、JR大阪駅構内にあるヘルスケアサロン「DotHealth OSAKA」を実証実験の場として運営していますが、万博が始まる前は社内でも「本当に人が来るの?」という懐疑的な見方がありました。
しかし、いざスタートしてみると予想以上の反響で満員御礼の日が続き、万博の
会期が終わるまで、その勢いがずっと続いたんです。店舗には計測用のポッドが2台設置されていて、1回の測定に6分程かかるのですが、営業時間内に対応できる人数が限られてしまうこともあり、日によっては2時間待ち、長い日は3時間待ちという日も珍しくありませんでした。
それだけ多くの方が「自分の健康状態を測ってみたい」と感じ、来店されていたということで、健康への関心の高さを実感する結果となりました。

後編に続く
この記事はいかがでしたか?
-
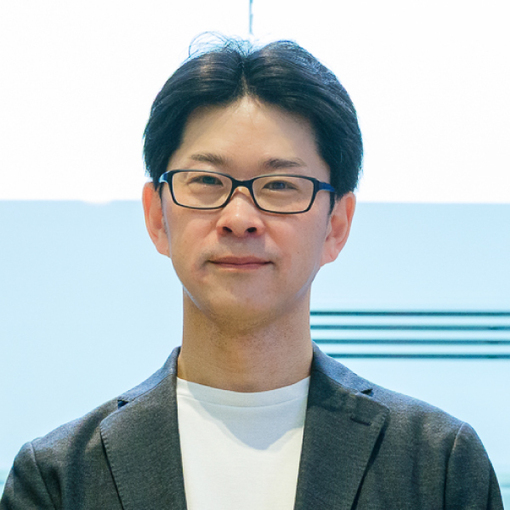 三宅 裕昭BIPROGY
三宅 裕昭BIPROGY
事業開発本部 事業推進三部長2001年BIPROGY(旧日本ユニシス)に入社。
営業部門において、主に官公庁(中央省庁/地方自治体)向けのシステム構築を担当。その後、官公庁と医療機関(病院等)向けSIビジネスの責任者として従事。2018年度に新設されたスマートシティ戦略本部を兼務し、観光やヘルスケアに関する新規事業創出に携わる。現在は、新規事業を担うビジネスクリエーション部門に所属し、ヘルスケア等の事業開発の責任者を務める。
-
 畑 康介西日本旅客鉄道
畑 康介西日本旅客鉄道
デジタルソリューション本部 ソリューション営業企画部 WEST LABO事業共創
ヘルスケアPJ統括/DotHealth Osaka店舗計画・設計・施工責任者2015年西日本旅客鉄道に入社。
建設工事部門において、広島・大阪・奈良エリアでの大規模改修工事、新駅設置、支社ビル移転などの設計・品質管理・施工管理を担当。その後、駅ホーム上の人流緩和を目的としたデジタル実証実験や、うめきた地下駅をはじめ、同社のアセットを活用した事業共創プロジェクトに携わる。現在はライフデザイン領域における新規事業開発を推進し、「ステーションヘルスケア構想」の事業化に向けたプロジェクト統括を務める。
-
博報堂
関西マーケットデザインビジネス推進局
チーフビジネスデザイナー/事業共創コンサルタントフロントプロデューサーとして、食品/生活用品/医薬品/流通/通信/旅客など多様なクライアントのマーケティング支援を経験したのち、2010年から業務主軸をコンサルティング領域にシフト。複数の共同事業(JV)を組成し事業マネジメント経験を積んだのち、現在は チーフビジネスデザイナー/DXコンサルタントとして、お得意様の事業開発コンサルティングとともに、自社/共創事業の組成/育成に従事。日本マーケティング協会講師(実践的事業創造)。