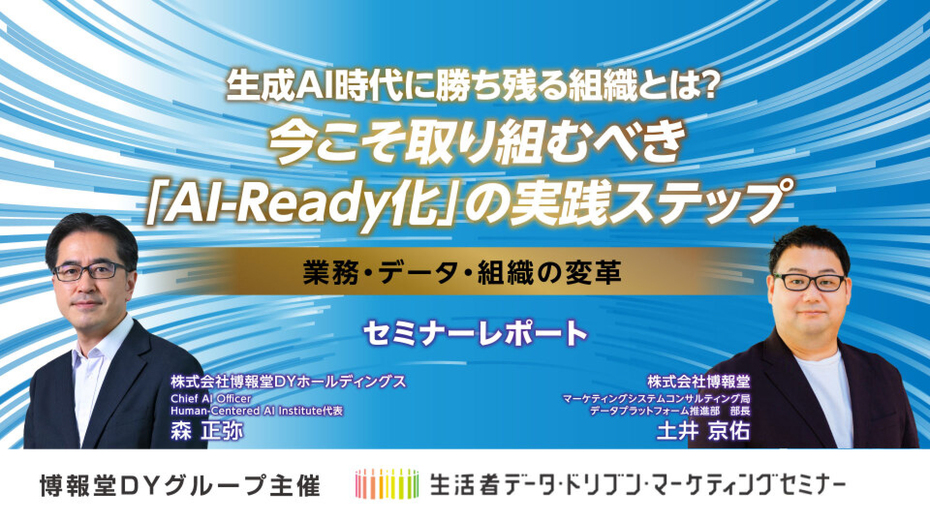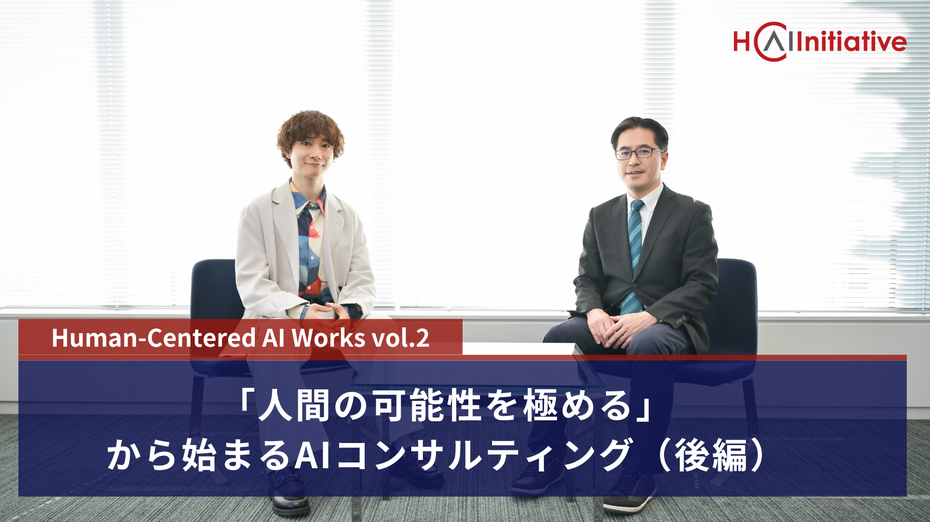対談〈AI PARTNERS〉第9回 「AI Ready」の時代における価値提供のあり方や仕事の進め方
博報堂DYグループのAI研究の拠点「Human-Centered AI Institute」の代表である森正弥が、博報堂DYグループがAIに取り組む意義、また企業のパートナーとして提供できる価値について対話を通じて掘り下げていく連載〈AI PARTNERS〉 。今回は読売広告社デジタルコンサルティングセンター長 立田真一郎に「AIを活用した価値提供のあり方」や「AIを活用した戦略」などについて聞きました。
企業のパーパスやDNAに沿ってAIが判断する時代へ
- 森
- 目まぐるしく変化するAI技術ですが、読売広告社(以下、YOMIKO)では現状の市場環境をどのように捉えていますか?
- 立田
- AI技術の進化が加速する中で、YOMIKOでは「GAME CHANGE PARTNER」というビジョンを掲げ、クライアントの事業パートナーになるべく、AIに関する設計・導入支援を行っています。現在特に力を入れているのが、AIエージェントの設計・導入支援です。
私たちは、これからの5年間を「仕事のプロセス」に焦点を当てる重要な期間と捉えています。クライアントに新たな価値を提供するためには、従来の業務プロセスを見直し、AIという技術をどのように取り入れ、業務の付加価値を高めていくかが重要になると考えています。
現在、AIに関して3つの技術的なコンセンサスがあると捉えています。
1つ目は、人間の知能をAIが大きく超えていくという点、2つ目はユーザーの行動を先回りして自律的に動く“アンビエントエージェント”の発展。3つ目はロボティクスの領域の進化です。こうした技術進化の方向性が見えてきた今、多くの人々が関心を寄せるのは、「仕事の進め方」や「価値の生み出し方」をいかに変革していくかという点です。私たちも、こうした変化や、クライアントが課題と感じていることに対して、具体的な答えを提示できる存在でありたいと考えています。
AIは単なるソリューションの導入で完結するものではありません。組織全体のオペレーションにどう浸透させるかが鍵になります。そして、AIの力を最大限に活かすためには、人間側のスキルや意識の変革も必要です。つまり、個人のスキルだけでなく、組織としてのスキルや企業としてのケイパビリティも同時に高めていく必要があります。
さらに、既存の資産やレガシーな仕組みとの整合性を考えながら連携していくことも不可欠になってくるため、人・組織・仕組みの全体最適を意識した取り組みが重要になります。

- 森
- YOMIKOグループとしては「AI×ストラテジー」「AI×クリエイティブ」「AI×データビジネス」という異なる専門性を持ったチームを組成し、あらゆるケイパビリティを総動員させていると聞いています。
- 立田
- 私たちは大きく分けて、戦略設計を担うチームと、データやエンジニアリングを担当するチーム、そしてクリエイティブを作るチームの3つで構成されています。それぞれが「AI」を積極的に活用しながら、連携して活動しています。
今年の9月には、グループ会社であるYOMIKO Digital Shiftの業務のAIエージェント化の進捗について発表しました。これは、業務プロセスを分解・モジュール化し、複数のAIエージェントが相互に連携し、それぞれの役割を果たしながら1つの大きな業務を遂行できるようにするというものです。このアプローチによって、業務そのものの効率化やPDCAサイクルの高速化はもちろんのこと、人間では到達しづらい新たな価値の創出や、従来よりも厚みのある提案ができると考えています。
さらに、今回発表したAIエージェント化は、単に指示通りに動くだけでなく、企業の掲げるパーパスやビジョンと整合性を持って業務を遂行するように設計しています。というのも、AIエージェントには目の前のタスクに直線的に取り組む傾向があり、企業の理念や価値観と衝突するリスクがあるためです。私たちはこの課題に着目し、AIが組織の「DNA」と調和した判断を下せるようにするための技術開発を進めてきました。このプロトコルはYOMIKOでの実証実験を経て、クライアントの皆さまにも順次サービスを提供していく予定です。
- 森
- 非常に興味深いですね。パーパス経営という考え方は一時期大きな注目を集めましたが、企業の掲げるパーパスを各事業部や社員一人ひとりの行動レベルにまで落とし込んで浸透させることは、現実的にはなかなか難しいという課題がありました。その後、パーパス経営とデータドリブン経営を結び付けて、各部署や個人のKPIが本当にパーパスと整合しているのかをデータで可視化して、評価しようという試みも見られました。企業のパーパスに最終的な顧客への提供価値をどうアラインさせていくかというのは継続して重要なテーマだと思います。
AIエージェントが出てきてAIが自律的に判断・行動できるようになった今、AIエージェントの処理がパーパスに沿っているかどうかも大きなテーマになるというのはなるほどと思いました。AIの判断軸が会社のDNAやブランドのフィロソフィー、組織のパーパス、ビジョンとぶれないように設計することが、これまで以上に重要になってくると感じました。
- 立田
- 他社でもブランドガイドラインを遵守して画像生成を行う取り組みは進んでいますが、組織内に存在する隠れた力学が作用する領域については、まだあまり取り組みが進んでいないのが現状です。そうした見えにくい領域こそ、AIの活用が重要になると考えており、今まさに我々も積極的に取り組みを進めているところです。
具体的には、組織が掲げるパーパスやビジョンをベクトル化し、AIに読み込ませたうえで、その価値観に沿った行動ができているかをモニタリングする仕組みを設けています。
またどのタイミングで監視するのか、どのように報告・再評価を実施するかといった確認フローを設計することで、AIの活用が組織の方向性と整合するようにしています。こうした仕組みを通じて、AIが企業の理念や価値観と調和した判断を下せるよう支援することが、私たちの目指す方向です。
企業のパーパスは「AI前提」へアップデートする
- 森
- 少し気が早い話かもしれませんが、逆の見方で考えてみると、企業のパーパス自体も、AIエージェントがパーパスを遵守しながら行動することを前提に設計しなければならないという話になってきますよね。パーパスも 「AI Ready」の時代に入ってくると考えると、すごく面白い気がします。

- 立田
- まさにAIエージェント時代にふさわしいパーパスを、今こそ再定義していく必要があると考えています。それと並行して、組織運営のあり方も見直す時期にあると考えています。
たとえば、組織を現場・ミドルマネジメント・トップマネジメントというレイヤーに分けた場合、それぞれが持つ情報の質や意思決定のプロセスにはどうしても差が出てきてしまいます。オフィススイートツールを使って、情報が伝達されているように見えていても、実際は現場の声が上層部に届かず、逆に経営層の意図が現場まで浸透していないケースも少なくありません。
こうした課題に対しては、AIが組織内のデータを継続的に収集・蓄積し、必要な情報を抽出して、各レイヤー層に適切に届ける仕組みを構築することで、これまで以上に質の高い意思決定が可能になるはずです。
さらに、組織運営の中にAIをどう溶け込ませていくかという観点も重要です。今はどうしても画像や動画の生成、自動マーケティングのようなわかりやすい活用領域ばかりが注目されがちですが、実際にはその裏側、組織の見えにくい部分にこそ大きな可能性があると私たちは思っています。
- 森
- パーパスについて、もう少し踏み込んで考えてみたいのですが、「パーパスが今の時代の変化に耐えうるものになっているか」という問いも出てくる可能性があると思っています。特にこれから本格化するAIエージェントの時代においては、再考すべき点が非常に多いのではないかと。コンプライアンスの問題で見ると、現在のルールや制度は基本的に「人が遵守すること」を前提に設計されていますが、もしAIエージェントが担うことになった場合はどうするのか、といった議論はこれから本格化するでしょう。
同様に、SaaSなどのインターネットサービスの利用規約も、「人間の利用」を前提に作られていますが、AIエージェントが自動で物を購入するような場合には、規約違反になるケースも出てくるため、現行の利用規約を大幅に見直す必要があるかもしれません。
このような課題を踏まえると、AIエージェントの時代に向けてパーパスをどのようにアップデートするかというのは、コンプライアンスや利用規約といった周辺制度も含めた包括的な視点で行う必要があります。そのなかで、企業同士の関係性や提供しているサービスの構造自体をどう設計し直していくのかを考えていかなければなりません。

- 立田
- AIの進化が加速する中、私たちは「AIの性能」そのものよりも、「AIをどう活かすか」という設計思想こそが、企業の成果に直結すると考えています。例えるなら、AIの能力は関数で言うところの“y切片(b)”に過ぎず、真に重要なのは“傾き(a)”すなわち、AIを活用することで組織を成長に導く設計です。
どれほど高性能なAIであっても、それを組織やビジネスの中でどう活かし、どう成長につなげていくかという視点がなければ成果につながりません。そのためには組織の意思決定プロセスや情報の流れ、現場と経営層の連携、意思決定の在り方など、構造的な見直しが必要不可欠だと考えています。
最近では、「やりたい仕事」に応じて、AIエージェントのテンプレートを選択し、クラウド上で完結。さらに他社のシステムと連携して取引までスムーズに行えるような仕組みも登場してきています。そうなると、企業は基本テンプレートをベースに、自社のパーパスや業務特性に合わせたカスタマイズを加えることで、独自のAIエージェントを構築することが可能になると考えています。
私たちは、こうしたAI活用の“設計”に重点を置いた支援を行っています。実証実験を通じて得られた知見をもとに、クライアントの皆さまに対して、業務プロセスの再構築や意思決定支援、AIエージェントの導入設計など、実践的なソリューションをご提供いたします。
人間とAIが共鳴する“ソフトな距離感”を理解しておく
- 森
- 社員のAI活用についてはどのようにお考えですか?
- 立田
- 人間の頭脳と違って、AIは常にアップデートされてパフォーマンスが向上していくので、その時点で最も優れたAIを引き出して業務に活用できることが重要です。クライアントに対して最善の提案をするためにも、常にその最新の知見を参照できる状態を保つことが欠かせませんし、実際に社内でもそう伝えています。
YOMIKOでは「AI駆動プランニング」という形で、社内展開を大規模に進めています。これまでの業務の進め方では、クライアントからオリエンを受けてから、社内で議論し、仮説を立てて方向性が見えるまでに1週間ほど要しており、初動対応に課題がありました。そこを変えるために、AIを活用して初期検討フェーズのスピードアップに取り組んでいます。
初動を早めることで、ヒアリング回数を増やしたり、最適なチーム編成を行ったりと、提案内容の質を高める活動に時間を割けるようになります。AI導入の最大の目的は、企画書を作成する作業ではなく、その前後の本質的な業務に集中できる環境を整えることにあります。
とはいえ、非エンジニアでDifyのようなAIツールを自在に使いこなせるレベルに達しているメンバーがまだ限られているという課題もあります。そういう観点では、ITスキルとAIリテラシーを土台にしながら、最新のAIの知性を日々の仕事に組み込んでいくスタンスが大事になってくると考えています。
まずは初期フェーズとして、AI駆動プランニングに強い関心を持ち、自ら学びを実践できる人材の育成に重きを置いています。全員に同じレベルの知識を一律に与えるというよりも、自走力や熱量を持って実践できる人たちを社内にどれだけ育てられるかが、中長期的にインパクトが大きいと考えています。
YOMIKOでは、そうした人材がAIを仕事に取り入れる様子を周囲が見て、「自分もやってみたい」と自発的に学び始める流れができていて、「濃いユーザーを育てる」ことに注力する戦略は結果的に正しかったと実感しています。

- 森
- スタンフォード大学のジェレミー・アテリー教授の言葉に、「創造性とは最初に思いついたこと以上のことをやること」というものがあります。つまり、最初の調査やプラニングをAIに任せるのはいいんですが、そのアウトプットをそのまま使ってしまうのは創造とは言えないと。むしろ、AIが出した最初の案を超えていくことが人間のクリエイティブな仕事だというわけですね。AIが100点満点を出したとしても人間が価値を付加して120点に変えられるか。あるいは、200点、300点まで目指せるか。それが大事かと思います。
YOMIKOの「AI駆動プランニング」というのは、まさにAI時代における戦略的・創造的な仕事の再定義だと思っています。AIを起点にすることでより早く、深く本質にたどり着き、人間ならではの視点で創造性を発揮していくやり方が、これからの時代に求められる新しい戦略構築の在り方を体現しているのではないでしょうか。
AIと人間との関係について考えるときに、私自身が感じているのは、「AIを単なる道具として扱う」という視点ではなく、人間が本来持っている創造性とAIが共鳴し合うような関係をいかに築くかが肝になるということです。クリエイティブなプロセスは、何かに刺激されたり影響を受けたりしながら、徐々に形になっていくものですよね。
AIについても、単に「使いこなす」ではなく、人とAIが対話するようにお互いを触発し合えるような構造や仕組みを作っていくことが欠かせないと思っています。
- 立田
- 私たちのようにクリエイティビティを核にしている組織にとっては、創作活動の中にAIが共鳴するような形で入り込んでくると、これまで人間では届かなかったところが届くようになるというか。ある種、AIとの“ソフトな距離感”を理解しておくことが、これからの創造的な仕事において非常に重要になってくるかもしれません。
- 森
- 立田さんが仰った話の中で、「ソフトな距離感」というのはすごく重要なキーワードだなと。これはパーパスの話にも通ずると思うんですけど、AIエージェントによって組織の有り様を変えていくというのは単に効率化の話ではなく、AIと共に社会を作っていくというわけです。
また、AIに依存しすぎてしまえばバランスが崩れてしまうからこそ、AIと人間がどう関わっていくのか。そのちょうどいい距離感をいかに築いていけるかが大事になってくるでしょう。そういう意味でも、立田さんの意見は非常に本質的で、自分の中でもしっくりと腑に落ちました。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
- 立田
- 社会やクライアントから期待される存在であり続けるため、新たなAIの分野を牽引していく枠組みの一つがHCAI(Human-Centered AI)だと思っています。そして、YOMIKOもその一翼を担いながら、主体的に取り組んでいきたいと考えています。
AIエージェントの進化によって、これまでの「生成AI」という言葉の枠組みも大きく塗り替えられていくでしょうし、おそらく来年以降は「AGI(汎用人工知能)」といったキーワードも、さらに広く語られるようになってくるかもしれません。
博報堂DYグループ全体でもさまざまなAIに関する取り組みが進んでいるので、ぜひそこにも注目し、期待していただけたら嬉しいです。
この記事はいかがでしたか?
-
読売広告社 デジタルコンサルティングセンター センター長
デジタルストラテジスト2013年、株式会社読売広告社に入社。
デジタルと戦略を融合し、企業のDX推進・新規事業開発・AI活用をリード。広告・プロモーションからCRM設計、データ基盤構築、AIエージェントを用いた業務自動化まで、幅広い領域で実績を持つ。独自のソリューション開発やマルチエージェント基盤の設計を通じ、持続的な競争優位を生む仕組みを創出している。
-
博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer
Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。
内閣府AI戦略専門調査会委員、経産省GENIAC-PRIZE審査員、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー。
著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。