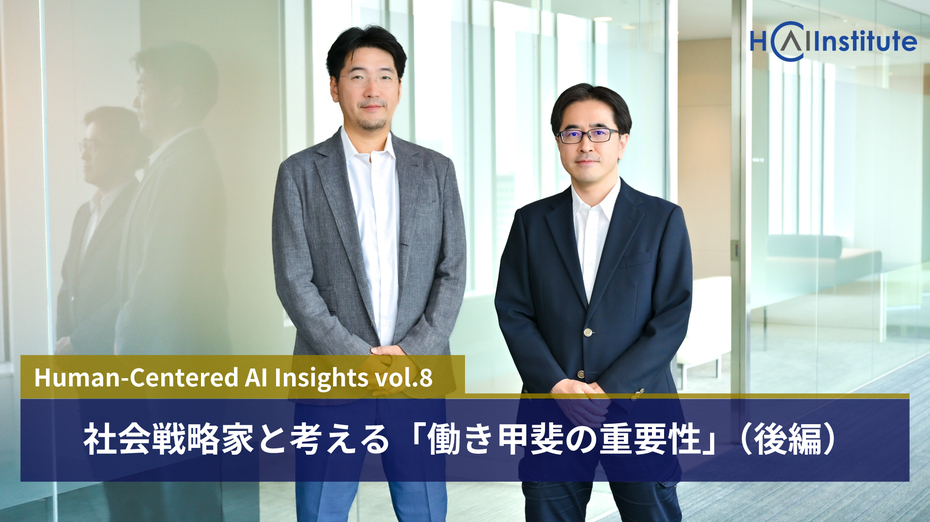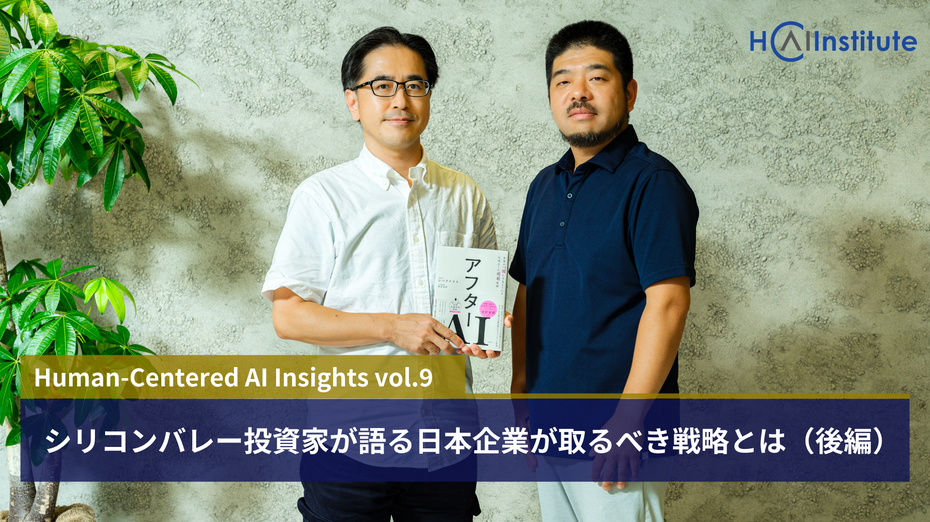

シリコンバレー投資家が語る日本企業が取るべき戦略とは(後編)
博報堂DYホールディングス 執行役員/CAIO 兼 Human-Centered AI Institute代表の森正弥が、業界をリードするトップ人材と語り合うシリーズ対談「Human-Centered AI Insights」。
NSVのパートナーとしてシリコンバレーの新興VCへのファンド投資、スタートアップへの直接投資を担う柴田 尚樹氏をお迎えした対談の後半です。前編では、2025年8月に出版された著書『アフターAI』や生成AIに対する日本の強みについてお伺いし、後編ではAI Readyとなるために必要なことや、今後のAI発展について議論していきます。
>前編はこちら
AI-Readyな社会で生き残るためには経営層のコミットメントが不可欠
- 森
- 柴田さんは投資家として、企業の情報を幅広く見渡すことで、他の人が見落としがちなベストプラクティスや現場のペインポイントを分析していることが理解できました。日本全体を見ると、AI-Readyな社会になるべく、各社でデータ整備を進めていますが、柴田さんが課題に感じていることや、真のAI-Readyな社会になるために必要とされることは何だとお考えですか?
- 柴田
- 日本に限らず多くの企業では、社内に必要なデータがあっても「部署間で共有できない」「アクセス制限がある」といった理由で、AI活用ができていないケースが少なくありません。もちろん、情報漏洩やセキュリティ対策は必須ですが、既存ルールのままではAI活用の推進に必要なデータを自由に使えない局面も出てきます。
この課題を解決するには、社長のコミットメントが重要です。経営層が「AIで会社を変える」と公言することで、社内におけるAI活用の優先順位が上がり、ルール整備もスムーズに進んでいくようになります。
もう一つ大事なのは、AI活用の目的をはっきりさせることです。多くの企業はAI導入の目的としてコスト削減を掲げますが、「売上を伸ばす」というポジティブな目的でAIを活用すると、会社全体のモチベーションや取り組み方が大きく変わります。ネガティブな目的だと、どうしても社員は不安になりがちですが、ポジティブな目的であれば前向きにAIを活用する文化が生まれやすくなります。
- 森
- コストカットにばかり目を向けると人員削減ありきの議論になってしまいがちですが、AIを導入するならアップサイドを想定するべきだと思います。やはり、色々な日本企業と話していても、データは部署ごとに階層的に管理されていて、「このデータはこの事業部門のものだから、他部署は利用不可」といったデータガバナンスのルールがしっかり構築されている印象を受けました。
そのようなルールを忠実に残した状態でAI活用を進めようとすると「部署内に閉じたAI」しか作れず、効果が限定的になってしまう。AIで価値を生み出すためには、部署間の壁を崩してデータをつなぎ直し、業務プロセスを再設計することが重要になるわけです。
- 柴田
- 実際には部署Aと部署Bでほとんど同じ業務プロセスを持っているのに、「部署が違う」とか「担当部長が別」などの理由だけでデータを一緒にできないケースが多いんですよね。本来AIを導入すれば一つに統合できるのに、これでは非効率だと言わざるを得ないと思っています。
- 森
- ペンシルベニア大学のイーサン・モリック准教授が提唱する考え方である「AIの不都合な真実」には、多くの人が既存のビジネスプロセスを過信しすぎているという指摘があります。要するに、既存の業務プロセスはよくわからない工程が複雑に入り組んでいる。AIを導入する時にはその複雑な工程を無理やりAIに置き換えるのではなく、ゼロベースでの再設計が不可欠だという主張だと言えます。
こうした視点を持つと、先ほどの「部署をまたいでプロセスを共通化する」ことも自然に発想できますし、本来のあるべき業務プロセスをAIで再構築し、バリューチェーン全体の効率化を図るといった方向にもつながると思います。

- 柴田
- ひとつ面白いサービスを紹介すると、とあるアメリカのスタートアップでは主に官公庁向けに「不要なソースコードを削除する」サービスを提供しています。官公庁のシステムは案件ごとに発注して作られたコードが積み上がっているため、サーバーの中には使われていないコードが山ほど眠っています。そのため、誰もどれが本当に必要なのか、あるいは不要なのかを把握できていないゆえに、セキュリティホールが狙われるリスクが高まっている状態になっているんです。
こうした課題を解決するために、「AIで使っていない古いコードを削除する」というサービスの発想が生まれたわけですが、実際に売上も大きく伸びています。結局のところ、AIの進化が目まぐるしい変革期においては、「部分最適」を積み重ねても限界があるので「全体最適」を優先的に進める方が効果が大きいんですよね。ただし、これを現場レベルで進めるのは難しく、全体最適に踏み切るには経営層のコミットメントが不可欠だと考えています。
- 森
- 日本企業がAI活用を進めていくために全体最適を図っていくうえでは、本当にリーダーシップを発揮できるCDO(チーフデジタルオフィサー)やCAIO(チーフAIオフィサー)のような存在が必要なんですよね。経営層がAIにコミットする姿勢を明確に示さないと、現場レベルではどうにも動けない。
その重要性を組織全体に浸透させなければ、現場レベルではなかなか動くことができません。経営層自らが旗振り役となり、「AIをどう活用し、どのように事業変革に結びつけるか」という組織の方向性を定めていくことが求められるのではと思っています。
AIを単なるツールではなく「後輩」のように接することが大事
- 森
- 当社グループでもDifyのエキスパートが450名以上いて、次々とAIエージェントを作って業務の高度化を果たしています。驚いたのは、これが進むと自然にMCPサーバーを立て始めて、従来のRPAとは全く違う次元の自動化が進んでいるような感覚があります。業務プロセスを細かく分解し、それぞれに特化したAIを開発することで、プロセス全体のオーケストレーションは格段に進めやすくなります。その結果、従来では難しかった業務プロセス自体の根本的な再設計や改善も現実的な選択肢として考えられるようになっていくわけです。
- 柴田
- 例えばAIエージェントを1人100個作っても、全て実用的になるわけではありません。しかし、そのくらい数をこなしていくと、「MCPサーバーが必要」ということに自然と気づくようになるんです。つまり、AIが日進月歩で発展するカオスな状況では「まずは数をこなすこと」が重要ですし、あるタイミングで「量が質に転換する瞬間」が訪れるんですね。
投資においては、「月に2件しか投資しないなら、100件も案件を見るのは時間の無駄だ」と指摘されることもあります。しかし、多くの案件に目を通すことで、さまざまなケースを比較検討し、試行錯誤を重ねることができます。この過程を通じて、投資判断の精度や視野が広がり、最終的に選ぶ案件の質が高まるわけです。
- 森
- クリエイティブな業界では「アイデアの100本ノック」ということはよく言われますよね。これは、いきなり質を追求するよりも最初はまず量を重視して多くのアイデアを出し、その中から優れたものを選び磨いていくというアプローチですが、AIも同様に数多くのモデルを作成し、試行錯誤を重ねることで性能や精度が自然と向上していくわけですね。
- 柴田
- まさにその通りです。何をするにも数をこなすことが重要です。
- 森
- 少し人間とAIの関係についても触れたいと思います。博報堂DYグループでは「人間中心のAI」というコンセプトの元、AIの研究やAIのビジネス実装を進めています。「人間中心のAI」という言葉自体は、1999年にISOで定義された「Human-centered Design(人間中心のデザイン)」から来ています。当初はシステムのUIやUXに関する概念で、ここで言われている“Human(人間)”はシステムを使うエンドユーザーのことだと明示的に指していました。エンドユーザーに限られていたとも言えると思います。つまり、ユーザーのニーズや意思決定を支援する範囲に限定されていたわけです。
ところが近年では、AIの適用範囲が広がり、需要予測や不正検知、自動運転などの領域に入り込むことで、リスク管理やガバナンスの議論も加わり、AI開発者や事業者も「人間中心」といった際の対象に含まれるようになっています。
「人間中心のAI」という概念を理解するうえでは縦軸に「人間とは何を指すか?」、横軸に「中心とは何を指すか?」の2軸で考えるとわかりやすくなります。まず縦軸では、従来「人間」はシステムのエンドユーザー(利用者)を指していた。それが、リスク管理やガバナンスの議論が加わり、「開発者」や「事業者」も入ってきた。ですが、今やAIの影響力は極めて大きくなり、直接的にAIを利用していない人もその影響を受けるようになっている。例えば、AIによる都市交通の最適化やエネルギー管理、AIを用いた犯罪防止などを考えれば、AIが生活者の生活にまで大きな影響を与えるようになっていることがわかります。つまり「人間」は「生活者」にまで拡張している。横軸では、従来「人間中心」の「中心」とは「人間のニーズをどう満たすか?」「意思決定をどう支援するか?」を意味していた。それが「AIが人間にとって安全であること」「人間がAIを管理できること」の意味にまで広がってきた。そして今や、主体的にAIを使うことで人間の能力がどう高まるか、可能性がどう広がっていくかという点にまで拡張されてきている。縦軸の「人間」の指す意味が生活者にまで及び、横軸の「中心」の指す意味が創造性にまで及んでいるというのがとても重要なポイントなのだと思っています。
博報堂DYグループは生活者は単なる消費者ではなく、働き手、学び手、家族、恋人、配偶者など、多面的な役割を持ち、創造的に生き活動していく人間だと捉えています。この全体像を理解して初めて、AIも生活者に寄り添った形で設計・活用できると思っています。

- 柴田
- とても大事なことだと思います。人間中心のAIを考えるうえで外してはいけないポイントは2つあります。まず大事なのは、やはりAI活用の中心が人間であるべきだということです。人間が便利になったり、幸せになるためにAIを使うことが最も大切だということです。やはり、人間の利便性や幸福度の向上にAIを使うのが本質的だと思っています。
さらに、付け加えるとAIを単なるツールやソフトウェアとして扱うのではなく、“可愛い後輩”や“同僚”のように接することも大事になるでしょう。この考え方を採用すると、ビジネスの成果も上がりやすく、企業や社会全体としてもAIと自然に共存しやすくなるのではと考えています。
日本のロボット開発は世界の「主要プレイヤー」になる可能性を持っている
- 森
- 今日の対談の中でも、柴田さんは「人間と同じ目線でAIと接する」という点を一貫して大事にされていると感じました。アメリカの技術哲学者で有名なダナ・ハラウェイさんの著書『コンパニオン・スピーシーズ・マニフェスト(The Companion Species Manifesto)』では、人間と機械の関係は一方的な関係ではなく、相互的な、互恵的な関係であると述べています。
彼女は犬を例に挙げて説明していて、犬はペットとして人間に飼われている存在に見えるけれど、実際には人間も犬の幸せを考えて犬小屋やドッグランを作ったり、犬と心地よく暮らせる家を選んだりしているわけです。その過程で人間と犬がお互いに影響を与えあいながら関係を築いていくことで、人間自身の生活も彩られていくんですね。
この「コンパニオン・スピーシーズ(伴侶種)」という考え方は、まさに人間とAIの関係にも当てはめられると考えていて、人間がAIを使うのではなく、共に生活や文化を形作っていく「共進化的な関係」として捉えるといいのではないでしょうか。
- 柴田
- まさにそういう視点で考えると、いろんなことがうまくいくと思うんですよね。犬だって、時には人を噛んでしまったり、トイレ以外の場所で排泄してしまったりと、“悪いこと”をしてしまう場面があります。でも、「コンパニオン・スピーシーズ」だと捉えれば、一緒に工夫して関係を築けるわけです。AIと人間のお互いの特性を理解し、補い合う関係を築いていくことが、これからのAI時代には重要ではないでしょうか。
- 森
- ありがとうございます。それでは最後に、読者へのメッセージをお願いします。

- 柴田
- 今後のAIの発展を考えると、「ロボット」が鍵になると考えています。OpenAIの設立時に掲げられていたAGIの実現のためには、言語領域と物理的なロボットの領域の両方が必要だと考えられていました。サム・アルトマン氏自身も、当初は言語よりもロボット技術が先に進むと思っていたそうですが、現実にはLLMの進歩が急速に進み、ロボット技術はまだ追いついていない状況です。しかし、いずれロボット技術もキャッチアップする時期が来ると予想しています。
特に最近はLLMが「目」を持ったことで、映像や音声をリアルタイムで処理できるようになり、ロボットの制御がやりやすくなっています。シンプルなゴミ拾いロボットのようなものだけでなく、もっと複雑な機能を備えたロボットも登場し始めています。個人的にも、ロボットの分野には大きな関心がありますし、むしろ日本が強みを発揮できる領域だと思っています。
フロア清掃ロボットのような簡易的な製品は、中国の方がコスト的に有利ですが、精密機械や軍事関連を含む製造業向けの高精度なロボットはそう簡単には参入できません。そうした分野こそ日本の得意領域ですから、AIエージェントと同じように、ロボットに関しても最初から日本が主要プレイヤーとして世界で勝負してほしいと感じています。
この記事はいかがでしたか?
-
 柴田 尚樹NSV Wolf Capital パートナーNSV Wolf Capital パートナー。シリコンバレーの新興VCへのファンド投資、スタートアップへの直接投資を担う。楽天執行役員、東京大学助教を経て、スタンフォード大学の客員研究員として渡米。AppGrooves共同創業者、「決算が読めるようになるノート」創業者(2022年に事業譲渡)。東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻 博士課程修了(工学博士)。著書に『アフターAI』『テクノロジーの地政学』(日経BP)など
柴田 尚樹NSV Wolf Capital パートナーNSV Wolf Capital パートナー。シリコンバレーの新興VCへのファンド投資、スタートアップへの直接投資を担う。楽天執行役員、東京大学助教を経て、スタンフォード大学の客員研究員として渡米。AppGrooves共同創業者、「決算が読めるようになるノート」創業者(2022年に事業譲渡)。東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻 博士課程修了(工学博士)。著書に『アフターAI』『テクノロジーの地政学』(日経BP)など
-
博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、
Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。
内閣府AI戦略専門調査会委員、経産省GENIAC-PRIZE審査員、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー 。
著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。