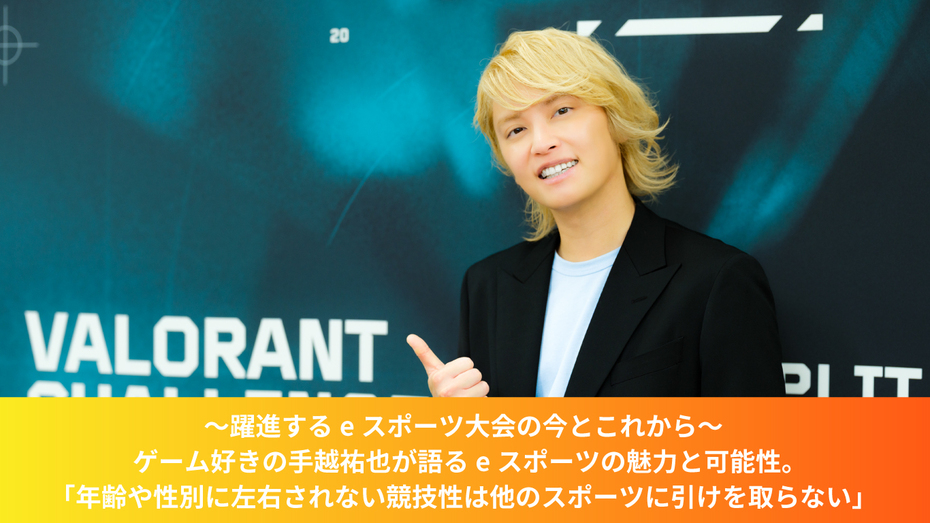生成AI時代のメディアの未来① 【対談】メディアがつくる「信頼される空間」への新たな一歩
インターネット広告がメディアビジネスにおいて主流となってきたいま、メディアはいかに、生活者に信頼され安心してもらえる“健全なインターネット空間”を生み出すことができるのか。
JIAAの2025年「インターネット広告に関するユーザー意識調査」に委員会メンバーとして携わった博報堂 グループメディアビジネス推進局の新美妙子と、東洋経済新報社にてデジタル広告全般の掲載管理や商品開発業務に携わる松下智彦さんが「インターネット空間の健全性」について語り合いました。
インターネットメディアと広告の相互影響が増している
- 新美
- まずは、現在のインターネット空間についての概要をデータと共に紹介させてください。
博報堂のメディア環境研究所が行ったメディア定点調査の結果を見ると、パソコン、タブレット、携帯電話/スマートフォンを合算したデジタル、すなわちインターネットの接触時間のシェアは6割を超えています。

博報堂メディア環境研究所「メディア定点調査2025」

JIAA[2025年 インターネット広告に関するユーザー意識調査]
一方で、JIAA(日本インタラクティブ広告協会)「インターネット広告に関するユーザー意識調査」の「メディアの信頼性」の項目を時系列で見ると、信頼性が高い上位3メディアであるテレビ、新聞、インターネットのうち、インターネットメディアが大きくスコアを落としているという結果が出ています。
これほど多くの人に利用されるメディアでありながら、その信頼性が高いとはいえないのがインターネットであるとも言えます。インターネットは誰もが発信できる開かれた空間であるのですべてを信頼性がある状態にするのには限界がありますが、私としては、マスメディアが関与するインターネット空間に関してはやはり健全であってほしいし、安心できる環境であってほしいと思っています。
現在東洋経済新報社でデジタル広告の運用管理を担当されている松下さんが、この現状をどのように捉えているかお考えをお聞かせください。
- 松下
- 課題感はおっしゃる通りで、メディアがつくるインターネットサービスやコンテンツにおいては、もっと信頼される空間がつくれることが理想だし、そこを目指したいと思っています。
そもそも私たちメディアがサービスを提供しているインターネットの空間は、オープンウェブという、良くも悪くもユーザーは誰がつくったコンテンツかはあまり意識することなく見られるような環境で、メディアが単独で安全性を維持することが実質非常に難しい状況です。例えばインターネットの広告も、動画やSNS、キュレーションサイトなどのサービスに予算が投下されることが多いのが現状だと思いますが、結果として、ユーザーが接触するインターネット空間では、広告枠が多すぎるとか表示される広告内容が好ましくないなど、ユーザー体験を損ねるケースが多々発生する状況になっています。
我々としては、自社サイトに来てくださるお客様に健全なインターネット空間を提供するために、アドベリフィケーションの取り組みの一つとして、不適切な広告が出ていないか、不正広告や低品質広告などを監視、ブロックしていますが、それもインターネット空間ではごく限られた領域での対策になっています。インターネット全体の健全性を高めることを目指すのであれば、一社の取り組みには当然限界がありますから、メディア業界全体、あるいは広告主、プラットフォーム事業者なども巻き込みながら、一緒に議論し、健全な空間をつくっていく努力が必要だと考えます。
- 新美
- メディアの努力だけでは解決が難しい問題ですね。
- 松下
- 私が現在所属している東洋経済新報社は、「健全なる経済社会の発展に貢献する」という理念に基づき企業活動を行っています。個人が正しい情報をもとに世の中に向き合っていくことが経済社会をつくる基本だと考えていて、インターネットサービスにも力をいれています。これをビジネスとして成立させるために最近では課金ビジネスの取り組みも力をいれていますが、オープンな空間でできるだけ多くの人に情報を届け、健全な言論空間を維持することも重要です。それを支える仕組みとして、広告自体の価値を高め、広告主の皆様の届けたい情報がきちんと届く環境をつくる必要がありますが、やはり、業界を超えた連携が求められるのではないかなと思います。

- 新美
- 確かにそうですね。
JIAAの「インターネット広告に関するユーザー意識調査」の結果で注目したのは、「有名/信頼できるサイト・アプリに不快/不適切な広告が出ると、そのサイト・アプリの評価や信頼が下がる」と回答した人が過半数、「不快/不適切なサイト・アプリに有名/信頼できる企業や商品の広告が出ると、その広告の評価や信頼が下がる」と答えた人も約4割、2021年と2025年を比べるとどちらの項目も増加していたことです。サイトか広告のどちらかを信頼できていたとしても、どちらかが信頼できない場合、信頼できない方に引っ張られてしまうという現状がわかります。

JIAA[2025年 インターネット広告に関するユーザー意識調査] をもとに作成
これまでの広告ビジネスは、メディアの信頼性を前提としており、その特性の上で生活者とコミュニケーションするというモデルでしたが、インターネットとなるとそうではない。インターネットメディアと広告は相互に影響し合いながら、信頼できる空間をつくっているということが明確化されたと感じました。松下さんもおっしゃるように、これは関係するすべてのプレイヤーがさまざまなレイヤーでこの課題を自分事化して、対策を考えるべきだと思った次第です。
- 松下
- 国内の有力メディア各社が参画する「コンテンツメディアコンソーシアム」において、“クオリティメディア”にのみ広告を配信するPMP(プライベート・マーケット・プレイス)「MediaString(メディアストリング)」という広告プラットフォームが2023年にリリースされました。
運営にはメディア側のメンバーが関わっていて、プラットフォーム各社が提供するPMPとは違う商品も提供しており、成果も上がりつつあります。メディア側でもセールスすることで、メディアと広告側の親和性がコントロールでき、お客様からも「信頼できる」と評価いただけています。ユーザーのアンケートを見ても、安心して広告を見られたという回答が得られており、インターネット広告でのブランディング広告としての可能性も感じています。「コンテンツに広告が包まれた状態で出していく」という従来のメディアが担っていた役割は、インターネット空間においても必要だと思いました。
インターネットにおいて健全な広告空間をつくりあげるために、テクノロジーを活用したPMPのような仕組みも含め、広告主と媒体社側と広告会社で会話をしながら、ある程度の費用も理解した上で適正な取引をしていくことが求められていると思います。
- 新美
- インターネットは効果・効率が可視化されやすい分、KPIが求められるメディアではありますが、ブランドをつくっていくメディアであるという感覚を皆が共有しないといけませんね。
また、マスメディアでは、広告出稿に際して校閲や審査を行っているわけですが、インターネット空間ではメディアに任せておけば大丈夫というわけにはいきません。その感覚も改める必要がありそうです。インターネット広告に関わるすべてのプレイヤーが自分事化しないと健全な空間はつくれないし、そこで努力をしなければ、おそらく最終的には生活者とコミュニケーションできる場がなくなってしまう。認識の転換が必要ですね。

- 松下
- おっしゃる通りだと思います。
- 新美
- 「インターネット広告の健全性」というと、堅苦しくて自分事化しにくいかもしれませんが、インターネット空間の新しい文化を皆でつくっていくというような感覚で取り組めば、違う風が吹いてくるかもしれませんね。
生成AI時代のメディアの“人感”と生活者の“熱量”
- 新美
- 健全性という意味で、昨今インターネット空間に大きな影響力を持つのが生成AIです。JIAAの調査結果でも、「生成AIを活用した広告に抵抗がある」という人が多く、抵抗がない人は2割ほどであることがわかりました。

JIAA[2025年 インターネット広告に関するユーザー意識調査]
これも、生活者がインターネット空間に安全性を感じていないということの証左だと思います。また、検索結果のトップに生成AIによる回答が出ることも当たり前になりました。その結果、検索結果に表示されたサイトをクリックする人が激減しているというデータも海外では出ています。こうした事態を受けて、今年6月のIAB(デジタル広告業界団体のカンファレンス)では早くも次世代の広告エコシステム構想が発表されていましたが、松下さんとしてはこの状況をどう捉えていますか。
- 松下
- クリエイティブな領域、特に画像制作などにおいては生成AIの活用は有効だと思うし、一部の制作案件で利用する場合もあります。生成AIの利用は、コンテンツ制作では良い方向にコントロールできると思いますが、一方で、人の手を介さないAIによる詐欺広告の生成については今のところ我々には止める手段がほとんど無いことも事実です。また、検索した結果、検索画面上でAIによる回答が出ることでメディアへのトラフィックが遮られるという現象は、すでに自分たちのコンテンツにおいても影響が出始めています。検索してヒットしてサイトに来てもらうというビジネスモデル自体が、崩壊し始めているという危機感はあります。
生成AIの活用は今後も拡大するでしょうから、ここでの課題は、生成AIを活用した新しいエコシステムをいかにつくるべきかだと思います。
たとえばアメリカでは、クラウドフレア社というクラウドサービス企業が、AIクローラー(自動的にインターネットを巡回し情報収集するプログラム)によりコンテンツ利用拒否できるようにするといったソリューションをリリースしコンテンツのマーケットプレイスを組成しようとしていますし、主要メディア各社はいかにAIを使ってビジネス展開するかといった方向に舵を切っています。ルールをつくりながら、どういう領域でAIを活用しビジネスを成立させるかは、直近数年の課題になってくるでしょう。
- 新美
- 何か知りたいことがあるから検索行動を起こすわけですが、それがすべてではなくて、人と話すことで考えがまとまったり、いろんな考えに触れて新たに生まれるものもある。そう考えると、やはり肝心なのは人であり、メディアの人感が重要な気がします。
- 松下
- たとえば弊社の記事広告では、コンテンツを読んでいただくきっかけとして、コンテンツに親和性の高いユーザーが多いという視点で自社メディアからの誘導にもこだわっています。というのも、読者に何ページまで読んでもらったか、最後まで読んでくれる読者が何%いるかという指標を重視しているからです。生成AIによってトラフィックは厳しくなるかもしれませんが、わざわざコンテンツを見に来ていただく方というのは、相当熱意あるお客様ということになる可能性もあります。ちゃんと読んでいただける、態度変容を起こせるコンテンツは、価値が上がっていくような気がします。やはりコンテンツで人を集めて、メッセージを届けることがメディアの生業だとすると、関心を持って来てくださったユーザーの数や熱量の方が重要なのかなと思います。
課題解決の鍵を握るのは業界横断でのプレイヤーの連携
- 新美
- 博報堂 メディア環境研究所が実施しているメディア定点調査では今年、「世の中の情報の発信元は、SNSなどのネットメディアだと思う」がテレビ、ラジオなどのマスメディアを上回りました。「新聞社、テレビ局といったメディアという存在にはシンパシーがない年代であっても、そこにいる特定の編集長なり、コメンテーターなり、その人個人の意見に賛同できることがあれば、もっと接点をもってくれると思うんです。そういう人たちが集まっているような場が、インターネット空間にあればいいのかなとも思います。

博報堂メディア環境研究所「メディア定点調査2025」
- 松下
- 弊社は会社の認知度で言えば、若年層では高いとはいえないのですが、公式YouTubeチャネルの動画をきっかけにコンテンツに接触いただく機会も増えています。メディア側が、若い世代に見ていただける場に出ていき、接点を持ち続ける必要性もあるなと思いました。
そうした言論空間をしっかりと維持し、やり続けないといけない。インターネットに関わるすべてのプレイヤーが、それぞれの立場でできることを考え、実現していく場が大切だと思います。
- 新美
- 生活者は不特定多数の声が集まるSNSをより頼りにするようになっていますが、
マスメディアが、特定多数の専門集団として、インターネット空間で、それぞれの異なる意見を伝えられるような健全な場をつくれないでしょうか。
- 松下
- 特に音声コンテンツでは、異なる専門分野の記者や編集者が取材を通じて得た知見や文脈を語る例も増えており、SNSの断片的な情報とは違う空間が生まれています。それぞれは小さな取り組みかもしれませんが、異なる意見を伝えられる「健全な場」の形成に寄与していくものではないかと思います。今後、複数のメディアが参加する専門家ポッドキャストの集合体をつくり、生活者が関心のあるテーマごとに専門家の声を選べるようにする、といったサービスなどできるといいかもしれませんね。
- 新美
- たとえ小さくても、そのエコシステムをどう回していくかは議論する価値はあるかと思います。その議論に業界横断で人と労力をかけられると理想的ですね。
- 松下
- またこの問題は、プレイヤーの若返り、つまりメディア業界において若い世代をどう育成していくかというテーマもはらんでいると思います。激変するメディア環境においていまもっとも求められているのは思考の柔軟性だと思います。若い世代に「自分たちはこの環境をどうしていきたいか」という意思を最初から持ってもらい、そのミッションに向けて彼らの力をもっと活かすことで、こうした事態に風穴があけられる可能性もあるのではないでしょうか。
- 新美
- インターネット空間の健全性というテーマにおいては、各社がそれぞれの取り組みを継続しつつ、業界横断で臨む姿勢が求められていると思います。
今後も引き続き、このテーマについては議論を続けていきたいと思います。本日はありがとうございました。

【インターネット広告に関するユーザー意識調査】
調査概要
調査エリア:全国
調査対象者:15~69才 男女個人
調査方法:WEB調査
対象者条件:PC、タブレット、スマートフォンでインターネットを「ほぼ毎日」利用者
サンプル数:有効回収 3840サンプル
割付:全国を8つのブロック*に分け、インターネット利用者構成に合わせて地区別・性年代別に割付
*北海道、東北、関東、甲信越・北陸、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄
調査期間:2025年2月18日(火)~21日(金)
この記事はいかがでしたか?
-
 松下 智彦東洋経済新報社
松下 智彦東洋経済新報社
ビジネスプロモーション局
デジタル業務推進部長新聞社で新聞広告やデジタル広告のセールスに従事、顧客データ基盤の開発に関わり、データを活用したデジタル広告商品の開発をリードする。その後、Sierにてスマートシティで活用するデータ連携基盤の運営や開発に関わり、2024年に東洋経済新報社に入社。東洋経済オンラインや会社四季報オンラインの広告掲載や商品開発業務に携わる。クオリティメディアコンソーシアムでは、加盟社としてクオリティメディア・アドネットワーク「MediaString」のセールスを進める。
-
博報堂
グループメディアビジネス推進局
ナレッジビジネスプロデューサー1989年博報堂入社。メディアプラナー、メディアマーケターとしてメディアの価値研究、新聞広告効果測定の業界標準プラットフォーム構築などに従事。2012年よりメディア環境研究所にて、メディア定点調査や定性インタビューなどからメディア環境の変化やメディアと生活者のつながりを研究。2025年4月、現職。これからのメディアビジネスとメディアの役割を研究開発・発信。