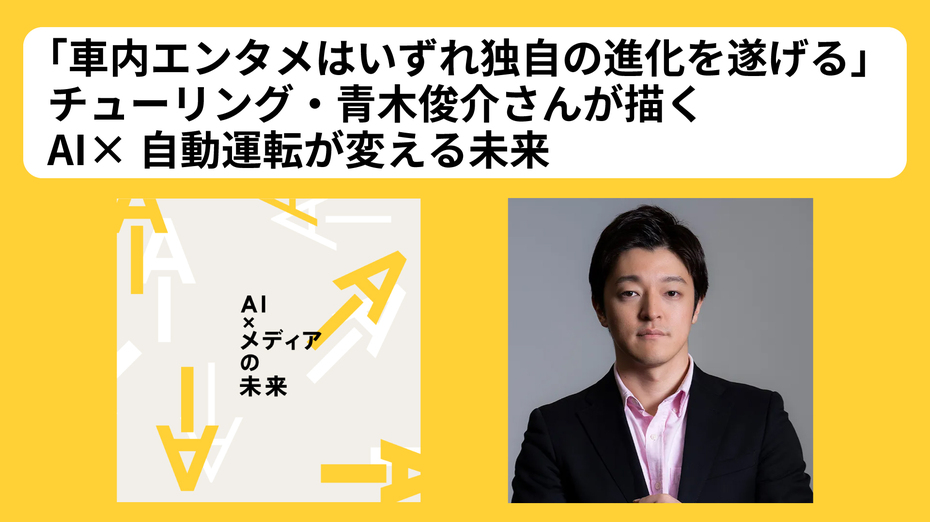「社会課題解決プロジェクト」が目指すもの【Vol.6】高岡交通と考える、これからの地域交通と交通事業者が担う役割
これからの日本社会が直面する交通課題。特に地方部では、地域交通の再編が求められ、マイカー交通やデマンド交通等、新しい交通サービスが生まれています。これまで富山県朝日町を中心に、公共交通やまちづくりの課題解決に取り組み、地域交通プラニングやソリューション開発を行ってきたメンバーが、高岡市のマイカー交通「ノッカル中田」の運行管理、地域乗合タクシー「もりまる」「のむタク」の運行を担う、株式会社高岡交通のみなさまと共に、交通事業者から見る地域交通の現状と将来像について語り合いました。
連載一覧はこちら
- 常廣
- 最初に高岡交通の皆さんの簡単な自己紹介からお願いいたします。
- 渡辺
- 高岡交通代表取締役社長の渡辺です。高岡市を中心としたタクシー事業の他、介護や観光など、幅広い分野で地域の足を支えるためのサービスを展開しています。
- 手崎
- 高岡交通常務取締役の手崎です。入社したての頃は介護タクシーの立ち上げに携わっていて、その後事務、人事系と担当してきました。デマンド交通やノッカルの立ち上げにはあまり深くかかわっておらず、そこら辺の経緯は現場の方が詳しく話せるかなと思います。
- 廣上
- 高岡交通営業本部長、タクシー部長の廣上です。平成の終わりに入社し、観光部門で大型二種免許を取って、タクシーではなくてバスの仕事をしていました。そのあとタクシーに移り、今の役職という形になっております。
タクシーという形で地域の皆さんとどのように携わっていけるか、地域の足をどう担保していくかを考えながら一生懸命やっております。
地域主体の交通サービスに、交通事業者としてどう関わるのか?
- 堀内
- まず、高岡交通さんの事業について簡単にお伺いできますでしょうか。
- 渡辺
- 高岡交通は元々「高岡地方交通」という社名で、昭和20年7月に設立されたタクシー会社です。タクシー事業を中心に、観光タクシー、空港送迎などの事業も展開しています。

- 堀内
- 今、我々博報堂と高岡市と一緒に取り組ませていただいているのが、デマンド制の乗り合いタクシーや、ノッカルのようなマイカーを使った交通ですが、高岡交通さんから見た地域交通の状況、またノッカルの状況を教えていただきたいです。
- 廣上
- 私は高岡市内の各地域の交通会議に参加しているのですが、民間企業を誘致したり、手を挙げた交通空白地に対して高岡市が支援したり、それぞれの地域課題に合った形で動いているという印象を受けています。鉄道やバスといった既存の交通網と共存する形で、どう地域交通を築いていくかが課題ですね。
- 堀内
- 交通空白地域が市内各地に広がっているのは、路線バスの撤退によるところが大きいのでしょうか。
- 廣上
- そうですね。中田地区はバスの本数が少なく、野村地区は路線が撤退したという経緯があります。その地域の中の交通網がなくなっている状態で、地域のみなさんの移動に関してお手伝いをしたいという思いです。
- 堀内
- 人口1万人規模の自治体ですと、地方交付税交付金等、いわゆる国からの補助で公共交通を維持している場所が多く、民間路線バスの撤退後に自治体がコミュニティバスを自前で運行しているところが大半です。しかし、高岡市の規模になると、民間の力で自分がやっていこうだとか、地区が自力で何とかやっていこうという機運がすごく強いのかなと感じています。
先ほど、地域で移動の足が不足している場所をサポートするとおっしゃっていましたが、高岡市の考えていることと、高岡交通さんの考えていること、そのあたりの兼ね合いは地域交通会議で話されるのでしょうか。
- 廣上
- 高岡市では、困っている地域が手を挙げて、既存交通と共存する形で交通事業者が応募し、市の了解を得る、という形で運営が進んでいます。事業者協力型になるのか自家用有償運送になるのか、というのは募集の時点で決まっていますね。
- 常廣
- 守山地区のデマンドタクシー「もりまる」は、地域にどういう交通が必要か、という最初の議論から高岡交通さんも参加されていたのか、ある程度地域で内容が固まってから運行をお願いされたのか、どちらの形になりますか。
- 廣上
- 最初から我々も会議に入らせてもらって、事業者として、地域にとって適正な交通の形はなにか、デマンド型という手もあるし、路線型か区域型か、という議論をしました。
- 常廣
- 運行形態については、地域からのニーズもあれば、高岡交通さんからご提案されることもあるということでしょうか。
- 廣上
- 基本的には運営に係る経費を見ながら本数を決めるというのが多いです。運行コストの見積をベースに、行政の方で試算したものを何パターンか交通会議で提示して、地域に選択いただいている形です。
地域デマンドタクシー「もりまる」のデジタル化
- 常廣
- 「もりまる」と「のむタク」は、最初はシステムを使わずに完全アナログで運行していたかと思います。「ノッカル中田」の運行管理をお願いしたことをきっかけに、「もりまる」「のむタク」にも同じシステムを導入させていただくことになりました。アナログで運行していたときの課題や地域の声、またデジタル化に至った経緯を教えていただきたいです。
- 廣上
- 当初は、スマホで登録するのが難しいという声があり、電話での事前予約という形で運行を始めました。ですが、「もりまる」を利用される学生の方々をターゲットに入れたときに、スマホで予約できるようにしたいという話が出てきました。
実際に予約するのは学生ではなく保護者の方ですが、その日の予定によって乗るか乗らないかを判断されるのでスマホで予約する方が楽だ、という声があったのと、管理側も一般のタクシーの予約の電話を同時並行で取ることを考えると、事務側は非常に楽ですね。野村地区の「のむタク」もデジタル予約の話はしていますが、実証実験段階でも高齢者の方が多かったので、時間はかかりそうだなと思っています。

- 清都
- 現在、各地域でスマホを使った予約方法のご説明をして回っています。特に高齢の方だと慣れていただくには時間がかかるのかなと思っています。先日の説明会では、はじめてLINEを触るという高齢者の方もいらっしゃいました。ただ、お教えするとすぐに使えるようになっていたので、最初の利用ハードルさえ乗り越えれば、今後は明るいかなと思っています。
- 常廣
- もっとLINEでの予約が普及すれば、電話予約のオペレーションも軽くなりますよね。そのほかに、デジタルの仕組みを導入してから変わったことはありますか?
- 廣上
- 運行の記録をすぐにデータで見られるようになったのが大きいです。今は、利用者数や運行日を月末に集計するためにデータを活用しています。「もりまる」のお買い物便については、大体固定の方が利用されているということが分かっています。3人グループで毎週何曜日に乗る、とか、地域の中で大体決まってきているようです。冬期のみの学生便も、2~5名くらいは定期的にご利用いただいています。利用しているのは中学生のお子さんで、期間中毎日、予約をとっている方もいらっしゃいますね。
- 清都
- 毎日の予約が全部アナログだと、申し込みするほうも、受け付ける方も、大変ですね。もし「もりまる」がアナログ管理のままだと、他の地域でも委託を引き受けたときに負担が増えすぎてしまいますよね。デジタルが全て解決できるわけではないので限界はあるかと思いますが、高岡交通さんに元からある経験・人材・車両などのアセットを、融通を利かせながらうまく活用されているのだと思います。

- 廣上
- ご一緒させていただく中で、地域が受け入れやすい、というのが博報堂さんのコンセプトなのだろうな、と感じています。導入後のフォローも非常に助かっています。会員証の発行や更新時期の管理などもシステムで管理できる。運行管理の負担が全部、運行主体に移っただけでは意味がないので、負担を減らしながら地域交通を回していく、という考え方は共感できる部分がありますね。
- 堀内
- デジタル化というと、最近だとAI運行を導入する地区も多いですよね。ただ、個人的には、地元のドライバーさんのほうがAIルーティングよりも適切な道を知っているのではないか、AIデマンドは専用車両が必要になってくるのではないか、とか、必ずしも交通事業者さんにとって最適な方法ではないのではないかと思っています。高岡交通さんから見て、既存のやり方の方が融通が利く、という印象はありますか。
- 手崎
- そうですね。別の営業所にAI配車システムが導入されていますが、ほとんど乗り合いは発生していないです。やはり1件1件を迎えに上がって目的地まで行く、という、タクシーのような動きになってしまっていて、ドライバーの感覚からすると運行スケジュールが非常にタイトなんですね。休憩もほとんどとれずに次の運行に向かわなくてはならない。本来は、もう少し到着時間に幅を持たせたほうが、運行効率が上がるはずですが。
- 堀内
- 人口密度が高くて乗る人が多い場所に向いているシステムなんですよね。
- 廣上
- そうですね。停留所の数に制限をかけたり、少し制約を持たせたりしないと、少ない台数で広範囲をカバーするのは難しいと思います。
持続的な公共交通のために必要な視点とは?
- 堀内
- 今後は高齢化もさらに進んでいきますが、高岡交通さんの視点で見たときに、高岡市の公共交通はどうなっていくとお考えですか?
- 手崎
- ドライバー人材や車両など、運行に必要なリソースが限られているので、地域が自前でドライバーも運行管理もやる、というスタイルが実現できるのであれば、そういった形が増えていくのかなと思います。
ドライバーさんが地域で確保できる場合は、最低限の公共交通インフラを自家用有償運送で維持していただく方が我々としてもありがたいですし、そういう交通空白地域のコミュニティ支援や投資を、市としても行っていくのかなと思っています。

- 清都
- 現状、マイカー交通、デマンドタクシー、デマンドバス、と様々な運行形態があると思うのですが、実際の地域ではどのようにして決まっていくものなのでしょうか。
- 廣上
- 自分たちの地域に合ったものが自然に選ばれていくのではないでしょうか。地域ごとの協議の場でも、複数の選択肢があって、どういう観点でどれを選ぶか、というような議論が中心になっていますね。
- 清都
- 県全体で、住民から民間事業者、行政まで一体となって交通を考えていこう、というフレームですよね。地域の方からは、どういった声が上がっていますか。
- 廣上
- 利用する方の目線でいうと、目的地まで一直線に行きたいという要望や料金を安くしてほしいという要望も多く出てきます。ただ、既存のバス路線を維持するという観点で、どうしてもバスに乗り継ぐところまでしか運行できない、という制約もありますので、その点は利用者説明会に同席するなどしてご説明させていただいています。
- 堀内
- 行き着く先は、コストとサービスレベルのバランスですよね。利用者の方にとっては200円でタクシーを運行してもらうのが一番いいですが、それだと持続性がないし、既存の交通網を壊してしまう可能性がある。補助にあたるルールや規制も含め、地域の方と一緒に考えていくというのが、住民参画型のあるべき姿だと思います。
- 廣上
- そうですね。数万人の利用者に影響する交通事業者であっても、来月からサービスを廃止します、というパターンが実はよくあるのです。地域の方からすればすごく急で困る話です。その段階になって地域住民の方が動き出して、路線の存続を検討してもらう、というのは大変な労力がかかりますし現実的ではありません。今交通が運行しているから大丈夫、と言える段階はすでに終わっていて、交通事業者の持続性も考えなくてはいけない段階にきている、ということを利用者の方にも認識していただかなくてはなりませんね。
- 常廣
- 地域協議会は、利用者の利便性も考えなくてはいけないので、運営を持続させていくためのコストや運行設計との板挟みになっているところが多いですよね。守山地区や野村地区は、そこの折り合いをどうつけていったのでしょうか。野村地区の「のむタク」も実証運行の時よりも便数を減らしたり、当日予約を廃止したりしていましたよね。

- 廣上
- 実証実験が終わった段階で、料金設定も300円から500円に変更しました。また、会員制なので、利用者の方からは年会費をいただいています。子供たちや高齢者の移動の足として必要な負担なので、地域の方々には納得いただいています。ただ、限られた数の利用者のためになぜ年会費を私達が負担しなければいけないのか?という声も、実証運行終了には出ていました。
- 清都
- 非常に重要ですけど難しい問題ですよね。サービスを作る段階から、できるだけ広く地域の方に関わっていただいて、普段公共交通を使わない人にも地域課題として自分事化してもらうことが重要ですね。
地域の交通事業者の未来
- 堀内
- タクシーの事業エリアの採算性を考えるときに、どのような判断基準や目安があるのでしょうか。
- 手崎
- データを取れば、採算性については分かります。ただ、採算性が良くないからと言ってお断りしたり手放したりすることはできません。例えば、1メーター程度の短い距離の移動のご要望であっても、お断りするというのはできません。
高岡交通の営業エリアは高岡市・射水市・氷見市でして、基本的にはこのエリア内からのご要望であれば、採算に関わらず、お迎えに上がるというのが基本的なルールです。ですが、台数が少ないときや、午前中など忙しい時間は、結局お迎えをお断りするということは発生しています。
- 堀内
- その議論はライドシェアにも繋がる話かなと思います。今、ノッカルのような事業は、最近解禁されている都市型のライドシェアとは異なる、生活密着型の「公共ライドシェア」という言い方をさせていただいているのですが、どうしても都市型のライドシェアと混同されてしまいがちです。先ほどお話いただいたような、ドライバー不足の問題からライドシェア議論がまさに今活発化する中で、誰が責任を取るのか、運行オペレーションをどうするのか、などに対してはまだ議論が必要だと思っています。そのあたりについて、高岡交通さんはどう思われますか。

- 手崎
- 私自身は前向きに考えています。近年急激にライドシェアが広まって、近隣でも解禁されている地域が出てきています。タクシーについてはドライバーの給与面、事故の発生などのネガティブな問題が注目されますが、それでも街中でタクシーを見ない日はないんですよね。タクシーに対する需要は確実にあると思いますし、ライドシェアの解禁はチャンスだと思います。安全確保については、タクシー会社と一般ドライバーで雇用関係を結ぶのか、業務委託という形にするのか、などまだ模索段階だとは思いますが。
そもそも富山県は運転代行の発祥地だと言われています。タクシー会社ではなく、地元の運転代行が走っていて、富山駅前なんかはかなりの台数がいますね。そういう形で、しっかりと制度を作り上げながら新しいサービスを作っていく、というのは、日本は得意なんじゃないかなと思います。
既存のタクシー会社にとって外資系企業の参入などの脅威もありますが、基本はライドシェアには賛成ですね。
- 廣上
- 今我々がご協力している空白地での自家用有償運送、交通難民の方がいらっしゃる地域での運行と、観光地で人があふれているところでのライドシェアはまったく別の話ですね。
- 堀内
- 黒字化がなかなか難しい地域交通を誰がどう担っていくのか、みたいなところも含め、新しいライドシェアについてはしっかりと考えていかないといけないですね。
- 常廣
- 今はまさに、交通事業者の役割や、地域における位置づけがどんどん変化していく局面だと思います。現場目線・経営目線含め、高岡交通として今後の目指している姿をお伺いできますか。
- 廣上
- 現場としては、現状実施されているライドシェアに限らず、利用者目線で助かるようなサービスを作っていきたいと考えています。
例えば、観光地に一斉に人が集まる時間帯はタクシーが不足してしまうので、その応援体制をどうするのか。地域のタクシー事業者全体で協力しながら、なんらかの形で需要のピークに対応できるような仕組みが必要だと思います。能登半島地震のときは、別な地域のタクシー会社が非常事態対応としてその地域でタクシーを走らせるということもありました。そのように交通事業者同士で連携し合うことで、もう少しスピーディーに地域に合う形のものを工夫して始められるのではないかな、とは思っています。
- 渡辺
- 経営目線でいうと、やはり会社として持続していかなきゃいけないというのはあります。我々は今、タクシー事業者でありながら、もともとバスがあった地域の移動手段を代替で担っているわけですが、そもそも地域公共交通はまちづくりとセットで考えなくてはならない。市として、まちづくりの方向性を示していただきつつ、タクシー事業者としてご協力できることを、しっかりやっていきたいと思います。
- 手崎
- 交通事業者の持続性が重要だと思います。弊社以外に、高岡の他地区にもタクシー会社はあるのですが、経営者の方もかなり高齢になっていて人手も足りず、タクシーも5~10台しかないので、自分で受けた電話の配車を自分で運行しにいくような状態だと聞いています。
なんとかしたいのはやまやまなんですが、交通事業者はどこも厳しい。小さいところだと特に、です。限られた予算、限られたリソースの中で、手探りではありながらなんとかいい形を見つけていきたいと考えています。
- 常廣
- 我々としても、引き続き連携させていただきながら、地域にとって一番良い公共交通のあり方を模索できればと思います。本日は、貴重なお話をありがとうございました。
この記事はいかがでしたか?
-
 渡辺 寛人氏高岡交通株式会社 代表取締役 社長
渡辺 寛人氏高岡交通株式会社 代表取締役 社長
-
 手崎 俊之氏高岡交通株式会社 常務取締役
手崎 俊之氏高岡交通株式会社 常務取締役
-
 廣上 隆広氏高岡交通株式会社 営業本部本部長 タクシー部長
廣上 隆広氏高岡交通株式会社 営業本部本部長 タクシー部長
-
博報堂 ストラテジックプラニング局 局長補佐/グループマネージャー京都生まれ京都育ち。2006年博報堂入社。入社以来、一貫してマーケティング領域を担当。
事業戦略、ブランド戦略、CRM、商品開発など、マーケティング領域全般の戦略立案から企画プロデュースまで、様々な手口で市場成果を上げ続ける。
近年は、新規事業の成長戦略策定やデータドリブンマーケティングの経験を活かし、自社事業立上げやDXソリューション開発など、広告会社の枠を拡張する業務がメインに。
-
博報堂 ストラテジックプラニング局 マーケティングプラナー福井県出身。2018年博報堂入社。マーケティングプラナーとして、飲料・不動産のマーケティング業務を経験したのち、地域交通のサービス実装、自治体DXのプランニング、システム・サービス開発に取り組む。近年では、交通領域での自社ビジネスの開発を担う。
-
北陸博報堂 ビジネスプロデューサー2021年北陸博報堂入社。ビジネスプロデューサーとして、北陸地域を中心とした地域事業者のマーケティング支援、地域交通領域の現場支援を行う。