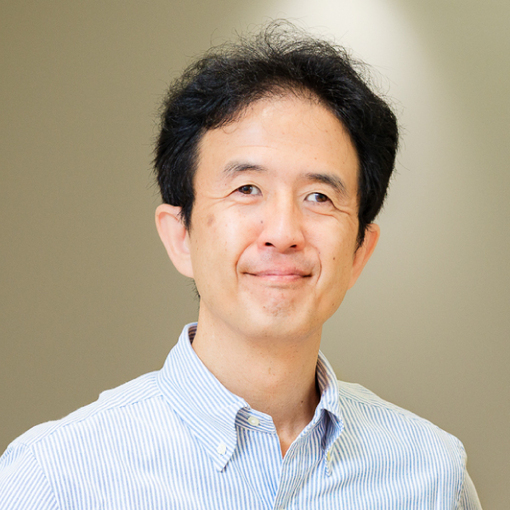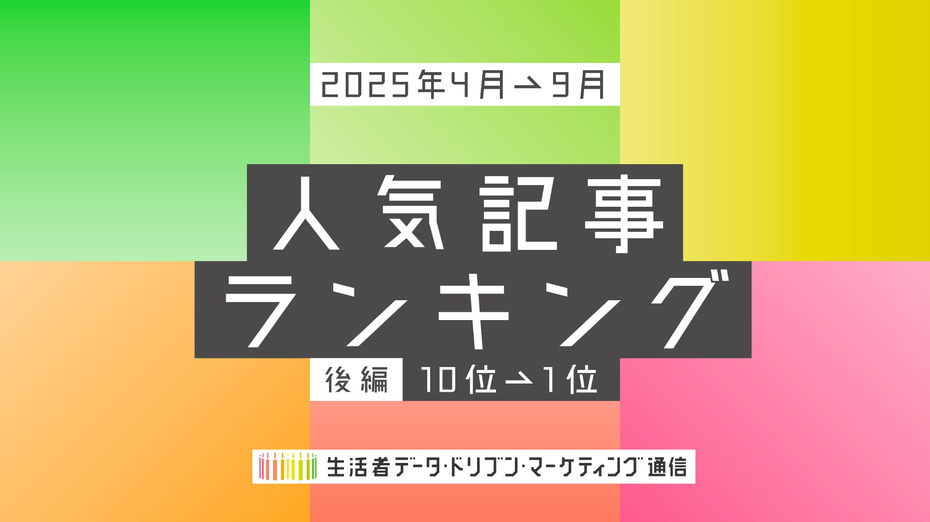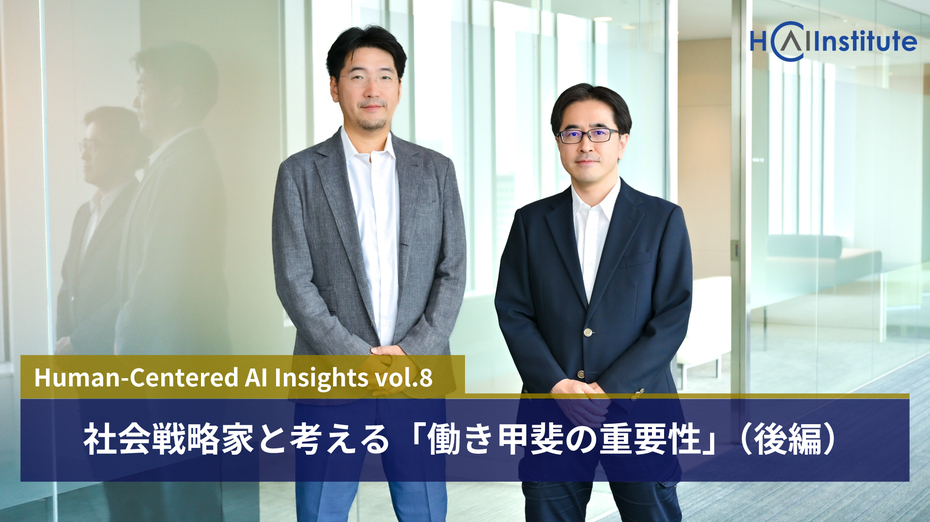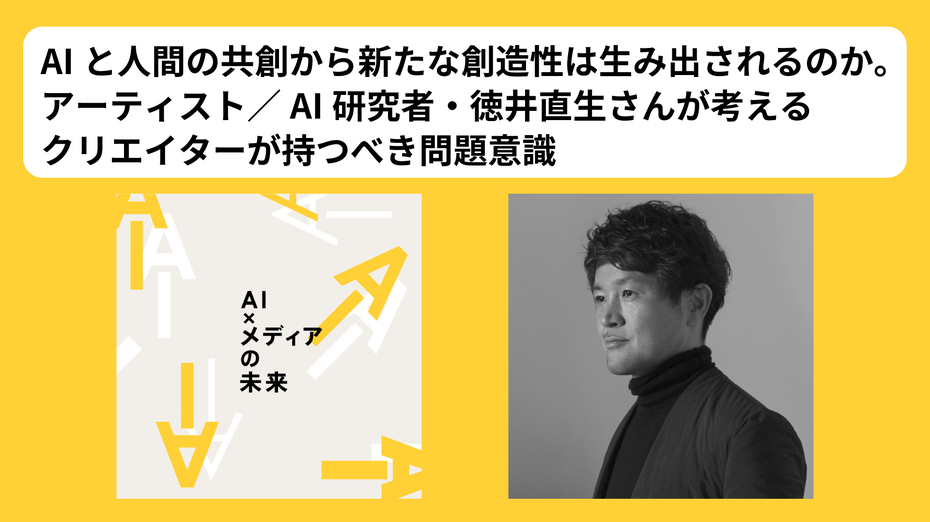Hakuhodo DY ONE 広告技術研究部レポート「デジタル社会の未来」vol.1 ミュージックテックがもたらした音楽業界大変革
音楽ストリーミングの一般化やマーケティングへのデータ活用など、近年の音楽業界は、テクノロジーの進化による激しい変革の真っただなかにあります。具体的な収益構造や市場環境の変化から、注目の次世代音楽クリエイターまで、Hakuhodo DY ONEの永松範之と高橋二稀に、博報堂 研究デザインセンターの島野真が聞いていきます。
■テクノロジーの進化により激変する音楽産業
- 島野
- 今回のテーマはミュージックテックです。以前、音楽業界の方が、「古くはシンセサイザーの誕生から現在のストリーミングビジネスの普及まで、どんな変化も音楽業界は柔軟に受け入れてきた」「音楽業界はテクノロジーによるイノベーションに慣れている」と話していたのが印象的でした。

- 永松
- 確かにそのとおりだと思います。特に近年はデジタル技術の進化に伴い、ビジネスモデルも含め大きな変化が起こっています。振り返ってみれば、レコードの時代からカセット、CDと音楽メディアは次々と変化してきました。中でも大きかったのは、MP3やiPodなどの登場でデータ化された音楽が容易にやり取りできるようになったことでしょうね。やがて音楽のダウンロードが当たり前になると、著作権管理が整備され、SpotifyやApple Musicなどの音楽ストリーミングサービスが登場しました。
ストリーミングを通してユーザーの視聴データを取得できるようになり、レコメンド機能などのデータ活用も進んでいます。また、デジタルプラットフォームを通じてインディペンデントのアーティストが世に出てくる機会も増えてきました。
- 島野
- 今までは物理的なモノをつくらなくてはならなかったし、世の中に売っていくための流通も確保しておかなくてはならなかった。現在はそうしたことが必須ではなくなり、さらにAIの活用も始まり、音楽領域ではまさにクリエイティブの民主化がさらに進んでいると言えそうです。
- 高橋
- 最近は音楽制作にクラウドを活用する例も増えています。国を超えてアーティスト同士が共同で制作することが容易になりました。Muse(ミューズ)という音楽制作ツールのDAW(ダウ)と連携できるアーティスト特化のミーティングアプリなども登場しています。最近は中国、韓国、日本のアーティスト同士のコラボがトレンドにもなっています。
- 島野
- 音楽市場全体としてはどのようなことが言えますか。
- 永松
- グローバルではすでにストリーミング配信がパッケージ販売の売上を大きく上回っていますが、日本はいまだ売上の6割をパッケージ販売が占めます。握手券付きCDや、コレクション用に複数パターンのCDを販売することも多く、アイドルなどの推し活の盛り上がりが日本のパッケージ市場を支えているとも言えます。これはグローバルと比較して非常に特徴的です。
- 島野
- ただ、全体の市場規模が拡大しているグローバルに比べて、日本はストリーミングへの転換がゆっくりな分、全体の売上は下回っています。日本はもっと貪欲にイノベーションを進めてもいいのかもしれませんよね。
- 高橋
- ブルーレイの生産終了が決まるなど、音楽ビデオ需要が激減していることも全体の売り上げに影響していると思います。ただ一昨年あたりから日本でも大物アーティストのストリーミング解禁が続いているので、この流れをしっかりととらえて、デジタルプラットフォームの活用をより進めていく必要があると思います。
- 永松
- ストリーミングサービスの利用状況を見てみると、日本の場合Spotifyと並んでLINE MUSICが人気なのも特徴的です。
- 島野
- あらためて日本の音楽市場は、グローバルの傾向とは異なるユニークな状況にあるということですね。
■AIスタートアップ協働による革新と収益構造の変化
- 島野
- デジタル化の進展によってプレイヤーにもバリエーションが出てきていますよね。アーティストにとっては収益を得るための手段を自ら選べたり、工夫できたりするのも大きな変化です。
- 高橋
- そうですね。特に、多数あるストリーミングサービスに楽曲を配信代行する「ディストリビューター」の存在感が高まっています。デジタル化によって音楽制作が容易になりインディペンデントのアーティストが増えましたが、レコード会社のレベニューシェアでは厳しかったり、そもそも契約できないケースも多いです。そこで、少ないシェアでもストリーミングに楽曲を載せてもらうことができるディストリビューターが非常にありがたい存在になっています。ディストリビューターがインディペンデントのアーティストとの取引を増やし、市場全体の約1/3の売上を占めているとも言われています。
- 島野
- とはいえ、アーティストが自分で曲をアップロードすることも技術的には可能ですよね。あえてディストリビューターを通す理由は何ですか。
- 高橋
- 確かに自分で曲をアップすることは可能ですが、複数のストリーミングサービスに上げていくのは非常に煩雑な作業になります。一方、ディストリビューターを活用すると、一括でさまざまなストリーミングサービスに曲を上げてくれるだけでなく、ユーザーの視聴データ分析や売上の管理、場合によってはアーティストのプロデュースやファイナンス面のサポートまで対応してくれます。ストリーミングサービスのキュレーターがつくるプレイリストに載るかどうかで再生回数が大きく変わってきますが、そうした面でもディストリビューターがうまく差配してくれます。アーティストは音楽制作に専念できるため、メリットが大きいのです。
- 永松
- 複数のプラットフォームがあることで著作権管理が複雑化していて、著作権市場全体が成長しているのも覚えておきたい点です。

- 島野
- 先日聞いた話では、海外で活躍する日本のアーティストは、いま世界のどこで支持されていて、どこでプロモーションをかけるべきかを、データを見ながら判断しているということでした。海外市場に挑戦する場合、これまではとにかくアメリカを目指しがちでしたが、今はリアルタイムでデータを見ていくことで、世界のどの地域、どの国から攻めていくべきか教えてくれます。そうして実際、海外のどこかで人気に火がつき、その波がほかの地域にも波及するという流れができている。アーティスト本人もプロデューサーも、本当の聞き手がどこにどれくらいいるかがタイムラグなく把握できるため、戦略を立てやすくなっていますね。
- 高橋
- インディーズのメタルバンドで活動している友人がいますが、海外でよく聴かれていることがわかってから英語で発信しはじめたところ、ファンが急増したそうです。現在は海外ツアーに行くほどの人気バンドとなっています。
- 永松
- 良い実例ですね。
同様の事例で、Snafu Recordsという海外の新興レーベルは、AIを活用して、聴取時間やSNSでの盛り上がりを分析し、アーティストの発掘や支援をしています。毎週100万曲ぐらいの中から、ヒットしそうな曲をピックアップし、アーティストにコンタクトをとって契約したり、プロデューサーを推薦したりするなどして活動をサポートしています。また、データを活用することで、今後どれくらい再生されそうかも精密に予測できるため、音楽収入自体も前払いして支援をしていくといった動きもあります。
- 高橋
- そのAI基盤自体を、レーベルやディストリビューターに提供している事業者も存在します。たとえばアメリカのBeatBread社は、アーティストやレーベルに知恵も資金も出し、ネットワークも提供して支援しています。まるでVCと起業家の関係のようで、面白いなと思います。
- 島野
- もともと音楽業界では、勘と経験も活用して未発掘の才能を見つけて、手取り足取り支援していたわけですから、ある意味VC的でしたよね。それが、データによって目利きの精度が向上し、より手厚く支援できるようになったということですね。
- 高橋
- それから、これまではレコード会社がトレンドを作る側だったと思いますが、今はあらゆるジャンルが満遍なく聴取されていますから、より生活者の好みに応じたトレンドが自然発生的に生まれるようになるのかもしれません。
いずれにしても、データによって投資とリターンがより計算しやすくなったことは大きいと思います。かつてはヒットが出るとレコード会社が収益を独占するといったこともあったかもしれませんが、ヒットすればきちんと全員が収益を得られるように、データによってビジネスが透明化されてきたのはいい傾向だと思います。
■ファンクラブが、複数機能が集約されたプラットフォームへと変貌
- 高橋
- デジタルトレカや限定配信などデジタルコンテンツが急速に増えたことで、ファンの楽しみ方もオンライン中心になってきました。ファンクラブの在り方も変わってきています。たとえば韓国の大手芸能事務所のHYBEが始めた「Weverse」は、ファンとアーティストが相互コミュニケーションできるプラットフォームで、HYBE所属以外のアーティストも多数利用しています。配信も、ファンのコメントに返信することも可能です。ファンとつながるための一連の機能が集約されたプラットフォームです。
- 島野
- レコードやCDをリリースしてお店で購入してもらう、ライブに来てもらう、テレビで歌ってるのを見てもらうというだけだと、一方通行だし時間が限定されていたのが、現在はデジタル化によって基本的に双方向かつ常時接続でつながり続けられるようになったわけですね。
- 永松
- そうですね。ファンクラブという場が、特定のアーティストとそのファンという関係性だけじゃなく、さまざまな音楽ファンとアーティストをつなぐ大きなプラットフォームになっています。
- 高橋
- 課金の場が多いのもポイントで、プラットフォームビジネスに貢献しています。他のファンの存在が見えるので、「あのファンはアーティストに返信されている」「私もやろう」というように、熱狂が生まれていくこともあります。
■台頭するデジタルネイティブ世代のクリエイターたち
- 高橋
- デジタルネイティブ世代のクリエイターの活躍も目覚ましくなってきました。筆頭は Billie Eilishです。SoudCloudというインディペンデントアーティストの利用が多いストリーミングサービスを活用していたところ、最初の曲がバズって拡散されたことで一気に世の中に知られる存在になりました。自宅の一室でお兄さんと一緒に制作し、お母さんがミュージックビデオの編集を行っていて、本当にインディペンデントアーティストの星のような存在です。デビュー後はさまざまなプラットフォームと連携して新しい機能のテストやコラボをしており、たとえばSpotifyではListen Party機能という、ファンとアーティストが同時に曲を聴いてリアクションし合うようなコンテンツを試しています。また30歳の女性シンガーDua Lipaは、ミレニアム世代のデジタルスター的な存在です。自ら何でもやる人で、自作したメルマガやカルチャーメディアを通して自分のライフスタイルや考えを発信しているのが特徴的です。
一方TikTokで「分かってないよ」という曲でヒットしたのが、WurtSです。もともと学生で、自らデジタルマーケティングを学び、セルフプロデュースをおこなっていて、注目を集めています。TikTokではほかにもimaseなども育てていますね。DIY感やリアル感、親近感を感じさせるところが、人気のポイントかと思います。

- 島野
- TikTokはシェアされる速度が早く、一度火がつくとそのあとの拡散がスピーディです。例に挙がった2人とも、シェアされてヒットするというTikTokの特性にうまく対応しているのでしょうね。
- 高橋
- 確かにそうですね。TikTokでヒットする曲は、イントロもAメロも聴かなくていい、いきなりサビから始まる、特徴がすぐに分かるような曲が多いと思います。TikTokの普及が、そうした楽曲のヒットを加速させているとは言えそうです。TikTokでは少し緩めのダンス動画も人気で、かわいい自分をアピールできるような歌詞、カバーしやすい楽曲がヒットしやすいようです。またダンス系のクリエイターが増えていて、彼らが紹介した曲がバズるといったパターンもあります。たとえばラッパーのChiba Yukiは、 Megan Thee Stallionという米国のラッパーとフィーチャリングした「Mamushi」という曲がTikTokでヒットし、結果的にワーナーとグローバルで3億円契約を結ぶに至りました。
ほかにも、Netflixなどストリーミングサービスで大勢が同じコンテンツを見ていることもあり、アニメの主題歌などのグローバル認知が広がりやすい傾向にあります。
- 島野
- Netflixの「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」はまさにその好例ですね。作中で歌われている曲がビルボードのトップテンの中に4曲入って話題になりましたから。やはりNetflixの圧倒的なグローバルへのディストリビューション力を背景に、コンテンツや楽曲の世界的なヒットが一気に起こるという、新しい潮流が生まれつつあるようです。
今後についてはどのようなことが言えそうですか。
- 永松
- 全般的に、やはりデジタルプラットフォームの影響力がグローバル規模で拡大しているということが言えそうです。アーティストの発掘も、流通販売の設計、ファン育成などにおいても、やはりプラットフォームの力を無視することはできない状況です。
また、近年は楽曲制作へのAI活用も進んでいます。AIを使用して制作された音楽からも適切にライセンス料を徴収できる新たなモデルの構築が始まっています。AI企業と音楽レーベルの関係性も、未来志向になりつつあるようです。
ほかにも、アーティストのマーケティング活動やファンとの関係性向上に、データを活用する動きはますます進んでいます。今後も、デジタルが介在することでアーティストとファンとの新しい関係性構築の可能性がありそうです。
- 高橋
- 広告ビジネスの視点でいうと、コンテンツと音楽とインフルエンサーの重要性が一層高まっています。ソーシャルを使ってバズったり、ファンコミュニケーションをとるインフルエンサーのようなアーティストの増加だけではなく、インフルエンサーがカバー・二次創作しやすい音楽性もポイントになっています。
ビジネスインパクトは局所的かもしれませんが、インディペンデントアーティストにフォーカスしたメディアが堅調に成長しているのを、個人的には感じています。たとえば「AVYSS」というクラブミュージックを中心に展開する個人メディアは、そのキュレーション能力の高さが評判になり、フェスやイベントのキュレーションで人気を集めたり、レーベルを始めたりしています。音楽制作や発信が容易になることで、インディペンデントアーティストの面ももつ生活者が増え、ニッチな音楽への熱量がより高まっているのではと思います。
データ活用という視点では、生成AIを使った生活者分析をすることで、より精緻なファンダムマーケティングも可能になるのではないかと思います。
- 島野
- ヒットするかどうかもデータでわかるし、アーティストやファンの姿もデータを通してよりクリアに可視化できるようになりますよね。デジタルプラットフォームの特性を活かしたり、データをうまく使いながら賢く戦っていくことが、これからの音楽業界には大事になってきそうです。
お2人ともありがとうございました!
この記事はいかがでしたか?
-
Hakuhodo DY ONE 新規テクノロジー事業開発本部 研究開発局長2004年デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)入社、ネット広告の効果指標調査・開発、オーディエンスターゲティングや動画広告等の広告事業開発に従事。近年はAIやIoT、XR等のテクノロジーを活用したデジタルビジネスの研究開発に取り組む。専門学校「HAL」の講師、共著に「ネット広告ハンドブック」(日本能率協会マネジメントセンター刊)等。
-
Hakuhodo DY ONE 新規テクノロジー事業開発本部 研究開発局2020年 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)入社。アドテクやソーシャルメディア、生活者に近いテクノロジーを中心としてデジタルビジネスのトレンド調査、事業開発に従事。
-
博報堂 研究デザインセンター 研究主幹
兼 博報堂DYホールディングス テクノロジーR&D戦略室
兼 博報堂DYホールディングス グループ広報・IR室博報堂に入社後マーケティング部門に在籍し、通信、自動車、ITサービス、流通、飲料など数々の得意先の統合コミュニケーション開発他に従事。2012年よりデータドリブンマーケティング領域の新設部門でマーケティングとメディアのデータを統合した戦略立案の高度化、ソリューション開発、DX推進等を担当。2020年よりメディア環境研究所所長 兼 ナレッジイノベーション局局長として、メディア環境の未来予測他の研究発表を行う。25年より現職。