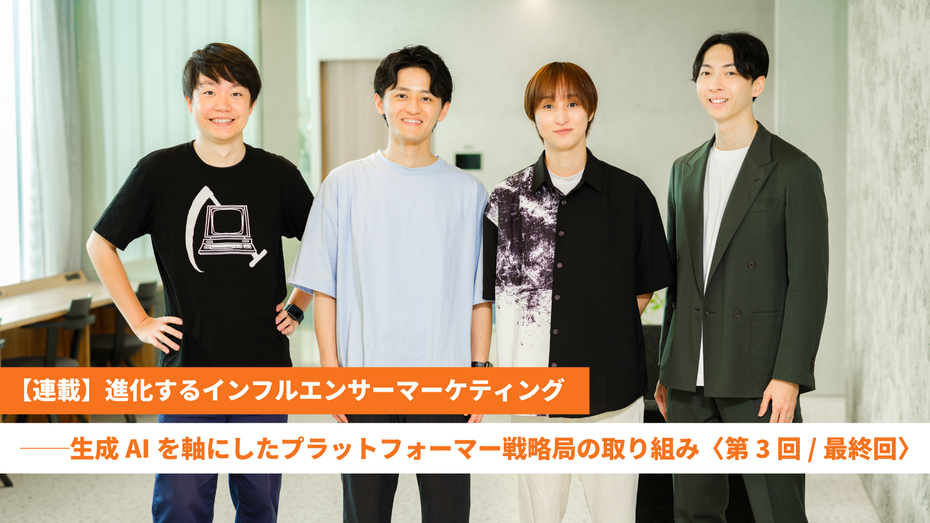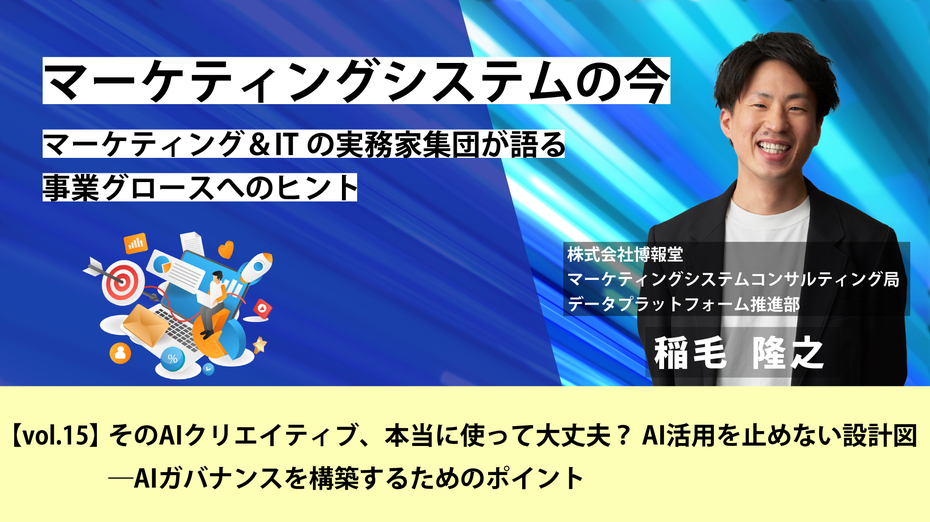生成AIスペシャリストたちが未来を語る!~博報堂DYグループが取り組む最前線の事例から見る、人間と生成AIの共存とは~
企業への導入コンサルや社内の業務改善、またサービス開発などを通し、まさに生成AIの最前線にいる博報堂DYグループのスペシャリストの3人が、最新の導入事例や具体的な活用方法、生成AIへの向き合い方から未来予想まで、熱く語り合いました。
中原 柊
Hakuhodo DY ONE
チーフAIストラテジスト
竹内 雄哉
博報堂 デジタルアカウントマネジメント室 マネジメント一グループ 兼
Hakuhodo DY ONE DX開発推進局 AI事業企画部
垣口 文香
博報堂 ストラテジックプラニング局 事業プラニング二部
■AIという莫大な知的労働リソースをいかに事業に取り入れていくか

- 中原
- 2023年に誕生し瞬く間に一世を風靡したChatGPTですが、最新版には以下の3つ進化が見られます。
一つ目はマルチモーダル化。
つまり目が見え、耳が聞こえるようになったことです。1年半前はテキストで会話できるだけだったのが、今はビデオ通話で、周りの動きや背景にある物などを認識し、感情豊かに発声したり音を認識したりできます。
二つ目は記憶力の向上。
かつてのChatGPTは、チャットがずっと続くと最初の方の内容を忘れられることがありましたが、今はトークン数、つまり扱えるデータ量が8倍以上に増え、記憶してくれるようになったこと。ある開発者は、「扱えるデータ量ニアリーイコール知性」だと言っていますが、それだけ世の中のさまざまな情報を踏まえて応答できるようになった。
最後に、かつては一字一句指示しなければ全然意味をくみ取ってくれなかったのが、曖昧な言葉もそれなりに分かってくれるようになったことです。
最新の生成AI、LLMはIQが130あることがわかっています(2024年時点)。平均的な人間よりほんのちょっと賢い、そんな知性を今後労働力として取り入れられるかどうかは、企業にとっても非常に大きなテーマです。AIという知的労働力が100万人の人間に匹敵するようになったときに、企業はどうすべきか。生産労働人口が減少する中、AIを莫大な知的労働リソースと捉えて取り組み始める企業は確実に増えています。
■人間のクリエイティビティを解放する、AI×人間の共創Workshopプログラム
- 中原
- まずは僕から、AIの企業実装コンサルティングとしてどんなことを行っているか、具体的にお話します。
たとえばとある得意先は、労働生産人口の減少から、長期的には従業員数の半減が避けられない状況にあると捉えており、売り上げ維持のためにもAIの導入が必要ということで、我々が支援に入り、AIのタスクフォースを立ち上げ、複数の部門と連携しAIの生産性向上ユースケースに取り組んでいます。
最近よくご支援させていただくテーマの一つとして、アイディエーションしたいというものがあります。こういうとき、当社では以下のようなお取組みをご一緒させていただくことが多いです。例えば、「AIを活用するポイントユースケースをアイディエーションするためのワークショップを実施してほしい」というものです。
我々は、まずは座学で生成AIについて学び、市場動向なども把握してから、ワークショップを行い、アイデアソンを実施するという提案を行いました。
ワークショップでは、最初にインスピレーションシャワーと言って、さまざまな活用事例を一気に見ていきます。実際にどういう使われ方をしているかについて理解いただいた後に、今度は実際に、AIと一緒にアイディエーションしていく。誰かが書いた数行のアイデアをAIに読み込ませると、それを具体化してくれるので、それを元にさらに人が磨いていくという、AIと人間が共創するスタイルです。
最後の発表も、AIが完成度の高いシートにまとめてくれます。こうしたワークショップが高い評価をいただいていて、さらに大きなお取り組みをご一緒させて頂くケースもあります。そこで出たアイデアそのものや個別のユースケース、ファシリテーションも評価され、指名で伴走支援を依頼され、そこからPOC開発に進むケースもあります。
アイディエーションにおけるAI活用で重要なのは、AIに考えさせることではなく、AIが作ったものをもとに、いかに人間が面白さや新しさを出していくかです。
ある研究では、たとえば新商品のアイデアがあったとして、それが「売れそうかどうか」という点ではAIのアイデアの方が人間のアイデアより評価が高くなる。一方で、評価基準を「新しさ」にすると、人間のアイデアが勝つんです。人間とAIはまさに棲み分けるものであり、その探究こそ、クリエイティビティプラットフォームとしての私たちの役割なのかと考えます。
■全従業員のあらゆる業務に寄り添う、専属AIアシスタント『HAKUNEO ONE』

- 竹内
- 私からは、現在AIでどんな業務改善を実践しているのかご紹介します。
いまや業務へのAI活用は当たり前の時代で、私の方にも、デジタル業推や営業ご担当者の方から「AIを使った施策の提案をお願いされたんだけど」とか「実績分析をAIでできないか」「デジタル広告のプランニングをAIで対応させられないか」などといった問い合わせが結構来ます。さらに、「AI=デジタル」というイメージからデジタル業推やデジタル担当者にこういった相談が集中し、どうしたらいいだろうかと我々の方に相談が回ってくるケースが多いというのが現状です。
いずれにしてもまずは、実際に触ってみることで理解することが肝要ということで、Hakuhodo DY ONEの従業員が触れ合えるAIソリューションとして開発されたのが「HAKUNEO ONE」です。
セキュアな環境で生成AIの業務利用が可能で、Hakuhodo DY ONEの業務フローに最適化したAIツールとなっています。
Webブラウザやチャットツール上など、業務スタイルに合わせて様々なタッチポイントで触れることができ、Hakuhodo DY ONEの公式のコミュニケーションツールであるSlack上でも活用できます。
業務内容に合わせ、一般的なモデルだけではなく、Hakuhodo DY ONEオリジナルのモデルについても開発していく予定です。
GPT系ツールのようなチャット形式での画面をイメージしており、直感的に操作できるデザインです。GPT-4o以外のモデルも選択できるなど高機能で、直感操作可能、オリジナル機能もあります。
また、Slack上ではたとえば「この文章を要約して」などと送ると、AIが回答してくれ、それをそのまま転送できる機能もあります。Slack内でやり取りが完結できるので、全体の工数削減にも繋がります。長々と会話が続いた場合も、スレッド機能を使えば、会話履歴を参照して要約もしてくれます。
Hakuhodo DY ONE独自のナレッジや、過去の問い合わせログ、過去の配信傾向、媒体ヘルプなどを組み合わせ、「HAKUNEO ONE」のメディアガイドというオリジナルモデルも実際に活用しています。
またこれまでは、デジタル業推は運用を担当するメンバーにその都度、デジタルの細かなメニューについての詳細や問い合わせをしていましたが、今ではまずAIに「これってどういう配信ができますか」「このメニューってどんな画像が入稿できるんでしたっけ」と聞くことで、精度の高い回答をもらうことができます。これにより、運用者の手を煩わせずに解決できますし、何よりAIは不平不満を言わないうえに24時間働いてくれます。夕方になって、「明日入稿だ、画像を作らないと」などというときにも、AIはすぐに回答してくれます。
競合他社にもAIアシスタント機能がありますが、当社にもすでに類似機能が存在しますし、オリジナルデータによる質問対応が可能なAIもあるので、他社と比べても当社ほどAI活用環境が整っている企業はなかなかないと思います。
あらゆる業務に独自の知識で対応してくれて、24時間いつでも対応できる。AIという1人1人の業務に寄り添う専属アシスタントがいるような、新しい仕事の日常が生まれつつあります。
■特許技術活用も!IPのAIキャラクターとの「グループトーク」が楽しめるサービス

- 垣口
- 私はIP×コンテンツ開発におけるAIを活用した取り組みとして、2019年に発足した新規事業開発組織「ミライの事業室」との協業プロジェクトに入っています。
今回ご紹介するのは、つい先日リリースしたばかりの「ジャパリトーク」の事例です。『けものフレンズ』というIPの公式キャラクターたちとグループチャットが楽しめるサービスです。
実際のグループチャットの画面を見ていただくと、たくさんのキャラクターが出てきて、ぽんぽん会話が出てきます。もっと喋ろうと思ってもらえるよう、会話が続くにつれていろんなキャラクターが出てくるといった工夫もあります。
変化球の質問に対しても、AIが違和感なくキャラクターらしく処理して、ちょっと面白く返してくれる。自分の話にキャラクターが答えてくれるという体験はもちろん、キャラクター同士の掛け合いもすごく面白いので、それを見るだけでも楽しめるようになっています。
この生き生きとした会話がファンコミュニティでも大好評で、『けものフレンズ』の公式VTuberさんが、配信の中でジャパリトークを使ってチャットしてくれるなど、反響があります。ユーザーさんからも、面白かったチャットや感動したチャットなどがどんどんSNSに上げられていて、いま1つのムーブメントになっています。「推しと話せるなんて、なんていい時代になったんだ」「ジャパリパーク(けものフレンズの舞台)が実在しているみたい!」といった声も挙がっているのは嬉しいですね。
ストーリーというサービス内コンテンツも特徴の1つです。ユーザーの発言や行動に合わせて選択肢が生成され、選んでいくと、それに合わせて物語が展開していきます。今までにない新感覚の、没入感のあるストーリー体験ができるコンテンツとなっています。
また、この度開発したシステムの中で、博報堂がリリースしている、AIとの会話からニーズを発掘し、商品を自然にレコメンドする特許技術を活用していくことも考えています。たとえば過去の会話データから、キャラクターがユーザーを理解していく中で、「あなたはこういう話にも興味がありそうだよね」といった感じでサービス内コンテンツをレコメンドするなど、今後もいろいろと実験的に活用していきたいと思っています。
■AIとの一個人としての向き合いについて
- 中原
- ここからはAIにまつわる様々な議論をしていきたいと思います。
まず、皆さんAIを使う頻度ってどのくらいですかね。僕の場合、ChatGPTを毎日15回から20回ぐらいは使います。たとえば先日美術館に行き、撮影した展示内容をもとに、ChatGPTに解説をしてもらいながら鑑賞しました。本当に日常的に、こまめに使っています。
- 竹内
- 僕も毎日使います。仕事中何かツールがうまく動かないといったときにはとりあえずHAKUNEOに聞きます。プライベートでも、たとえばワインのエチケット(ラベル)の写真を撮り、ブドウの品種や、どういう料理に合うかなども聞きます。ある意味、ウィキペディアに聞いていたようなことをAIに聞くようになったと言えるかもしれません。
- 中原
- 好奇心の赴くまま疑問、質問をAIにぶつけ、何となくの回答を得ることが習慣化しました。バラエティー豊かな知的引き出しを増やす手段になっている。調べるハードルをぐっと下げてくれた感覚がありますね。
- 垣口
- 私もヘビーユーザーで毎日使っています。プログラムを書くのもAIの得意分野なので、ジャパリトークの制作などでよく使います。
■AIと生活者発想について
- 中原
- では次に、AIを「生活者発想」にどう活用できるか?という議論に行きたいのですが、垣口さんいかがですか。
- 垣口
- 生活者のさまざまなペルソナをAIに読み込ませてバーチャル生活者をつくり、疑似的な生活者との対話が可能なツールが開発されています。アイデア出しの壁打ち相手としても使いやすいと思っています。
- 竹内
- 普通なら会話ができないようなペルソナの方もAIが疑似的に再現してくれるのは大きいですよね。解像度高く、生活者を身近に感じるきっかけになりうると思います。
- 中原
- たとえば感情のまま勢いで文章を書き、AIに「表現を丸くして」とお願いしたりしています。自分のバイアスや主観から離れて、ニュートラルに相手に伝わるように翻訳してくれる点でAIはとても有効です。
■AIによって仕事が奪われてしまうのか。人員削減につながってしまうのか。
- 中原
- AIによって人の仕事が奪われるのではないか、ということを皆さんもよく聞かれるかと思うのですが、僕としては「人員削減に繋がらない」とは言えない、とは思います。なぜなら人口は減っているから。現状の労働生産人口がマックスだとしたら減らすべきで、その後、その人に対して適切な量の仕事を与えるということなのだと思います。
- 竹内
- ポイントは2つあって、1つは、「仕事を奪われるんじゃなくて仕事を交代させる」ということ。
いわゆる集計業務などを全部自動化できたとしたら、空いた時間で得意先の分析をするとか運用の研究をするとか、残業をやめるといった選択肢ができる。奪われるという感覚は少し違うのかなと思います。もう1つは、AIはまだ人の仕事を全て奪い切るレベルには達していないということです。
おそらく「仕事を奪われるかも」と思っている方は、それだけAIに期待をしているということかと思いますが、僕は期待しつつもそこまで夢を見きれてはいません。
- 中原
- どちらかというと、正解を求めるような業務はAIに代替されやすい気がします。博報堂DYグループがクリエイティブプラットフォームという発想を大切にしている限り、代替されることはないのではないかと、比較的楽観視しています。
- 垣口
- 私は、人間にたくさん腕が生やせるようになるようなものかと思います。あるいは人間の守備能力や、時間あたりのアウトプットを増やし、生産性を高めることができるもの。単純に人間ができることが増えるだけであって、AIは人が代替されるものではなく、あくまでも人が使い倒すものだと思います。
■AIと友情を築けるか。
- 垣口
- AIと友情が築けるか、ということもよく議論に上がると思うのですが、ぜひ中原さんと竹内さんに伺わせてください。いかがでしょうか。
- 中原
- AIと人間は、この先20年くらいで融合していくものだと思います。なので、感じることはできるでしょうね。たとえば、アイドルのAIとファンが喋れるというサービスがあります。AIが好感度を評価して、喋れば喋るほどユーザーの好感度が上がるという仕組みなのですが、好感度が一定より高くなると、本人と本当に喋れる可能性が出てくるんです。なので相手がAIとはいえ、ユーザーは真剣に話すようになる。これってある意味、AIと本人が融合している状態ですよね。同じように、いずれは、誰かにSNSでメッセージを送って返ってきた返信が、AIによるものなのか、その人本人によるものなのか、というように曖昧な世界になっていく。そのときには、人間とAIとの友情は自然と築けている気がします。
- 竹内
- 僕も築けると思います。
「十分に発達した科学は魔法と見分けがつかない」と言われるように、AIが発達したら人間と区別つかないレベルで会話をするようになるでしょうから。実際に今、僕がプライベートで使っているGPTでは、ちょっと年の近い先輩みたいな喋り方をするように注文してあって、友情を感じています。
- 垣口
- ジャパリトークでも、会話していると好意的な感じで返してくれて、嬉しいという気持ちが自然と湧いてくるんですよね。それが愛着に繋がる気がします。
■ここから10年後くらいまでの間にAIやAIを取り巻く環境はどうなっていくのか。
- 中原
- 今後の展望について最後にお話していきたいのですが、企業実装という視点で見ると、チャンスとピンチが同時に来るのが1年後ぐらいではないかと思います。
というのも、1年後に入ってくる新卒社員は、これまで2年程ガッツリAIを使っているはずなんです。AIが一般的に使われ始めたタイミングに学業のピークを迎えているわけですから。AIネイティブがいよいよ社会進出してくる。今、各社で生成AIの取り組みを進めるために、社内でエバンジェリストを探そうとか、AIが得意な人材を探そうとしていますが、いよいよAIを自然と使いこなしてきた世代が入社してくるということは、チャンスと取れると思います。
一方で、今年はAIに投資する企業が増え、さまざまなPOCや、社内のカルチャー変革含めた取り組みも行っていますが、その成否が分かれるタイミングが来年やってくるのではないでしょうか。
ここできっと、諦めてしまう企業も絶対に出てくる。AIがどれだけ進化しても、結局人間や組織が変わらない、業務が変わらないことがボトルネックになり、失敗する企業も出てくると想定します。そこを乗り越えて、しぶとく投資した企業や、変革を止めない企業は、その後の未来に差をつけていけるのだと思います。
※2024年8月時点での対談になります。
この記事はいかがでしたか?
-
Hakuhodo DY ONE
チーフAIストラテジスト大手コンサルティングファーム、SaaSスタートアップを経て、アイレップ(現・Hakuhodo DY ONE)へ参画。未来学に基づき、生活者や市場の変化を見据えた課題解決を得意とする。メディア/Webサービス/通信/エネルギー業界を中心に、DX企画、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わり、コンサルティングファームでは最年少マネージャーに。現在は、ChatGPTをはじめとした生成AIの企業実装全般のコンサルティング活動を中心として、外部講演への登壇や記事執筆などを通じた情報発信活動にも注力。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)がある。
-
博報堂 デジタルアカウントマネジメント室 マネジメント一グループ 兼 Hakuhodo DY ONE DX開発推進局 AI事業企画部博報堂に新卒入社。制作営業、テレビを中心とするメディア営業を担当。2018年から博報堂DYデジタル(2019年デジタル・アドバタイジング・コンソーシアムと統合、現・Hakuhodo DY ONE)で、デジタル業進を担当。全社的な繁忙状況に課題を感じ、業務改善を図るプロセスイノベーション局に新設段階から参画。生成AIを活用した業務改善や業務フローの整備などを経て、現在はデジタル領域のアカウントマネジメントと社内/グループ内の生成AI利用の浸透に取り組む。
-
博報堂 ストラテジックプラニング局 事業プラニング二部学生時代の演劇の脚本・演出の経験を活かし、学部卒業時にストーリーを生成するゲームシステムを提案。2023年入社後、コンテンツプラニング、IP開発、DX/GXソリューション開発などの業務に携わる。