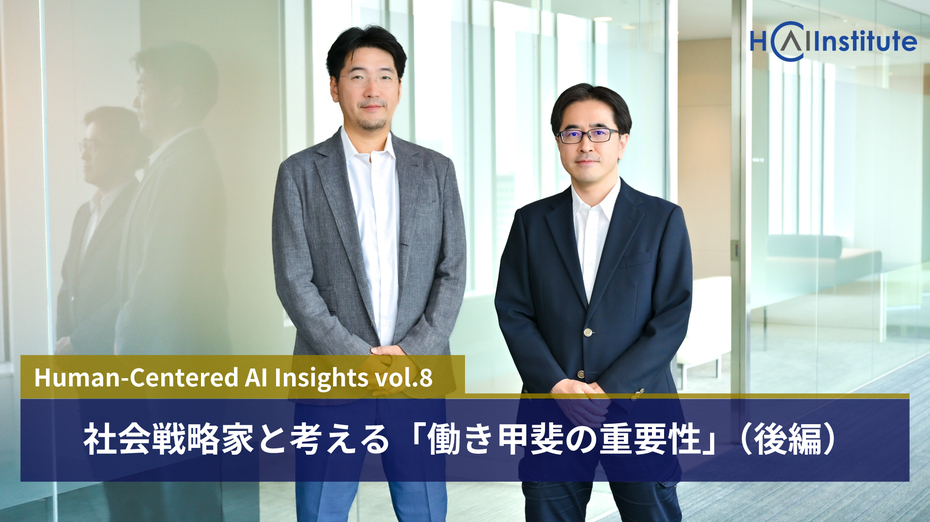万博レガシーを社会実装する異業種3社の挑戦。「医療の手前」にある新たなヘルスケア市場を切り拓く(後編)
万博レガシーの社会実装に向けて、博報堂、BIPROGY、JR西日本による「PHRコネクト共同企業体」では、「医療の手前のヘルスケア」領域における新たなサービス開発に取り組んでいます。前編に続いて後編では、実証実験で見えてきた“兆候”やビジネスの可能性、今後の事業の展望についてプロジェクトメンバーが語りました。
※PHR(パーソナル ヘルス レコード)…個人が自身の健康に関する情報を、一元的に収集・管理・活用するための仕組み
前編はこちら
三宅 裕昭氏
BIPROGY
事業開発本部 事業推進三部長
畑 康介氏
西日本旅客鉄道
デジタルソリューション本部 ソリューション営業企画部 WEST LABO事業共創
ヘルスケアPJ統括/DotHealth Osaka店舗計画・設計・施工責任者
岩宮 克臣
博報堂
関西マーケットデザインビジネス推進局
チーフビジネスデザイナー/事業共創コンサルタント
枠組みに縛られない異業種3社ならではの連携
── 3社が一緒に取り組んだからこそ実現できたのはどのようなことでしょうか?
- 岩宮
- 2025万博の府市パビリオン向けに開発され、いま駅ナカでも活躍している「カラダ測定ポッド」は、「体験時間をいかに短くするか」を追及して開発されています。6分間のポッド体験のなかで、カメラ4台での多面的な画像解析、手からの心血管計測、目の動きからの脳機能の計測など、多様なデータ取得と解析処理が同時並行で行われています。
JR西日本が電車や改札機などの鉄道機器を開発する中で培われた“センサ/機器の同時/高度処理技術”と、BIPROGYが持つ多様なデータを連携・管理するシステム構築技術が融合したからこそ、この高度な仕組みを具現化することができています。
── PHRコネクト共同企業体によるヘルスケアの仕組みは、従来の他のデータ活用によるヘルスケアの取り組みとどのような点が異なるのでしょうか?
- 岩宮
- 私たち3社は、医療や薬事といった業界のキープレーヤーではありません。それもあり、敢えて“医療・薬事の枠組みではない立ち位置”を重視して活動しています。当たり前のことなのですが、ヘルスケア領域は“まだ健康”な状態であるため、生活者にとって無関心になりがちです。が故に我々は、ヘルスケアデータにこそ、一種の嗜好性・エンタメ性が重要だと考えています。
まだ医学的意義が低いとされる健康データだとしても、そのデータを介して、より生活が楽しくなったり、交流が生まれたり、新しい趣味ができたりする。お客様の生活に彩りを創出でき、それが継続的に続けたいと思えるものであれば、そこにはとても大きな価値が生まれると考えています。

当初は医療/薬事の専門家をチームに中核に入って頂くことも検討しました。しかし、よりフラットな視点をもち、生活者発想でやりたいこと/面白いと感じること/やるべきと思えることに、柔軟に動けるチーミングにしたのが、このチームの最大の特徴だと思っています。
「お客様が関心を持つ健康データから、どのようなサービスを生み出し、付加価値をつけていけるか。」
このような発想を持ってチーミング出来ているからこそ、単に各社のアセットを組み合わせるだけではなく、生活者の感覚を中心に据えたプロジェクトを生み出し・推進してゆける…と思っています。
実証実験で見えてきた生活者が求める“ヘルスケア”の本質
── 現在JR大阪駅などに設置している「カラダ測定ポッド」の実証実験で見えてきた“兆し”や“気づき”は何かありますか?

カラダ測定ポッド
- 岩宮
- 「カラダ測定ポッド」は、“短時間で計測できる”だけでなく、“日常生活の延長で気軽に計測できる”ことを重視して開発されています。肌や頭皮・髪の状態、脳の認知機能、心血管・筋骨格のコンディションなど、靴や服はそのままでポッド体験を済ませるだけで、様々な健康データを計測することができます。
データとしての有用性は、まだまだ有識者の方々にご協力いただく必要がありますし、まだまだ“成長途上”です。しかしお客様自身は、このカラダ測定ポッドの体験を通じ“自分の健康データを継続的に管理したい”という動機が生まれた方が沢山いらっしゃいます。取得したデータを自分なりに解釈し、色々な方法で日常生活の中で活用頂いている。ここが重要なポイントで、私たちが提供しようとしている “ヘルスケア” の特徴だと感じています。
駅という日常の場所に、本当に手軽に計測できる装置を置くからこそ、生活者が自ら気軽で・自分なりの使い方をしはじめる。ヘルスケアデータの新しい使い方/楽しみ方を、ここから生み出すことができると思っています。
今後、この新しい“使い方/楽しみ方”の概念を正しく伝えるためにも、“ヘルスケア”という広義すぎる言葉ではなく、別の言葉/カテゴリーを生み出していく必要があるのかもしれません。
- 畑
- 実証実験を重ねるなかで、VoC(お客様の声)を集めながら分析を進めたところ、思いがけない結果が見えてきました。ご利用いただいたお客様は20代から60代以上までと幅広かったのですが、特に印象的だったのは、想定以上に多くの女性にご利用いただいたことです。
当初は「働き盛りの40代前後のビジネスパーソン」を中心に、健康意識の高い層のご利用を想定していました。しかし実際には、40代以上の女性のお客様が大半を占め、大きな反響をいただくことになりました。
この結果から、肌の状態や認知機能といった領域が、多くの女性にとって身近で関心の高い分野であることが改めて分かりました。万博会場のカラダ測定ポッドはエンタメ性のある体験として楽しんでいただけるものですが、DotHealth OSAKA設置のカラダ測定ポッドStation版を利用されたお客様からは「日常的に計測を続けたい」という声や、PHRの理念に共感する声も数多く寄せられました。
私たちとしても、こうした利用実態やお客様の反応は非常に興味深く、今後の展開に向けて多くの気づきを得る結果となりました。
- 三宅
- 「カラダ測定ポッド」で測定した健康データをきっかけに、コミュニケーションが生まれるのも興味深いと思いました。自分の状態が数値として「見える化」されると、例えば、女性のお客様はもちろんですが、50~60代の男性経営者の方なども、自分の健康データの数値を見せながら「こういう結果が出たんだ」と皆さんで盛り上がっているんですよね。健康データは単なる健康指標ではなく、人と人をつなぎ、健康行動を促すためのコミュニケーションツールとしても機能しているんです。
- 岩宮
- まさに今回の取り組みは、ヘルスケアへの入り口として機能し、ハードルを下げる役割を果たしてくれるのではないかと考えています。
女性からは「肌の状態」や「脳の認知機能」といった健康データを1か月に1回くらいの頻度で測りたいという声が多く聞かれました。
体重計は家で毎日測れますし、健康診断は年に1回あることがほとんどですが、肌や髪の状態のように「日常的に気になるもの」を測る機会がない。
そのような領域こそ、今の生活者が本当に求めている部分なのだと感じましたね。
「カラダ測定ポッド」の健康データ活用で万博レガシーの事業拡大を目指す
── 今後の事業についての展望をお聞かせください。
- 三宅
- 本格的なサービス開始は来年4月を想定しており、そのタイミングでスポット利用やサブスクなど複数のメニューを提供していくのを視野に入れています。
ただ、ポッドの利用料だけで事業を回していくのは難しいため、このサービスを通じた生活者との接点で得られるデータを活用したサービスや、マーケティングへの応用も視野に入れながら、ビジネスとして成立させていくことを目指しています。

- 畑
- JR西日本では「ステーションヘルスケア構想」のもと、駅ナカにクリニックを設置するなど、利便性の高い場所で医療サービスを提供する取り組みを展開していきたいと考えています。診療だけでなく、処方薬を駅構内や自宅など、どこでも受け取れるような仕組みづくりも進めており、こうした一連のサービス全体で収益化を目指していく方針です。
一方で、各地の駅に測定ポッドを短期間で設置していくのは容易ではないため、まずは「お客様との接点をどう設計するか」が今後の鍵になってくるでしょう。
- 岩宮
- PHRコネクト共同企業体では、未来のヘルスケアサービスを創造するためにPHRデータをつなぎ合わせ、エンターテインメントや生活の彩り、医療の手前のヘルスケア領域など、いろんな角度から万博のレガシーを社会実装する取り組みを進めていく予定です。
まずは駅を起点にスタートしていますが、それ以外の場所にもコンビニチェーンや不動産デベロッパーと協力し、オフィスビルなどの都市空間でワーカーの健康と結びつける方法を検討しています。このように、PHRデータを活用する仲間を増やしながら、継続的に取り組みを進めていきたいと思っています。
PHRコネクト共同企業体が「結節点」となって未来のヘルスケア体験をつくる
── どのような企業との連携を想定されていますか?
- 岩宮
- 様々な企業が健康データの活用や健康関連商品の開発を試みている一方で、それをどう効果的に届けるかという点に苦労していると感じています。
今回の大阪ヘルスケアパビリオンでは、多くの協賛企業が集まったことで、今までできなかったことが可能になる「結節点」のような仕組みを作れたと考えています。
JR西日本は巨大なインフラ企業として、複雑な要素を組み合わせながら一つにしていくノウハウをお持ちで、BIPROGYはデジタルシステムで様々な価値をつなげる技術があります。そして博報堂は、新しい発想や別解を生み出すクリエイティビティという強みを持っています。
この3社が協働して取り組めば、今まで思いつかなかったアプローチやシステムを活用しながら、新しい価値提供ができると捉えていますし、PHRコネクト共同企業体が推進する事業とシナジーのある企業ともぜひ連携していきたいですね。
- 畑
- カラダ測定ポッドにおいては、様々な領域を測定できるセンシングデバイスを搭載していますが、今後はさらにユーザーフレンドリーなプロダクトとなるよう測定項目を厳選し、ブラッシュアップしていく予定です。その際には、できるだけ手軽かつ非接触非侵襲で測定可能なセンシング技術を持つ企業とも共創しながら、新しいポッドのバージョンを開発していきたいと考えています。

「DotHealth OSAKA」の店舗では2台のポッドが稼働していますが、どうしても待ち時間が発生していました。そこで、その時間を有効活用しながら、ポッドではカバーできていない項目に対してアプローチする体験を提供できる企業と連携できれば、より付加価値の高いサービスを実現できると考えています。
さらに、ポッドで取得したPHRデータをもとに、最終的にはパーソナライズされたレコメンドを提供していく予定です。そのため、この領域でソリューションを持つ企業との協業も積極的に進めていきたいですね。
- 三宅
- 今回の取り組みでは、自分の健康に関心がある生活者に絞ったPHRデータを活用していますが、このデータはマーケティングデータに近いデジタルデータであり、「プラットフォーム」と呼べるものであると考えています。
このプラットフォームを基盤に、我々だけでサービスを作るのではなく、外部の企業やベンチャー、中小企業が既に提供しているサービスと接続し、生活者が自分に合ったサービスを受けられるようにしたいと考えています。
これまでは良いサービスがあっても、対象となる生活者に届きにくいという課題がありましたが、このプラットフォームを介すことで、効率的にマッチングが可能になるでしょう。
結果として、生活者はより健康な状態を維持・向上でき、我々としてもビジネスとして成立させつつ、多くの企業やサービスが活用できる環境を作っていく。
そうなることで社会全体に、より良い健康体験を提供できると考えています。

この記事はいかがでしたか?
-
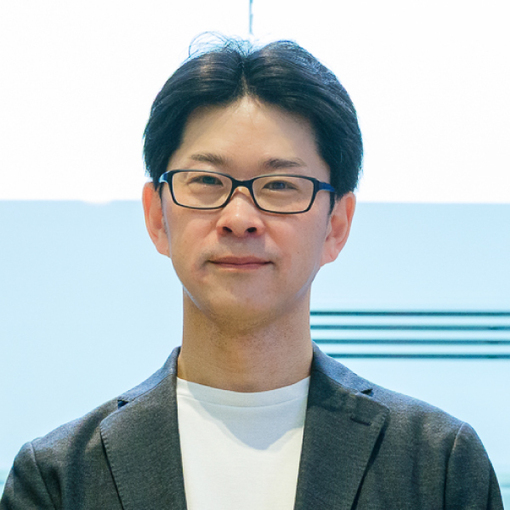 三宅 裕昭BIPROGY
三宅 裕昭BIPROGY
事業開発本部 事業推進三部長2001年BIPROGY(旧日本ユニシス)に入社。
営業部門において、主に官公庁(中央省庁/地方自治体)向けのシステム構築を担当。その後、官公庁と医療機関(病院等)向けSIビジネスの責任者として従事。2018年度に新設されたスマートシティ戦略本部を兼務し、観光やヘルスケアに関する新規事業創出に携わる。現在は、新規事業を担うビジネスクリエーション部門に所属し、ヘルスケア等の事業開発の責任者を務める。
-
 畑 康介西日本旅客鉄道
畑 康介西日本旅客鉄道
デジタルソリューション本部 ソリューション営業企画部 WEST LABO事業共創
ヘルスケアPJ統括/DotHealth Osaka店舗計画・設計・施工責任者2015年西日本旅客鉄道に入社。
建設工事部門において、広島・大阪・奈良エリアでの大規模改修工事、新駅設置、支社ビル移転などの設計・品質管理・施工管理を担当。その後、駅ホーム上の人流緩和を目的としたデジタル実証実験や、うめきた地下駅をはじめ、同社のアセットを活用した事業共創プロジェクトに携わる。現在はライフデザイン領域における新規事業開発を推進し、「ステーションヘルスケア構想」の事業化に向けたプロジェクト統括を務める。
-
博報堂
関西マーケットデザインビジネス推進局
チーフビジネスデザイナー/事業共創コンサルタントフロントプロデューサーとして、食品/生活用品/医薬品/流通/通信/旅客など多様なクライアントのマーケティング支援を経験したのち、2010年から業務主軸をコンサルティング領域にシフト。複数の共同事業(JV)を組成し事業マネジメント経験を積んだのち、現在は チーフビジネスデザイナー/DXコンサルタントとして、お得意様の事業開発コンサルティングとともに、自社/共創事業の組成/育成に従事。日本マーケティング協会講師(実践的事業創造)。