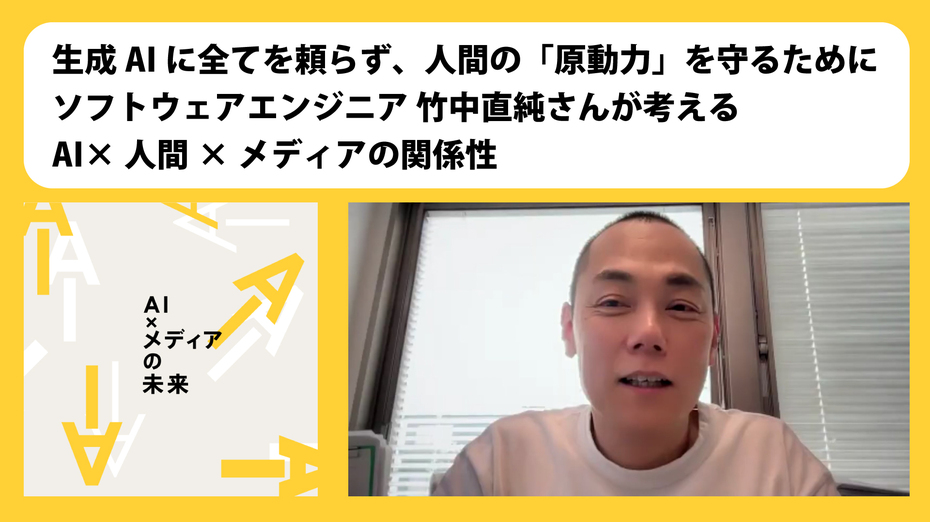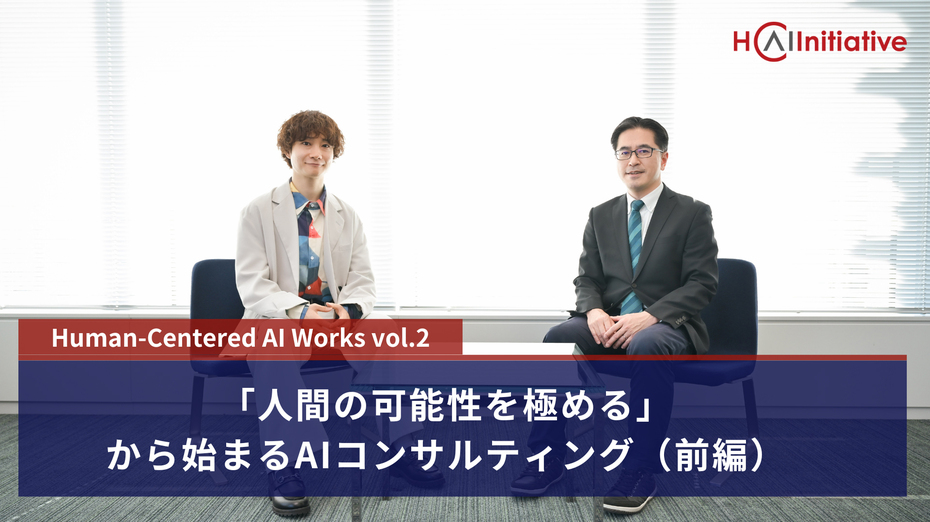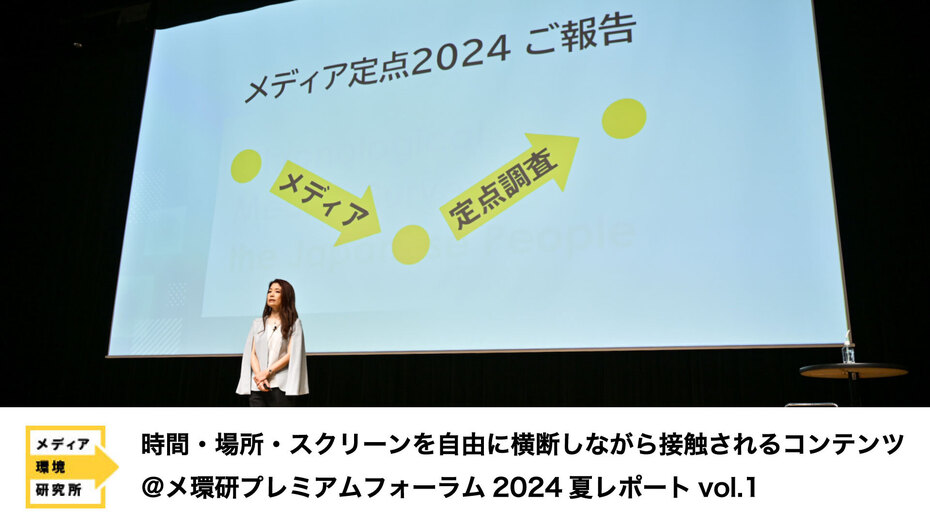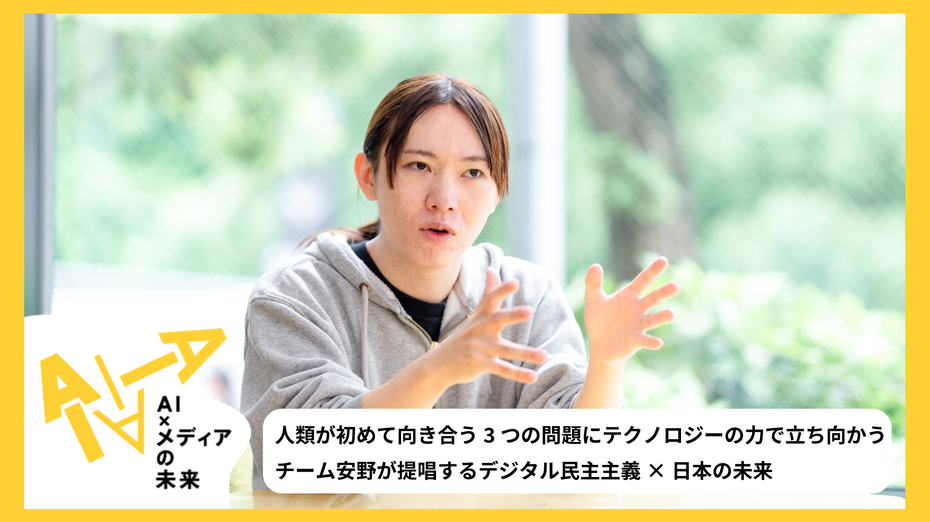デジタル時代の「新・ブランド論」【第10回】 AIはわたしたちの感情を揺さぶるのか?AIの進化と生活者の情報行動への影響を考える
SNSなどデジタル環境の変化に伴い、生活者の情報選択・購買・消費行動は大きく変化しています。また、様々なテクノロジーの登場によって、企業の行うデジタルマーケティングも日々進化しています。その一方で、長期的な視点に立った企業と生活者との絆づくりである「ブランド」はどうでしょうか?デジタル時代において、改めてブランドとは、ブランディングとはどうあるべきなのか──そんな問題意識からスタートした「デジタル時代の新・ブランド論」構築プロジェクト。
本連載では、マーケティング、消費者行動論、社会心理学などに精通した研究者と博報堂DYホールディングスのマーケティング・テクノロジー・センターのメンバーによって進められているプロジェクトをご紹介します。
第10回では、前回に引き続き、生成AIが広がる時代の「情報の検索・探索」行動について、また「AIは感情を揺さぶるのか?」というテーマについて議論していきます。
連載一覧はこちら
<プロジェクトメンバー>
(写真左から)
石淵 順也氏
関西学院大学商学部 教授
柿原 正郎氏
東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授
杉谷 陽子氏
上智大学経済学部経営学科 教授
西村 啓太
博報堂DYホールディングス
Human-Centered AI Institute 所長補佐
本プロジェクト共同代表
澁谷 覚氏
早稲田大学大学院経営管理研究科 教授
本プロジェクト共同代表
米満 良平
博報堂DYホールディングス
マーケティング・テクノロジー・センター GM 上席研究員
生成AIによる情報探索から、感情の盛り上がりはうまれるか
- 西村
- 前回(第9回)は、博報堂 メディア環境研究所(以下、メ環研)のレポート「AI時代の『検索』どうしてる?最前線」の調査結果をもとに、検索が“無意識化”していることや、若年層が「検索上位」や「フォロワー数」などを情報の信頼性の拠り所にしている点などを取り上げてきました。
- 澁谷
- マスメディアからSNSへ信頼の拠り所が移っているように、30年ほど経って今の若い人が50-60代になったとき、今度はSNSからAIに拠り所が移っている可能性もありそうですね。
- 米満
- 今の深化のスピードからすると、もしかしたらもっと5年10年と早いペースで移ってもおかしくなさそうです。
- 西村
- そうですね。信頼の拠り所は、世代論にかなり依存していて、若い人たちがSNSの次にAIを受容していくと、そのほうが信頼できるというパーセプションを築くかもしれません。一方で、現時点では先の調査では、AIは「若年層が信頼する情報源」として下位であることです。デジタルネイティブなら、よりAIのほうを信頼してもよさそうです。これがなぜか、とても興味がありますね。ハルシネーションなどの話もありますが、さらには「感情を揺さぶらない」からだと思うんです。
ここまでの一連の議論で、我々は「感情が揺さぶられるとそれがトリガーとなって、『評価する』ことを飛ばして購買行動に至るのではないか」といったことを話し合ってきましたが、AIの情報は現時点でそのようなトリガーになっていないと捉えられます。AIの情報も、近い将来に感情を揺さぶるようになるのでしょうか?
- 石淵
- 現状では、AI検索は、たとえばビジネスホテルの膨大なレビューをまとめたりしてくれるので、それは個人的にとても便利です。けれど、まだ楽しいわけではないので、感情が揺さぶられるかというと違います。ここで、心に訴えるような楽しい提案ができるかどうかが、今後の進化を左右しそうです。

- 澁谷
- たしかに現時点ではそこまで至っていませんが、確実に「感情を揺さぶるもの」になると思います。現に、単なる検索・探索を超えたディープリサーチのようなことを進めると発表しているAIエージェントもあります。ただ、それは情報そのもので感情に訴えるというより、インフルエンサーや動画配信者がエモーショナルに物事を伝えるのと似たことを実装する形のようです。基本はその人に合う情報を提供するための便利さ、使いやすさの勝負になるのだと思いますが、今はもう基盤モデルの差がだんだんなくなってきていますから、伝え方の勝負になってくるのかなと。
人間が持つ「AIに共感できる」という誤解の力
- 西村
- すると、マルチモーダル(※テキストや音声、画像など、異なるデータ形式を組み合わせて統合的に処理するAI技術)がやはりカギになりそうですね。たとえば澁谷先生のお顔と声で、回答を話してくれたら、説得力がありますし感情も揺さぶられそうです。また別の身近な人の顔で伝えられる、という形になれば、親近感が湧きそうです。
現状でAIとSNSの違いを考えると、どうしてもAIは1対1で閉じている感じがします。フォロワー数や拡散数の多さを信頼できるというのはSNSならではなので、こうした機能を備えないと、AIも感情に訴えない、グッとこないのかもしれないです。

- 杉谷
- そうですね。AIがこれからもっと変わっていけば、AIの情報に感情的に揺さぶられることが起こりそうです。個人的にも、最近、AIを搭載した製品を体験し、感情を大きく揺さぶられる経験をいたしました。
一方で、以前聞いたAIの議論でなるほどと思ったのは、AIには実際には感情はないのだから、感情が揺さぶられると思っても、それは受け取る側のプロセスにある種の“誤解”が生じている状態だと。SNSでは“人”が発信していますから、発信側と受信側が人間同士だからこそ、感情が揺さぶられたり共感したりするわけですよね。AIと人との間で“共感”や”感情”というとき、人間の側にある種の“誤解”がうまれている状態だとも言えます。あくまでそういう気分になっているだけ、とも捉えられます。なので、AIとのやり取りとSNSでのやり取りを語るとき、それが疑似体験なのか、人間相手の本物の感情体験なのかを考えることは前提にしなければいけないのかな、と思います。

AIが生活に浸透したとき、人の行動はどう変わる?
- 柿原
- 前回、新聞やテレビの報道は「信頼できる」と思い込んでいるという話が挙がりましたが、AIもいったん「信じられる」と思ったら、信頼性が高まるように思いますね。SNSでも、フォロワーの多い人を信じられるというのはある種の思い込みで、構造的には同じですから、AIを信じるのも意外と早いような気がします。
- 澁谷
- そのあたりの「構造が同じ」という点では、このプロジェクトで最初のころお話ししていた「プロジェクション理論」が該当すると思います。メディアだろうがロボットだろうが、こちらの思い込みを対象にプロジェクションしている、という。
- 米満
- プロジェクション(投射)は、頭の中で作り出された経験や知識、いまお話しているような誤解や思い込みも含めてを、実際の現実世界に当てはめようとする心の働きということでした。プロジェクションに関する書籍では、ブランドやモノに対して愛着を抱くことなどもそのひとつとして説明されていますね。我々も日常的に「ブランドに共感する」と表現します。

- 柿原
- おもしろいですね。AIによって感情が揺さぶられるかというのは、とても興味深い問いだと思います。自分にとって共感や親和性を抱くインターフェースやUXがあれば、素直に感情が動くと思うんです。冒頭の調査(第9回)では、まだAI検索は「情報の検索意図がクリアになっているときに使う」ものだと読み取れたので、そうすると利用シーンは限られると思いますが、先ほど西村さんが「マルチモーダルがカギ」と言われたように、テキストから動画まで自然に組み合わされてインタラクションされるようになると、AIが生活にするっと入ってくるのではないかと。
- 澁谷
- SNSのように、AIに接するようになるかもしれないですね。
- 柿原
- そうですね。英語でのコミュニケーションだと、すでにレストランの予約電話ぐらいはAIが音声で十分に対応できるようになっていて、それがAIだとわからないくらい自然になってきています。日本でもAIの存在や技術自体が生活に浸透して、見えない存在になったとき、人の行動はどう変わるのかというのはとても関心がありますね。AIエージェントは確実に増えるでしょうから、そうなるといろいろな仕組みや場面で気づかないことだって増えてくると思います。
冒頭の調査(第9回)で、AIは執事や先生のイメージという結果がありましたが、どこまで調整して教えてくれるのがいいのかはわからないですよね。たとえば、AIが「このユーザーは体重を気にしている」と把握していたら、レストラン検索で低カロリー系のお店ばかり推薦してくるとか。
- 西村
- それは難しい問題ですね。
- 柿原
- 情報の透明性という観点だと、調整せずに答えるのが正しいのかもしれませんが、むしろうまく「低カロリー系の店を選ぶように」誘導することもできてしまいそうです。本当に難しい話だと思います。
- 澁谷
- インターネットや検索エンジンが浸透する前の時代の人間って、すごく狭い情報の範囲内で生きていましたよね。それに比べると今は情報が幅広すぎて、一周回ってもっと狭くていいという意見もあります。なので、AIがコントロールするのが良い悪いという議論は別として、2つ3つの候補で満足しそうな気はしますね。

AIが擬人化されることのリスク
- 石淵
- いずれにしても、AIの活用が、人間の能力の拡張につながることは間違いないと思いますね。たとえばホテルのレビューをAIが要点だけ提示してくれるのも、能力の拡張のひとつですし。ですが、その先ですよね。要点や3つほどの候補をAIが出してくれた後、自分で調べるのか、それとも狭い中で満足して選ぶのか。
- 西村
- 狭い世界に入りそうな気もしますが、その狭さも方向性がありそうです。以前は、検索エンジンが出してくる情報量を自分で精査することで信頼性を担保していたのが、SNSになると感情が揺さぶられ、即購入に至るようなことも出てきました。それがAIになるとより専門性が出てくるのか。
- 柿原
- 一方で、AIが擬人化されることのリスクも冷静に考えないといけないと思っています。自分が信頼できる人の風体をしたAIを、アドバイザー的に使うようなことは増えると思うのですが、裏を返すと「このユーザーはこういう見え方のAIを用意したら信じそうだ」と意図的にAIを仕立てることもできるわけですよね。どこまでコントロールして設計していいのかという点は、今までのメディアビジネスや広告も同じかもしれませんが、現状の原始的なテキストベースのインターフェースのままのほうがよいということもあるのかもしれません。

- 澁谷
- インターフェースが現実世界に近づけばいいわけではないと、私も思います。ただ、生成AIと「恋人関係になった」という人の話が記事などに出ていましたが、むしろテキストだけのほうがイマジネーションが働くということもあるのかもしれないなと思います。先ほどの本物に似せれば似せるほど、本物との違いが目立って、いわゆる“不気味の谷”を超えられないのかもしれませんね。
人間らしいAIロボットは望まれるか
- 柿原
- ロボットの擬人化は“人型ロボットの夢”として、もう100年来、数々の小説や映画に出てきますよね。この夢を捨てる必要はないと思う一方で、本当に用途とシーンに気を付けないといけないと感じています。AIの自律性は、やはり人間がコントロールしないといけないなと。
- 杉谷
- そうですね。全部人型にすればいいわけではなく、場面によってあえて人間っぽくないロボットや、テキストベースのAIが適しているといった形で使い分ける議論が出てきそうです。
最近耳にした研究でおもしろいと思ったのは、何らかのサービスエラーが起きた際に謝るのは、やはり人間でないとお客さんは納得しないらしいんです。一方で、「当店ではこのようなサービスはありません」などのネガティブなお知らせは、人が行うと感じが悪く、AIが機械的に行うほうがお客さんは受け入れやすい、と。まだ体系化された実務的提案には至っていないようですが、こういう場面ではAIロボットにお願い、というシーンがマーケティング上で出てきそうですね。
- 石淵
- 従業員だと問題になる感情労働も、AIなら心配いりませんね。
- 西村
- 逆に、厳しい指摘が入りそうな会議の前に、AIに「厳しい指摘をして」と頼んで本番に備えたりもできますね。
- 柿原
- 自分の目的にフィットした形で生成AIを利用するのは、すごくいいことだと思います。AIが生活に浸透しても、執事やアドバイザーのように、要所要所で叱ってくれるような存在になるといいですね。たとえば、その人が好むからといって高カロリー系の店ばかり薦めてくるAIが占めていくなら、その先に美しい未来は待っていないような気がします。
- 西村
- たしかに。おっしゃるように、ときどき叱ったりたしなめたりする方向性でのチューニング自体に、価値が生まれそうです。ただ、そういうAIエージェントを選ぶかどうかは、それぞれの人に委ねられていることが望ましいと思います。
- 澁谷
- 自分の興味の範囲内でどんどん狭い選択肢を提示するAIか、それとも新たな提案や叱ったりもしてくれるAIか。自分の幸せのタイプを選ぶというか、どう生きたいか、という話になってくるのかもしれませんね。
この記事はいかがでしたか?
-
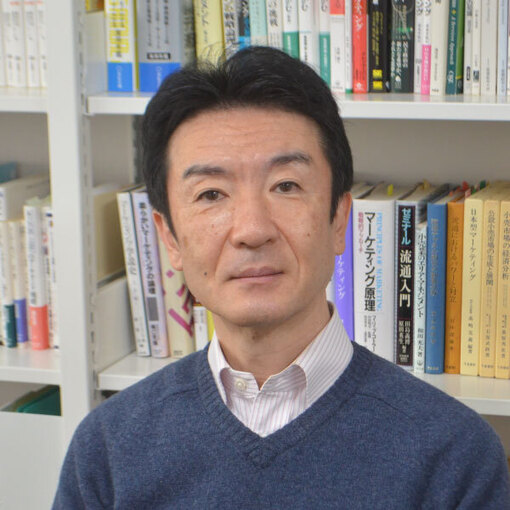 澁谷 覚氏早稲田大学大学院経営管理研究科 教授
澁谷 覚氏早稲田大学大学院経営管理研究科 教授
本プロジェクト共同代表東京大学法学部卒業、東京電力(株)に勤務。慶應義塾大学でMBAを取得。同社退社後に慶應義塾大学で博士(経営学)を取得。新潟大学助教授、東北大学教授、学習院大学教授、レンヌ第一大学ビジネススクール客員教授等を歴任。学習院大学では2020~21年に国際社会科学部長を務めた。2022年より現職。
この間、情報通信サービス、IT系を中心に、食品、住宅、エンターテインメント等多くの企業において、特にデジタル・マーケティング戦略、顧客分析、ブランド構築、人材育成等の策定、実行支援を数多く経験。日本消費者行動研究学会会長、『消費者行動研究』編集長、日本商業学会『JSMDジャーナル』編集長、日本マーケティング学会『マーケティングジャーナル』副編集長、等を歴任。
-
 柿原 正郎氏東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授関西学院大学経済学部卒業、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士課程修了(Ph.D. in Information Systems)。関西学院大学商学部講師・准教授、Yahoo! Japan研究所研究員、Google(東京およびシンガポール)リサーチ統括(検索領域・APAC)等を経て、2022年4月から現職。専門は経営情報システム、ユーザー行動分析。Google在職中から続く研究テーマは、デジタル環境下における消費者の情報探索行動。最近は、eスポーツやVTuber等のエンターテイメントコンテンツビジネスにおける消費者行動についても研究を進めている。
柿原 正郎氏東京理科大学経営学部国際デザイン経営学科 教授関西学院大学経済学部卒業、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士課程修了(Ph.D. in Information Systems)。関西学院大学商学部講師・准教授、Yahoo! Japan研究所研究員、Google(東京およびシンガポール)リサーチ統括(検索領域・APAC)等を経て、2022年4月から現職。専門は経営情報システム、ユーザー行動分析。Google在職中から続く研究テーマは、デジタル環境下における消費者の情報探索行動。最近は、eスポーツやVTuber等のエンターテイメントコンテンツビジネスにおける消費者行動についても研究を進めている。
-
 石淵 順也氏関西学院大学商学部 教授関西学院大学商学部中途退学(大学院飛び級入学のため)。同大学商学研究科博士課程後期課程修了。博士(商学)。福岡大学商学部専任講師、助教授を経て、2006年4月関西学院大学商学部助教授(現准教授)、2011年4月より現職。専門は、消費者行動論、マーケティングリサーチ、商業論。特に、買物行動、消費者行動における感情の働き、商業集積の魅力などを研究。主著に『買物行動と感情―「人」らしさの復権』(有斐閣, 2019年)。日本消費者行動研究学会理事、日本マーケティング学会常任理事、日本商業学会理事、日本マーケティングサイエンス学会学会誌編集委員等を歴任。
石淵 順也氏関西学院大学商学部 教授関西学院大学商学部中途退学(大学院飛び級入学のため)。同大学商学研究科博士課程後期課程修了。博士(商学)。福岡大学商学部専任講師、助教授を経て、2006年4月関西学院大学商学部助教授(現准教授)、2011年4月より現職。専門は、消費者行動論、マーケティングリサーチ、商業論。特に、買物行動、消費者行動における感情の働き、商業集積の魅力などを研究。主著に『買物行動と感情―「人」らしさの復権』(有斐閣, 2019年)。日本消費者行動研究学会理事、日本マーケティング学会常任理事、日本商業学会理事、日本マーケティングサイエンス学会学会誌編集委員等を歴任。
-
 杉谷 陽子氏上智大学経済学部経営学科 教授慶應義塾大学商学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。上智大学経済学部経営学科助教、准教授を経て、2019年より現職。専門は消費者心理学、ブランド論、マーケティング論。日本商業学会関東部会理事、日本マーケティング学会常任理事、消費者行動研究学会理事。日本商業学会『流通研究』編集委員、消費者行動研究学会『消費者行動研究』副編集長等を歴任。
杉谷 陽子氏上智大学経済学部経営学科 教授慶應義塾大学商学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。上智大学経済学部経営学科助教、准教授を経て、2019年より現職。専門は消費者心理学、ブランド論、マーケティング論。日本商業学会関東部会理事、日本マーケティング学会常任理事、消費者行動研究学会理事。日本商業学会『流通研究』編集委員、消費者行動研究学会『消費者行動研究』副編集長等を歴任。
-
博報堂DYホールディングス
Human-Centered AI Institute所長補佐
本プロジェクト共同代表The University of York, M.Sc. in Environmental Economics and Environmental Management修了、およびCentral Saint Martins College of Art & Design, M.A. in Design Studies修了。
株式会社博報堂コンサルティングにてブランド戦略および事業戦略に関するコンサルティングに従事。株式会社博報堂ネットプリズムの設立、エグゼクティブ・マネージャーを経て、2018年より博報堂DYホールディングスにて研究開発および事業開発に従事。
-
博報堂DYホールディングス
マーケティング・テクノロジー・センターGM 上席研究員マーケティング・リサーチ会社勤務の後、株式会社博報堂にてストラテジックプランニング・ディレクターとして、事業・ブランド戦略立案から顧客獲得、コミュニケーションに関するプラニングに従事。VoiceVision、ブランド・イノベーションデザイン局にて、生活者共創やユーザー・イノベーションを専門に、コミュニティ・プロデューサーとしてプロジェクト推進を行う。2021年より博報堂DYホールディングスにて、マーケティング実践領域の研究開発に従事。経営学修士(MBA)。博⼠後期課程。大学非常勤講師(マーケティング、消費者行動、ブランド戦略)。